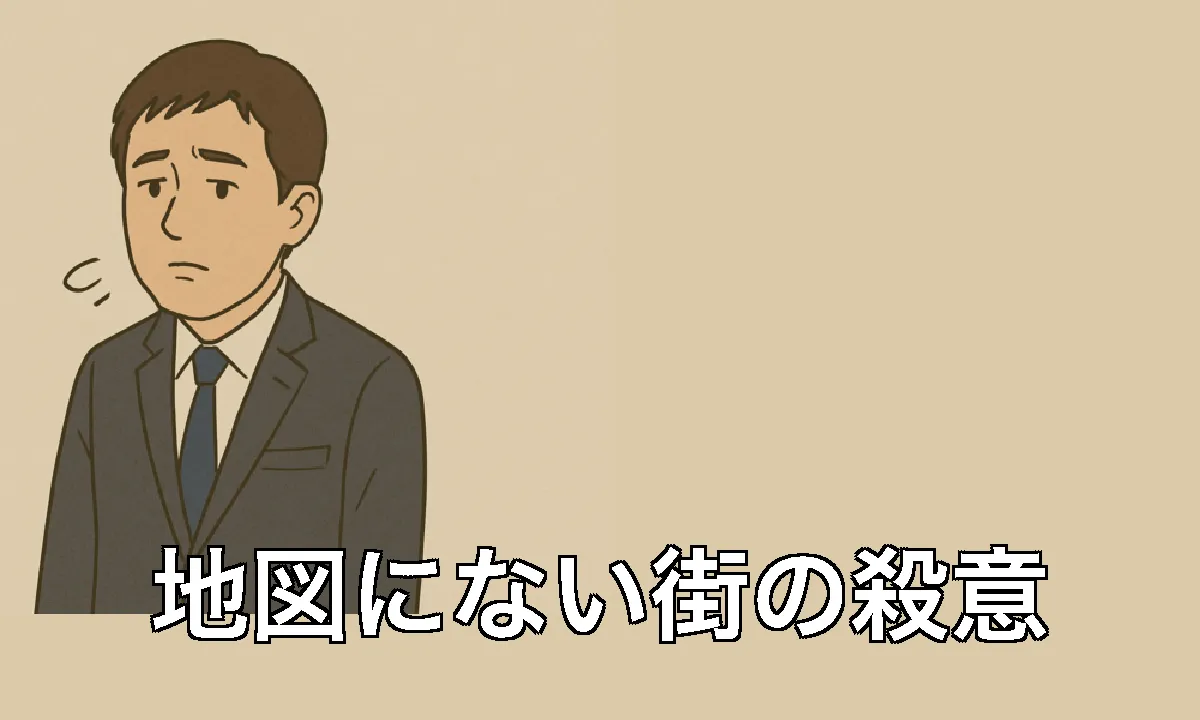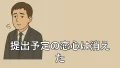地図にない街の殺意
引越しの相談に来た依頼人
「すみません、司法書士の先生、土地の名義変更って今からでも間に合いますかね」
朝一番、事務所に現れた中年男性は、どこか所在なげで落ち着きのない目をしていた。
古びた茶封筒からは、折り目のついた住宅地図と一枚の仮換地通知書が覗いていた。
「仮換地」とつぶやいた言葉が気になった
「仮換地……ですか?」
私はその言葉に敏感に反応した。というのも、ここ数年、仮換地に関するトラブル相談がやけに多かったからだ。
この地域も区画整理が進み、元の住所と新しい地番のギャップに誰もが混乱している。
区画整理地に浮かぶ名前のない住所
依頼人が指差した地図上の場所には、番号も地番も記載されていない空白地が広がっていた。
仮換地の指定はあるが、まだ正式登記されていない、いわば“法律上の幽霊地帯”。
「ここの土地に家があるんですよ。父が住んでまして」と男は口を濁した。
突然現れた殺人の知らせ
その翌日、サトウさんが顔色一つ変えずに告げた。
「先生、昨日の依頼人が話していた場所で、遺体が見つかったそうです」
まるで『名探偵コナン』ばりに事件が起きる事務所に、私はため息を漏らした。「やれやれ、、、」
死体のあった場所は地図に存在しない
地元の新聞には、「住所不詳の土地で変死体」とだけ記されていた。
そう、そこはまだ正式な地番が与えられていない仮換地区域。
住所が存在しないというだけで、事件処理は後手に回るのが常だった。
サトウさんの冷静な分析
「仮換地って、言ってしまえば“仮想の住所”ですよね」
パソコンの画面を叩きながら、サトウさんが淡々と説明を加える。
「つまり、犯人は“存在しない場所”に死体を運び込めば、調査そのものを遅らせられると考えたんでしょう」
現地調査と測量図の矛盾
私は久しぶりにスーツを着て現地へ向かった。測量図を片手に土地の境界を確認する。
しかし、杭の位置と図面が微妙にずれていた。ほんの数十センチの誤差。
けれど、元野球部の感覚で「これはわざとだ」と直感が走った。
なぜか登記簿に残る旧地主の名前
仮換地の通知は出ているはずなのに、登記簿には旧地主の名前がそのままだった。
しかも、その地主はすでに死亡している。というより、亡くなったとされていた。
しかし、それを確認する戸籍は存在しなかった。どこかおかしい。
「仮」だからこそ消せたもの
登記が仮だからこそ、所有者の移転も、死亡の事実も、役所が完全に把握していなかった。
つまり、登記制度の“スキマ”をついた犯罪だったのだ。
おそらく犯人は、土地の真の所有者である父親をすでに殺し、仮換地通知と家を利用して死体を“隠した”。
新旧の地番が交差する境界線
「ここですね、殺人が行われたのは」
警察官が指したのは、新地番の仮図ではA12、旧地番では乙231番地。
だがその間の杭は、誰かの手で意図的に抜かれ、別の場所に打ち直されていた。
嘘をついていたのは依頼人の方だった
事務所に戻った私は、サトウさんの目配せを受けてPC画面を見る。
「この依頼人、仮換地の申請者でもなんでもありません。そもそも相続登記すらしてない」
なるほど、地番なき土地は、彼にとって隠し場所として最適だったのだ。
土地の仮換地を悪用した完全犯罪
誰のものでもない、だが誰かのものになる予定だった土地。
そこに“遺体”を置けば、それはどこの事件にもならない。
仮換地という制度が、完璧な密室と化した瞬間だった。
サトウさんの一言で全てが繋がった
「そういえば先生、この依頼人、地元で“換地マニア”って呼ばれてたそうですよ」
「なにそれ、新手の怪盗キッドか?」
私は思わず吹き出しながらも、背筋が寒くなった。犯人は制度の隙間を熟知していた。
シンドウが見抜いた決定的な矛盾
「この登記申請書、添付されてる印鑑証明が古すぎますよ」
サトウさんに見せた申請書には、十年前の日付があった。
「死人の印鑑証明を使って登記を進めようとした。つまり、偽装相続だ」
真犯人が残した最後の印鑑証明
依頼人はすぐに逮捕された。決め手は、被相続人の“生きていた証拠”が存在しなかったこと。
土地というのは人のものでもあるが、紙と制度の世界でもある。
それを操ろうとした男は、自ら仮換地の闇に沈んだのだった。