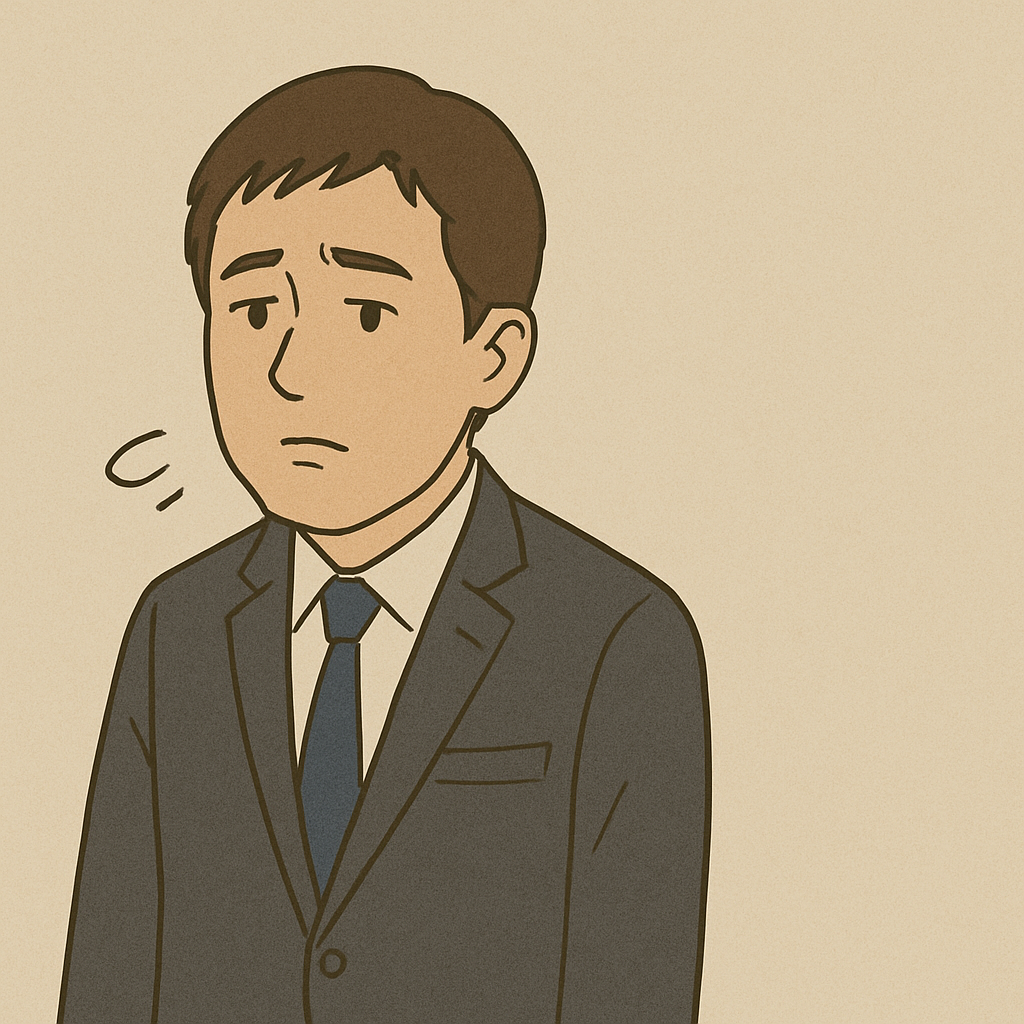依頼人は無口な老婦人
朝から雨がしとしと降っていた。事務所のガラス扉を開けたのは、黒い帽子を深くかぶった老婦人だった。細い手には、革の封筒が握られている。
「遺言書を見てほしいの」とだけ呟いて、それ以上は何も語らなかった。だが、その視線は強く、何かを訴えているようだった。
押印された遺言書に違和感
老婦人から差し出された封筒には、見慣れた様式の遺言書が入っていた。だが、最後の署名と印影を見た瞬間、妙な違和感が胸に広がった。
「これは……」思わず声に出しそうになった。たしかに見た目は正しい。しかし、何かが腑に落ちないのだ。まるで“完璧すぎる”印象だった。
サトウさんの冷静な観察
「この印影、少し変ですね」サトウさんが覗き込んで言った。彼女の目は鋭い。僕が見落としたものを一瞬で見抜く。
「上下が微妙にずれてます。たぶん、印鑑を捺したあとに押し直してますね。これは練習した印影ですよ、シンドウさん」
筆跡と印影の矛盾
さらに調べていくと、筆跡と印影の不一致が浮かび上がってきた。名前の文字は老婦人の筆跡によく似ているが、力の入り具合がどこか違う。
まるで、誰かが意図的に“それらしく”書いたように見えた。サザエさんの波平のような達筆さではなく、ワカメが真似て書いたような違和感だ。
印影に潜む嘘の痕跡
印鑑登録証明書を取り寄せて照合してみると、違いは明らかだった。本物の印影には独特の擦れがあり、朱肉のにじみ方も異なる。
捺印の日付と老婦人の入院日が一致しているはずなのに、記録上ではその日は集中治療室にいたことが分かった。
印泥の鮮度が語るもの
「これは新しい印泥ですね。変色も乾きもない」サトウさんが言った。遺言書が“あの日”に作られたものでないことは明白だった。
やれやれ、、、また誰かが法を“道具”として使おうとしたらしい。僕の仕事は、そんな小さな嘘を拾い集めることだ。
口を開かない相続人
連絡を受けて現れたのは、中年の男だった。老婦人の甥だという。彼は終始うつむき、質問にはほとんど答えなかった。
だが、彼の視線は落ち着きなく泳いでいた。まるで「バレることはない」と自分に言い聞かせているような不自然さだった。
無反応の裏に隠された恐れ
「叔母は俺を可愛がっていたんです」そう言いながら、彼は何度も汗を拭った。その手が震えていたのを、サトウさんは見逃さなかった。
相続を受けられなくなることよりも、“何か”が露見することを恐れているようだった。その“何か”こそが、事件の鍵だった。
調査資料に現れた新たな証言
調べを進めるうちに、病院の看護記録にたどり着いた。遺言作成とされる日、老婦人は昏睡状態だったと記録されていた。
つまり、遺言書は誰かによって“代筆”され、印影も偽造された可能性が高いということだ。それはもう、ただの違和感では済まされない。
遺言書の作成を巡る不可解な動き
さらに奇妙なことに、遺言書の作成直後に、不動産の登記簿に動きがあった。まるで“その日”にすべてを終える前提で準備されていたように。
そこまで計算していたのなら、これはただの偽造ではない。完全な計画犯罪だった。
サトウさんの決め手
「決まりですね」サトウさんがパチンと指を鳴らした。「病院の記録、印影のズレ、筆跡の違和感。全部つながってます」
「でも証拠にはならない」と僕が呟くと、彼女はフッと笑った。「証拠は、依頼人の手の中にありますよ。彼女は最初から訴えてたんです」
本当に書かせたかった人は誰か
老婦人が封筒とともに持っていたもう一通の書面。それは、病室で書かれた自筆の手紙だった。達筆とは言えなかったが、想いはまっすぐだった。
「本当に残したかったのは、私の心です」その一行に、すべてが込められていた。
事件の終わりと新たな始まり
遺言書は無効とされ、代わりに意思能力を確認した上で、正式な書類が作成された。甥は黙ってその場を去った。抵抗もせずに。
雨は止み、事務所に少しだけ光が差し込んでいた。
サトウさんの塩対応に救われる
「シンドウさん、また情に流されましたね」サトウさんが冷たく言った。「でも……それでいいのかも」
「おまえがそう言うってことは、たぶん正解なんだろうな」僕は苦笑しながら、まだ乾ききらない印影をそっと見つめた。