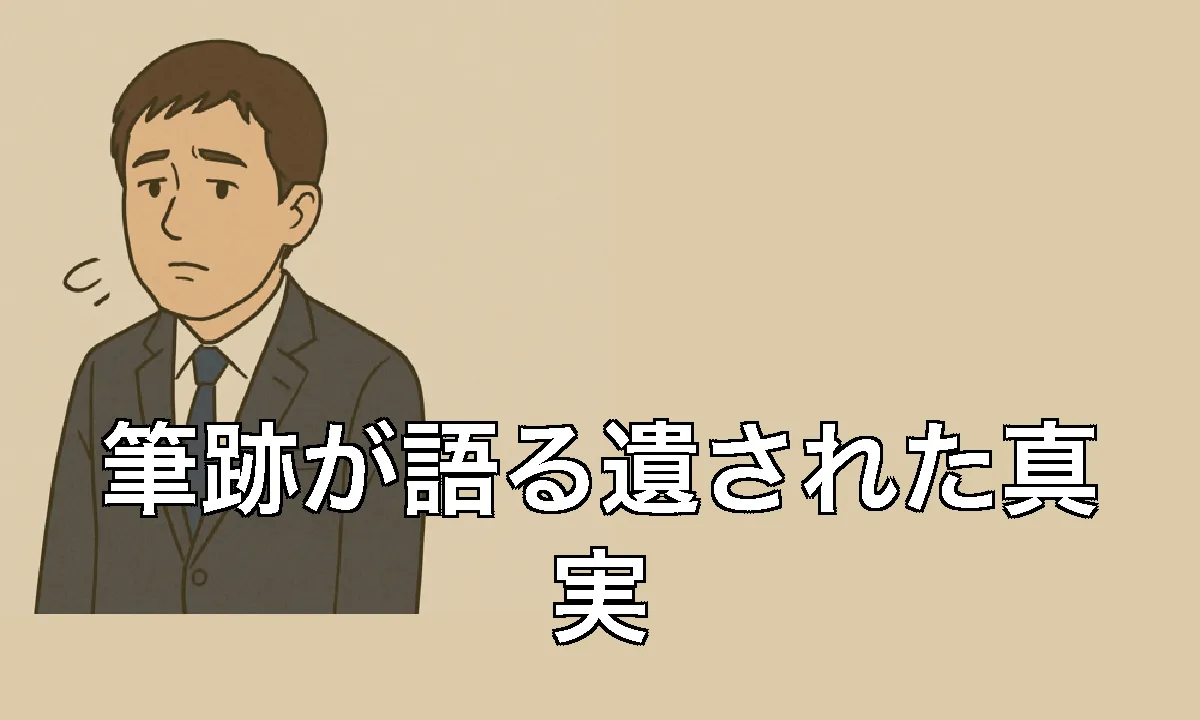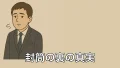ある朝届いた一通の手紙
机の上に、白い封筒がぽつんと置かれていた。差出人はなく、裏面にだけ不自然に歪んだ「感謝」とだけ書かれていた。僕はその字を見た瞬間、背中がざわっとした。
字の形が、なにかを訴えかけているように感じたのだ。普通の感謝ではない。まるで、最後のメッセージのように。
封筒の中には震える文字
封を切ると、細かく折られた便箋が現れた。震える筆跡で「これは私の遺言です」と書かれている。けれど、それが誰のものか、なぜ僕のところに届いたのかはわからなかった。
遺言とはいえ、正式な形式もない。司法書士として扱うには、あまりに素性が不明だった。
依頼者は沈黙を守る未亡人
後日、黒の喪服姿の女性が僕の事務所を訪れた。夫が亡くなり、遺言書が出てきたという。しかし、彼女はその存在を知らされていなかったという。
その遺言書は、先日の手紙と同じ筆跡だった。偶然の一致なのか、それとも。
司法書士の仕事は遺言書の検認
形式不備とはいえ、家裁で検認申立ては可能だ。ただ、内容があまりにも不自然だった。遺産をすべて弟に譲ると書かれていたが、故人は生前、弟と絶縁状態だったと聞いている。
「ちょっと待てよ」僕の中で、怪盗キッドのように一つの仮説が立ち上がった。
筆跡鑑定という落とし穴
筆跡は似ている。だが、同一人物が書いたとは限らない。人の筆跡は、感情や体調でも微妙に変わる。特に、死の間際ならなおさらだ。
筆跡鑑定はあくまで補助的手段。過信は禁物だ。
誰が書いたか分からない文書
それでも、どこか引っかかっていた。「感謝」という字の「し」が妙にねじれていたのだ。まるで、サザエさんのタマがひっかいたような曲線だった。
同じくねじれた「し」を、別の書類でも見たことがある気がする。
サトウさんの冷静な観察
「この字、確かに変ですね」とサトウさん。彼女は冷静に、机の奥から過去の遺産分割協議書を数枚引っ張り出した。
「この書類にサインしたときの筆跡と似てますよ。これ、亡くなったご主人が書いたとは思えません」
同一筆跡ではない可能性
並べて見比べると、確かに「感謝」の「し」は別人だった。どうやら、「遺言」を書いたのは本人ではないらしい。
ということは、これは偽造。しかも、身内の誰かがやった可能性がある。
遺言と不一致の財産記載
遺言には記されていない不動産があった。それは、登記簿を調べなければ分からないような細かい名義だった。
そんな情報を知っているのは、限られた人物だけだ。
見過ごされた土地の登記簿
僕は旧所有権の履歴を洗い出してみた。すると、つい最近の贈与で名義変更されていたことがわかった。
その申請書の筆跡こそ、問題の手紙と同じものだった。
亡くなった夫の秘密
亡くなった夫には、実は一度認知を拒否した息子がいたことがわかった。件の「弟」は、その人物だった。
しかも、数年前に失踪している。
もう一通の手紙の存在
未亡人は震えながら、机の引き出しからもう一通の手紙を出した。それは、真正の遺言書だった。封印された公証人の印が押されていた。
「なんで、これを最初に見せなかったんですか」
やれやれ、、、また一波乱か
僕は頭をかきながら、サトウさんに目をやった。彼女は無言で腕を組んでいる。すべて読んでいたかのような表情だ。
まったく、名探偵コナンもびっくりの展開だ。
筆跡から浮かび上がる共犯者
贈与登記の申請書を書いたのは、未亡人の甥だった。司法書士の知識はなかったが、筆跡を真似て書いた痕跡があった。
どうやら、未亡人の指示で書かせたようだ。理由は――生活苦だった。
登記申請書に潜む罠
登記の提出日と死亡日が微妙にずれていた。そのせいで、意思能力の有無を問われる立場になっていた。
「これは無効になります」僕はその場で結論を告げた。
偽造を裏付ける文体の違い
公正証書遺言は明確だった。対して、偽造された手紙は主語と述語の整合が取れていなかった。
人は、真似はできても本物にはなれないのだ。
サザエさんのタマのような足跡
最後の証拠は、封筒に残された猫の毛だった。甥が飼っていた猫のもので、封筒にくっついていたのだ。
「サザエさんのタマより分かりやすいな、、、」思わず口にしてしまった。
ポストに残された謎の封印
近所の監視カメラには、甥がポストに封筒を投函する姿が映っていた。未亡人の後ろでうつむく彼の姿が、少しだけ寂しげだった。
「罪は罪だが、情状酌量の余地はある」僕はそう思った。
司法書士の直感と論理
今回の事件も、直感と書類の整合性の勝利だった。人は嘘をつけるが、筆跡は嘘をつけない。
書かれた文字には、その人の人生がにじみ出るのだ。
過去の事件と符号する手口
似たような事件を昔扱ったことがあった。そこでも、遺言書の偽造があったが、やはり筆跡がカギだった。
「歴史は繰り返す」と誰かが言っていたが、司法書士の世界でも同じらしい。
サトウさんの冷ややかな一言
「最初から私がやれば、もっと早く終わってましたよ」サトウさんの冷たい目が突き刺さる。
「やれやれ、、、俺は何だったんだよ」僕はため息をつきながら、背もたれに体を預けた。
「だから言ったでしょ」
彼女は椅子から立ち上がると、コーヒーメーカーに向かった。いつの間にか、雨が止んでいた。
カップに注がれる音だけが、静かに響いていた。
真相の鍵は癖字の「し」
あの「し」の字がなければ、きっと見逃していた。あの文字に込められた偽りが、真実へとつながる鍵になった。
司法書士の仕事は、字を見ることから始まる。見えない真実を炙り出す、それが僕の役目だ。
被相続人の筆跡を裏付ける証拠
最終的に、被相続人が公証役場で自筆した証拠が提出された。すべての争いは、その一枚で静かに終わった。
紙一枚で、人生が守られることもある。だからこそ、字は重い。
偽造したのは誰だったのか
甥は正直に罪を認めた。未亡人は、全ての責任を背負う覚悟を見せた。真実は重く、けれど必要なものであった。
僕ら司法書士は、誰かの真実に寄り添う仕事なのかもしれない。
追い詰められる遺族の一人
生活苦と孤独が招いた偽造。それでも、法の下では罰は避けられない。
けれど、その涙が本物であれば、少しだけ、明るい未来に繋がるのかもしれない。
司法書士が届けた最後の真実
公正証書遺言が開封され、すべてが正される。誰にも恨みを残さず、穏やかに終えられた遺産分割。
それは、故人が望んでいた形にきっと近かった。
公証役場の記録がすべてを証明する
人が嘘をついても、公証記録は嘘をつかない。あの日の記録が、未来を守った。
筆跡とは、ある意味で魂の証拠なのだ。
静かに終わる事件の余韻
雨上がりの午後、僕は事務所の窓を開けた。蝉の声が戻ってきていた。
一件落着。それでも、また何か起きるんだろうな。そんな予感が、夏の空に溶けていった。
一枚の手紙が守った相続の秩序
偽造された手紙ではなく、本物の遺言がすべてを救った。最後に勝ったのは、故人の想いだった。
やれやれ、、、紙一枚の重みを、また思い知った気がする。