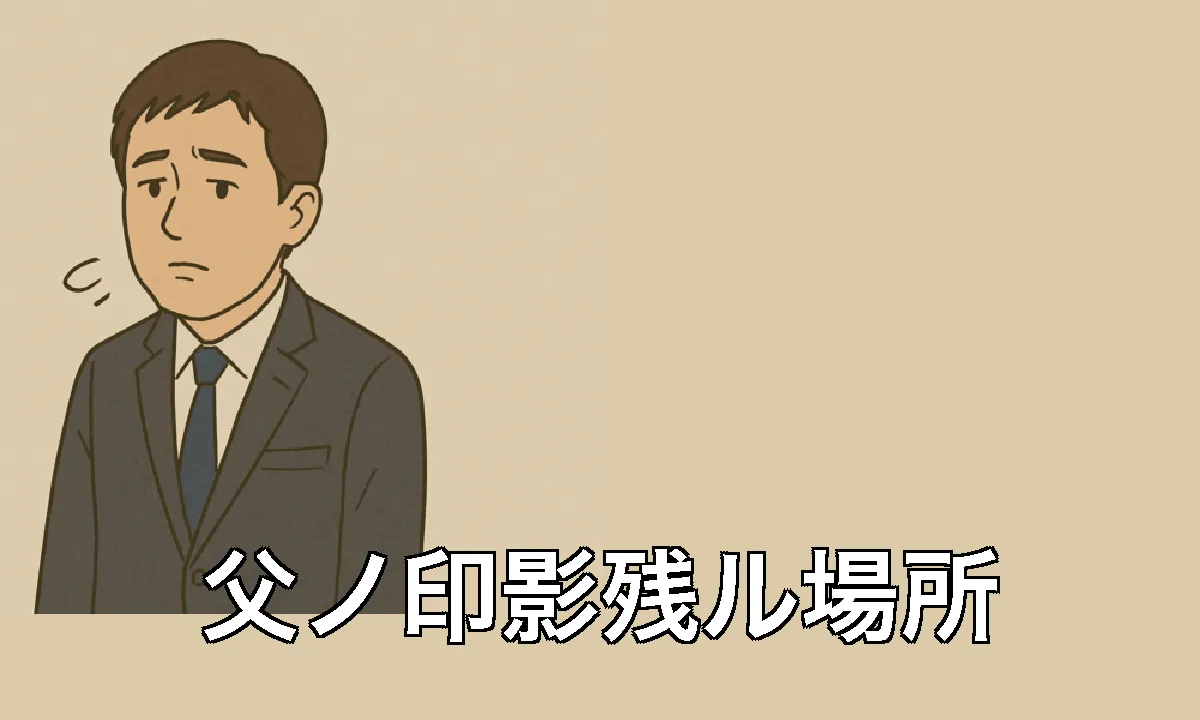朝の登記相談にて
登記相談に来た老婦人が手にしていたのは、古びた印鑑登録証だった。
役所帰りにふらりと寄ったというその女性は、小さな封筒から黄ばんだ印鑑登録証を取り出した。
「これ、亡くなった主人のものだと思うんですけど…なんか、違和感があって」
目を細めながら彼女は言った。私はその紙片を受け取り、目を凝らした。
父の名と異なる印影
登録証にある名前と、印影の持ち主に違和感を覚える。
確かに氏名は亡くなったというご主人のものだった。だが、印影に違和感があった。
父親の印鑑って、なんというか、時代の風格みたいなものが出るのに、妙に現代的なフォントで…。
まるで市販の三文判のような、そんな軽さが鼻についた。
サトウさんの冷静な観察
「これは…偽造の線もありますね」サトウの推理が動き出す。
「シンドウさん、これ、使用されていた印鑑とは全然違うみたいです。
以前の遺産分割協議書に押されていたのと照合しても、一致しません」
塩対応の事務員、サトウさんが、冷たくも鋭く指摘する。
登録証の交付日
役所に保存された交付記録から見えてきた、不自然な日付のズレ。
役所に照会をかけた交付日が奇妙だった。なんと、被相続人が亡くなったはずの翌週になっている。
死亡届が出された日から考えると、発行自体が不可能なはずだ。
つまり、誰かが死亡後に、本人になりすまして印鑑登録を行ったことになる。
三年前の失踪と一致
老婦人の夫が亡くなった時期と、交付日が奇妙に重なっていた。
「ちょうどその頃、主人の弟が急に家に出入りするようになったんです」
老婦人の言葉に私はピンと来た。相続を巡って、親族間で密かな火花が散っていた気配。
弟が代理人として振る舞い、何かを企んでいた可能性がある。
書類に残された父の癖字
実家に保管されていた古い遺産分割協議書の筆跡が決め手となる。
印鑑だけでなく、協議書に添えられた署名の筆跡にも注目した。
老婦人が大切に保管していた書類には、確かに「本人直筆」と記された署名が。
ところが、以前私が手続きをした際の資料にある署名と、筆跡が完全に異なっていた。
偽造された相続放棄
誰かが父に成りすまし、密かに登記を操作していた可能性が濃厚に。
つまりこういうことだ。亡くなった被相続人になりすました人物が印鑑登録をし、
それを使って無効な協議書を作成し、相続放棄の登記を偽装したのだ。
そしてその背後にいたのが、遺産に固執する義弟というわけだ。
登録証の本当の持ち主
印影の持ち主は、亡くなった父ではなかった。別人の影が浮かぶ。
市販の印鑑だったことが決め手となった。役所には登録印の写真が残っている。
照合の結果、なんと義弟が同型の印鑑を過去に使用していた記録が判明。
つまり、義弟が登録証を偽造した張本人である可能性が極めて高くなった。
実印登録と法定相続のからくり
司法書士としての知識で、正規の手続きと偽装の構造を分解していく。
印鑑登録証の提示だけでは、本人確認としては不十分なことがある。
だからこそ、公的証明との照合が必要になるのだ。私は法定相続情報一覧図を元に、
本来の相続関係と、協議書の矛盾を精密に指摘し、偽装を暴いた。
やれやれ、、、ようやくたどり着いた真実
元野球部らしく粘り勝ちで、登録証の真実に辿りつく。
「やれやれ、、、まるでナイター延長戦みたいだったな」
疲れた頭を掻きながら、私はソファに腰を落とした。
結果的に、義弟による相続財産の不正取得は未遂に終わり、再協議が開始された。
登録台帳の消せない記録
過去の記録は改ざんできない、それが司法の正義だと信じて。
登録台帳に一度記された情報は、永久に残る。
どれほど巧妙な偽装も、いつかは誰かの目に留まり、解かれていく。
そしてその「誰か」は、意外と地味な司法書士だったりするものなのだ。
サトウさんの無言の労い
「コーヒーでも淹れますか?」塩対応の中にある、かすかな優しさ。
事件がひと段落した頃、サトウさんがぽつりと呟いた。
「コーヒーでも淹れますか?」まるでサザエさんの波平がうなずくようなテンポで。
私は何も言わずに頷いた。塩味の中にほのかな甘みがあった。