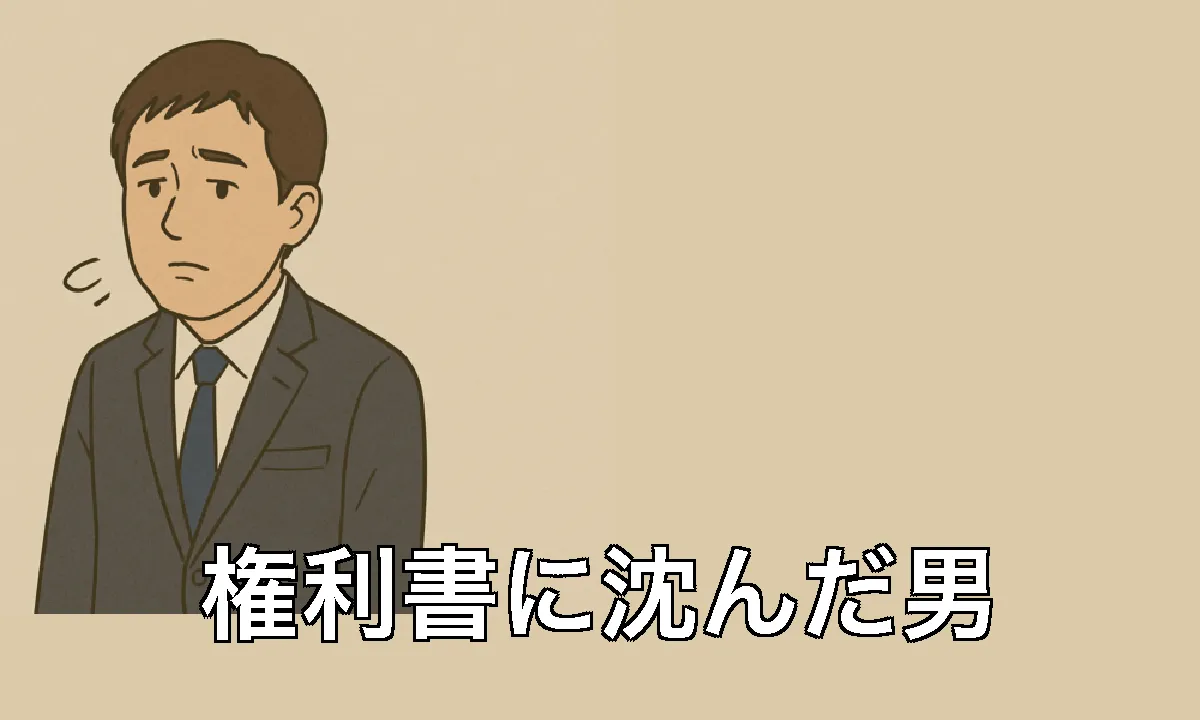朝の事務所に届いた封筒
「シンドウ司法書士事務所」という文字が印刷されたポストに、分厚い茶封筒がひとつ無造作に投げ込まれていた。差出人欄には何も書かれておらず、妙にしっとりと湿った感触があった。普段ならゴミと間違えてサトウさんに叱られるところだが、封を開けてみると中からは見覚えのある書式の権利書が一枚、ふわりと現れた。
差出人不明の分厚い茶封筒
誰が、なんのために、こんなものを送ってきたのか。思わず眉をひそめながら書類の端を撫でる。封筒には消印もなく、宛名すら雑に書かれているだけ。差出人不明の郵送物など、ろくなことがない。経験上、それは大抵トラブルの香りだ。
中に入っていた一枚の権利書
どう見ても古いフォーマットの登記済証。しかも「甲区一番」の所有者名義が、最近どこかで見た名前と一致していた。だが、不思議なのは、その人物がすでに亡くなっていること。そして、この土地がまだ売買された形跡がないことだった。
消えた依頼人と未登記の真相
前日に来所した、痩せぎすの中年男性のことを思い出す。彼は、遺言の相談だとだけ言い残し、身分証も出さずに立ち去った。あの時の妙な違和感が、今になって首元をじわじわと締めてくるようだった。
電話がつながらない理由
控えていた番号にかけるも、コール音すら鳴らない。どこかで聞いたような虚ろな応答音だけが響く。まるでその番号が最初から存在していなかったかのような感覚に襲われた。サトウさんに相談すると、いつものように淡々と「偽装でしょうね」と一蹴された。
過去の登記記録との矛盾
法務局の端末で確認した登記簿には、確かに男が話していた地番が存在した。ただし、名義は別人。さらに、その人物は登記上、今も生存していることになっていた。だが現実には、新聞の片隅に載った訃報記事で、既に亡くなっていたはずだ。
サトウさんの冷静な分析
「この権利書、印刷時のインクが平成じゃなくて昭和ですよ」と、パソコンのモニターから一切視線を外さずに告げるサトウさん。その一言で、事務所に流れる空気が変わった。まるでアニメの名探偵が「それ、前から気になってたんですけど」と呟いた時のような、変な高揚感があった。
書式の違いが示す落とし穴
平成の様式にはあるはずの細かな防犯加工が、この書類にはない。インクの染み具合も、あきらかに手作業のようだった。つまりこれは——誰かが意図的に古い形式を模して作った偽造書類、という可能性が浮かび上がった。
封筒に残された古い印影
茶封筒の内側にわずかに残っていた赤い印影。それは朱肉ではなく、血のような色に見えた。「不動産ミステリーなら、ここで突然死体が出てくるんですけどね」と呟いたつもりがサトウさんには聞こえていたらしく、「やめてください」と冷たく言われた。
権利書の出所をたどる
ここから先は、地味で地道な作業だった。公図を片手に法務局を数件回り、資料を精査しては照合を繰り返す。まるで古い推理漫画のように、ページをめくるたびに新しい矛盾が現れ、答えは遠ざかっていくばかりだった。
法務局の端末に現れた異常
端末に表示された謄本のデータの中に、奇妙な履歴があった。誰にも知られず、一度だけ名義が変更され、すぐに戻されたような痕跡。履歴自体は抹消されているが、操作ログには削除命令の記録が残っていた。
過去に売買された痕跡のない土地
地番の履歴をたどると、売買の記録はなかったが、相続による名義変更が繰り返されていた。問題は、その相続の中に、存在しない戸籍が一つ紛れ込んでいたことだ。つまり——誰かが架空の相続人を作り上げていた。
男の正体と別名義の謎
ようやく見えてきた全体像は、驚くべきものだった。依頼人の男は、登記簿上存在していたが、実際には数年前に失踪扱いになっていた人物の弟だった。そして、兄の死後、身分を乗っ取って土地を手に入れようとしていた。
遺言書に書かれていた知らない名前
茶封筒の底から出てきたもう一枚の書類——それは雑に書かれた自筆証書遺言だった。しかし、その中に書かれた受遺者の名前は、登記名義人でもなく、依頼人の名前でもない。これはダミーだったのだ。男は混乱させるために偽の遺言を添えていた。
司法書士としての違和感
書類を読み込めば読み込むほど、ぼくの中に司法書士としての違和感が募っていった。こんなに不自然な名義変更の準備をした人間が、なぜ司法書士を頼るのか? それは、司法書士に「正当な形で処理された証拠」を出してもらうためだったのだ。
不動産業者との接点
調べを進める中で、かつて失踪した名義人が契約していた不動産業者にたどり着いた。古アパートの名義もその男のものだったが、すでに取り壊されていた。しかし、売買契約書は一部が保管されており、そこに記された筆跡が、依頼人のものと一致していた。
古アパートの売買契約書
そこには、壊されたはずのアパートの売買契約書が残されていた。捺印もある。ただし、その日付は依頼人の証言とは食い違っていた。さらに、契約時に立ち会った人物の証言で、男が名義人のふりをしていたことが明るみに出た。
契約書にないはずのサイン
コピーされた契約書の裏面に、消えかかったサインが浮かんでいた。よく見ると、そこには現在の依頼人の本名が書かれていた。名義を偽っていたことを自ら証明する形になっていたのだ。
やれやれと言いたくなる展開
ここまで来てようやく全てがつながったが、もはや疲労感の方が勝っていた。「やれやれ、、、」と呟いたぼくに、サトウさんが容赦なく「これ、法務局に報告してください」と書類の束を押しつけてきた。正義って、地味で重たい。
名義貸しの闇と登記の罠
事件の本質は、名義貸しと偽装登記の悪用だった。形式だけ整えても、中身が真実とは限らない。登記というものが持つ「事実に見える嘘」が、今回の事件を可能にしていた。司法書士でなければ気づけなかったかもしれない。
誰が得をして誰が損をするのか
一番得をするのは、不動産を手に入れようとした依頼人。そして、一番損をするのは、失踪した兄の戸籍を信じた人々だ。名義だけで真実が決まるなら、法の意味は崩れてしまう。そう考えると、背筋が寒くなった。
決め手となったひとこと
事務所に報告に来た不動産業者が放った一言が、すべての点を線につなげた。「あの印鑑、あの人のじゃないです。ずっとシャチハタだったんですよ」。その一言で、男の偽装が決定的となった。こんな小さな違和感が、最後には真実を暴く鍵になる。
「この印鑑はうちのじゃない」
後日、依頼人を警察に引き渡したあと、亡くなった兄の妻がそう口にした。彼の印影を覚えていたのは彼女だけだった。過去の人間関係や些細な記憶が、こうして真実を支えることもあるのだ。
証拠となった昭和の登記簿
最後の証拠となったのは、古い昭和時代の登記簿。そこには手書きで細かく記された筆跡と、現在のものとは違う印影が残されていた。改ざんも偽造もできない、唯一無二の記録だった。
事件の幕引きと司法書士の仕事
事件は解決したが、どこか虚しさが残る。法の裏をかいた犯罪に立ち向かうのが司法書士の役目だとすれば、ぼくらの仕事はまだまだ続くのだろう。事務所に戻っても、書類の山は減っていなかった。
男はどこへ消えたのか
警察に引き渡された男は、一切の供述を拒んだまま、弁護士を呼んで沈黙を貫いた。真実の全貌は、結局語られなかった。ただ、彼の行動の動機は、金でも恨みでもなく「逃げるための手段」だったのかもしれない。
責任の重さと役目の意味
登記は、ただの書類の手続きじゃない。人の生活と財産、そして命までもがそこに乗っている。今回の事件で、司法書士としての責任の重さをあらためて感じさせられた。
サトウさんの塩対応に救われる
事件後、ぼくがぼんやりと事務所のソファで伸びていると、サトウさんがコーヒーを差し出してくれた。口数は少ないが、それが彼女なりの労いなのだろう。「お疲れさまです」と一言だけ。塩対応だが、沁みる。
冷たいけれど的確な一言
「でも、最初から怪しいって言いましたよね?」とサトウさん。確かにそうだ。結局ぼくは彼女の言葉に導かれていただけだったのかもしれない。やれやれ、、、次の事件が起きないことを祈るばかりだ。
今日も机の上は書類だらけ
晴れた日の午後。静かな事務所。コーヒーの香りの中、ぼくは次の相談者を迎える準備をしていた。そう、仕事はまだまだ終わらない。司法書士としての日常は、今日も続いていく。