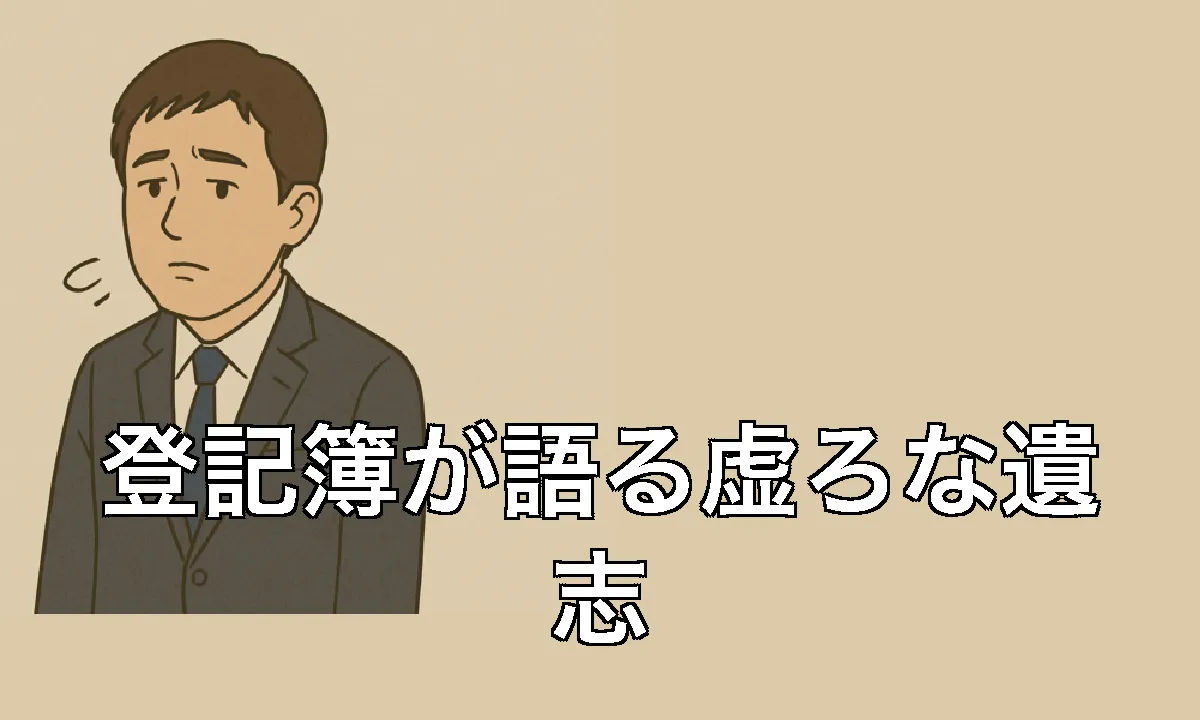朝一番の違和感
「先生、朝一で相談が入ってます」 サトウさんが無表情に伝える。いやな予感しかしない。こんな時に限ってコーヒーが薄い。 依頼人は70代の女性で、夫が亡くなったばかりとのことだったが、様子がどこか変だった。
依頼人の足取りと重たい空気
話の要点が見えず、亡夫の遺言書について聞いても目を伏せるばかり。 「遺言があるのか、ないのか、それだけでも…」と尋ねると、ようやく「ありました、たぶん」と返ってきた。 なんだそのあいまいさは、と内心でツッコミながら、ふと彼女の足元に視線を移した。まるで砂を噛むような歩き方だった。
遺言書と登記簿の食い違い
後日、持ち込まれた遺言書は自筆のようだったが、どうにも筆跡が怪しい。 しかも、不動産の表示が登記簿と微妙に違っている。「昭和三十七年地図に基づく」と書かれていたが、今は地番変更されている。 誰かが古い情報を見て書いた? それとも、意図的か。
相続登記に潜む疑問
「全部法定相続じゃないんですか?」とサトウさんが、ふと漏らす。 そうだ、遺言書には相続人のうち一人だけにすべてを相続させるとあったが、その理由が見当たらない。 しかもその指定された相続人、三男の名前が住民票に見当たらないのだ。
筆跡鑑定の必要性
古くからの顧客に紹介された鑑定士に依頼し、遺言書の筆跡を照合する。 結果は「類似性はあるが、異なる可能性もある」と煮え切らない答え。まるで「タラちゃんがイクラちゃんに似てる」レベルの曖昧さだ。 だが、引っかかったのは「住所の書き方」。漢数字を使うクセが違っていた。
不自然な評価証明書
固定資産評価証明書の発行日が、死亡日の翌日になっていた。 普通、そんなスピードで動けるだろうか? むしろ、事前に準備していたように見える。 しかも提出元の役所は、亡夫が生前通っていた地とは異なる支所だった。
訪問した空き家の違和感
物件の確認のため、該当の土地を訪れた。 そこには使われていない空き家がぽつんと佇んでいた。郵便受けには数ヶ月分のチラシ。 玄関の前でサトウさんが言った。「ここ、売買された形跡ないですよ」
閉ざされた仏間と未開封の手紙
無理を言って鍵を開けてもらい中に入ると、仏間に埃をかぶった仏壇があった。 手紙が一通、遺影の前に置かれていた。封は切られていない。 宛名は長男。三男の名はどこにもなかった。
ご近所さんが語る生前の故人
近くの農家の老夫婦が語るには、「あの家の旦那さん、最期の方は認知が出ててな…」とのこと。 「三男さんは全然来とらんかったよ。よく世話してたのは長男さんとその奥さんだった」とも。 これで遺言書の内容にさらなる疑問符がついた。
サトウさんの冷静な分析
「遺言が偽造されたとして、問題は誰が得をするかです」 サトウさんはいつもの調子で言う。こちらが徹夜明けでヨレヨレでも、彼女の冷静さは変わらない。 調査を進めると、三男の妻が登記申請人となっていることが判明した。
名寄帳から見えた不審な動き
市役所で名寄帳を閲覧すると、三男名義で同じ町内に新築住宅の取得がされていた。 申請日は遺言書の日付の一週間後。登記簿の移転とタイミングが一致している。 つまり、相続を見越して動いていた可能性がある。
固定資産税の通知に残る手がかり
翌年分の納税通知書は、長男宛に送られていた形跡があった。 つまり、固定資産課では長男を正当な相続人と認識していたということ。 それに反して登記が動いていたとなると…。
真実へと繋がる旧姓の記録
除籍謄本をたどると、三男の妻は旧姓でかつて同じ町内の司法書士事務所に勤めていたことが判明。 これは見過ごせない。どこかで登記書類に手を加えることができた可能性がある。 それを聞いたとき、サトウさんは一言、「やっぱり、ですね」とだけ呟いた。
住民票除票が示す意外な関係
さらに調べると、亡夫と三男の妻が、かつて同じ住所に一時期だけ同居していた記録が出てきた。 その時期、三男自身は別の県で単身赴任中だったはずだ。 まさか、そこで何かあったのでは?
かすれた除籍謄本の裏にあったもの
古い除籍謄本の裏に、メモ書きが鉛筆で残されていた。 「最後は長男に…」と読める文字。 誰かがこの意志を無視したのか、それとも遺言の差し替えがあったのか。
忍び寄る偽装の気配
ここまできて、ようやく全体像が見えてきた。 鍵は三男の妻。そして彼女がかつて勤めていた事務所。 「これは…こっち側の人間じゃないとできないやり方ですね」とサトウさん。
登記識別情報の偽造疑惑
登記済権利証ではなく、識別情報で申請されていたことが気になっていた。 識別情報通知書のコピーを取り寄せると、フォーマットが旧式で偽造の可能性が出てきた。 かつての同僚に依頼して、司法書士会に匿名通報を依頼する。
印鑑証明書の発行日と謎の委任状
委任状の筆跡も、遺言書と酷似していた。しかも印鑑証明書の発行日が前倒しで取得されていた。 「誰かが、計画的にやったってことか」 サトウさんはうなずき、ボソッと「やれやれ、、、」とつぶやいた。珍しいことだ。
決定打となる供述
元同僚の司法書士から、「三男の妻が何度か“亡くなったらよろしく”と言ってた」との証言が得られた。 軽く聞き流していたが、今思えばそれが伏線だった。 すぐに関係者に照会書を送る。
元職員の証言で明かされた経緯
その元職員が語ったのは、三男の妻が自作した文書を「相談」という名目で何度も見せていたこと。 「司法書士さん、こんな書き方で合ってますか?」 その内容は、今回の遺言書と酷似していた。
介護記録に残された本人の声
介護施設の記録に「家は長男に任せたい」と書かれていたメモが見つかった。 本人の直筆、日付も死亡の数週間前。 これが真の遺志であると考えるべきだった。
やれやれ、、、最後の詰め
申立てを通じて、遺言の有効性を争う民事訴訟が提起された。 三男側は強気だったが、証拠の積み重ねは揺るぎなかった。 「先生、これでいいですか?」とサトウさん。ええ、ようやく一息つけそうです。
駆け込みで登記申請された理由
三男は、父の死を受けて即日申請する準備をしていた。 通常の相続登記ではありえないスピードだ。 それが逆に、動機と手口を明るみにした。
本当の相続人が語った覚悟
長男は、「父の意志を守れてよかった」と静かに涙した。 本来なら争うつもりはなかったという。 だが、あまりに不自然な動きに、胸騒ぎがしたという。
事件の真相と意外な結末
三男の妻は文書偽造と不正登記の容疑で告発され、司法書士会でも厳しい処分が下された。 やれやれ、、、まったく、他人事じゃない。 今回の件は、誰にでも起こりうる落とし穴だ。
不正登記の動機と人間の哀しさ
金か、承認欲求か、それとも親への執着か。 動機は複雑だったが、結果はすべてを壊した。 法の力だけでは救えない哀しさが、そこに残った。
サトウさんが見せた一瞬の笑み
事務所に戻ると、サトウさんが珍しくコーヒーをいれてくれた。 「一件落着ですね」そう言って、かすかに笑った。 「そうだね、やれやれ、、、」僕も力なく笑った。
登記簿が照らすもの
不動産の登記簿は、ただの法的記録ではない。 そこに刻まれるのは、人の思惑と歴史と、時に罪だ。 僕ら司法書士は、その裏側を知り、関わってしまう。
司法書士としての責任
印鑑ひとつ、署名ひとつに、どれだけの意味があるか。 それを知っているからこそ、慎重でなければならない。 僕たちの仕事は、裏切らないことだ。
「正しさ」とは何かを問いかける
正義とは何か。法とは何か。 今回の件で、それをまた痛感した。 でも、たぶん――答えは出ない。それでも進むしかない。