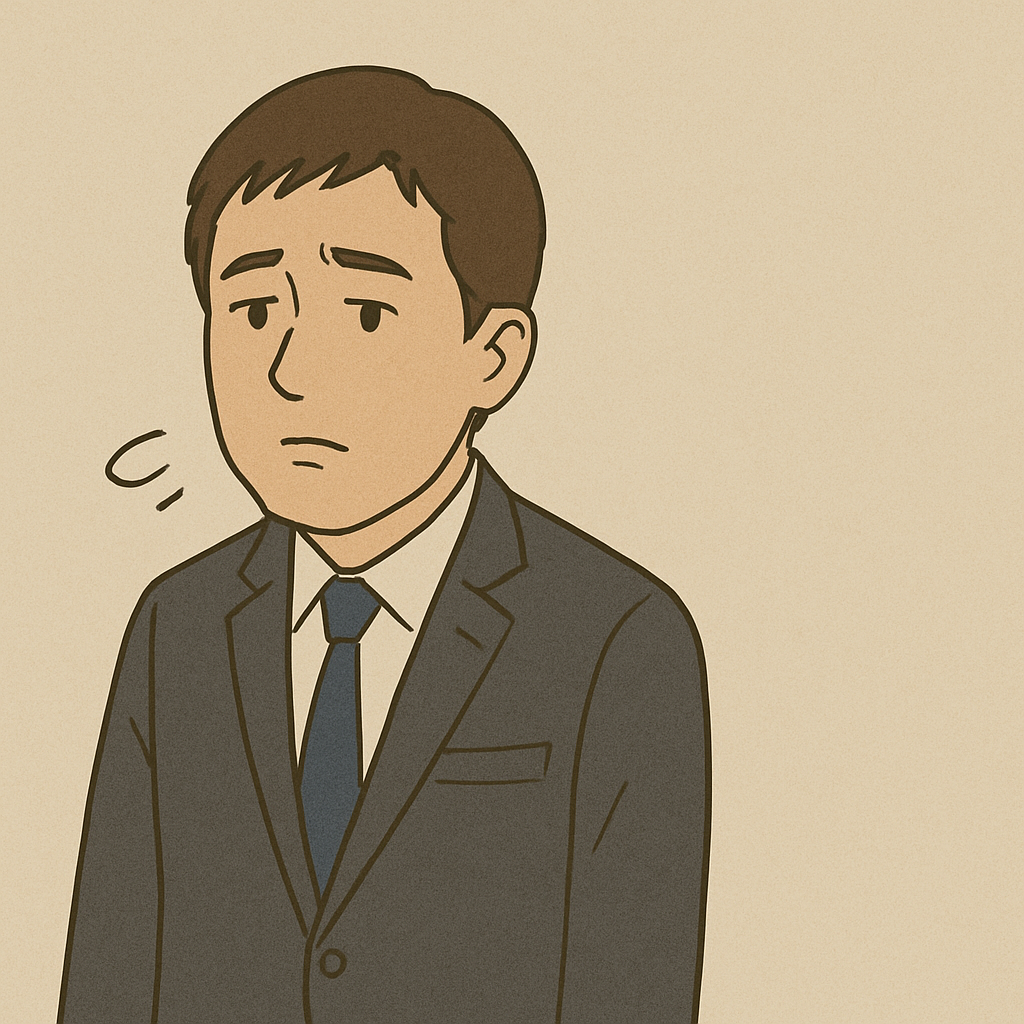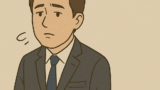事務所に届いた一枚の紙
朝のコーヒーがまだ冷めきらないうちに、郵便受けに差し込まれた一通の封筒。白無地に細い万年筆のような筆跡で、僕の事務所宛に送られていた。差出人名はなかったが、嫌な予感というのは、たいてい当たる。
中から出てきたのは、遺言書だった。日付は数日前。つい最近亡くなったばかりの男性、川名という名が記されている。その場にいたサトウさんは、何も言わずに腕を組んで黙読していた。
見覚えのない封筒の差出人
普通、遺言書というのは公正証書として残されるものだ。それがこのように一筆書きの形で、封筒に入って郵送されてくるとは、あまりに妙だった。しかも差出人不明。僕の中の何かがうずいた。
「これ、誰が送ってきたんでしょうね」とサトウさんがぽつり。冷静な声に、いつものとおり僕は内心ビクッとする。「ま、まさか死者本人が…」という冗談を言いかけて、呆れた目で睨まれた。
手書きで記された遺言書
その遺言書には、川名家の不動産をすべて一人の女性に譲渡する旨が記されていた。だが、法的な体裁は整っていない。証人の署名もなく、筆跡もどこか素人くさい。
しかも奇妙なことに、「この家の庭の桜だけは誰にも切らせてはならない」と強調する文が入っていた。普通は財産の話で終わるものだが、情緒的すぎて違和感がある。サトウさんがまた無言で目を細めた。
依頼人は突然の死を遂げていた
川名は先週、バイク事故で死亡した。単独事故とされているが、天候は晴れ、道に異常はなかった。彼の死を「偶然」と言い切るには何かが足りないように思えた。
しかもこの遺言書が見つかったことで、残された親族が不信感を持ち始めた。「こんなものは父が書くはずがない」と息子は言った。だが、真実は紙の上では見えない。
死因は事故か自殺か
もしもこの遺言が偽造されたものだとしたら、それを送りつけた人物の意図は何か? 事故に見せかけた自殺? それとも遺言の効力をねじ曲げるための策略か?
「ミステリー漫画なら、このタイミングで“怪盗紳士”が現れるところですね」と僕がつぶやくと、サトウさんは「現実では郵送で偽造文書送る程度ですよ」とバッサリ切り捨てた。やれやれ、、、心が削れる。
遺族が疑問に思う一文
遺族の中でも、特に娘は「桜を切るな」の一文に驚いていた。というのも、その桜の木は昨年伐採されたばかりだったからだ。つまり、この遺言が最近書かれたものではない可能性が出てきた。
「ええと、それってつまり、去年以前の文書を今さら出してきたってことですか?」と僕が聞くと、「違います」とサトウさん。「“去年”にはもうこの木は無かった。それを知らない誰かが書いたということです」。
筆跡鑑定と不自然な曲線
ここで登場するのが、司法書士あるあるの地味な裏技、筆跡鑑定。とはいえ本格的なものではない。過去の契約書に残る文字と照合して、癖や特徴をざっと比べる。
すると、“桜”の文字に妙な特徴があった。川名本人が書くときのような、やわらかな筆運びではなく、緊張したような、力強すぎる線。「これは他人の字ですね」とサトウさんが断言した。
サトウさんの冷静な分析
「この筆跡、女性の書く癖に近いです」とサトウさんは言った。「たぶん、誰かが亡くなったあとで、遺言が必要だと考えて書いたのでしょう。でも、筆跡には性格が出ますから」
彼女の冷静な観察力にはいつもながら脱帽だ。元野球部の直感頼みの僕とは大違いだ。やれやれ、、、もう少し根性だけじゃなくて頭脳も鍛えておけばよかった。
ある特定の癖に隠された違和感
“譲渡”という文字の「渡」の部分。川名本人はいつも左払いを短くする癖があった。ところが今回のそれは、大きく長く書かれていた。しかも墨の濃さが途中で変わっている。
「たぶん途中で筆を置いたんでしょうね」とサトウさんが言った。「一気に書いたように見せて、ところどころ意図的に演出している感じがします。これは作られた“演出された遺言”です」
遺言に隠された第三の人物
依頼人の周辺を洗うと、財産を譲り受ける予定の女性が浮かび上がった。川名の元恋人で、十年以上前に一度だけ婚約までしたが破局したという。現在は多額の借金を抱えているらしい。
「その人が川名の死を聞いて、遺言を偽造して送ってきたと?」僕の問いに、サトウさんは頷いた。「たぶん、彼の死がチャンスだったんです。過去の関係を盾に、遺言の偽装で財産を奪おうとした」
筆跡と過去の借金問題の関係
調べてみると、その女性は消費者金融から数百万円単位の借金を抱え、返済に窮していた。タイミング的にも、川名の事故死直後に“彼の遺志”を装って送付された遺言が一致する。
証拠が揃い始めていた。残るは、この女性に直接話を聞くだけだった。「直接行くんですか?」と僕が尋ねると、「ええ、そういうのは元野球部の出番でしょう」とサトウさんが皮肉を込めて笑った。
疑惑の中心に浮かび上がる元恋人
彼女は一見すると落ち着いた雰囲気だったが、話すうちに声が上ずり始めた。遺言について聞くと、「私が預かっていたんです。彼が書いたから」と主張したが、証拠は逆を示していた。
最後には彼女自身の口から、「少しだけ書き足した」と自白がもれた。「少し」どころではない。丸ごと偽造だ。「偽造と詐欺未遂ですね」とサトウさんが淡々と告げると、女性はうなだれた。
暴かれる偽筆と動機
事件はその後、警察に引き継がれた。遺言書は無効とされ、相続は正式な手続きに基づいて行われることとなった。サトウさんが準備していた書類が、ようやく日の目を見ることになった。
ふと見ると、彼女が片付けながら小さく笑っていた。「なにかいいことでも?」と聞くと、「いえ、ちゃんとした書類はウソをつかないなと思って」と一言。やれやれ、、、本当に頼れる事務員だ。
遺された家族が選んだ結末
川名の家族は、元恋人に対して民事の損害賠償も請求する意向だという。しかし、それ以上に大事なのは、真実が明らかになったことだった。遺言は、死者の言葉であってはいけない。
僕は窓の外に目をやる。庭の桜は、すでに無くなっていた。その跡地に小さな石碑が立っていた。「真実は風に消えず」――きっと、そういうことなんだろう。