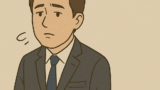供託通知書の不自然な日付
朝イチの事務所に届いた供託通知書。その日付は、明らかに今日の日付より三日前になっていた。しかも、差出人欄には懐かしい名前が記されていた。
まさかとは思ったが、俺の記憶が正しければ、それは五年前に別れたあの人の名前だった。失恋という言葉すら今や古傷にすぎないと思っていたが、胸の奥がわずかに疼く。
やれやれ、、、朝からこれは荷が重い。サザエさんなら波平がちゃぶ台をひっくり返すレベルの展開だ。
午前九時の来客とピンクの封筒
その日の九時、チャイムが鳴った。ドアを開けると、若い男性が一枚のピンクの封筒を差し出した。封筒には丁寧な筆跡で俺の名前が書かれていた。
「依頼者から預かってきました」と彼は言った。話を聞くと、弁護士事務所の補助者らしい。差し出し人は、やはり彼女だった。
それを見ていたサトウさんが呆れた顔をした。「まさか恋愛の供託ですか?お幸せに」と、塩対応のひと言を残してデスクに戻っていった。
供託された金銭と別れのメモ
封筒の中には、数万円の供託金とともに、一枚のメモが添えられていた。メモには「あなたに借りたままの気持ちを精算します」とだけ書かれていた。
金額は妙に中途半端だった。35,270円。どういう計算かまったく見当がつかない。だが、彼女らしい律義さがそこにはあった。
メモの裏には、以前ふたりで行った喫茶店の名前と日付が書かれていた。それが何を意味するのかはまだ分からなかった。
別れたはずの恋人からの手紙
供託通知書の他に、弁護士事務所からの送付書類もあった。その中に、直筆の手紙が封入されていた。手紙には、こう綴られていた。
「もしあなたがこの供託に気づいたなら、あの日の真実に気づくでしょう。私が残したものは、すべてあなたの選択に委ねます」
久々に見る彼女の筆跡は、心にしみるほど優しかったが、それ以上に意味深で、司法書士としての嗅覚がざわめいた。
破られた封筒の端に残る違和感
よく見ると、封筒の端が二重になっていた。破られた跡のように見えたが、実際には元から二重構造になっていたようだ。
その間から、もう一枚の紙片が見えた。そこには「戸籍附票の原本返却は不要です」と書かれていた。なぜそんなものが?
この供託は、単なる感情の清算ではなく、何か法的な仕掛けが絡んでいるようだった。
サトウさんの塩対応と名推理
「供託額、ぴったり婚姻届の印紙代と同額ですよ」とサトウさんがぼそりと言った。確かに、35,270円は収入印紙+諸経費のそれだった。
「たぶんこれ、結婚届を出すつもりだったって意味じゃないですか。あるいは、それを出さなかった理由の証明」
やれやれ、、、なんで俺より先に気づくんだよ。ほんと、サザエさんのカツオばりにこっちは空回りだ。
供託理由の欄に書かれた謎の数字
供託通知書には理由欄があり、そこには「番号527の件について」とだけ記載されていた。だが、当事務所で「527」という記録には心当たりがなかった。
過去の案件をすべて洗い出してみると、三年前の五月二十七日に、彼女の親族の名義変更を扱っていたことが判明した。
それは、彼女の祖母の相続登記で、彼女が唯一の相続人だった。あの日、彼女は「何もかも片付けたいんです」と言っていたのを思い出す。
シンドウの記憶にない三年前の事件
記録を見る限り、特段不自然な点はなかった。だが、彼女が当時提出した委任状の日付が、今回の供託日と一致していた。
偶然にしては出来すぎている。彼女は、三年前からこの日を計画していたのだろうか。もしそうだとしたら、まるで怪盗キッドのような先読みだ。
「供託」は、彼女なりのメッセージだったのかもしれない。あるいは、愛の最期の形だったのか。
供託書に添付された訂正印の痕
さらによく見ると、供託書の一部に訂正印が押されていた。そこには、一度「婚姻費用」と書かれた箇所を「その他」に訂正した痕跡があった。
つまり、当初は婚姻関係を前提とした供託だった可能性がある。それを途中で「その他」として曖昧にしたのだ。
この供託が意味するのは、単なる失恋ではなく、関係性の存在そのものを「供託して抹消」しようとする行為ではないか。
サザエさん一家がヒントをくれた夜
仕事が終わり、帰宅してテレビをつけると、ちょうどサザエさんが始まっていた。波平が「バカモン!」と叫んでいた。
その瞬間、俺は思い出した。彼女の祖母が亡くなったのも、婚姻届の話が出たのも、あの日の夜だったのだ。サザエさんの時間帯に。
思い出はいつも、そんな些細なきっかけで蘇る。あのとき、俺は「今は無理だ」と言ってしまった。それがすべての始まりだったのかもしれない。
波平の「バカモン」で蘇る一つの真実
波平の叱責で目が覚めるなんて情けないが、俺にとっては十分すぎるヒントだった。そう、供託は俺に対する“遅すぎた告白”だったのだ。
愛していた。でも、それを伝えるには俺はいつも遅すぎた。そういう男なのだ。だから、供託という“形式”で彼女は最後の意思を示したのだろう。
やれやれ、、、ドラマじゃあるまいし、と呟きながら、俺は明日彼女の事務所に行く決心をした。
裁判所で見つけた偽名の足跡
翌日、俺は供託書に記された代理人の情報をたどり、裁判所の供託課に足を運んだ。すると、申請者名義が「田中春菜」となっているのに気づいた。
春菜は、彼女の旧姓だ。婚姻届を出す前に、あるいは出さずに終わった場合に使用される名前。つまり、これは意図的な偽名使用だった。
司法書士としては見過ごせないが、恋人としては、何も言えない。彼女なりのケジメだったのだろう。
過去の供託案件に紛れたひとつの嘘
調べると、同じ名前で三つの供託履歴があった。そのうちのひとつは、明らかに偽装された住所が使われていた。
その住所は、かつて二人で暮らす計画をしていたアパートの予定地だった。工事は途中で止まり、今は更地になっている。
まるで彼女は、そこに幻の人生を記録しようとしたようだった。それが供託として残る形になったのだ。
元恋人と現在の依頼人の奇妙な接点
さらに奇妙なことに、彼女の名前が今月の依頼者リストにあった。名義変更の手続きで、別人として依頼をしていたのだ。
彼女はあくまで「過去を整理する依頼人」として、俺に最後のメッセージを伝えに来ていた。そして俺は、それにまったく気づかなかった。
彼女は、名も知らぬ依頼人として俺の前に現れ、何も言わず、全てを終えたのだ。
遺言執行者としての責任と疑念
遺言書が出てきたのは、その数日後だった。彼女は亡くなっていた。俺に依頼をする三日前に。
つまり、あの供託通知書は、死の前に用意された遺言の一部だったのだ。俺はその執行者に指名されていた。
やれやれ、、、これじゃあ、供託じゃなくて遺言推理ゲームだ。まるで金田一少年の事件簿だ。
真実は供託された心の中に
彼女の手紙には、最後にこう書かれていた。「いつかまた会えるなら、そのときは私の本当の名前で呼んでください」と。
シンドウとしての俺は、常に他人の法務に関わってきた。だがこのとき初めて、自分の“心”の登記をした気がした。
彼女の愛は、供託という形で残った。そしてそれは、今後も誰かの胸の中で、静かに証明され続けるのだ。
やれやれ、、、あの日の別れは演技だったのか
ふたりの別れは、本当の別れじゃなかったのかもしれない。ただ、それを確かめる方法はもうない。
けれど、司法書士としての俺には、文書の向こうにある“思い”を読み取る義務がある。たとえそれが、亡き恋人の願いでも。
やれやれ、、、そんな気持ちを供託できたら、楽なんだけどな。
事件は終わりを迎える
俺は供託された金額を法務局に返還し、彼女の遺志に従い全ての書類を処理した。心の供託も、少しずつ手放していこうと思う。
最後に彼女の家族から届いた手紙には「ありがとうございました。春菜もきっと喜んでいると思います」とあった。
きっと、彼女は笑っているだろう。俺のうっかりを見守りながら、どこかで。
供託金は愛か罪か
供託された金は、手続き上は「その他」で処理された。でも俺の中では、あれは確かに「愛」だった。
愛を、法で処理できるとは思っていなかった。でも、そういう別れもある。供託という最後の恋文として。
そして俺はまた、誰かの人生のページを捲るため、明日も事務所のドアを開けるのだった。