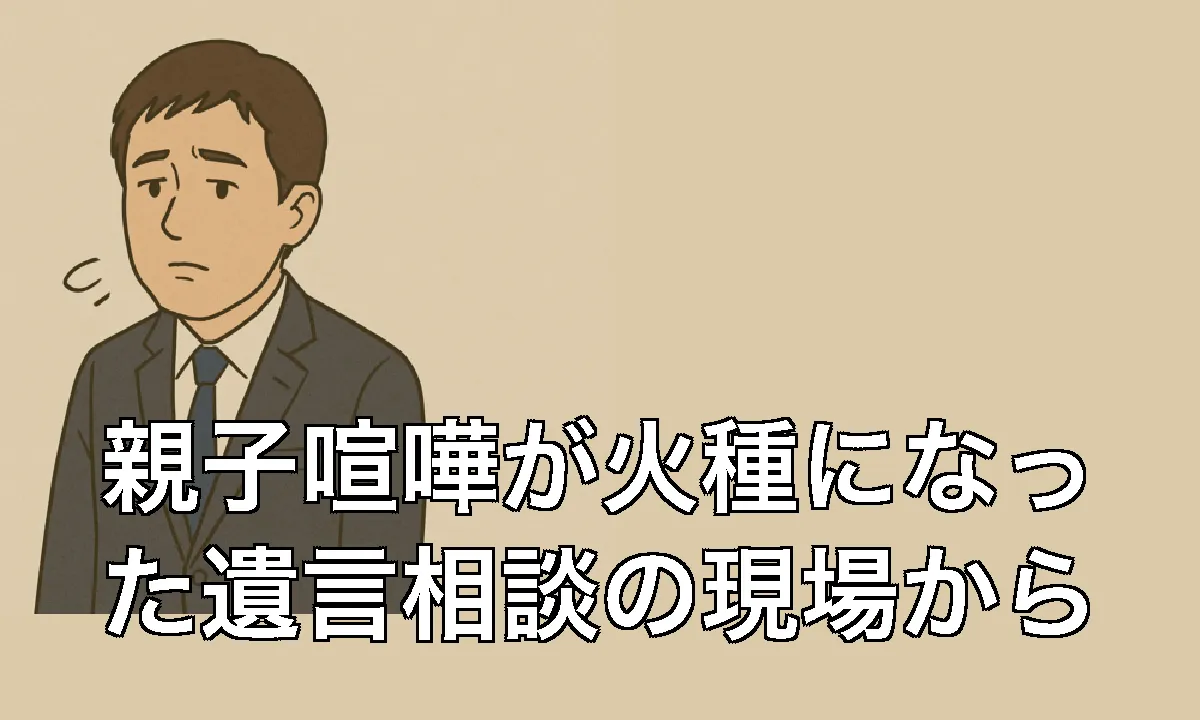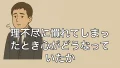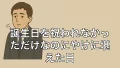静かな遺言相談が一転 家族の怒声が飛び交う瞬間
最初はただの静かな相談でした。「遺言書を作りたいんです」と年配の男性が一人で訪ねてきた。こういう依頼は珍しくありません。ところが、二回目の相談日になると様子が一変。隣に座っていたのはその男性の息子。笑顔の裏に張りつめた空気が漂い、次第に声が荒くなる。「それは違う」「俺が一番親の面倒見てる」——気がつけば、司法書士である私は、完全に親子喧嘩のリングの真ん中に立たされていたのです。
「うちは揉めてません」から始まる地雷原
「うちは揉めてませんから」と冒頭で言われるときほど、実は一番警戒が必要だというのが経験上の鉄則です。本人の希望がハッキリしているようで、実際はその背後に家族の思惑が渦巻いていることが多い。以前、母親と娘二人で相談に来られたケースでは、娘たちがそれぞれ違う主張をし、母親は終始沈黙。後で聞けば、母親は娘たちの顔色をうかがいながら遺言内容を変えたがっていたという。口では「揉めてない」と言っていても、目の奥では火花が散っている。そういうの、すぐにわかるようになりました。
初回面談で感じる微妙な空気
この仕事を長くやっていると、ほんの数分で「この家族、何かあるな」とわかってしまうことがあります。無言のうちに誰が力を持っているか、誰が遠慮しているか、空気の重さが教えてくれるんです。特に多いのは、父親と長男の間にある無言の圧力。顔は笑ってても、どこか硬い。そういう場面では、私はできる限りフラットに、でも少しだけゆっくり話すようにします。相手の本音が出るまでには時間がかかる。でも、焦ってはいけない。焦れば焦るほど、見えないものが見えなくなるんです。
相談者の背後にいる“もう一人の声”
「お父さん、これでいいよね?」と何気なく言う家族の言葉には、たいてい“誘導”が含まれています。とくに長男が同席する場合、「面倒は全部見てきた」という自負がある分、相続に対する主張も強くなりがち。その時、相談者である親がうつむいたまま黙っていると、「これは本音じゃないな」と気づくのです。司法書士としては、どこまで踏み込んでいいのか迷うところ。でも、その沈黙を見逃すと、あとで大きな後悔に繋がることもあるのです。
相談室に同席する家族の存在
遺言相談に家族が「たまたま一緒に来た」と言うケース、実はけっこう多いんです。だけど、たまたまの割には意見をズバズバ言う。結局、相談ではなく“調整”の場になってしまうことも。そこに立たされると、司法書士というよりも調停委員か裁判官のような気分になります。でも、私は法律家であって、家族の感情を裁く立場じゃない。にもかかわらず、感情の渦の中に引き込まれてしまう。この“立場のねじれ”が、仕事のつらさの一つでもあります。
“たまたま一緒に来ました”の罠
「ついでに車出しただけなんで」「うち、兄弟仲いいですから」そんな言葉の裏に、どれだけの感情が潜んでいるか。過去には、父親の隣に座った長女が、「弟は昔から親の財産をあてにしてきた」と涙ながらに訴えたこともありました。その時点で、もう“公平な遺言”なんて幻想に過ぎない。関係が壊れている家庭に理想を持ち込むと、誰も幸せになれない。司法書士は現実に向き合うしかないんです。
その場で始まる親子喧嘩と制止のタイミング
喧嘩が始まると、止めるタイミングは本当に難しい。黙って見ていると激化するし、遮ると余計に火に油を注ぐこともある。過去に一度だけ、あまりに酷くなって「ここは法律相談の場です、少し落ち着いてから出直してください」と言ったことがあります。その日は結局、何も進まなかった。でも、その一言がきっかけで、後日父親が一人で来て、本音を打ち明けてくれたんです。「あのときはごめんな」と言ってくれた瞬間、ああ、この仕事続けててよかったなと思いました。
遺言書が家族関係の引き金になるとき
本来、遺言書は“家族の思い出”のような存在であってほしい。でも現実は、火種になることの方が多い。財産の大小に関係なく、「なぜ私じゃないのか」という感情が生まれてしまう。親の意思が明確であるほど、逆に“納得できない側”が生まれる皮肉。この構図が、毎日のように私の前に現れるのです。
親の本音と子の期待が食い違う構造
親が子に対して「申し訳なかった」「迷惑をかけたくない」と思って用意した遺言が、かえって子どもたちの怒りを買う。そんな悲劇を何度も見てきました。子どもたちは「もっと頼ってほしかった」「公平に扱ってほしかった」と感じていたりする。でも、親にとっては「自立している子には残さなくていい」という考えもある。どちらも悪くない。だからこそ難しい。そして、司法書士にはその板挟みがのしかかる。
親が言いたいことを言えない理由
親が本音を語れない理由は単純です。「子どもを傷つけたくない」それに尽きる。でも、傷つけたくないあまり、何も伝えずに終わってしまうこともある。それが一番つらい。私は、「言えない気持ち」も遺言書の中に込められるような仕組みを工夫しています。例えば、付言事項という欄を活用して、「感謝の気持ち」「これまでの思い出」などを書いてもらう。法律だけでなく、気持ちも整理できる遺言が理想です。
子が「本心」を誘導してしまう構図
「それでいいよね?」と聞かれて「うん」と答える高齢者の姿を何度も見てきました。でも、その「うん」が本心かどうか。実は誰にもわからない。本人でさえ、わからなくなっていることがある。これを“誘導”と言ってしまえばそうなのかもしれないけれど、家族の中ではそれも一つのコミュニケーションなのかもしれない。司法書士としては、ただ一つ、「他人の意見に流されずに書かれたもの」であるかを、可能な限り確認する責任があると感じています。
あとがき そして一人静かに焼酎を飲む夜
仕事を終え、誰もいない事務所で一人、コンビニで買った焼酎をちびちび飲む。誰かに話したいけど、話す相手がいない。昔の野球部仲間も、みんな家庭持ちになって、夜の誘いには応じてくれなくなった。そういう夜が続いても、明日また一人の依頼者のために椅子を整え、ペンを握る。この仕事、楽じゃない。でも、不器用な人の人生に、ちょっとだけ関われる。それが今の、俺の役割だと思っています。