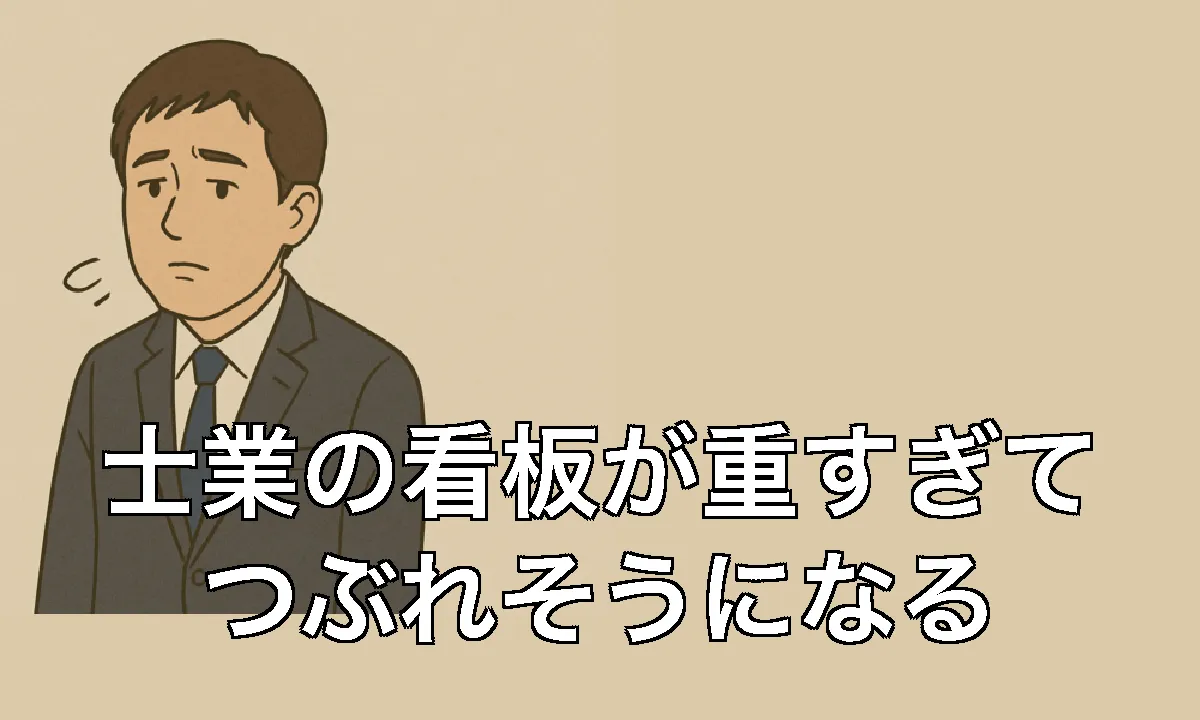士業の看板が重すぎてつぶれそうになる
朝起きた瞬間から感じる重圧
目覚ましの音が鳴った瞬間、胸の奥にズシンとくるものがある。身体は布団から出ようとしているのに、心が拒んでいる。今日も何か起きるんじゃないか、何か忘れているんじゃないか、そんな不安が頭の中をぐるぐる回る。士業という肩書きは、誇らしいものである反面、間違えられないという恐怖をも背負っている。独立して十年以上経つが、その重圧は年々薄れるどころか、むしろ増しているように思える。
目覚めと同時に始まるプレッシャー
かつては朝の静けさが好きだった。鳥の声やコーヒーの香りが一日の始まりを祝福してくれているようで。でも最近は、目が覚めた瞬間から「今日もちゃんとやれるか?」という声が脳内で響く。特に登記関係で期限が迫っているときなど、朝一番から胃がキリキリする。まるで毎朝、試合前のロッカールームにいるような気分だ。元野球部だった頃の緊張感が、今も違う形で蘇ってくる。
看板を背負う責任が頭から離れない
事務所の表札に自分の名前がある。これは小さな誇りであり、同時に逃げ場を失わせるものでもある。「司法書士事務所」と書かれた看板には、法の専門家としての信頼と責任が凝縮されている。その看板の前を通るたびに、自分はその名に恥じぬ仕事ができているかと自問自答する。休むことも、弱音を吐くことも許されないような気がして、いつも背筋が伸びる反面、どこかで肩の力が抜けない。
「間違いが許されない」という呪縛
士業というのは、致命的なミスが許されない世界だ。特に登記や相続関連の業務では、一つの数字、一文字のミスが大きなトラブルに発展する。たとえ事務員が入力した内容でも、最終的な責任はすべて「代表者である私」に降りかかる。その緊張感に耐えきれず、独立を諦める人がいるのも頷ける。私自身、何度も「こんな重圧、いつまで続けられるのか」と自問しながら、それでも今日も机に向かっている。
信頼されることの怖さ
「先生に頼めば安心」と言われるたび、嬉しさよりも先に不安がこみ上げる。信頼されることは光栄だけど、その裏には「絶対に失敗できない」というプレッシャーが付きまとう。司法書士という肩書きがあるだけで、完璧な対応を期待される。でも、私だって人間だ。ミスもするし、忘れることもある。だけど、そう思うことすら許されない空気に、いつも押し潰されそうになる。
「先生だから大丈夫でしょ」の言葉の重さ
たとえば相続の案件で、家族が揉めている中、「先生にお任せすれば間違いない」と言われることがある。その期待に応えたいと思う。でも一方で、「この件、絶対に波風立てないように収めなきゃ」と無理なプレッシャーがかかる。実際には法律だけでは解決できない感情のぶつかり合いがあり、そこに士業が介入しても限界があるのに、「プロならなんとかしてくれる」と期待されてしまう。
信頼と期待が混ざり合うジレンマ
お客様が抱く「信頼」は、時に過剰な「期待」にすり替わっていく。これは士業全般に言えることかもしれない。誠意を持って接していればいるほど、「なんでも引き受けてくれる人」だと誤解されることもある。仕事が集中し、息つく暇もなくなる。でも断れば「冷たい」「期待を裏切った」と言われかねない。このバランス感覚が難しく、優しさが仇になることも多々ある。
過去の失敗が今も尾を引く
昔、ある登記の件で思い込みから小さなミスをしてしまい、関係者に大きな迷惑をかけたことがある。その件は謝罪と修正でなんとか収めたが、未だにふとした瞬間にその出来事がフラッシュバックする。完璧でなければいけない、という呪縛に取り憑かれてしまったのはその時からかもしれない。あの一件以来、自分を許すことが難しくなった。