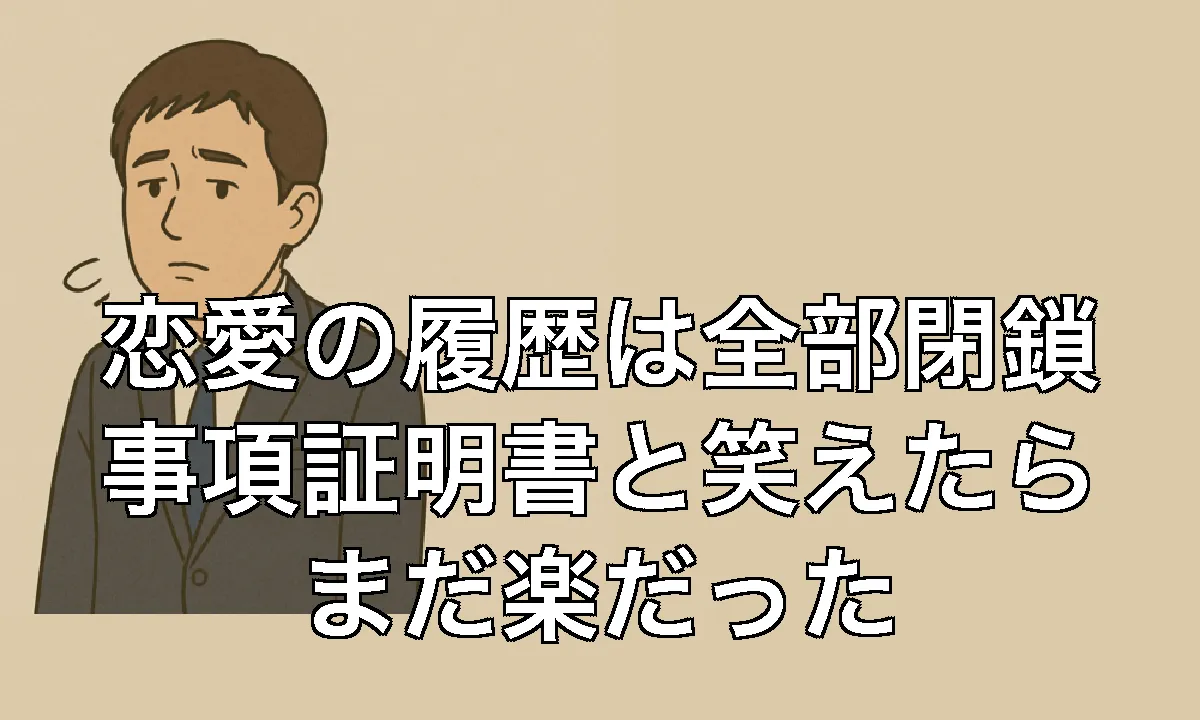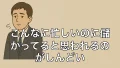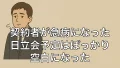恋愛と無縁だった司法書士という肩書の孤独
司法書士という肩書は、世間的には「しっかりしてそう」とか「堅実そう」とか思われることが多い。でも実際は、机に向かって黙々と登記と書類に向き合う毎日で、人との出会いなんてほとんどない。事務所には事務員さんが一人。朝から晩までの電話と書類の山。人と関わってるようで、実は誰とも関わっていない。そんな生活が15年続いている。ふと夜に一人で食べるカップラーメンの湯気が、妙に寂しさを際立たせる。
資格を取れば人生が変わると信じていたあの頃
30代前半、資格試験に合格したときは、本気で人生が変わると思っていた。安定した収入、頼られる仕事、そしてなにより「ちゃんとした大人」として見られること。それが恋愛にもつながると、どこかで期待していた。でも現実は、資格を取った瞬間に恋愛市場からも姿を消していた。気づけば、周りは家庭を持ち始め、自分は事務所の開業資金で通帳が空になり、恋どころではなかった。
現実は仕事と登記と電話対応の日々
書類の締切に追われ、電話に追われ、気づけば夕方。昼食を食べ損ねて、事務員さんに「おにぎりでも買っておきましょうか?」と聞かれた時の申し訳なさ。仕事に熱中していると錯覚できるけど、実際は余裕がないだけ。恋愛なんて、心のどこかにあったはずの感情が、こうして少しずつ削れていった。忙しさは言い訳にもなるし、現実逃避にもなる。誰にも責められない代わりに、誰にも頼れない日々。
休日の昼に差し入れなんて来るはずもない
日曜の昼、ふとテレビを見ていると「彼氏に手作りのお弁当を届けに来ました」なんてコーナーがあった。笑えるはずが、チャンネルを変える指が止まった。誰も来ない事務所、鍵が閉まったままのガラス扉、沈黙の中で電子レンジが鳴る音だけが響く。差し入れなんて来ない。誰にも知られてない、誰にも待たれてない。そんな現実にふと背中が丸くなる。
恋愛履歴に名前を書く相手がいないという事実
司法書士の業務で「閉鎖事項証明書」という言葉をよく使うけど、自分の恋愛履歴もまさにそれ。書くことはできるけど、もう誰も見ないし、誰も興味を持たない。過去に数人、付き合った人はいたけど、今その名前を思い出しても、まるで登記済の過去。もう更新もない。自分の心の中で閉鎖された情報だ。誰かと過ごす時間がこんなにも遠いものだったなんて、想像もしていなかった。
元カノのことを思い出せるのはいつまでだろう
大学時代に付き合っていた彼女の名前を、久しぶりに思い出そうとしても、苗字がもう出てこない。あの頃は本気だったし、いつか結婚するんだと思っていた。でも自分の優柔不断さと、仕事ばかりに向かってしまった性格が、彼女の心を遠ざけてしまった。思い出すたびに後悔がよぎるが、今さら連絡を取る勇気なんてない。そもそも、彼女はもう別の名前になってるかもしれない。
SNSで流れてくる結婚報告と子どもの写真
スマホを開けば、かつての同級生や同僚の幸せそうな写真が並ぶ。子どもとピクニック、夫婦で旅行、記念日のディナー。いいねの数も、コメントも、まるで人生の偏差値のように見えてくる。こっちはいいねすら押せずに、そっと画面を閉じる。嫉妬とは違う、ただ置いていかれたような感覚。自分は何をしてたんだろう。何を守ってきたんだろう。そう考えてしまう夜は、しばしばある。
それでも既婚者たちの愚痴にはついていけない
一方で、既婚の友人たちは家庭の愚痴をこぼす。「子どもがうるさい」「嫁が冷たい」なんて話を聞くと、思わず「贅沢な悩みだな」と心の中で思ってしまう。こっちは、誰かに話しかけられることすらないのに。だけど、その思考もまた、自分が寂しさに耐えきれず皮肉っぽくなっているだけかもしれない。彼らには彼らの現実があるのだと、言い聞かせながら、会話を合わせている自分がいる。
事務員さんとの会話が一日の中で一番の癒し
唯一の従業員である事務員さんとの会話が、もはや社会との接点になっている日もある。「今日寒いですね」「また電話多かったですね」そんな何気ないやりとりが、心のバランスを保ってくれる。たぶん彼女は気づいていないけれど、そのひと言で今日もやっていけるという日がある。こうして人に支えられて生きていることを、改めて思い知るのが、こんな静かな日常の中だったりする。
何気ないやりとりが仕事へのモチベーションに
書類のチェック中にポツリと話しかけられる。「先生、字が疲れてますよ」なんて言葉に、思わず笑ってしまう。誰かと会話をすることで、自分が人間であることを思い出す。書類だけ見てると、数字と判子でしか価値が測れなくなってしまうから。仕事の精度も、たぶんこういう会話があるから保てている。人との関わりが、ここまで自分にとって大切だったとは、事務所を持つまで知らなかった。
でもそれ以上を期待しちゃいけない理由
とはいえ、その関係が「仕事上」である以上、越えてはいけない一線がある。年齢も離れているし、彼女には彼女の生活がある。ほんの少しの言葉に心が動きそうになるけど、それは自分の寂しさを埋めたいだけかもしれない。そんな気持ちを押し殺して、あくまで「所長」として接するよう心がけている。誰かに頼りたいときほど、冷静さが必要になる。わかってるけど、それが難しい。
勘違いしないようにと自分に言い聞かせている
たまに笑顔を向けられると、つい「もしかして」と思ってしまう瞬間がある。だけど、それはただの優しさであり、礼儀であり、仕事の一環だとわかっている。だからこそ、自分に言い聞かせる。「これは仕事、これは勘違いだ」と。そうしないと、また誰かを傷つけることになるし、自分が勝手に落ち込む羽目になる。慎重になるってことは、もう傷つきたくないってことかもしれない。
元野球部が語る 恋愛よりも大切だったもの
高校時代、野球部だった自分は、恋愛なんてものよりも、グラウンドと仲間との時間がすべてだった。夏の甲子園予選で負けた帰り道、みんなで泣きながら飲んだ自販機の缶コーヒーの味は、今でも忘れられない。そのときの感情は、恋愛とは違うけど確かに「誰かと一緒にいた」証拠だったと思う。社会に出てから、そんな関係性を築けたことがあっただろうか。そう思うと、今の自分の人間関係の薄さが少し悲しい。
仲間との汗と涙は今でも宝物
あの頃の仲間たちは、今それぞれの道で頑張っている。家族を持ち、仕事をして、野球とは関係ない日常を送っている。でも会えばすぐにあの頃に戻れる。恋愛では得られなかった、無償の信頼と連帯感。恋は終わることがあるけど、あの頃の絆は不思議と終わらない。恋愛が閉鎖事項証明書だとしたら、友情はずっと有効な登記記録のまま。そんなふうに思うと、自分の人生も捨てたもんじゃない気がしてくる。
でも守りたかった背番号は恋ではなかった
あの背番号を誇りにしていたあの頃、自分の人生は確かに輝いていた。でも、それを守り続けることに必死になりすぎて、恋や家庭といった“もう一つの幸せ”には手が伸びなかった。今さら恋愛を始めるには遅いのかもしれない。だけど、背番号を脱いだ今の自分にも、何かを守る覚悟は残っているはずだ。過去の栄光にすがるだけじゃなく、もう一度誰かと心を重ねる日が来ることを、少しだけ願ってみる。