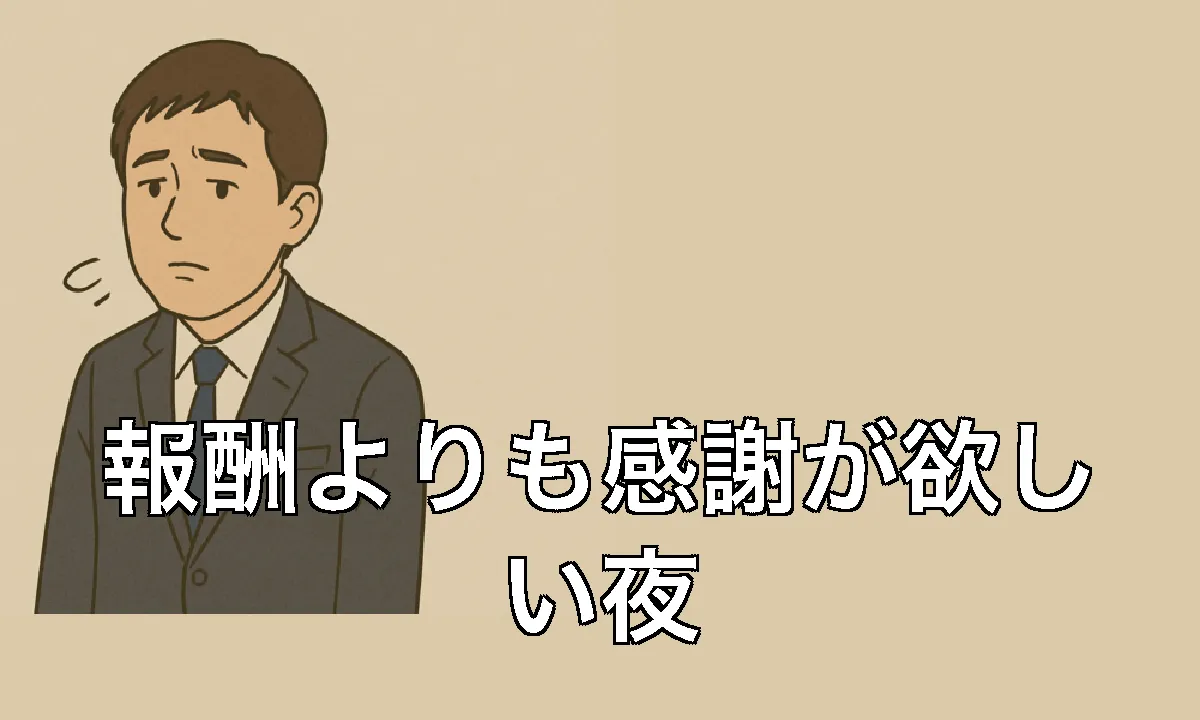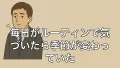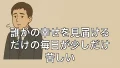報酬よりも感謝が欲しい夜
ふとした夜、帳簿を締めながら考えるのは「稼ぎ」ではなく「報われたかどうか」だったりする。司法書士という仕事は、黙っていても人から頼られる分だけ、結果だけを見られがちだ。手続きを終えた瞬間から、感謝の言葉もなく次の依頼へ進む日々。そんなとき、「ありがとう」のひとことが、どれほど心を救ってくれるか。報酬があるだけ恵まれているのだろうけれど、夜が更けるほど、心の空白が広がる。
報酬があっても心が満たされないとき
登記の完了報告をメール一本で済ませた帰り道、コンビニの明かりすらまぶしく感じた。今日も自分は“作業”を終えたけど、それだけだった。きっちり報酬は振り込まれたし、文句のひとつもなかった。それなのに、なぜこんなにも虚しいのだろう。お金だけじゃ補えない何かが、胸の奥で擦れている。あの頃、野球部の仲間から飛んできた「ナイスプレー!」の一言。あれが今、一番欲しい。
お金よりも欲しかった一言
あるとき、相続登記の相談に乗った高齢の女性がいた。話すスピードもゆっくりで、正直時間も手間もかかった。それでも丁寧に対応し、無事に登記も終えた。報酬も普通に受け取った。でも、最後にその方が言った「あなたがいてくれて助かったわ」の一言が、どんな報酬より心に響いた。あの一言のためなら、もっと苦労しても良かったとさえ思った。結局、人のために頑張るって、そういうことなのかもしれない。
頑張りを誰も知らないという孤独
自分がどれだけ夜遅くまで書類をチェックしても、法務局に何度足を運んでも、その努力は誰にも見えない。ミスがないのが当たり前で、無事に終えるのが当然とされる世界。トラブルがなければ称賛はなく、逆にあれば責任だけが重くのしかかる。そんな理不尽を積み重ねながら、それでも現場に立ち続けているのは、きっとどこかで「誰かの役に立っている」という確信を探しているからだ。
感謝の言葉がもたらす魔法
感謝されることは、司法書士という職業において、実は想像以上のエネルギー源になる。たった一言の「助かった」が、数日分の疲労を吹き飛ばしてくれることもある。なぜならそれは、自分の存在が「役に立った」という証だから。誰にも見えないところで頑張る仕事ほど、そうした言葉が胸に染みる。だからこそ、今日もまた誰かに寄り添いたいと、小さなモチベーションで自分を支えている。
たった一言で救われる夜もある
かつて、認知症のお父さんを抱えるご家族の成年後見申立てを手伝ったとき、家族から「書類が多すぎて気が狂いそうでした。でも先生のおかげで前に進めました」と言われた。あの言葉は今でも鮮明に覚えている。事務作業に見えるこの仕事が、誰かの生活の扉を開く鍵になる。そう気づけた瞬間、今日の夜は報われた、と感じられた。どんな疲労感も、その言葉に包まれたら帳消しになるのだ。
事務員さんのささやかな労いが沁みる
自分ひとりではない、そう思わせてくれる存在が事務員さんだ。書類を綴じながらぽつりと「先生、昨日の対応すごかったですね」と言われただけで、ふっと肩の力が抜けた。報酬では得られない、心のやりとり。それを職場で感じられることが、実はかなり大きな支えになっている。人は誰しも、見られていたい、気づかれたい生き物だと、こういう瞬間にあらためて思う。
地方の司法書士という選択の重み
都市部と違って、地方の司法書士は「便利屋」的な扱いをされることも少なくない。登記だけでなく、身の上相談、町内トラブル、果ては役所への同行まで…。幅広く求められる一方で、その負担を引き受ける覚悟も要る。東京に出ていれば、もっとスマートに業務ができたのかもしれない。けれど、ここで働くことを選んだのは、自分なりの「意味」があると思ったからだ。
頼られる喜びとその裏にある疲弊
「先生、ちょっと教えて」と気軽に声をかけられる。それは嬉しい。でも、それが毎日となると話は別だ。一つひとつの相談が意外と重く、生活や人生がかかっているからこそ、応える責任も大きい。相談後に「ありがとう」があると救われるが、なければただ疲弊するだけ。頼られることに喜びを感じつつも、その期待に応えることの苦しさに、時折押し潰されそうになる夜がある。
田舎ゆえの距離感が心をすり減らす
地元で開業していると、依頼者が近所の人だったりする。「あそこの先生、●●さんの相続やってるらしいよ」と噂がすぐに回る。プライバシーの線引きが曖昧で、気が抜けない。正直、何もかも見られている感覚に、心がすり減ることもある。でも、逃げられないからこそ、自分を律する力もついた。田舎特有の濃さは、諸刃の剣だと感じている。
元野球部の自分が選んだ孤独なマウンド
かつては仲間とともに汗を流し、声を掛け合いながらプレーした野球部。今は、たったひとりで書類と向き合い、責任を背負って戦っている。試合と違って、誰も見てくれない。勝っても歓声はなく、負ければすべて自分の責任。でも、それが司法書士という仕事だ。だからこそ、野球で培った精神力が、今の自分を支えてくれている気がする。
チームプレーから個人戦へ
高校時代、エラーしても仲間が声をかけてくれた。「ドンマイ、次頼むぞ」と。今、仕事でミスをすれば、それは「信用問題」。声をかけてくれる人はいない。だから、個人戦だ。でも、心のどこかで「一緒に働いてる」と思える事務員の存在は、ほんの少しだけチーム感を与えてくれる。完全に一人じゃない、それだけで前を向けるときがある。
一人で抱えるプレッシャーとの闘い
司法書士の仕事には「絶対に間違えてはいけない」場面が多すぎる。登記の期限、記載ミス、申請不備…。どれも「先生の責任」として返ってくる。眠れない夜は、何度も手帳を見返し、控えた記録を確認する。野球なら、次の打席で取り返せた。でも、この仕事に“次の打席”はない。だからこそ、日々自分を追い込み、闘っている。
モテない司法書士のつぶやき
「先生、結婚されてるんですか?」と聞かれて「いや、独身です」と答えるときの、あの空気。どこか気まずい、そして少し寂しい。仕事に打ち込んでいれば、誰かが見てくれると思っていた。でも、それは幻想だった。結局、どれだけ頑張っても、プライベートは別物。ふと、仕事での充実感が足りない夜に、それが何倍にも膨らんでしまうのだ。
恋愛も仕事も不器用なままで
気になる人ができても、うまく話せない。相談に乗ることは得意でも、雑談はからっきしダメ。結局、タイミングを逃して何も進まない。そうやって何年も過ぎた。仕事のことなら冷静に判断できるのに、恋愛となるとどうしてこうもうまくいかないのか。そんな自分に笑ってしまうが、まあ、それも含めて「らしさ」だと諦めている。
誰かに必要とされる経験の乏しさ
「必要とされたい」と思う気持ちは、意外と根深い。司法書士としては必要とされても、一人の人間としてはどうだろう。誰かの人生に深く関わる仕事をしているのに、私生活では関わる人が極端に少ない。このギャップに、時折、押し潰されそうになる。だからこそ、たまに言われる「先生がいて助かった」という言葉は、どんな宝石よりも価値がある。
司法書士を目指す人への正直なアドバイス
この仕事は、華やかではない。地味だし、地道だ。だけど、人の人生の節目に立ち会うという意味では、とても尊い職業でもある。目立ちたい人には向かない。感謝されたい人には向いているかもしれない。日々の書類と格闘しながら、たまに差し込む「ありがとう」という光を頼りに生きる。そんな毎日を、受け入れられる人には、きっとこの仕事は向いている。
華やかさより、地道さを愛せるか
スーツを着て、印鑑を押して、堂々と話す司法書士の姿。そう見えるかもしれないが、実際の中身は、書類との根気比べだ。黙々と書類をチェックし、ミスを防ぎ、依頼人の言葉を丁寧に拾う。地味な作業に耐えられるか。むしろそれを「自分らしい」と思えるかどうか。それが、この職業で続けていけるかの分かれ目だと思っている。
愚痴すら支えになる仲間の存在
「今日も疲れた」「また無理なお願いされたよ」…そんな愚痴を言い合える仲間がいるだけで、救われることがある。地方では同業者も少なく、孤独を感じやすい。だからこそ、たまに話せる先輩や後輩とのやりとりが、何よりの支えになる。完璧でなくていい、弱さを見せられる場所を、少しでも持っておくことが、続ける秘訣かもしれない。