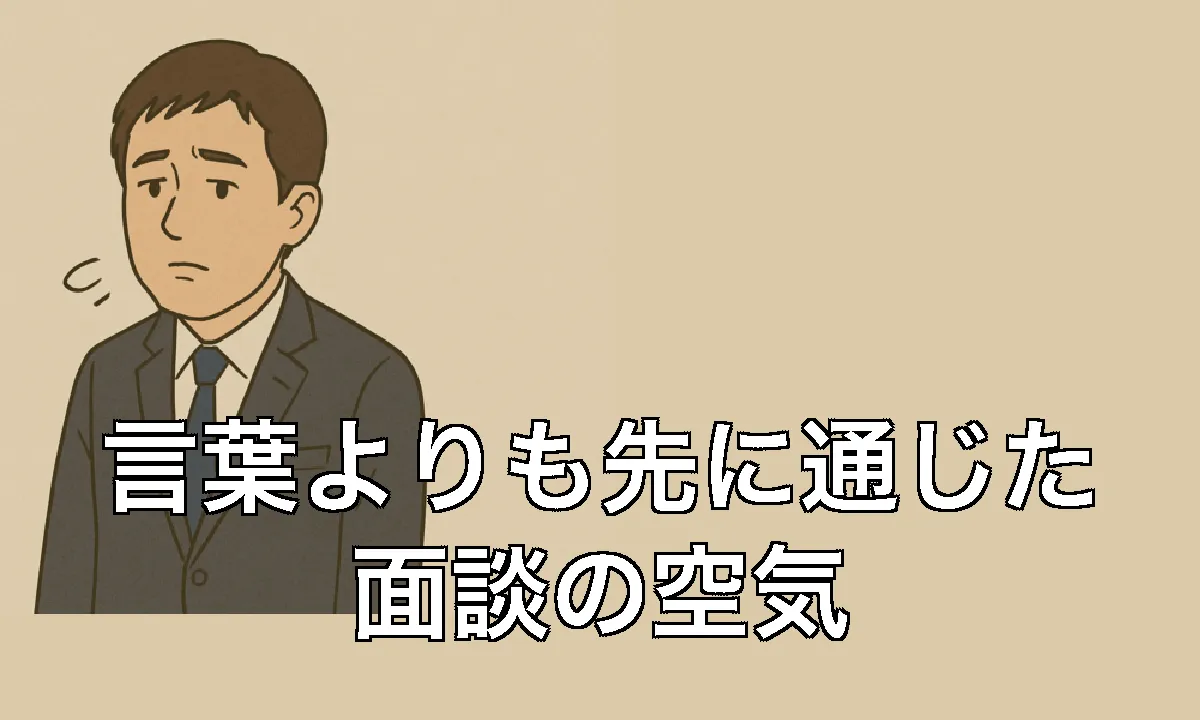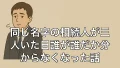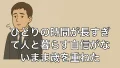面談というよりも空気を読む時間だった
あの日の面談は、正直なところ、こちらが用意した言葉の出番はほとんどなかった。机を挟んで座ったその瞬間、なんとなく空気で感じた。「ああ、この人はもう覚悟を決めてきているな」と。形式的な挨拶はした。必要な説明も一通り行った。でも、それらはただの確認作業でしかなかったように思う。話している途中も、何度も目が合った。言葉が途切れても不自然じゃなかったのは、たぶんお互いに「もう伝わってる」と思っていたからだ。
目が合った瞬間に察したこの人は分かってる
初対面の人と目が合った瞬間に、ふと心の奥を覗かれたような気持ちになることがある。先日、相続の相談に来られた60代の女性もそうだった。何かを語りかけるような眼差しで、私の反応を確かめるように静かにこちらを見つめていた。「長くかかりますよね、こういうの」と一言だけ。それに対して私は「そうですね、簡単ではないです」とだけ返したが、それで十分だったように思う。その後の会話は必要最低限。にもかかわらず、妙に印象に残った面談だった。
言葉よりも先に伝わるものがある不思議
司法書士の仕事は、言葉が多くを占める。書類の説明、登記の流れ、費用の内訳。だが、それ以上に大事なのが、相手の表情や雰囲気を感じ取る力だと最近つくづく思うようになった。どんなに丁寧な説明をしても、相手の不安が消えないこともある。一方で、ほとんど話さなくても「大丈夫です」と言って安心して帰っていく方もいる。あの差は何なのかと考えると、やはり「空気のやりとり」としか言いようがないのかもしれない。
面談の場で余白に救われた話
以前、やたらと沈黙が多い面談があった。こっちも何を話していいのかわからず、気まずさに耐えていたら、相手の方がポツリと「…忙しいんでしょう?」と聞いてきた。「まあ、正直なところ…」と返した私の苦笑いに、その方は少しだけ笑ってくれた。あのとき、無理に喋り続けず、沈黙をそのままにしておいてよかったと心底思った。余白は気まずさにもなるが、信頼の入り口にもなり得るのだと知った。
話が弾まなかったのに気まずくなかった理由
会話が盛り上がる面談はありがたい。けれど、話が弾まなかったからといって失敗とは限らない。むしろ、言葉少なでも気まずくならなかった面談は、結果としてスムーズに進むことが多い。こちらが何かを言い過ぎないことで、相手が自分のペースを保てるようになる。ある日、ほとんど言葉を交わさなかった若い男性の相続相談があったが、最終的に「ここに頼んでよかったです」と一言残して帰っていった。そういう時こそ、「通じた」という実感がある。
無言の時間に流れる理解と信頼
何か話さなきゃ、と焦ってしまう気持ちはよく分かる。私もそうだった。でも、あるときから「沈黙は悪ではない」と考えるようになった。話さなくても成立する関係性は、むしろ信頼の証拠かもしれない。無言の時間に、お互いの呼吸が少しずつ合っていく。その感覚を知ってからは、面談の雰囲気も少しずつ変わっていったように思う。
事務的な説明をしすぎない面談の効用
面談ではつい、丁寧に説明しすぎてしまうことがある。とくに、相続や登記のような専門的な話になると、どうしても「説明責任」を意識してしまう。でもそれが逆に、相手を置いてきぼりにしてしまうこともある。説明は必要最小限にとどめ、あとは相手の反応を見ながら必要に応じて補足する。そうすると、不思議と相手の顔が和らいでくる。話すよりも、間合いを見る。これも一つの技術なのかもしれない。
面談で話すことに意味があるのかという迷い
何年もこの仕事をしていて、ふと「そもそも面談って意味あるのか?」と思うことがある。相手が答えを持ってきている場合、ただ確認するだけの作業になることもあるし、逆にこちらの説明を右から左へ受け流しているように見える時もある。それでも面談が必要なのは、やはり「人と人として向き合う」ためだ。書類では伝わらないものが、目の奥にあったりする。
形式的な質問を重ねてしまう自分が嫌になる
どうしても面談がルーチンになってくると、形式的な質問ばかりになってしまう。「ご兄弟の方は何人いらっしゃいますか?」「ご住所はこのままでよろしいですね?」。確かに必要な確認事項ではあるけれど、あまりにテンプレ化しすぎると、まるで機械みたいだなと自己嫌悪に陥る。相手が人間であることを、こちらが忘れかけてどうするんだ、という自戒を込めて。
本音で話せたときのほうが案件はうまくいく
一度、明らかに疲れている方がいらして、「正直、今日くるのもしんどかった」と言われたことがある。そのとき、私もつい「こっちも正直きついですね」と返してしまった。すると、相手は「そうですか、じゃあ今日は最低限だけで」と笑ってくれた。不思議と、その案件はその後すんなり進んだ。本音のやりとりは、どこかで信頼のスイッチになる。
マニュアル通りの応対がもたらす距離感
昔、司法書士になったばかりの頃は、応対マニュアルみたいなものを一生懸命守っていた。でも、それが逆に相手との間に壁を作っていたように思う。丁寧にやっているはずなのに、なぜか冷たいと言われることもあった。それはきっと、こちらの感情が表に出ていなかったからだ。マニュアルに頼らず、素直な受け答えをしたほうが、面談はうまくいくと今では実感している。
面談相手の態度に振り回される疲れ
面談の相手が無表情だったり、逆に饒舌すぎたりすると、どうしても気疲れしてしまう。こっちは仕事だからと割り切ってはいるが、感情の揺れ幅が大きい方に当たると、終わった後にどっと疲れが来る。面談とは、情報交換以上に、感情のやりとりでもあるのだと思い知らされる瞬間だ。
表情ひとつで印象が変わるのが面談の怖さ
あるとき、何気ない顔で説明していたら、「怖い顔されてましたよ」と言われてしまった。自分では普通のつもりだったが、相手には圧を与えていたらしい。その一言にショックを受け、今では鏡を見てから面談に臨むようになった。表情管理なんて、モデルでもあるまいし…と思いながらも、やはり第一印象は大切だ。
経験ではなく空気を読む力が問われる場面
経験年数を重ねるほどに、スキルは上がっても「慣れ」も増える。その慣れが逆に相手の繊細なサインを見逃す原因になることがある。ベテランだからこそ、もう一度初心に帰って、「目が合ったときの空気」や「声のトーンの揺れ」に敏感でいたいと思う。司法書士の仕事は、最後は人間力だとつくづく思う。