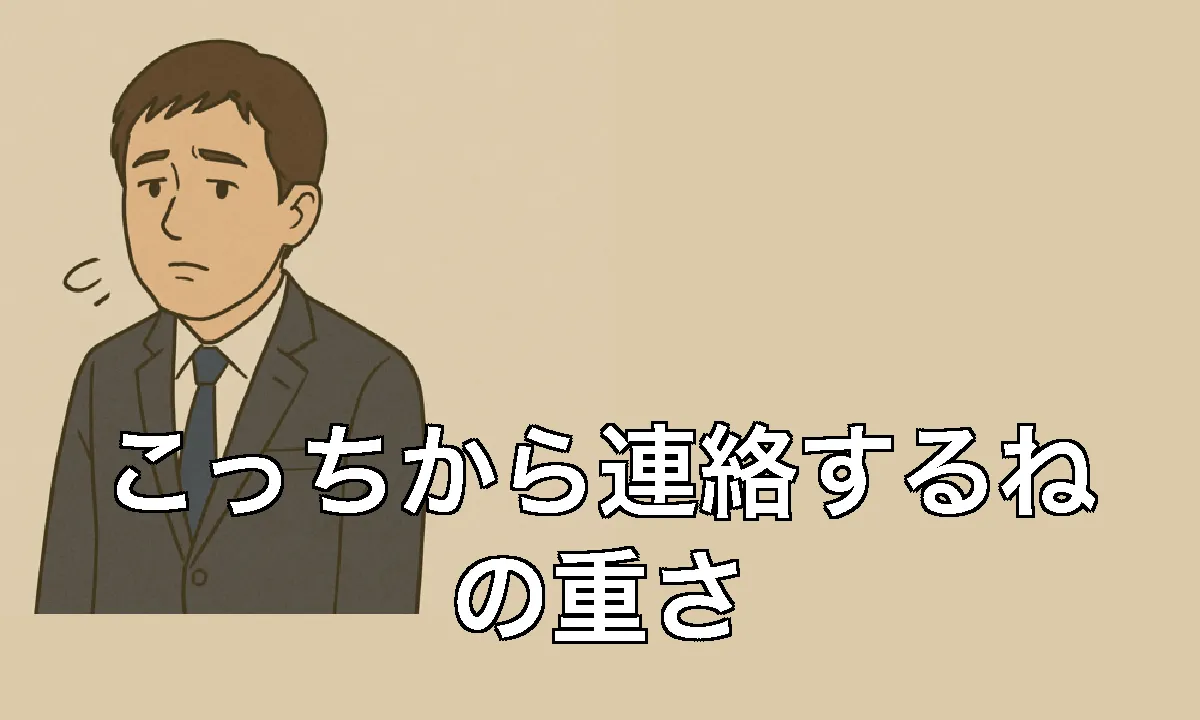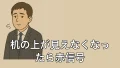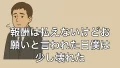こっちから連絡するねに込められた気まずさ
「こっちから連絡するね」——この言葉には、不思議な重みがある。言われた瞬間、その人とはもう連絡を取り合うことはないんじゃないか、そんな予感がしてしまう。言葉そのものはやさしいのに、そこに含まれているのは「終わり」だったり、「断り」だったりする。司法書士としての仕事では、打ち合わせの終わりなどに使うこともあるが、プライベートとなると、この言葉が妙に刺さる。まるで期待していたやり取りの幕が静かに下ろされたかのように感じるのだ。
言葉の終わりが告げる関係の終わり
「こっちから連絡するね」と言われると、それ以上こちらから踏み込んではいけないような、そんな空気になる。本音を言えば、「連絡を待ってるね」くらいの温度が欲しいのに、それを言う勇気もなくて、ただ「はい」と返してしまう。この言葉、私の中では「優しい拒絶」として定着している。学生時代、野球部でケガをしてレギュラーを外されたとき、監督に同じようなことを言われたのを思い出す。「また使うから」って。でも結局、一度も呼ばれなかった。そういう記憶が、この言葉に余計な重みを与えているのかもしれない。
たった一言に詰まった諦めの気配
「こっちから連絡するね」は、断るための最も穏やかな表現だ。でも、その穏やかさが逆に冷たく感じることもある。期待していた気持ちにふたをされ、「あ、終わったんだな」と納得するしかない。プライベートで仲良くなった女性に言われた時もそうだった。「また飲みに行こうね」と言った後に返ってきたのがこの言葉。それっきりだった。連絡を待ち続ける自分が虚しくなって、スマホを見るのも嫌になった時期もあった。あの一言で、心がすっと離れていく音が聞こえた気がした。
「またね」が言えない距離感
本当に関係を続けるつもりがあるなら、「またね」とか「次はいつ会える?」って自然と出てくるはず。でも「こっちから連絡するね」には、再会の約束が含まれていない。まるで、別れを告げるために使われる儀式のようだ。ある意味で礼儀正しく、でもとても他人行儀。仕事の現場でも、そう言われてしまうと、こちらからフォローの連絡を入れるのもためらってしまう。適度な距離感が求められる業種とはいえ、人間らしいぬくもりが欲しくなる時もあるのだ。
経験としての「こっちから連絡するね」
司法書士という仕事は、関係が短期的になりがちだ。登記が終われば、もう会わない人も多い。そういう中で、「こっちから連絡するね」と言われることが時々ある。だが、それはほぼ「さようなら」の意味だ。自分でも使ったことがある。事務的に処理しただけで終わってしまった案件、連絡がこなくて放置になった相談。何度も何度も、それを繰り返すうちに、この言葉の重さに気づいた。口にする自分が、実は一番傷ついているのかもしれない。
婚活でのやり取りに疲れた夜
婚活アプリで出会った女性とのやりとりも、やはりこの言葉で終わることが多かった。メッセージを重ねて、ようやく会えたと思ったら、帰り際に「こっちから連絡するね」。一度や二度ではない。三度目くらいからは、「あ、またか」と慣れてきたふりをして、内心はしょんぼりしている。司法書士の仕事で名刺を渡して「何かあれば」と伝える時と、少し似ている。連絡が来ないことを、最初からわかっているのに、それでも期待してしまう自分がいる。
仕事でも私生活でも似たような幕引き
何かを始めようとするたびに、「こっちから連絡するね」によって終わっていくことがある。セミナーを開こうとしたとき、地元の団体に話を持ちかけたら、「またこちらからご連絡します」と言われたきり。お誘いも、営業の提案も、プライベートの誘いも、みんな同じように終わっていく。まるで自分が「一時的な存在」でしかないような感覚になる。どれだけ真剣でも、それが伝わらなければ意味がない。それでも、自分の中で「よくあること」として処理する癖がついてきてしまった。
司法書士としての関わりとその距離感
司法書士という職業には、どうしても「距離」が必要だ。依頼者と過度に親しくなってはいけないという暗黙の了解もある。だが、それが時として冷たく見えるのかもしれない。逆に、距離を保っているつもりが、相手からは「もう関わらない」というサインに受け取られることもある。そんなすれ違いが、「こっちから連絡するね」という言葉に集約されてしまう。
業務上のやり取りにも潜むこの言葉
不動産の売買や遺産相続などの案件で、一通りの説明を終えたあと、「またこちらからご連絡しますね」と伝えることがある。だが、これは本心からの言葉でもある。資料がそろい次第、手続きを進めるからだ。でも、相手にとっては「そのまま終わりそう」と不安を抱かせてしまうこともある。そういう時は、なるべく「○日までに一度ご連絡します」と期限を伝えるようにしている。そうしないと、相手との信頼関係が静かに崩れていくのを感じる。
お客様に言われる「また連絡します」
逆に依頼者から「また相談したいときに連絡します」と言われると、それが本当に実現することは少ない。こちらとしては何か心配な点があればすぐに相談してほしいのに、その「また」はほとんどが来ない「また」だ。ひとつの仕事が終わると、その人とのつながりも消えてしまうことに、寂しさを感じる瞬間がある。仕事だから仕方ない——そう思うようにしているけれど、人間としては少し切ない。
実際にかかってこない電話
携帯に名前を登録したまま、一度も鳴らなかった番号がいくつもある。そのたびに、あの時の「こっちから連絡するね」を思い出す。もう不要なのだろうけど、なんとなく削除できずに残してある。もしかしたら、何かのきっかけで連絡が来るんじゃないか、そんな淡い期待をまだどこかで持っているのかもしれない。
追いかけるわけにもいかないジレンマ
こちらから連絡を入れればいい話かもしれない。でも、それをしてしまうと「しつこい」と思われるかもしれないという不安がつきまとう。だから連絡を待ってしまう。「こっちから連絡するね」に対して、ただひたすら待つしかできない。このジレンマが、また自分を孤独にしていく。
事務員とのコミュニケーションでも時折感じるズレ
一人だけ雇っている事務員とは、なるべくフラットな関係を心がけている。でも、こちらが何かを頼んだあと、「わかりました、あとでやっておきます」と言われると、ふと「やってくれるかな…」と不安になる瞬間がある。もちろん彼女はちゃんとやってくれるのだけれど、言葉の温度差に過敏になっている自分に気づくと、少し情けなくもなる。言葉の背景にある気持ちを、必要以上に読み取ろうとしてしまう自分がいる。
独り身であることとこの言葉の親和性
独身でいると、「こっちから連絡するね」という言葉にますます敏感になる。家庭があれば、誰かが日常の中で自然に話しかけてくれる。でも、私にはそれがない。だから、ひとつひとつの言葉が、自分との関係性を強調してくる。「自分は関係の中にいないのかもしれない」という孤独を、たった一言で感じるようになってしまった。