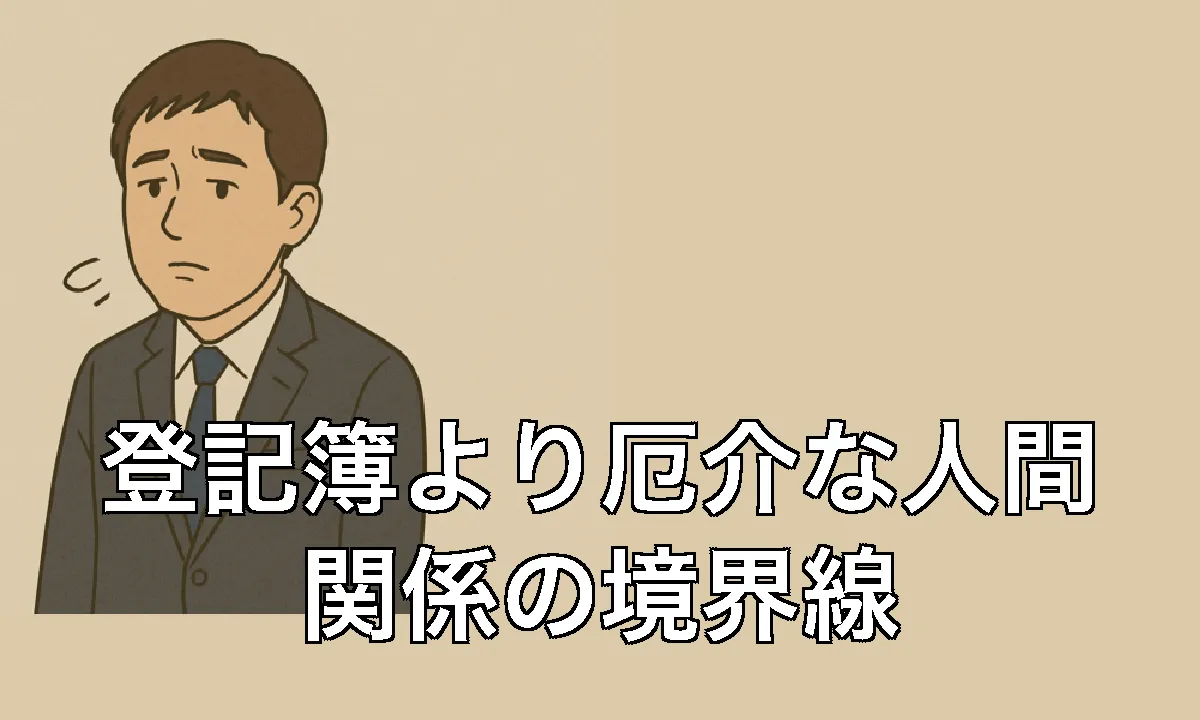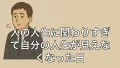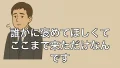登記簿より厄介な人間関係の境界線
土地の境界線なら杭を打てば済むのに
司法書士の仕事をしていて思うのは、「土地の境界線は杭を打てば明確になるけど、人間関係はそうはいかないなぁ」ということ。たとえ隣接地との境界に多少の争いがあったとしても、法務局に提出する図面があって、現地で立ち会って、境界確認書を交わせば終わる。でも、人との関係はそう簡単に割り切れない。こちらが気を使っても、相手の受け取り方次第で全く別の方向に進んでしまう。杭を一本打ち込むだけで済めば、どれだけ楽だったことか。
図面と現地が違うときもあるが人間関係はもっと曖昧
たまにあるのが、図面では確かに線が引かれているのに、現地に行ってみるとフェンスやブロック塀が微妙にズレているというケース。依頼者も困惑して、こちらとしても一緒に悩むことになるけど、最終的には測量士さんや法務局と連携して調整すれば解決できる。でも、人との関係は「どこまでが仕事の話で、どこからが余計なお世話か」といった判断が本当に難しい。図面があればいいのに、なんて思う場面が多すぎる。
登記簿の整合性は努力すれば保てる
登記簿の整合性を保つために、書類を整え、関係者と連絡を取り、期日を守って対応すれば、基本的にはうまくいく。ルールが決まっていて、その通りに動けば結果がついてくる。努力が報われる世界だ。しかし、人間関係はそうはいかない。真面目に対応したつもりが、相手には冷たく映ったり、逆に過剰に出たことで「踏み込みすぎ」と思われたり。自分の意図と他人の受け取り方がズレると、結果は読めない。
人付き合いは一方通行では成り立たない
土地の権利は単独で所有できるけど、人間関係は相手がいてこそ成り立つ。こちらが誠意を尽くしても、相手の状況や心情によっては通じない。そうすると、疲れてしまうのが正直なところ。電話一本のかけ方で悩み、メールの言い回しを何度も書き直す。「そんなに気を遣わなくても」と言われても、気を遣っている自分がいる。この感覚、分かってくれる人、どれくらいいるんだろう。
境界確認より難しい気持ちの調整
現地調査や境界確認のような作業は、目に見えるからこそ対処しやすい。ところが、感情のぶつかり合い、勘違い、期待のすれ違いといった心の問題になると、一気に不安定になる。法律のプロとして振る舞いながら、同時に人として誤解されないように気を配る。その二重のプレッシャーが地味に堪える。法律と感情、どちらにも境界線があるのに、その線引きがブレやすいのが現実だ。
書類に残せない感情の処理
登記申請書や委任状、議事録などは紙に残せるし、見直せば内容がはっきりする。でも、仕事中にふと交わす雑談や態度、表情に宿る感情のやり取りは記録に残らないし、後で証明もできない。たとえば、ある依頼者に少し冗談を言ったら、それが「バカにされた」と捉えられたことがある。こちらは場を和ませようとしたつもりだっただけにショックだった。紙より人の心のほうがずっと繊細だ。
法務局では解決できない領域
トラブルになっても、登記の不備や調整なら法務局で相談もできるし、改善の余地がある。でも、人間関係のこじれはそうもいかない。いざこじれたときに、どこへ行けば解決できるのか。カウンセリング?友人?それとも、ひとりで反省して終わりにするしかないのか。正直、そんな問題ばかり積もる日もある。冷静な判断と感情的な傷つきが同居する仕事って、しんどい。
仕事と私情のバランスの取り方に苦慮する日々
依頼者との関係や、事務員との距離感など、感情を交えずにはいられない場面も多い。とはいえ、過剰に感情移入すれば逆にトラブルになる。「ちょうどいい関係」を意識すればするほど、ぎこちなくなるジレンマ。気を許せば「なめられる」、距離を取れば「冷たい」と言われる。そんなバランス感覚に疲弊しながらも、なんとか今日も仕事をこなしている。
近すぎず遠すぎずの距離感が一番難しい
司法書士として、信用と信頼のバランスは命綱だ。けれど、それを支える人間関係の調整が一番難しい。「先生」と呼ばれる立場にありながら、威圧感を与えないように気を配る。でも、フレンドリーすぎると軽んじられる。仕事は真面目に、でも人間関係は柔らかく。それが理想だけど、現実にはなかなかうまくいかない。
気を遣いすぎて疲れてしまう性格
もともと、気を遣いすぎる性格なのかもしれない。学生時代から、野球部でも「空気を読む」タイプだった。監督の機嫌、先輩の顔色、試合中の仲間の緊張感、全部を察して立ち回ってきた。今もその癖が抜けない。依頼者の話し方、服装、ちょっとした沈黙にまで気を張ってしまう。結果、1日終わるころにはぐったりしている。
事務員さんとの関係にも微妙な境界がある
今の事務員さんは気が利いて、よくやってくれている。ただ、こちらが雇い主であることに変わりはない。その関係性のなかで、フランクに接しすぎるとおかしな空気になるし、厳しくしすぎても萎縮される。たまに「先生はそういうつもりで言ったんじゃないと思うんですけど…」とフォローされて気づく。関係は良好でも、境界線はつねに意識してしまう。
優しさが裏目に出ることもある
できるだけ優しく、丁寧に、誠実に対応しようとしている。それは自分の信念でもある。でも、その優しさがときに「断れない人」「曖昧な人」と映るらしく、面倒ごとが舞い込む。気づけば、「先生、なんでも引き受けてくれるんですよね?」という空気。いい人でいたい気持ちと、自分を守りたい気持ちの間で揺れ続けている。
法律のプロでも人の心には線が引けない
境界線という言葉にこれほど敏感になる職業もそうそうないと思う。でも、それはあくまで土地の話。人と人の間に線を引くことのほうが、よっぽど難しい。こちらが望んでも、相手が拒めば関係は成立しない。逆もまた然り。司法書士としては線を引くことが仕事だけど、人間としては線の引き方をいつも悩んでいる。
感情のもつれに理屈は通じない
書類の不備にはロジックで対応できる。でも、感情の不一致にはそれが通じない。どれだけ論理的に正しくても、感情が傷ついていれば意味がない。ある依頼者に対して、手続きを急ぐために率直に話したら、「冷たい」と言われたことがある。理屈と気持ち、両方を満たすのは簡単じゃない。
正しさと優しさの間で揺れる
法律に基づいて、正しい判断を下す。それが司法書士の役割。でも、「正しい」だけでは通らないのが人間社会。ときには、少し間違っても「優しさ」が必要な場面もある。そのたびに、「自分の判断は間違ってなかったか」と悩む。正しさを優しさで包むには、自分が削られていくような感覚になる。
それでも人と関わるしかない職業
疲れるし、面倒だし、傷つくことも多い。それでも、司法書士という仕事は、人と人の間に立って成り立っている。避けては通れない人間関係の境界線。その難しさに何度もぶつかりながら、それでも明日もまた人と向き合う。たとえ線が引けなくても、心の中に「ここまでは大丈夫」と言える自分の軸だけは持っていたい。