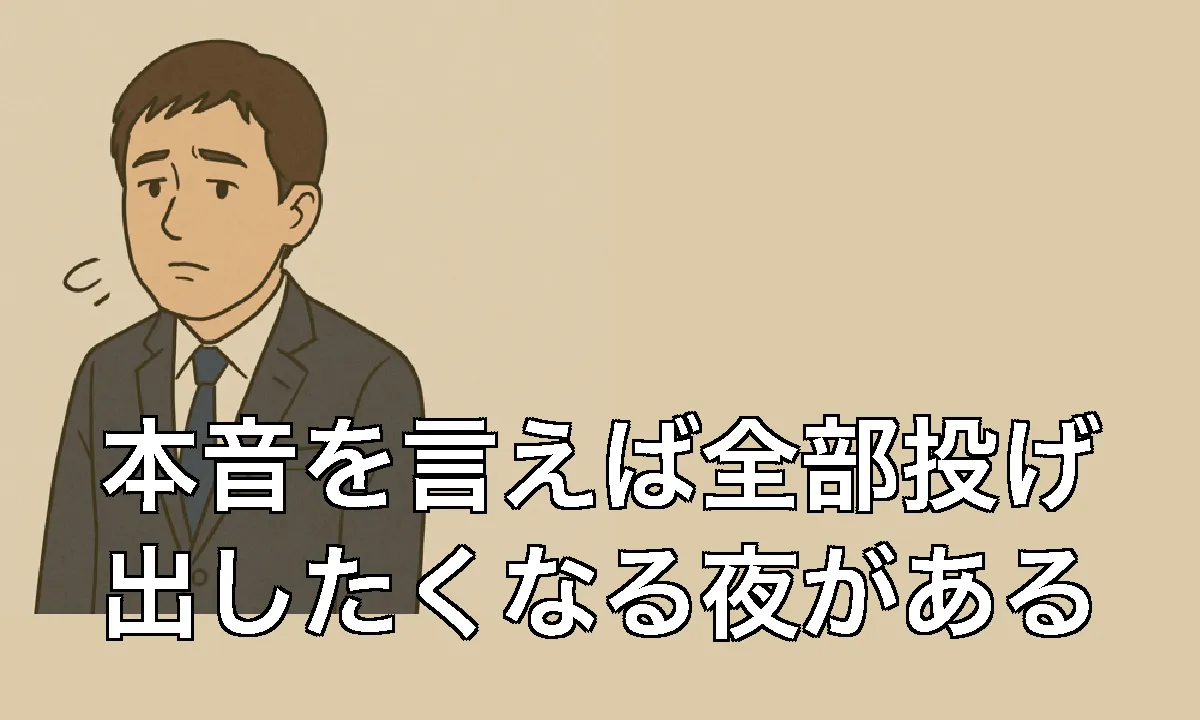本音を言えば全部投げ出したくなる夜がある
ふと全部やめたくなる夜は確かにある
日々の業務に追われる中で、「もう全部投げ出したい」と思う瞬間がある。司法書士という職業柄、責任の重さやプレッシャーは相当なものだ。特に地方で一人事務所を構えていると、逃げ場がない。繁忙期になると朝から晩まで仕事に追われ、ミスは許されない。ふと時計を見れば深夜1時。そんなとき、ふと湧いてくるのだ。「もういいや、辞めてやろうか」と。これは弱音ではなく、本音だ。誰にも言えないが、こんな夜は確実に存在する。
きっかけは些細なミスだったりする
ある日、簡単な相続登記で書類の一枚を入れ忘れたことがあった。依頼人に渡す直前に気づいたが、冷や汗が止まらなかった。たったそれだけのミスで、今までの信頼や積み重ねがガラガラと崩れるような感覚に陥る。誰も怒っていないし、実害もない。でも、自分だけがその重みに潰されそうになる。司法書士の仕事は、完璧であることを前提に回っている。ミスが人の人生に影響を与えるかもしれない。そんな緊張の中で、心が折れそうになるのは当たり前なのだ。
登記の書類が一枚だけ足りない夜
その夜、書類が一枚足りないことに気づいたのは、事務所に一人残っていた時だった。事務員はすでに帰宅し、相談できる相手もいない。冷たい蛍光灯の下で、プリンターとにらめっこしながら、何度も確認した。「あるはずのものがない」その不安と焦りは、まるで試合終盤にエラーした気持ちと似ている。元野球部としては痛いくらいに思い出せるあの感じ。孤独と自己嫌悪が交差する夜だった。
事務員の帰った後に気づく絶望感
事務員がいるだけで、普段は気にも留めないことが支えになっているのだと、こういう時に気づかされる。たった一人で事務所に残り、誰にも相談できない状況でトラブルに気づくと、絶望感が一気に押し寄せてくる。「またか…」と、何度も呟きながら椅子に沈む。誰かに責められたわけじゃない。でも責めているのは自分自身。誰にも見られないところで、静かに潰れていく夜は本当にしんどい。
忙しさに慣れたと思ったのに限界がくる
司法書士として十数年やってきた。忙しさには慣れているつもりだった。でも、ある日突然、限界が来る。それは体ではなく、心の方だ。仕事は減らず、書類は増え、人とのやりとりも複雑になる。年々感じるのは、「こんな働き方、いつまでできるんだろう」という漠然とした不安。それでも止まれない自分がいる。止まった瞬間に、誰も助けてくれないことを知っているから。
やりきれないタスクの山
机の上に積み上がったファイル、返していないメール、処理しきれない登記申請。何から手を付けるべきか分からず、ただただぼーっと立ち尽くす夜もある。そんなとき、頭の中では「効率的に動け」と自分に命令するが、体が動かない。「これ、ひとりでやる量じゃないよな」と呟く自分に、誰も返事をくれない。やるしかないとわかっていても、心がついてこない夜がある。
気合と根性じゃもう乗り切れない
昔は「気合いで乗り切れ」と言っていた。でも40を超えて、気合も根性も限界があると痛感した。身体の疲れは翌日に残るし、精神的な疲弊は積み重なる。無理をした翌日は、判断力も鈍るし、集中力も切れる。自分だけでなく、依頼者にも迷惑をかけてしまう。気合だけで仕事を回す時代は終わったのだ。それでもなお走り続けなければならない矛盾に、心が耐えきれなくなる。
誰にも相談できないのが司法書士という仕事
司法書士は「士業」として独立して働くことが多く、基本的にはひとりで何もかも背負う職業だ。誰かに「ちょっと聞いてよ」と言いたい気持ちがあっても、相手がいないことの方が多い。事務員に話すには重すぎるし、他の同業者には弱みを見せづらい。孤独感は年々深くなり、心を閉ざしてしまう人も少なくない。自分もそうだった。
失敗はすべて自己責任の世界
この仕事に「他人のせい」は通用しない。書類の不備、スケジュールの遅れ、依頼者との行き違い──全部、自分の責任として返ってくる。誰かのせいにして逃げる場所がない。それが独立して働くということだ。人に頼ることができないからこそ、強くなる部分もあるが、同時に脆くもなる。失敗が続いたとき、逃げ場のなさが一番こたえるのだ。
上司も部下もいない個人経営のつらさ
会社勤めなら、何かあった時に上司に報告し、同僚に愚痴をこぼすこともできる。でも個人事業主にはそれがない。事務員はいても、対等な話し相手ではないし、すべてを共有するわけにもいかない。経営から実務、クレーム対応まで全部自分。誰も助けてくれない。どんなに優秀でも、どんなに頑張っても、ひとりで抱えるには重すぎる日がある。
先生と呼ばれる違和感
「先生」と呼ばれることに、未だに違和感がある。社会的には士業は敬意をもって呼ばれるべき存在なのだろう。でも、自分の中には「いや、ただの疲れたおじさんです」と言いたくなる気持ちがある。立場上、弱音を吐けないことが増える。「先生なんだから大丈夫ですよね」と言われるたびに、どこかで自分の本音が遠ざかっていく気がする。
人間くさい部分は見せられない
本当は、不安や愚痴や失敗を誰かに聞いてほしい。でも「先生」という仮面を被った瞬間、それらは封印される。飲み会の席でも気を抜けず、相談されるばかり。自分の話は、誰にもしてはいけないような空気がある。人間らしさを隠して、仕事を全うしなければならないのが、この職業のしんどさでもある。
愚痴もこぼせない仮面生活
愚痴を言った瞬間に、「頼りない先生だ」と思われるんじゃないかと不安になる。だから黙ってしまう。飲み屋で隣に座った見知らぬ人にすら、つい仮面をかぶってしまう。実は、その仮面を脱ぎたい夜が何度もある。でも、脱いだ自分を誰が受け止めてくれるだろうか。そう思うと、今日もまた仮面をつけたまま眠るしかない。
それでも辞めなかった理由を数えてみる
こんなにしんどい仕事なのに、なぜ辞めなかったのか。それはたぶん、自分でも気づかないうちに、やりがいや誇りを感じていたからだろう。ふとしたときに、依頼者の「助かった」の一言が胸に残ったり、難しい案件をやりきったときに得られる静かな達成感。それが自分を支えていたのだと思う。
依頼者の助かりましたに救われたこと
ある年配の女性から、遺言書の作成と相続登記の依頼を受けた。手続きがすべて終わったとき、深々と頭を下げて「あなたにお願いしてよかった」と言われた。その言葉が、心のどこかに染み込んでいた。大変な仕事だけど、人の役に立てる瞬間がある。それを思い出すと、もう少しだけ頑張ろうという気持ちになる。
ひとりきりでも乗り越えた達成感
どんなに孤独でも、どんなにしんどくても、自分で最後までやりきった時の達成感は何にも代えがたい。誰かに拍手されるわけでもなく、ニュースになるわけでもない。ただ、自分の中に静かな充足感が広がる。それだけでも、この仕事を続ける価値があると信じたいと思う。
あの登記が終わったときの静かな達成感
一度だけ、本当に難しい農地転用の案件を通したことがある。関係機関とのやりとりが煩雑で、心が折れかけた。でも、すべて終わって登記完了の証明書が手元に届いたとき、誰もいない事務所でひとり静かにうなずいた。「やったな」と。誰も褒めてくれないけど、自分だけは分かっている。あの瞬間があるから、また次の日も動き出せる。
地味でも意味のある仕事だと思える瞬間
この仕事は華やかではない。目立つこともないし、一般の人から見ればただの事務仕事に見えるかもしれない。でも、誰かの人生の大切な節目に関わっているという点では、誇りを持てる仕事だ。表には出ないけど、陰で支える存在。そんな自分の役割を少しでも信じられるうちは、まだこの仕事を続けられる気がしている。
もし後輩に聞かれたらこう答える
もし、司法書士を目指している人や、駆け出しの後輩から「辞めたいって思ったことありますか?」と聞かれたら、私はこう答えると思う。「あるよ、めちゃくちゃある」と。でも同時に、「それでも続けてきてよかったこともある」とも伝えたい。弱さを知った上で、それでも踏みとどまった経験を語れる人間でありたい。
投げ出したくなる日は絶対にある
完璧を求められる職業である以上、プレッシャーも孤独もつきまとう。だからこそ、「投げ出したい」と思う日は誰にでもある。むしろ、そう思えるくらい真剣に向き合っている証拠だ。無理にポジティブにならなくていい。逃げたくなる日は、心の防衛反応。だからこそ、まずはその気持ちを認めてやることが大切だと私は思う。
でもその日を越えると少しだけ強くなれる
不思議なことに、限界だと思った日を一つ越えると、少しだけ心が強くなっている。昨日の自分よりも、少しだけ耐性がついている。それは誰にも見えないけれど、自分の中に確かに積み重なっていく。司法書士という職業は、その小さな積み重ねを糧にして進むものかもしれない。今日もまた、そんな一歩を重ねていこうと思う。