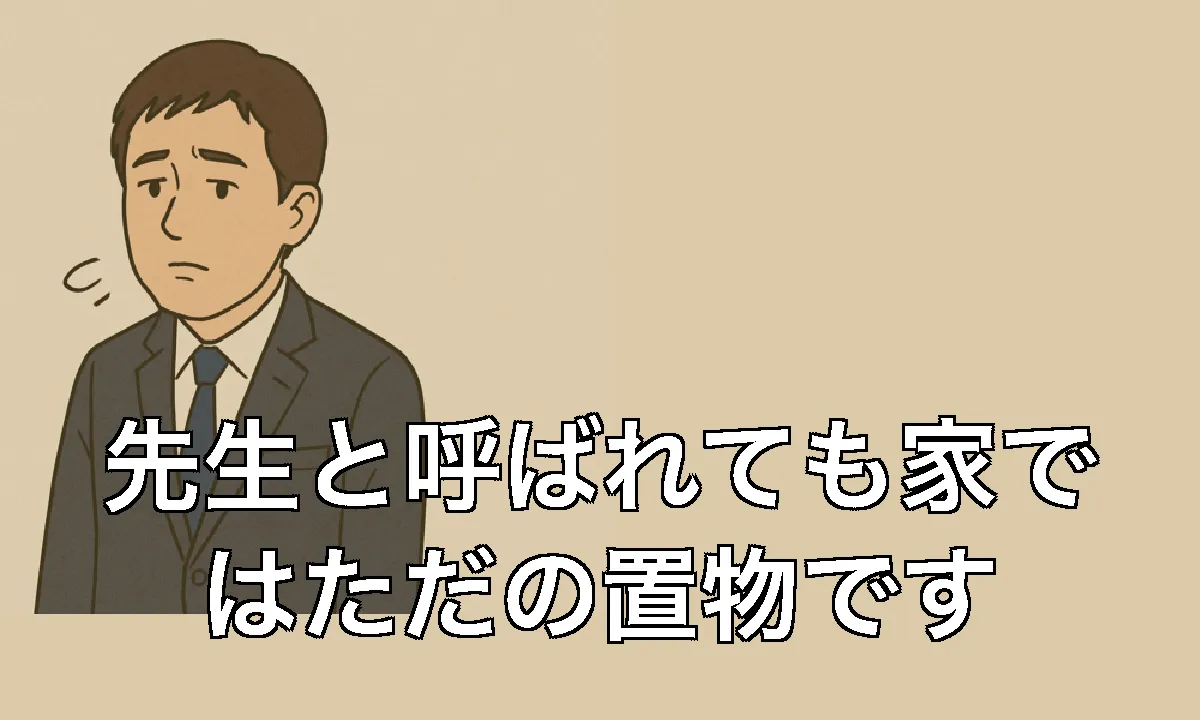外では先生家では無言の空気感
「先生、ありがとうございました」と頭を下げられ、深々と感謝されることがある。登記が無事に完了した後、依頼者の笑顔を見て「やっててよかった」と思うこともある。けれども事務所のドアを閉めて家に帰ると、その空気感は一変する。誰からも声をかけられない。誰も出迎えない。テレビの音もなければ、家の中に人の気配すらない。自分が空気みたいにそこに存在していても、何も始まらない。あの「先生」と呼ばれていた自分は、まるで別人だったかのようだ。
「先生」と呼ばれても家では何も始まらない
事務所では書類を片手に、時にはちょっとした法律相談にも応じ、「先生、ちょっと聞いていいですか?」と頼られる。電話口でも「稲垣先生」と名指しされるたびに、こちらも気を引き締めて応える。でも、家ではそんな役割は存在しない。椅子に座ってもテレビはついていないし、炊飯器の中身すらない。誰かが「今日もお疲れさま」と言ってくれるわけでもない。やるべきタスクもなければ、誰かと交わす会話もない。家に帰ると、急に人生が停止したような気分になる。
玄関のドアを開けた瞬間にスイッチが切れる
毎日、事務所の鍵を閉めてから帰る道のりが一番の切り替えポイントだ。信号の赤を待ちながら、明日の申請のことや、あの案件の補正が来るかもしれないと頭を巡らせている。ところが、自宅の玄関に足を踏み入れた瞬間、そのすべてがスンと消える。誰もいない部屋。冷えた空気。照明のスイッチを自分でつけながら、ふと自分の存在を確かめる。ああ、自分って何なんだろうなと、そんなことすら思ってしまう。
ただいまと言っても誰も反応しない夜
癖になっているのか、玄関の扉を閉めるときに「ただいま」とつい口に出してしまう。もちろん返事はないし、むしろその「ただいま」が部屋にむなしく響くだけだ。たまに宅配の人が置いていった不在票がドアに挟まっていて、「ああ、人と会ったのって今日あれだけか」と思う日もある。昔は帰宅後に「飯どうする?」とか「今日のニュース見た?」みたいな会話があるのが普通だと思っていた。今では、その「普通」がどれほど貴重だったか、やっとわかってきた。
事務所では頼られる存在なのに
毎日、様々な相談や登記案件が舞い込む中で、私は「先生」として機能している。それなりに信頼もあり、リピーターも増えてきた。そういう意味では、この地方の小さな司法書士事務所としては、よくやっているほうだと思う。でも、その“機能”が終わると、自分という存在がスイッチオフになる感覚がある。「稲垣先生」としての役割を脱いだ瞬間、誰にも見られていない、何者でもない自分が残るだけなのだ。
依頼者の前では威厳があるふり
相談者の前では、それなりに自信があるような顔をして応対している。過去の判例や法務局の対応傾向なども交えながら、的確なアドバイスをしているつもりだ。でも本当のところは、帰って一人になると「これでよかったんだろうか」と不安になる日もある。たとえ正しい手続きをしていても、人の人生に関わる分、どこかで怖さがある。そして、その不安を誰かに話す相手もいないのが一番しんどい。
事務員さんの冷静さが身に染みる
事務員さんは真面目で、淡々と仕事をこなしてくれる。ありがたい存在だ。ただ、忙しさに飲まれてしまい、ろくに感謝の言葉もかけられていないのが現状だ。時々、昼休みにポツリと「今日も一日長そうですね」と言ってくれる一言が、何よりの癒しだったりする。けれど、それ以上の会話は基本的に業務連絡だけ。距離感を保たなきゃと思うあまり、結局また孤独に戻ってしまう。
忙しい日々に埋もれる自分
登記の期日、法務局の対応、依頼者からの電話やメール。予定表が真っ黒になっているときは、むしろありがたいと思ってしまう。忙しいと「考えずに済む」。寂しさや孤独感をごまかすのに、仕事はちょうどいい隠れ蓑になる。でも、それが終わった夜にくる静けさは、何よりも重い。元野球部だったころは、声を出してなんぼだったのに、今はその声を出す相手すらいない。
朝から晩まで登記と書類と締切に追われる
朝イチのメールチェックから始まり、申請書類の最終確認、補正対応、相談者との面談…。一日中デスクから動けず、気づいたら夕方になっていることもある。そんなとき、ふと「今日も誰ともちゃんと話してないな」と気づいてしまう。人と接しているようで、実は“業務”としてのやりとりだけ。誰かと笑うとか、ぼやき合うみたいな時間は、意識して作らない限りどこにも存在しない。
ランチタイムはコンビニおにぎりで3分
ランチなんてものは、たいていコンビニで買ったツナマヨおにぎりをデスクで頬張って終わる。3分で済ませて、そのまま電話対応へ。ゆっくり味わうなんてことはない。昼飯が“作業”になっているこの生活も、もう何年になるだろう。たまに外食している人を横目に、「ああ、ああいう余裕っていいな」と思うが、気づけば足はいつものコンビニに向かっている。
ふと気づくと独り言だけが増えていく
「あれ、これどこにしまったっけな」とか「この日付でいいんだっけ」なんて、無意識のうちに声が出ていることがある。昔はこんなに独り言を言うタイプじゃなかったのに、今ではそれが日常。人と会話しない時間が長くなると、自然とそうなるんだろうか。喉を動かさないと、自分が存在してるって実感できないような気もする。
しゃべっているのは電話か自分だけ
事務所では電話が鳴る。その応対をしている時は“誰かと話している”気になる。でも、それは本当の意味での「会話」じゃない。むしろ、終わった瞬間に「あれ、今日自分の声ってこれが最初だったな」と気づくこともある。人と繋がっているようで、何も残らない会話ばかりだ。せめて、自分の言葉で誰かを笑わせられる日があったら、どんなに救われるだろう。
誰かと話すのが怖くなってくる瞬間
寂しさに慣れてくると、逆に人と話すことが億劫になってくる。久しぶりに旧友と話しても、何を話していいのかわからない。「最近どう?」と聞かれても、仕事の話以外に出てこない自分が情けない。友人は家庭を持ち、子どもの話や休日の出来事を話してくれる。でもこちらは「特に何もないよ」と返すしかない。会話が続かない自分を見て、さらに距離を感じてしまう。
それでも仕事に救われることもある
どれだけ疲れていても、たまに「先生に頼んでよかった」と言われることがある。その一言で、なんとか今日を生き延びられる。人の役に立てたという実感だけが、自分の存在を肯定してくれる。たとえ家に帰っても無音で、誰にも気づかれないとしても、日中に誰かの役に立てたのなら、それで少し報われる。
「助かりました」の一言が沁みる日も
補正対応でバタついた案件がようやく終わり、依頼者から届いた「本当に助かりました」というメール。それを読みながら、「ああ、自分の仕事って意味あるんだな」と思う。たった一文。それでも、その日一日の疲れがふっと軽くなる感覚がある。お金じゃない。評価でもない。ただ、誰かにとって「必要だった」こと。それが、また明日も仕事を続けられる理由になっている。
自分が必要とされている場所を実感する
誰にも気づかれない存在だと思っていても、必要としてくれる人がいる限り、自分はまだ「先生」として存在できる。外ではそうやって役に立ち、誰かに感謝されることもある。家では無音。だけど、それでも生きている意味はある。誰かの「ありがとう」でつながっているこの仕事が、今の自分を支えてくれている。