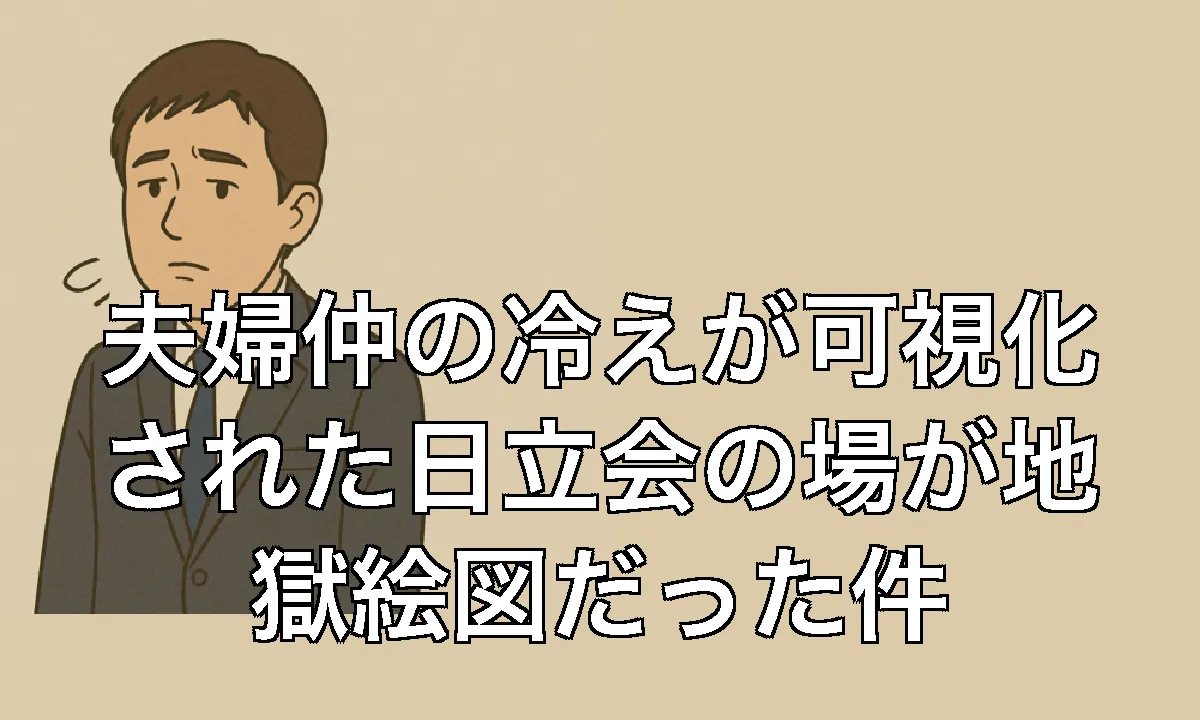立会の現場で起きた異変
その日はなんというか、朝から変な胸騒ぎがしていた。電話越しのご依頼者の声が妙にトゲトゲしかったのも気になっていたが、まさかあんな空気になるとは。登記の立会に伺った先は、郊外の新築戸建て。書類の準備は万端、段取りも問題なし。なのに、玄関を開けた瞬間から、肌にまとわりつくような緊張感。夫婦の間に言葉はない。ただ視線も合わさず、手だけが機械的に動く。私は場違いな場所に踏み込んでしまった感覚に襲われた。
違和感は玄関から始まっていた
ピンポンを押して出てきたのは奥さん。軽く頭を下げた後、すぐに背中を向けてリビングに戻った。玄関に立っていた私は、軽く靴を脱ぎながら「これはちょっと変だな」と思った。普通なら、「寒い中すみません」とか、「こちらです」とか、何かしらの一言があるものだ。でもこの日は違った。出てこないご主人、声を発しない奥さん。まるで私は空気のような存在だった。玄関マットの位置がズレたままになっていたのも、なんだか象徴的だった。
席に着いた瞬間に感じた張りつめた空気
ダイニングテーブルに並べられた書類、そして奥さんの正面に座るご主人。どちらも必要最低限の視線しか向けてこない。私はできるだけ明るく、そしてスムーズに手続きを進めようとするけれど、うまく呼吸が合わない感じ。夫婦間の会話は一切なく、私が「こちらにご署名をお願いします」と言うと、黙ってペンを持って記入する。ただそれだけ。その沈黙の重さは、いっそ耳鳴りが聞こえてくるレベルだった。まるで冷蔵庫の中にでもいるような時間だった。
無言の応酬に挟まれる司法書士の孤独
登記の立会というのは、形式的な作業だと思われがちだが、実際には「人と人」の関係性の中に立ち会う仕事でもある。今回のような冷えきった夫婦の間に座ると、その空気がずっしりと胸にのしかかる。私はあくまで中立で、淡々と業務を進めるべき立場。でも、心が疲れるのだ。笑顔を向けても返ってこない。質問をしても、目をそらしたまま答えが返ってくる。ここにいていいのか?という感覚すら芽生えてくる。
ボールペンを渡す手が震える午後
「こちらにご署名いただけますか?」と差し出したボールペン。奥さんがそれを受け取る瞬間、手がわずかに震えてしまったのを自覚した。緊張で、というより、場の重苦しさに心が負けかけていたのだと思う。普段なら何百回とこなしているルーティンのはずなのに、その日は自分の存在が邪魔に思えた。私はただ書類に名前を書いてもらいたいだけなのに、まるで修羅場に巻き込まれた傍観者になったような気分だった。
想定外の言葉が場を凍らせる
なんとか書類の説明を終え、あとは実印を押していただければという段階で、事件は起きた。私が「最後にこちらに押印を」と言ったとき、奥さんが小さく、しかしはっきりとこう言ったのだ。「別に、もういいけどね。どうでも」。その一言で、すべてが止まった。
奥さんの「別にいいけどね」による破壊力
その言葉には怒りも、悲しみも、諦めも混ざっていた。ただ、最も強く感じたのは「冷たさ」だった。ご主人は黙ったまま目線を逸らし、押印を躊躇する。私はその場を収めるために何か言葉を探したが、出てこない。時間が止まったような感覚。言葉がナイフになる瞬間を、私は目の前で見た。あの「別に」という言葉の中には、長年積み重ねた何かが詰まっていたのかもしれない。
ご主人の沈黙という名の応答
奥さんの言葉のあと、ご主人はただ無言だった。それが逆に怖かった。怒鳴るでもなく、諭すでもなく、ただ沈黙。その沈黙がまた空気を冷やしていく。私は何かを取りなすべきかと一瞬考えたが、関係性の深みに踏み込むのは司法書士の仕事ではないと自分に言い聞かせた。結局、ご主人は押印したが、その手の動きは機械のように鈍く重かった。
立会が「立ち会い」にならなかった瞬間
立会という言葉には、なにか人の交わりのような意味が含まれている気がする。でもこの日のそれは、完全に形式だけのものだった。三人で同じテーブルにいたのに、誰一人、心を通わせてはいなかった。私はただの書類の監視者、奥さんは諦めの実行者、ご主人は感情を失ったスタンプマシン。あの場は「立ち会い」ではなかった。「居合わせただけ」だった。
そこにいたくないのはたぶん全員
心の中で、誰もが「ここにいたくない」と思っていたんじゃないだろうか。私もそうだったし、奥さんも、ご主人も。違う形での立会だったなら、もっと温かい空気になったのかもしれない。けれど、この日は全員が冷えていた。書類だけが整然と並び、人間関係はボロボロだった。終わった後、私は外の冷たい風をわざと浴びながら歩いた。心の温度をリセットしたかった。
現場を通して感じたこと
登記業務というのは、紙の手続きだけじゃない。人の気持ち、人生の節目、関係性の変化、そういったものが目の前で繰り広げられる。事務的に済ませようとしても、心までは遮断できない。そして、時にその感情に巻き込まれてしまう自分がいる。
私たちは記録係ではない
書類を確認し、印をもらい、完了を報告する。それだけなら、AIでもできるかもしれない。でも、私たち司法書士は「人の人生の瞬間」に立ち会っている。特に不動産の売買や相続、離婚後の名義変更などは、感情が渦巻く現場だ。そこにただの記録係としているわけにはいかない。どうしたって空気を読み、時には耐え、時には寄り添いながら業務をこなしている。
人間関係の「証人」にもなっている自覚
ときどき、私は法的な証明をするだけでなく、人間関係の「証人」になってしまっているのではと思う。名前を並べるだけでは済まない、人の繋がりや断絶、その一端を目の当たりにすることが多い。この日も、あの夫婦の冷え切った関係に、無言で「在った」という証人として記憶に残ってしまった。業務は無事に終えたけれど、心には妙な後味が残っている。
だからこそ心が削られる日もある
司法書士の仕事は地味だ。でも、地味なだけじゃない。静かな場所で、静かに心を削られる日もある。その疲れは誰にも見えないし、誰にも伝わらない。でも、私たちはそういうものと向き合いながら働いている。だからこそ、時には愚痴の一つも言わせてほしい。元野球部の気合いで踏ん張っているけれど、冷え切った現場の記憶は、今もたまに夢に出てくる。