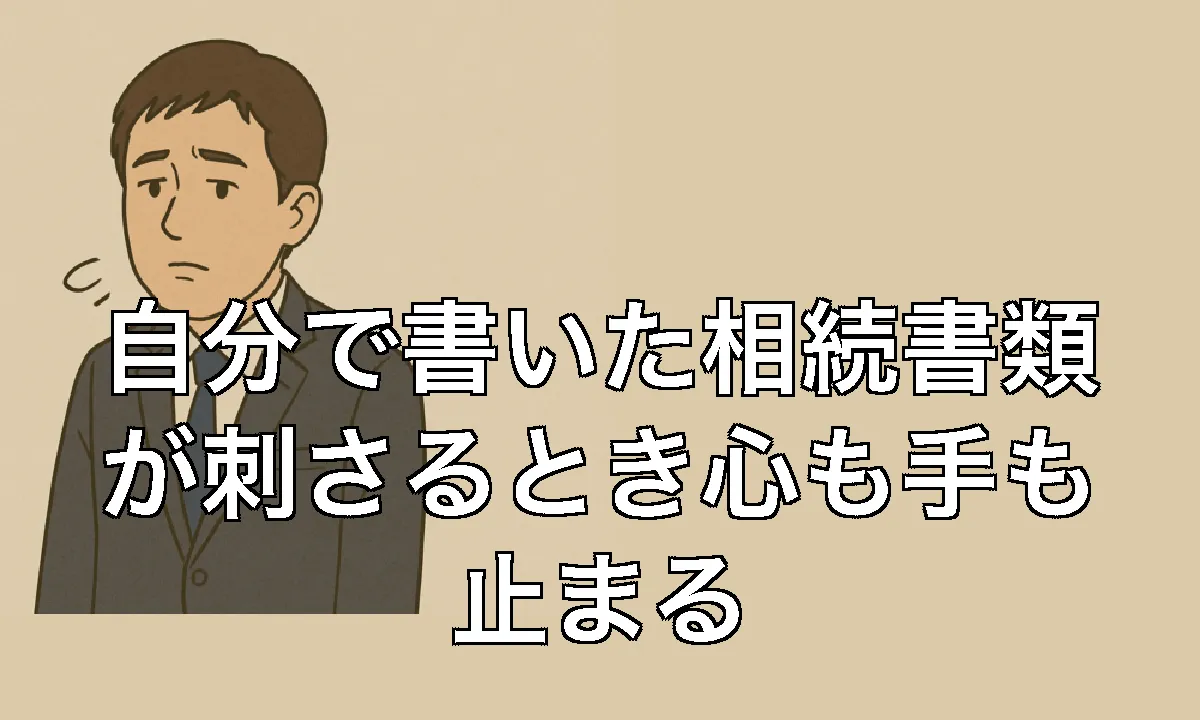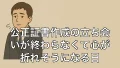いつものように始まった相続の相談
相続の相談なんて、もう何百件も受けてきた。淡々とヒアリングして、必要な書類を案内して、スケジュールを確認して。そういうルーチンで動くことが多くなっていた。地方の事務所で一人事務員と細々やっていると、効率を重視しないと回らない。でも、そんな中でふとしたことで立ち止まることがある。あの日の相談も、最初は「よくあるパターン」だと思っていた。
形式的なやりとりに慣れすぎていた自分
正直に言えば、最近の自分は「またか」と感じながら話を聞いていることが多かった。特に法定相続通りで争いもない案件だと、頭の中で必要書類のリストを思い浮かべながら相槌を打っていた。事務員から「この人、自分で書類作ってきたそうです」と渡された封筒を受け取ったときも、まぁ内容は見れば分かると思って、特に期待もせず封を開けた。
「自筆で書いてきました」からの違和感
その書類は、A4のルーズリーフに細かい字でぎっしりと書かれていた。形式的な雛形に沿っているわけではない。でも、整ってはいないその文章が、逆に妙に目に残った。内容を読み進めるうちに、明らかに「伝えたい」意図がにじんでいた。これはただの準備資料ではない。そう思った時点で、すでに私は”効率”というフィルターを外されていた。
内容よりも筆跡が語りかけてくる
文字がかすれていた。おそらくボールペンで何度も書き直したのだろう。ところどころに線を引き、消した痕跡が残っていた。きれいな書類じゃない。でも、必死に誰かに何かを伝えようとしていた。それが、行間というよりも、筆跡の乱れから伝わってくる。「誰かの思いが乗った紙」を久々に手に取った気がして、気づいたら読み終えるまで一言も発さず集中していた。
司法書士なのに心が持っていかれた
感情に引きずられてはいけない。それは、資格を取った頃に叩き込まれたことだ。事実に基づき、法的に処理をする。その冷静さを失えば、ミスが出る。それでも、自分で書いた相続書類を前に、心が勝手に動いてしまう瞬間というのはある。そして、それは決して悪いことではないのかもしれないと思うようになった。
事務的処理と感情のあいだで揺れる
書類としては使えない。形式に合っていないから、そのままでは登記も何も進められない。でも、相談者のその思いを一切無視してしまって良いのか、と自分に問いかけてしまった。私は法的なアドバイスをするためにここにいる。でも、依頼人が望んでいるのは、もしかしたら「聞いてくれる人」だったのかもしれないと気づいた。
書類なのに感情が滲んでしまう瞬間
たとえば、「弟には本当に世話になったから少し多く渡したい」と書いてあった。法律上はそう単純にはいかない。でも、その人の中では、それが当然の流れだったのだろう。感謝、後悔、心残り、全部がこの1枚の紙に詰まっていた。書類を読んで泣くなんて、少なくとも司法書士としては恥ずかしいと思う。でもこのときばかりは、少し目頭が熱くなってしまった。
たった一行の言葉が刺さる理由
「親父が最後に笑ったのは、たぶん俺のせいじゃない」。この一文があった。相続とは無関係なはずのその一文が、どうしても頭から離れなかった。家族という存在がいかに重く、そして不器用に関係を結んできたかを物語っていた。司法書士というフィルターを通しても、その言葉の破壊力は十分すぎるほどだった。
その書類に詰まっていたのは人生だった
何百件とやってきたけれど、一つとして同じ相続はない。そのことを改めて実感した。結局、書類の裏側にある人生をどれだけ想像できるか。そこに私たちの役目があるのかもしれない。想像で書類は作れない。でも、背景を知らずに処理だけしてしまうのは、やっぱり寂しい。
遺された人が書いた言葉の重さ
相談者は、父親の死後も「許されたかった」のだと思う。自分なりのけじめとして、その気持ちを書き綴った。司法書士に渡すには場違いな内容かもしれない。でも、それでも「読んでもらいたかった」気持ちは、まっすぐに伝わってきた。そして、それを受け取ったこちらも、少なからず影響を受ける。それが、仕事の重さでもある。
誰のための相続かを問われた気がした
登記のための相続か、家族の再確認のための相続か。そのバランスは常に難しい。こちらとしては、正確に、迅速に処理をすることが求められる。でも、相続をきっかけに家族がもう一度つながったり、あるいはきっぱり別れたりすることもある。今回の書類は、まさにその狭間にあった。
プロとしての立場と人としての迷い
結局、その自作の書類は参考資料として使うにとどめた。でも、それを読んだことで、私はその家族の関係性や、依頼人の気持ちを深く理解できた。法律家としての役割だけでなく、人としてどう接するか。それを考えさせられた出来事だった。
効率か共感かいつも揺れる
一人事務所の忙しさは変わらない。事務員にも無理はさせられない。だからこそ効率を重視する。でも、そんな中で立ち止まってしまう案件がある。それは、決して無駄ではないと思っている。むしろ、そういう瞬間があるから、この仕事を続けていられるのかもしれない。
事務員の一言に救われた午後
「先生、さっきの相談者の方、すごく丁寧でしたね」。そう事務員がぼそっと言った。何気ないその一言が、自分のモヤモヤをちょっとだけ軽くしてくれた。日々の業務に追われていると、大事なことを見落としがちになる。事務所の空気を感じ取ってくれる存在がいることは、本当にありがたい。
忙しいけどこういう時間のために仕事してる
心が動いたからといって、報酬が上がるわけではない。むしろ手間は増えるし、効率は悪くなる。それでも、「やっててよかった」と思える瞬間がある。それは、こういう感情が芽生えたとき。結局、人が人に関わる仕事なんだなと、改めて思わされた。たまには、手も心も止めていい。そう思える午後だった。