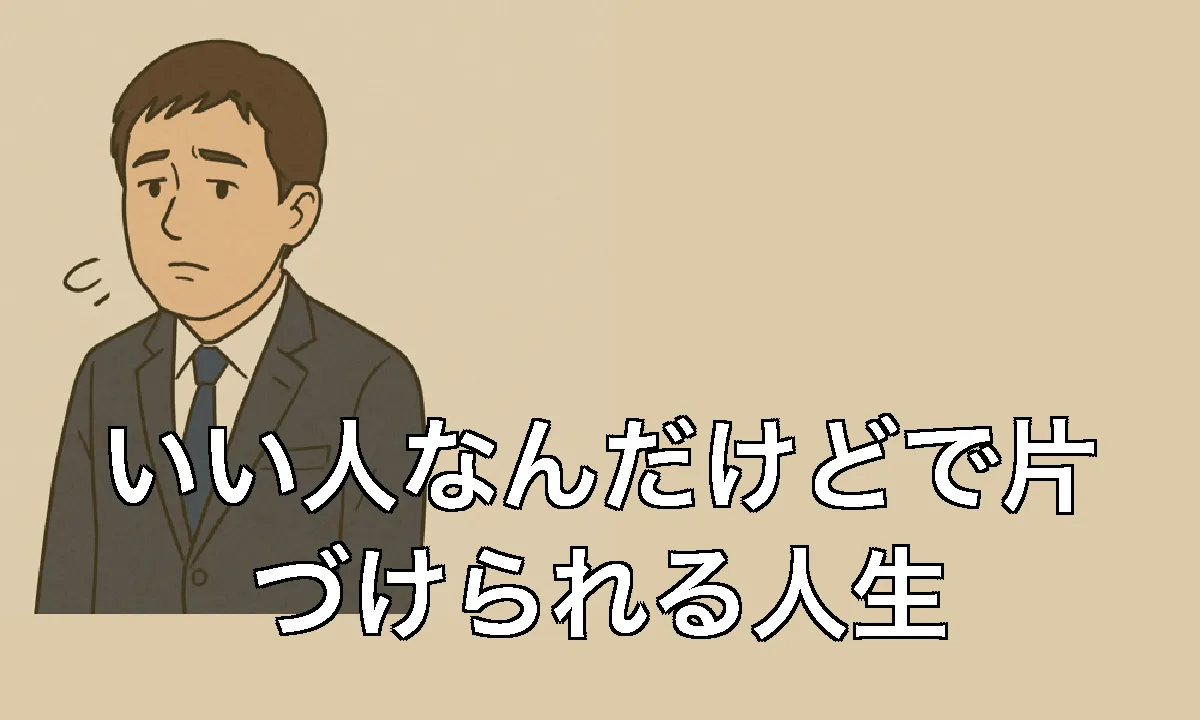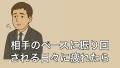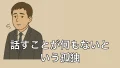いい人止まりの肩書きが刺さる日
誰かと話していて、「あの人、いい人なんだけどさ」というフレーズを聞くと、なんとも言えない感情がこみ上げてくる。自分のことを言われたわけでもないのに、「なんだけど」の先にある否定が、じわじわと胸に染み込んでくるからだ。これは司法書士という職業に限らず、人としての評価に直結する感覚だと思う。「優しい」「真面目」「ちゃんとしてる」——そんな評価を受けても、それが主役に繋がらない虚しさ。いい人止まりというのは、いわば“無難な脇役”にされているような気持ちになるのだ。
あの人いい人だよねという地味な終わり方
思い出すのは、地元の異業種交流会でのこと。何度も顔を合わせていた女性と、ようやく一緒に食事に行けた。話も弾んだし、悪くない手応えだと自分では思っていた。ところが、その後に共通の知人を通じて聞いた言葉が「稲垣さん?いい人だったよ、でもなんかピンとこなかった」だった。結局、進展もなく、そのまま自然消滅。あれはただの会話の感想かもしれないが、「いい人」という一言で片づけられたのは、妙に心に引っかかっている。
仕事でもプライベートでも「まあまあ」で処理される
この「まあまあ」という言葉もなかなかに強敵だ。クレームはない、けれど感動もない。地味にちゃんとやっていることが、結果として印象に残らない評価へとつながる。司法書士の仕事もそうで、登記がミスなく終わって当然、説明が丁寧なのも「そりゃプロだしね」で片づけられる。問題は、感謝されにくいこと。たとえミスがゼロでも、あまり印象に残らない。失敗しないことが当たり前になると、逆に「記憶に残らない人」になってしまう。
誰にも嫌われないけど誰の心にも刺さらない
八方美人とまでは言わないが、波風を立てずに過ごしてきた自覚はある。元野球部の頃は、チームの和を重んじていたし、今でも事務員との関係でもそうだ。穏やかに、気遣いを忘れずに。でも、それが逆に「強さ」や「頼もしさ」としては伝わらないらしい。好かれてはいる、でも「この人じゃなきゃ」とは思われない。そんな評価をされると、どこか虚しさが残る。いい人は、誰かの心に残る「特別な人」にはなれないのか。
元野球部的に言えばベンチのムードメーカー止まり
高校時代の野球部でも、まさにそうだった。スタメンで出るわけではない。でもベンチから声を出して、チームの雰囲気を支える役。監督からの信頼はあったが、注目を浴びることはなかった。あの頃は「チームのため」と納得できていたけれど、社会人になるとそうはいかない。結果がすべて、数字と印象が評価に直結する。ムードメーカーでは給料も上がらないし、次の依頼にもつながらない。大人の世界は、想像以上にシビアだった。
ガッツはあっても打順は回ってこない
実務の現場でも同じような場面がある。たとえば大手の不動産会社からの依頼、いつも声がかかるのは別の事務所。こちらは地道に関係性を築いても、「今回は馴染みの先生で」と断られる。営業的なことも嫌いではないし、手を抜いているつもりはない。でもどうしても“勝負の場面”に呼ばれない。「あの人、いい人なんだけどね」で終わってしまうのは、心の準備もしてきた自分には結構堪える。報われなさが、じわじわ積もっていく。
チームに貢献してもMVPにはなれない
例えば登記の現場で、依頼者や関係者全体の調整をうまくやったとする。トラブルもなくスムーズに完了。でもその裏側にある細かい調整は、誰にも見えない。結果的に何も起きなかったことが、むしろ「印象に残らない理由」になってしまう。何かを派手に解決したわけでもなく、ただ淡々と業務をこなしただけ。そんな時に言われる「稲垣さんって、本当に感じのいい人ですね」が、どうしても空しく聞こえてしまう。
司法書士としても「いい人」枠のまま
司法書士という職業柄、誠実であること、真面目であることは求められる。でもそれは最低ラインであり、それだけでは「選ばれる存在」にはなれない。地味な実務に徹しても、他の目立つ先生の名前が紹介にあがる。結局、「感じのいい人」で止まると、それ以上の展開がない。それは仕事の広がりにも、収入にも直結してくる。
丁寧で真面目だねと言われて終わる苦しさ
顧客から「安心できました」「丁寧に対応してもらえて助かりました」と言われる。それ自体はありがたい。でも、どこかパターン化されたセリフに感じてしまうのも正直なところ。こちらとしては、もっと踏み込んで「稲垣さんに相談して本当によかった」と言われたい気持ちもある。でもそこまで届かない。淡々と評価される日々が続くと、「これでいいのか?」という気持ちが頭をもたげてくる。
それって結局、印象に残らないということ
そつなく対応できることが、「覚えられない理由」になるとは思っていなかった。けれど現実は、記憶に残るのは「強く印象を残した人」。多少のクセがあっても、頼りになるオーラのある人、話術のある人、愛嬌のある人。自分にはそのどれもが欠けていて、結局「間違いのない人」で終わってしまう。その評価が、じわじわと自信を削ってくる。
いい人=当たり障りがない人 という評価
ここで言う「いい人」は、あくまで無難な人という意味だろう。「優しい=強く主張しない」「丁寧=自己主張しない」。そう評価されるたびに、「そこにしかいられないのか?」と自問する。誰からも嫌われないというのは一見すばらしいが、誰にも選ばれないということにもなり得る。この現実を受け止めながらも、やはり寂しさは拭えない。
それでも今日も登記をする理由
それでも、日々の業務は続く。依頼は来るし、期限は迫るし、事務員さんにも迷惑をかけられない。いい人でもなんでも、司法書士としての仕事をこなすことには意味がある。誰にも見えなくても、自分だけは知っている「ちゃんとやってる」自分がいる。それだけは、誇りに思いたい。
いい人でも必要とされる瞬間はある
先日、あるお年寄りの登記手続きで、少し複雑な事情が絡んでいた。他の事務所で断られたらしく、困り果てた末にうちに来られた。そのとき、「あなたみたいにちゃんと話を聞いてくれる人がいて助かったよ」と言われた。それは「いい人」という言葉とはちょっと違った。たしかに、自分でも納得できる「ありがとう」だった。こういう一言があるから、なんとか続けられている。
目立たない役割が支える縁の下の現場
司法書士の仕事は、派手ではない。でも、社会の大事な土台を支える仕事だと思っている。登記や法律文書、信頼されて当たり前のものを、きちんと形にする。ミスなく、トラブルなく。それは「いい人」であることとはまた違う、責任のあるポジションだ。自分がいなければ困る人が、確かにいる。それが唯一の支えだ。
愚痴を吐きながらでも前に進む
正直、しんどい日は多いし、愚痴も減らない。でも、こうして一つひとつの仕事を片づけていくことが、自分なりの価値だと思っている。派手な賞賛はいらない。だけど、誰かの「助かった」の一言だけは、これからももらい続けたい。そのために、また今日も、登記簿と向き合っていく。