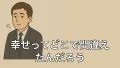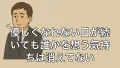正義感という看板を掲げて始めた日
司法書士として独立した当初、僕の胸には「困っている人を助けたい」という強い正義感があった。世の中には理不尽な目に遭っている人がいて、自分がその人たちの盾になれたら、なんてかっこいい仕事だろうとさえ思っていた。正義感という言葉が、まだ汚れていなかった頃の話だ。だが、現実はきれいごとばかりではない。小さな町の事務所で、電話と書類とハンコに追われながら、正義感だけでは回らない現実を痛感する日々が始まった。
理想に燃えた新人時代
修行時代、遺産分割の調整に奔走していた頃の話だ。当事者同士がバラバラで、感情もこじれていたけれど、なんとか全員が納得する形にしたくて奔走した。朝は役所、昼は家族訪問、夜は法務局と、必死に動き回った。でも最終的には、書類を揃えても「もう会いたくない」と言われて終わった。頑張ったのに、どこにも「ありがとう」はなかった。それでも当時の僕は「こういう地味な努力こそ正義だ」と信じていた。
「困っている人を助けたい」という純粋さ
ある依頼者のおばあちゃんが、「こんなに丁寧に話を聞いてくれた人は初めてだ」と涙をこぼした日。あれは僕にとっての原点だった。世の中には、声を上げられずに苦しんでいる人がいて、自分が話を聞くだけでも救いになるかもしれない。そんな思いが心を動かしていた。正義感というより、目の前の人に手を差し伸べたいという感情が、仕事の原動力になっていた。
社会的使命と自己満足の境界線
ただ、ふとした瞬間に「これは本当に依頼者のためになっているのか、それとも自分の達成感のためか」と迷うこともあった。丁寧すぎる対応で相手の負担を増やしてしまったり、こちらの正義を押しつけてしまっているかもしれない。正義感が強すぎると、自己満足にすり替わるリスクがある。それに気づいた時、少しずつ僕の中の「正しさ」の輪郭が曖昧になっていった。
現実にぶつかる毎日
今では一人事務員を雇って何とかまわしているが、日々の業務は膨大で、思うように理想を追い求められない。手続きひとつとっても、相手方の事情、役所の対応、依頼者の期待、全てが揃わないと前に進まない。正義感を持って丁寧に対応すればするほど、業務は膨らみ、時間と気力が削られていく。
正義感が通用しない場面
たとえば、明らかに騙されているような相続案件に直面しても、「これは違法ではないんですよ」としか言えないことがある。正義感で突っ走りたい気持ちはあっても、僕ら司法書士は「現場で戦う人」ではない。ときに、冷静な第三者でいることを求められる。正義を振りかざしたくても、それが許されない立場というのは、けっこうきつい。
「割り切り」も仕事のうちと知った日
あるとき、どうしても納得のいかない登記依頼が来た。相続人が形式的には合法な方法で土地を独占しようとしていた。でも法律的には問題がない。葛藤の末、僕は淡々と業務を進めた。終わったあと、自分の中に嫌な沈黙が残った。正義感で動けない自分を責めた。でもこれが仕事。割り切るしかない。そう思い聞かせたのを覚えている。
疲弊と罪悪感の狭間で
いつからか、「人のために頑張っている」という感覚が薄れていった。頑張っても文句を言われ、感謝されないこともある。やってもやっても終わらない日常の中で、「自分は何のために仕事をしているのか」という問いが、夜中の天井を見つめる時間にこだまするようになった。
本当に誰のために働いているのか
依頼者のために、というのはもちろんそうだ。でも最近は「クレームを減らすため」「トラブルを回避するため」といった消極的な動機が先に立っている気がする。自分が怒られないための仕事になってしまっているのではないか。気づけば、あの頃のような「人の役に立てた嬉しさ」を感じることが少なくなった。
依頼者の笑顔の裏に潜むモヤモヤ
一見満足そうに帰っていく依頼者の笑顔。でも「これでよかったのかな」と思う案件もある。相続の問題、財産分与、時には家族を分断してしまうような案件もある。僕はただ、淡々と手続きを進めただけ。でも、なんとなく後味が悪い。それを依頼者の笑顔でごまかしている自分に気づくと、夜が静かに重くなる。
感謝されない案件のやり切れなさ
以前、明らかに感情的にこじれている遺産分割の案件があった。どれだけ調整しても誰も納得しない。ようやく登記が終わっても、どちらの当事者からも「ありがとう」の一言はなかった。正義感はすり減り、残るのはただの疲労感。こんな日は、家に帰っても気持ちが切り替わらず、風呂に入っても寝つけなかった。
夜に襲ってくる感情の波
夜、一人になったとき、「何やってんだろうなぁ」と思うことがある。仕事をして、お金をもらって、でも正義感を大事にしてきたはずの自分が、今はただの書類処理機になってるような感覚。どこに正しさを置けばいいのか、誰のために頑張ればいいのか。そんな疑問が、ふとした瞬間に襲ってくる。
何度も思った「向いてないかもしれない」
同業の仲間が笑顔で仕事の話をしているのを見ると、「自分は向いてないのかもしれない」と思うことがある。ミスを恐れて慎重になるあまり、無駄に時間をかけたり、結局後悔したりする。もっと割り切って、効率的にできる人が向いているのかもしれない。そんな思いが心の中で渦を巻く。
それでも翌朝机に座る理由
だけど、朝は来る。メールを開いて、電話を取って、また書類に向き合う。そしてたまに、依頼者から「ほんとうに助かりました」と言われる。その一言で、少しだけ救われる。正義感はもう、ピカピカには輝いていない。でも、くすんでもいいから持ち続けていたい。たとえ眠れない夜があっても。
正義感を捨てずに生き延びる方法
正義感だけじゃやっていけない。けれど、まったく持たずに仕事をするのもまた、苦しい。バランスを取りながら、ほどよく力を抜いて、日々を回していく術を身につける必要がある。完璧を目指すのではなく、「まあ、今日も無事終えたな」と思える夜を積み重ねていくこと。それが、この仕事を長く続けるコツかもしれない。
一人で抱え込まない働き方へ
最近は、事務員さんに頼れることが増えてきた。前は全部自分でやらないと気が済まなかったけど、今では「助けて」と言えるようになった。それだけで、ずいぶん気持ちが軽くなる。正義感で自分を追い詰めすぎると、誰も得しない。仲間の存在が、正義感を適度に和らげてくれる。
事務員さんの存在が支えになる瞬間
忙しくて昼ごはんを食べる暇もなかった日に、「先生、これパンです」と渡されたコンビニの袋。何気ない優しさが、妙に沁みた。僕の正義感なんかより、よっぽど実用的で温かい支えだった。支えてくれる人がいるから、正義感を空回りさせずに済んでいる。そんな気がしている。
自分の「弱さ」にも正直でいい
「正義の味方」は、どこか強くないといけない気がしていた。でも今は、「眠れない夜があった」と正直に言えるほうが、人間らしいと思う。悩んだり、愚痴をこぼしたりしてもいい。それでもこの仕事をやめずに続けているという事実が、何よりの証なのだから。