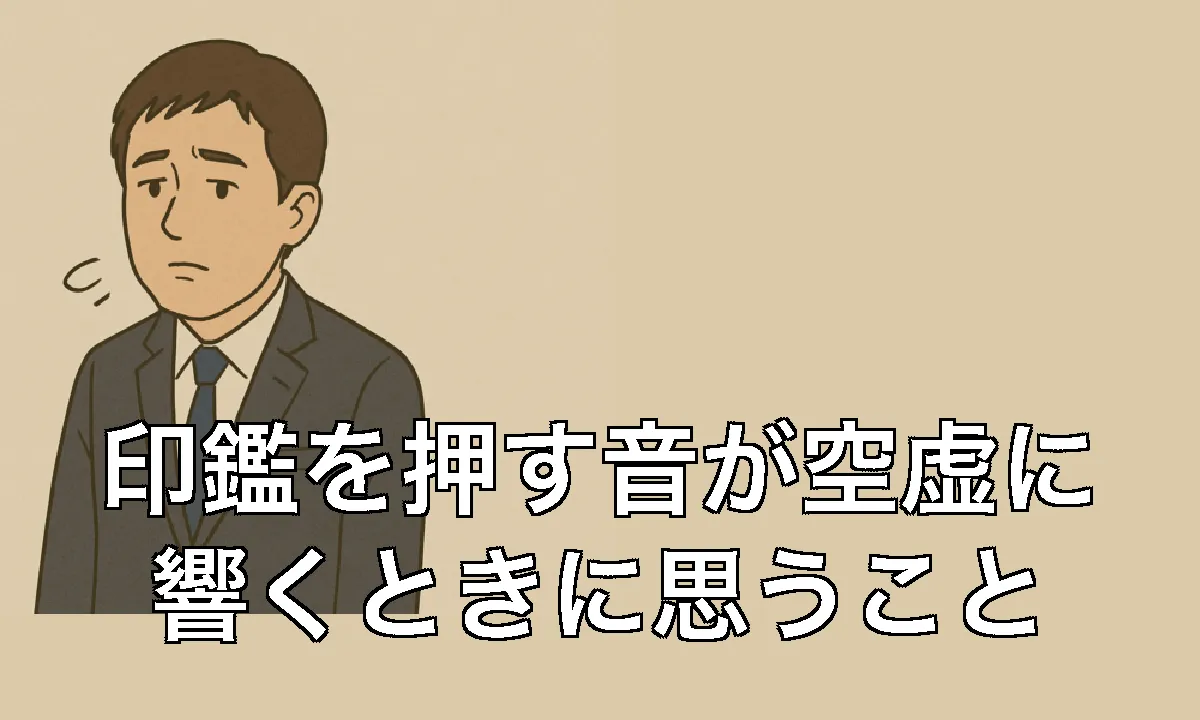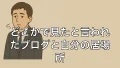静けさの中に響く印鑑の音が気になる日がある
毎日のように押している印鑑。その音が、ある日ふと、やけに大きく、そして空っぽに聞こえた。事務所はいつもと変わらない静けさで、書類の山も変わらない。でも、なぜかそのときだけは、その「カチン」という音が妙に響いて、心の奥がざわついた。単なる疲れなのか、それとも心がどこか別のところを向いてしまっているのか、自分でもうまく説明がつかない。印鑑を押すという行為は、たしかに仕事の一部。でも、そこに「意味」を感じられなくなると、一気に全てが無機質になる。そんな違和感を、時々抱えるようになった。
慣れすぎた手の動きに感情が追いつかない
印鑑を押す手の動きは、もうほとんど自動的に動く。何十件、何百件と処理してきた中で、手はすっかり覚えている。だが、その一連の流れに、自分の心がついてこない時がある。機械的に作業をこなしているうちに、ふと「これ、なんのためにやっているんだろう」と思ってしまう。依頼者にとっては大切な書類だと分かっている。でも、毎日毎日同じ作業が続くと、そこに込めるべき意味がどこかに消えてしまう。以前は、ひとつひとつの印に責任や覚悟を持っていたはずなのに、今ではそれすら薄れているように感じる。
事務所にこだまする音がいつもと違って聞こえた瞬間
その日は特に忙しかった。朝から電話が鳴り止まず、登記の書類も立て込んでいた。ようやく一息つけた夕方、ふと押した印鑑の音が、いつも以上に響いた気がした。普段は気にも留めないその音が、なぜか胸の奥にまで届いた。まるで、空っぽの部屋にコツンと石を落としたような、そんな音だった。たぶん、その音はずっと前から変わっていないのだろう。ただ、自分の内側が変わっただけなのかもしれない。音に感情が乗ることなんてないはずなのに、その瞬間だけは、妙に重く感じた。
それは疲れなのか空虚なのか自分でもよく分からない
最近は、ちょっとしたことで心がザラつくようになってきた。仕事が嫌いなわけじゃない。むしろ、司法書士という仕事には誇りを持っている。でも、忙しさに追われ続けると、自分がどこへ向かっているのか見失ってしまう。事務所を開いて十数年。最初の頃の情熱や目標は、どこへ行ってしまったのだろう。何かを終わらせるたびに押す印鑑。それが一つの区切りになるはずなのに、今では「ただの作業」としか思えないこともある。心が置き去りになったまま手だけが動いている、そんな感じだ。
印鑑を押すことは作業だけど気持ちはついてこない
この仕事に就いたばかりの頃は、印鑑を押すたびに少し緊張していた。「これが正式な手続きの証になる」と思うと、手が震えるほどだった。それが今では、まるで流れ作業の一部。効率よくこなすことに意識が向きすぎて、大事な感覚をどこかに落としてきてしまったようだ。きっと慣れというのは、良くも悪くも感情を鈍くする。正確さは保っているつもりだ。でも、心の中では「このままでいいのか」と、薄く不安が残る。誰に相談するでもなく、ただひとり、印を押し続けている。
形式だけの承認が続くことに違和感を覚える
司法書士の仕事は、形式を大事にする。書式、手順、期限。全てがルールの上に成り立っている。でも、あまりにもその「形式」が中心になると、そこに人間らしさが入り込む余地がなくなる気がする。印鑑を押す行為もそうだ。形式上必要なものであるのは分かっている。だけど、相手の思いに寄り添った上での手続きでなければ、ただの「スタンプマン」になってしまうのではないか。それに気づいたとき、自分の仕事に対するスタンスも少し変えなければならないと感じた。
誰のためにこの印を押しているのか分からなくなることもある
仕事が立て込んでくると、「この印は誰のためのものだったっけ?」と、自分でも分からなくなる時がある。依頼人の顔も声も思い出せないまま、淡々と押すだけ。書類はちゃんと処理しているし、手抜きなんてしていない。でも、気持ちがそこにないと、まるで無人の電車を運転しているような感覚になる。効率を追いすぎて、目の前の人の存在を見失っている。そんな自分に気づくと、情けなさと後悔でいっぱいになる。もっと丁寧に、もっと心を込めて関わりたかったと思うのだ。
本来の意味を見失いそうになる
司法書士の仕事に意味を感じられなくなったら、それは危険信号だと思う。でも、忙しさに追われていると、どうしても感情が後回しになる。特に独立してからは、「売上」「効率」「時間管理」といった言葉ばかりが頭を占めて、本来大切にしていたはずの「人のために」という気持ちがどこかへ行ってしまう。印鑑を押すという行為の先にあるはずの「信頼」や「安心」を忘れかけていた自分に気づいたとき、正直、少し怖くなった。
依頼人の人生を背負うという実感が薄れるとき
登記や相続、会社設立――司法書士の仕事には、依頼人の大きな節目が詰まっている。そのはずなのに、いつの間にかその「重み」を感じなくなっていた。例えば、相続の案件。昔なら、故人のことを思い浮かべながら、家族の気持ちを想像していた。でも最近では、手続きの効率ばかり気にしてしまう。そういうときほど、何か大切なものを落としてきた気がする。依頼人にとっては、たった一度の大切な手続き。そこに気づける感性を、もう一度取り戻したいと思う。
数をこなすほどに感情の入る余地がなくなる
毎月、処理する案件の数は増えている。事務員と二人で回すには限界ギリギリだ。それでも無理して受けてしまうのは、収入への不安や、断ることへの罪悪感があるからかもしれない。でも、その結果、自分の心が疲弊していく。時間に追われるほどに、案件一つ一つに向き合う余裕がなくなり、気づけば「こなすだけ」になってしまっていた。数をこなすことに慣れてしまうと、本来持っていたはずの「向き合う姿勢」まで薄れていく。それが分かっているのに止められないのが苦しい。
書類に命を感じられなくなる怖さ
一枚の登記簿、一つの契約書。その背後には、依頼者の人生や決断がある。以前は、そのことを強く意識していた。でも、最近では「ただの紙」としか見えなくなる時がある。それが本当に怖い。紙に命を吹き込むのは、こちらの姿勢次第なのに、自分がそれを忘れてしまったら終わりだ。事務所に来る人たちは、いろんな思いを抱えている。そのことに敏感でありたいし、そうでなければ司法書士を名乗る意味がない。忘れたくないのに、忘れてしまいそうになるのが一番辛い。
それでも印鑑には意味があると信じたい
どんなに忙しくても、どれだけ疲れていても、印鑑を押すという行為には「意味」があると信じたい。そこには責任もあるし、信頼もある。自分の名前を背負って押す印鑑。その重みを、もう一度思い出す必要がある気がしている。疲れていても、やる気が湧かなくても、それでも「この印で誰かが安心する」と思えれば、まだやっていける。仕事の意味を自分で見つけ直すこと、それが今の自分にとって何より大事なことかもしれない。
お客様の「ありがとう」が印象を塗り替える
ある日、相続の手続きで来た年配の女性が、帰り際に深々と頭を下げて「本当に助かりました」と言ってくれた。いつものように印鑑を押しただけの手続き。でもその「ありがとう」で、すべてが報われた気がした。ああ、この仕事にはやっぱり意味があるんだと実感できた瞬間だった。どんなに機械的にこなしていたとしても、その向こうには「人」がいる。その人が安心して、笑顔になって帰ってくれるなら、自分の押す印鑑にも価値がある。それを思い出させてくれた言葉だった。
同じ作業でも心の持ちようで変わる
やることは同じでも、自分の気持ち一つで見える景色は変わる。ただの書類でも、「この人の未来に関わっている」と思えば、気持ちの込め方も違ってくる。最近は、忙しさの中でも少し立ち止まるようにしている。事務員と他愛のない会話をしたり、コーヒーを飲みながら外を眺めたり。そんな些細なことで、気持ちの切り替えができることもある。印鑑を押す手に、ほんの少しでも心を込めること。それが、またこの仕事に意味を見出す第一歩になる気がしている。