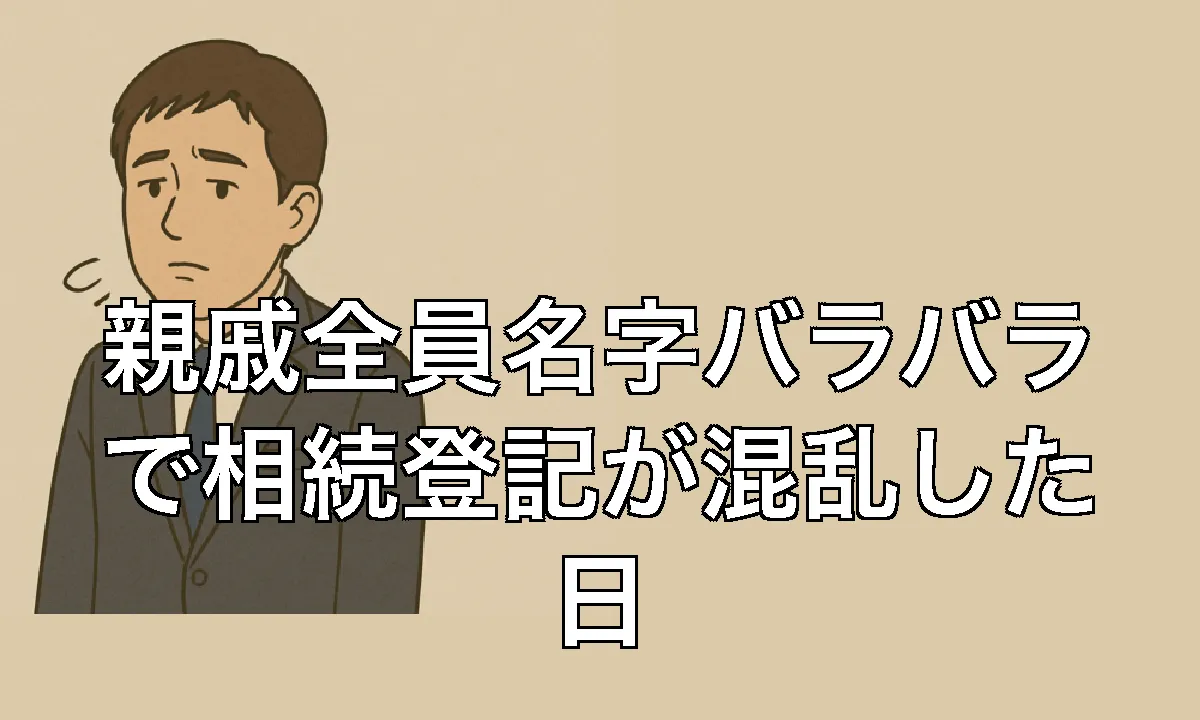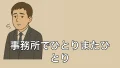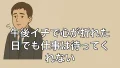なぜこんなに名字が違うのかという疑問から始まった
相続登記の依頼が入ったとき、最初に目を疑ったのが「関係者全員名字が違う」という戸籍謄本の並び。あれ?依頼人の説明だと「親戚一同の相続」って言ってたのに、苗字が全員バラバラ。旧姓や再婚、離婚を経て名字が変わること自体は珍しくない。でも、ここまでくると誰が誰の子か、兄弟なのか義理なのかも分からない。戸籍をたどっていくうちに、どんどん深みにハマっていく感覚に襲われた。
戸籍をたどると見えてくる複雑な家族構成
一枚の戸籍に記された情報だけでは全体像は見えてこない。旧戸籍から現戸籍に至るまで、いくつもの名字が飛び交う。依頼人からすれば「親戚」でも、こちらからすれば「書類上のつながり」がなければ登記は進まない。とにかく関係図を手書きして整理するところからのスタートだった。
母方父方が入り混じると名前の一致は奇跡に近い
例えば、父方の兄弟はすべて再婚していて、子どもはそれぞれ母親の姓を名乗っている。一方、母方のいとこたちは結婚して名字が変わっている。となると、全員親族なのに誰一人として同じ名字がいない。しかも書類上は「○○家」などという概念はない。もはや「名字が違う」ことを前提に進めなければならない。
再婚離婚事実婚 錯綜する現代家族のリアル
さらに話をややこしくしたのが、事実婚や再婚後の養子縁組の履歴。たとえばある人は、戸籍上3つの名字を経験している。相続人として確定するには、すべての戸籍を取得してつなげるしかない。昔は「○○家の長男」なんてわかりやすかったのに、今はその感覚でいると確実に迷子になる。
登記簿に記す名前が誰のことなのかが分からない
名前が違うのは百歩譲っていいとして、「この人=あの人」である証拠がないと手続きが進まない。依頼人の話を聞いても「多分そうだと思います」と曖昧な返答ばかり。最終的にはこちらが調べて裏付けを取るしかなかった。
おそらくこの人とこの人は同一人物…でも確証がない
ある戸籍では「中村花子」、別の書類では「佐藤花子」と記載されている。依頼人いわく「結婚して名字が変わっただけ」とのことだが、正式な記載がなければそれは通らない。結局、婚姻届受理証明書を役所から取り寄せ、ようやく「同一人物」として確認が取れた。たった一人分にこれだけの労力がかかるのだ。
戸籍のつながりが断絶したケースの苦労
中には、除籍された古い戸籍が保存期間を過ぎていて取得できないというケースもあった。その場合、もう関係性を示す資料が存在しない。「つながっていたはず」だけど、それを証明するものがない。泣く泣く法務局と相談し、補完的な書類で何とかするしかなかった。
同姓同名ならまだしも名字バラバラが一番しんどい
よくあるのは同姓同名のパターンだけど、こちらは戸籍の本籍地や生年月日でなんとか区別がつく。しかし、今回のように名字すら違う場合、「どこに共通点があるのか?」というところから始まる。確認の数も手間も段違い。書類の山に埋もれながら、なぜ司法書士になったのか一瞬わからなくなった。
説明しても伝わらない 依頼人の理解とギャップ
こちらがどれだけ丁寧に説明しても、「そんなに難しいことなんですか?」と返されるときの空虚感。相手からすれば「ただの手続き」でも、こちらからすれば「証明責任を負ってる業務」。だからこそ説明にも限界がある。
それ私のいとこですって言われてもこっちは困る
「いとこ」って言われても、その根拠となる戸籍がなければ法務局は納得しない。関係性を証明できなければ登記の対象にもならない。「昔からそう呼んでた」とか「親がそう言ってた」は一切通じない。こちらは法律上の事実だけを扱っているのだ。
書類を揃えるのは誰なのかの線引きが難しい
そしてその「いとこ」に書類を求めようとすると、「私関係ないので無理です」と返される。依頼人からしてみれば「お願いしてくれればもらえると思う」と軽く言う。でも実際は関係性が希薄で、音信不通な場合がほとんど。資料収集の限界を感じる瞬間だった。
私関係ないんでと言われたら地獄の始まり
この一言が出た時点で詰み。結局、相続人の協力がなければどうにもできない。説得しても無駄なこともある。そんなとき、こちらとしては何度も説明書を書いて、関係図をつけて、やれるだけのことをしてから依頼人に「ここまでが限界です」と伝えるしかない。疲れる。ほんとに疲れる。
家族の名乗り方が自由になった現代の落とし穴
自由っていいことだけど、登記業務の現場では厄介なことも多い。通称を使う人、旧姓をそのまま名乗る人、家庭内で名前を使い分けている人…。自由の裏側には「記録の不一致」がついてくる。
通称と戸籍名が異なるとどうなるか
よくあるのが、「会社では山田だけど戸籍は中村です」パターン。名刺も契約書も「山田」だけど、法的には「中村」。相続登記で使えるのは後者。だから「私じゃないことになってます」と混乱する人が出てくる。でもこっちからすれば「それがあなたです」としか言えない。
SNSでは○○さん でも登記には□□さん
SNSなどで別名を使う人も増えてきた。結果、親族間の呼び名がバラバラ。書類上の名前と一致しないから、関係性の説明が困難になる。たとえば「インスタでは桜子、戸籍は佳子」みたいな感じだ。情報が氾濫している分、確実な記録を重視するしかない。
証明のための説明書きをつける不毛な手間
最終的に、あらゆる名前のズレを補足するために、関係説明書や上申書を何枚もつけることになる。しかもそれを法務局が納得してくれる保証はない。「いち司法書士の推測」として退けられれば、また一から書き直し。正直、割に合わないと思うこともある。
結論 やっぱり家系図は作っておいた方がいい
もしこれを読んでる方が相続を見据えているなら、お願いだから家系図だけは残しておいてほしい。誰が誰とどういう関係か、ざっくりでもメモがあるだけで全然違う。私たちも助かるし、結局は依頼人の負担も減る。紙一枚が、数週間の混乱を防いでくれるんだから。
事前に家族関係をまとめることの効力
何も準備していない相続は、正直しんどい。家族で揉めるし、書類も多いし、精神的にも疲弊する。逆に、あらかじめメモ書きでもいいから家系図があると、登記の流れがすごくスムーズになる。誰が相続人か、どこに連絡すればいいか、それだけでも全然違う。