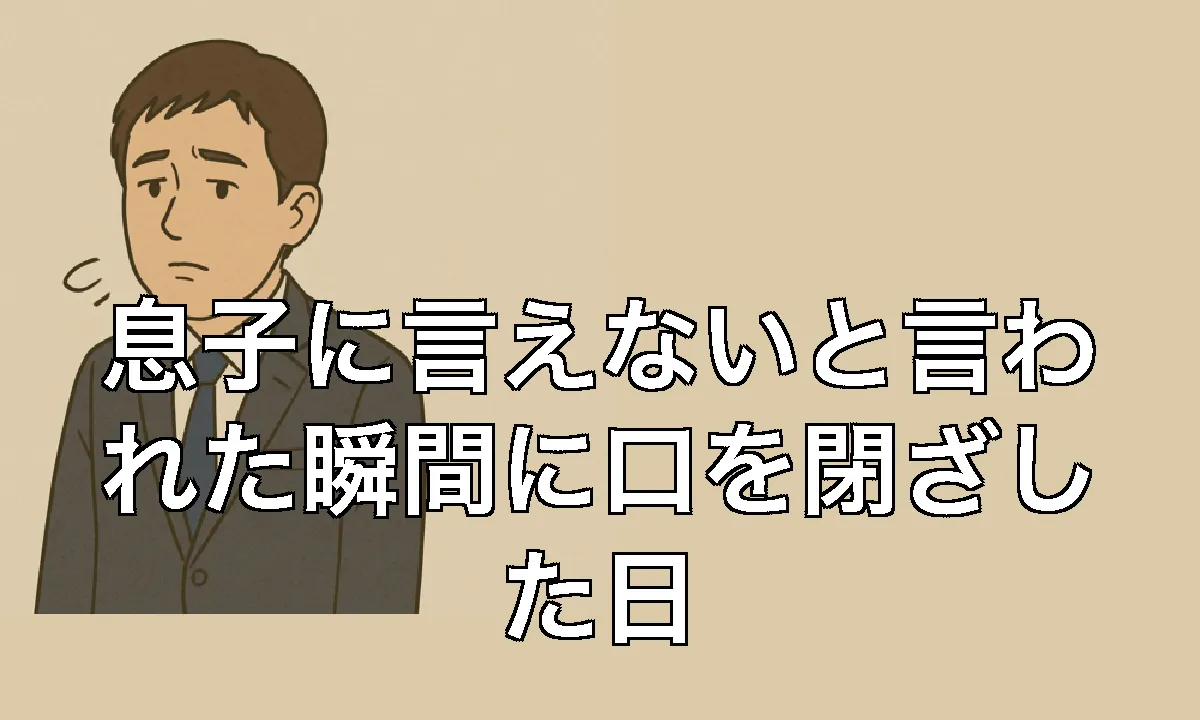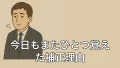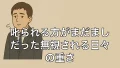あの依頼がきたのは雨の日だった
静かな雨音が事務所の窓を叩く午後、ひとりの中年女性がふらりと現れた。濡れた傘を畳む手元がやけにゆっくりで、緊張しているのが伝わってきた。応接席に腰を下ろすと、小さなため息をひとつついて、ぽつりぽつりと話し始めた。「実は…これ、息子には内緒でお願いしたいんです」。その一言に、なんとも言えない重さを感じた。書類はしっかり揃っていたし、法律上の問題もない。だが、それでも、僕の中で何かが引っかかった。
封筒を持つ手が震えていた依頼人
封筒から取り出された書類は、よくある遺言書の原案だった。名前も住所も筆跡も整っていて、本人が用意したものなのは明らかだった。でも、肝心なのはその内容ではなく、「誰にも知られたくない」という意思だった。特に「息子に言うつもりはないんです、あの子はちょっと気が荒いから」と、どこか怯えるように話すその様子に、正直、こちらの手までこわばった。目の前で起こっていることが、ただの相続対策なのか、それとももっと根深い家庭の問題なのか…その場では判断できなかった。
名字だけで呼んでくれと前置きされたとき
最初に名刺を渡したとき、「あ、苗字だけで大丈夫ですから」とすぐに遮られた。そのとき、彼女の中では何かがもう決まっていたのかもしれない。身内にすら見せられない思いや準備を、僕のような第三者に託すというのは、相当な覚悟がいる。けれど、その一方で、司法書士としては、依頼者の意思を尊重する義務がある。でも、心の奥底では「このままでいいのか」と、ずっとモヤモヤが渦巻いていた。
親子関係に踏み込む怖さを感じた瞬間
「これを手続きを進めてしまえば、息子さんはすべてを後から知ることになるわけですよね」と、喉まで出かかったが、飲み込んだ。その瞬間、自分が家族ではないという事実を痛感した。いくら相手を思っても、踏み込んではならない線がある。でも、こうして迷ってしまうのは、やっぱり人として当たり前だと思いたい。法律のプロとしての自分と、人としての自分が、真っ向からぶつかり合っていた。
判断に迷うとき司法書士はどうするか
僕ら司法書士は、書類の整合性を確認して、法的に問題がなければ依頼を遂行するのが基本だ。けれど、それが「正しい」とは限らない。誰かの感情が置き去りにされているようなとき、自分の中にある「これで本当にいいのか」という疑問が騒ぎ出す。今回の依頼も、まさにその典型だった。自分が手続きを進めれば、確かに一つの業務は完了する。でも、それで良心は納得できるのか――。
職務と良心のはざまで
ある種の依頼は、手続きの話では済まない。たとえば、今回のように家族に内緒で相続を進めたいというケース。法的には問題がなくても、道義的にどうかという葛藤が生まれる。だからといって、「やめましょう」と言える立場でもない。結局、依頼人の意思が明確で、書類に問題がない限り、僕たちは動かざるを得ない。それが制度の枠の中で生きるということなのだ。
誰のための書類かを考え続けた
書類を前にしたとき、僕は毎回考える。「これは誰のための書類なんだろう」と。依頼人のためか、将来の受遺者のためか。それとも、ただ“手続きとして完了させること”が目的になっているのか。今回の件では、その問いが特に重くのしかかった。書類を提出する自分の手に、誰かの人生が委ねられている。その事実に慣れることは、たぶん一生ない。
線引きの難しさと責任の重さ
「関わるべきか、関わらないべきか」。この線引きは、現場に出るようになってからずっと悩み続けているテーマだ。今回のように家庭の事情が絡むと、正解なんてない。ただ、プロとしての責任だけが残る。自分の判断が、将来誰かを傷つける可能性がある。その恐れと、どう向き合っていくのか。正直、答えなんて未だに出ていない。
この仕事の厄介なところ
司法書士の仕事って、見た目は「紙とハンコの世界」に見えるかもしれない。でも、実際は人間の感情にずぶずぶと関わる仕事だ。淡々と事務的に処理すれば済む案件でも、その裏には必ず誰かの物語がある。今回は「息子には内緒で…」という言葉に、ずっと引っかかりを感じながら進めることになった。その苦しさが、この仕事の厄介さだと思う。
言われた通りにやればいいという話ではない
「プロなんだから、言われた通りにやればいい」と思われるかもしれない。でも、現実はそんな単純じゃない。依頼者が抱える背景や感情を無視して進めるのは、機械に任せればいい。人間がやるからには、そこに「迷い」や「ためらい」があるのが自然だと思う。僕はまだその迷いを捨てきれない。捨てられないまま、十年以上やってきた。
守秘義務と道義心のあいだ
「秘密を守る」のが僕らの仕事。だからこそ、今回のような“家族に内緒”という依頼にも応じることがある。でも、その一方で「それでいいのか?」と自問することも多い。守秘義務があるからこそ苦しいし、誰にも相談できないからこそ重い。だから夜になると、つい事務員に当たりそうになる。いや、実際少しだけ当たってしまった日もあった。申し訳ないと思いながらも、気持ちの整理がつかないのが本音だ。
それでも書類には判を押さねばならない
最終的には、依頼人の意思と法的要件が揃っていれば、書類にハンコを押す。それが仕事。わかっている。でも、あの日の押印は少しだけ手が止まった。もしかすると、これで何かが壊れるかもしれない。それでも、押さなければならない。それがこの仕事のつらさであり、重さでもある。
あとから思い出してしまう依頼もある
処理が終わったからといって、すべてを忘れられるわけじゃない。今回の依頼も、ふとした瞬間に思い出す。たとえばスーパーのレジ待ち、寝る前、電車の窓に映る自分の顔を見たとき。あの依頼者はいま、息子さんに何を話しているだろうか。何も話していないのだろうか。そんなことを考えて、またため息が出る。
机の上の書類に書かれた一言
そのときの遺言書の最後には、「ありがとう」という手書きの一文が添えられていた。形式的な文面の中に、突然現れたその言葉に、思わず手を止めてしまった。僕は何に「ありがとう」と言われたのか。手続きを受けてくれたことか、黙っていてくれたことか。それともただ、話を聞いてくれたことか。今でも答えはわからない。
自分の家族だったらと想像してしまう
「もし自分の親が、こんなふうに誰にも言わずに何かを準備していたら…」そう思うと、胸がざわついた。結局、僕たちは他人の家庭を預かっている。でも、感情は切り離せない。ましてや独身で、実家との関係も薄くなってきた今、自分の親の老いを考えたときに、急に身近な話に思えてしまった。
その夜は焼酎がやけに沁みた
仕事が終わったあと、いつものコンビニで焼酎とカップ惣菜を買った。たいした晩ご飯じゃないけれど、その日は妙に沁みた。テレビをつけても頭はぼんやりしていて、なんだか気持ちだけがふわふわしていた。「これでよかったのか?」その問いだけが、静かに心に残り続けていた。