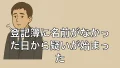優しさに飢えた朝に目覚めることが増えた
誰かに優しくされたい、そんな気持ちを朝から抱くことが増えた。何か特別な出来事があったわけではない。ただ、目覚ましの音に無理やり起こされて、カーテンを開けても気持ちが晴れない。冷蔵庫を開け、昨日買っておいたコンビニのパンを口に運ぶ。誰にも気づかれず、誰にも褒められず、それでも日常を回し続ける毎日。人に頼られることは多いくせに、自分が誰かに頼ることはできない。そんな日々が続くと、「優しさ」という言葉がどれだけ貴重なものか、身にしみてくる。
昨日の疲れが取れないのは心の問題かもしれない
身体的な疲労は睡眠である程度回復できる。しかし、心の疲れというのは、そう簡単に回復しないらしい。昨日は午後から相続登記の相談が立て続けに3件。高齢の依頼者が多く、説明には気を使うし、聞き返されることも多い。事務員もひとりなので、フォローできる範囲は限られている。結果的に、全部自分で抱える。帰宅しても、気が抜けない。テレビをつけても内容が頭に入ってこない。そんな夜を過ごした翌朝、「今日も頑張ろう」なんて気持ちになれるわけがない。
仕事は回っているのに満たされない感覚
たしかに、書類は期日通りに仕上げている。登記ミスもないし、クレームもない。外から見れば順調な事務所経営に見えるだろう。でも、自分の中では何かがずっと欠けているような感覚がある。心のどこかで「もっと感謝されたい」と思ってしまう自分がいる。それが報酬だというのは分かっている。でも、人間ってそんなに割り切れない。「ありがとう」って、そんなに贅沢な言葉なのか。ときどき、そう問いかけてしまう。
書類が片付くほど心が空っぽになる不思議
一日中デスクに向かい、登記簿や契約書に向き合っていると、達成感よりも空虚感のほうが大きくなってくる。片付ければ片付けるほど、「また誰にも会わずに終わったな」と思う。元々野球部で、仲間と一緒に声を出して汗をかいていたころの自分からは想像もつかないような、静かで冷えた世界。誰かと笑い合うことも、冗談を交わすこともない毎日。必要とされているのに、誰にも必要とされていないような、そんな妙な矛盾を抱えて今日も事務所に座っている。
人に頼れない司法書士という立場
司法書士というのは、言ってしまえば「何でも屋」になりがちだ。書類作成から説明、相談、電話対応、全部が自分の責任。事務員がいても、細かい判断は結局こっちに回ってくるし、法的責任もすべて背負うことになる。「間違えたらどうしよう」と不安に思いながら、それでも淡々と処理していく。そんな繰り返しのなかで、人に頼るという感覚がどんどん薄れていく。「自分でやったほうが早い」が口癖になってしまったあたりで、もう誰にも甘えられなくなっている。
事務員一人に任せきれない不安
うちの事務員は真面目で優秀だ。けれど、それでも限界はある。電話が鳴って、相談者が来て、郵便が届いて、取引先から急ぎの連絡が入る。そんな日には、事務員一人ではさばききれない。自分もバタバタして対応するけれど、ふと「これって全部俺が回してるだけじゃないか」と思ってしまうことがある。経営者なんだから当たり前だと言われればそれまでだけど、たまには「大丈夫ですか?」って声をかけられたい。そんな余裕のある組織だったら、きっと違う気持ちで働けていたかもしれない。
報酬以上に重い責任の重圧
司法書士の報酬は、一見すると安定して見える。でも、そこには「責任」という重たい荷物がついてくる。間違いは許されないし、依頼者にとっては人生の節目に関わる場面も多い。そういう空気の中で仕事をしていると、心のどこかが常に緊張していて休まらない。休日に出かけても、ふと「あの登記、大丈夫だったかな」と頭によぎる。責任という名の重圧は、目には見えないけれど、ずっと肩にのしかかっている。
「先生」と呼ばれても中身はひとりの人間
「司法書士の○○先生」と呼ばれるたびに、違和感を覚える。確かに資格を持って仕事をしているけれど、心の中ではまだ自信なんて持てていない。「先生」と呼ばれるたびに、「そんなに立派なもんじゃないよ」と思ってしまう。自分の中身は、ただの45歳の独身男。元野球部で、汗臭かった高校時代の記憶のほうがよっぽどリアルに感じる。名前の前につくその一文字だけが、妙に重く感じられることがある。
それでも続ける意味を見失いたくない
こうして愚痴を書き連ねてしまう自分を、少しだけ情けなく思う。でも、それでもこの仕事を辞めようとは思わない。なぜか。やっぱり、依頼者の「助かりました」「ありがとう」という言葉に、救われているからだ。たまにでも、誰かの人生の役に立てている実感がある。その小さな実感だけで、また朝を迎える勇気が湧いてくる。そして今日も、「優しさに飢えた心」で目覚めながらも、デスクに座る自分がいる。
依頼者の「ありがとう」に支えられた瞬間
先日、亡き父の相続登記で悩んでいた女性がいた。不安そうに書類を差し出す彼女に、ひとつひとつ説明して、無事手続きが終わったとき、「本当に、先生にお願いしてよかった」と言ってもらえた。その瞬間、張り詰めていた糸がふっとゆるんだ。たった一言かもしれない。でも、それがどれだけ心を救ってくれるか。優しさって、こういうところにちゃんと残っているんだと、改めて思った出来事だった。
過去の自分からの励ましが今をつなぐ
高校時代、真夏のグラウンドでヘトヘトになりながらも、声を張り上げて練習していたあの頃の自分。あの自分なら、今のこの状況でも「根性出せ」と言うだろう。逃げたい日もあるけれど、過去の努力や仲間との時間が、今の自分の背中を押してくれる。司法書士という静かな戦場で、声を出すことはなくなったけれど、あの頃の気持ちは、まだ胸の奥に息づいている。
元野球部の根性論だけではやっていけない
ただ、根性だけではどうにもならないのが、今の仕事だとも思っている。精神論では処理できない書類の山、複雑化する法制度、変わっていく依頼者のニーズ。走り込みで身につけた粘り強さは、たしかに役には立っている。でも、それだけじゃ足りない。もっと余裕がほしい。もっと優しさを受け取れる場所がほしい。そう思うたびに、「司法書士としてどうあるべきか」より、「人としてどう生きたいか」を考えるようになった。