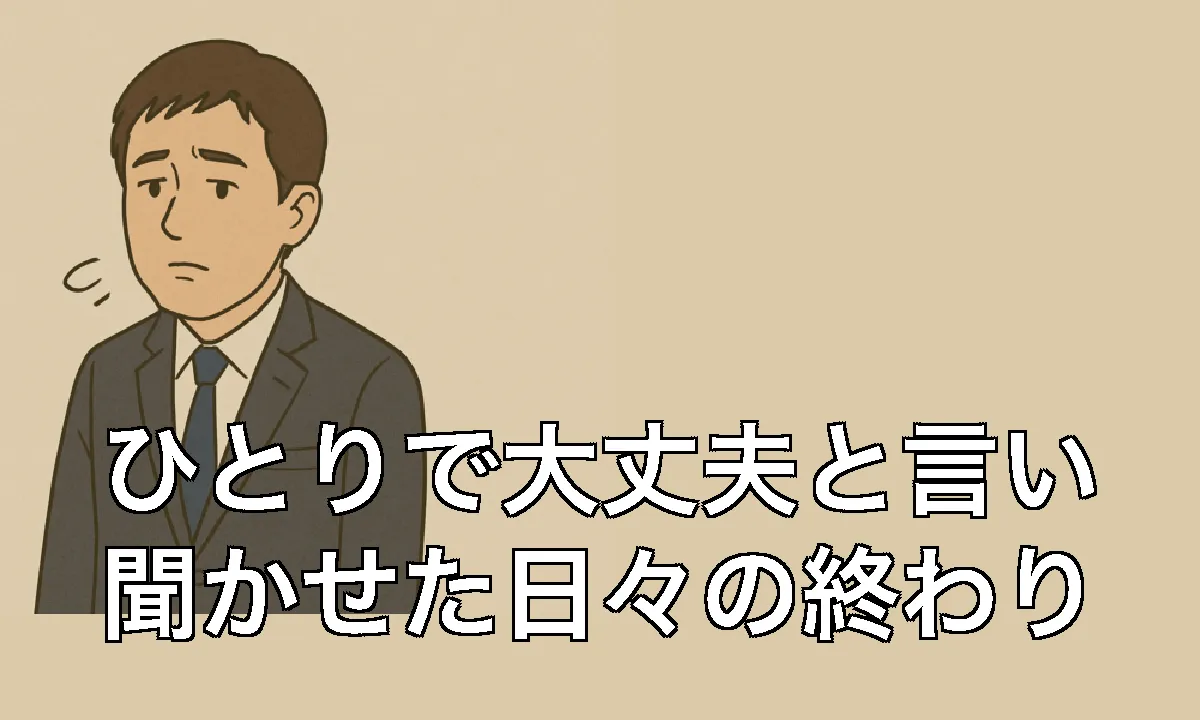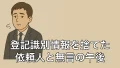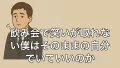自分で選んだ道なのにと思う瞬間
司法書士になろうと決めたのは、自分の力で食っていける職業がいいと思ったからだった。誰にも頭を下げず、頼らず、コツコツと積み重ねていける仕事。地方に戻って事務所を構えたとき、誇らしい気持ちもあった。けれど、数年経つと、その「自分で選んだ道」に押しつぶされそうになる瞬間が増えてきた。孤独は覚悟していたけれど、実際にそれが毎日続くと、心がすり減っていく。
人に頼らないと決めたのはいつだったか
高校の頃、野球部でキャプテンを任されたとき、「最後まで責任を持て」と言われたのがきっかけだったかもしれない。あの頃から、誰かに頼ることは弱さだと勝手に思い込むようになった。自営業という働き方も、どこかその価値観の延長線にあった。自分のことは自分で、困っても自分でなんとかする。そんな姿勢が知らず知らずのうちに、自分を苦しめる壁になっていた。
強がりが習慣になるまで
独立してからというもの、弱音を吐く場面なんてなかった。顧客の前では常に「大丈夫です」と笑っていたし、事務員の前でも「任せておいて」と余裕を見せていた。でも実際は、夜中に一人で書類と格闘しながら、ミスがないかと何度も見返していた。強がるのがクセになっていた。気づけば、本音を言える相手もいなくなっていた。
「大丈夫です」が口癖になるまでの流れ
最初は丁寧さや責任感のつもりで使っていた「大丈夫です」という言葉が、いつしかただの反射になった。たとえ無理をしていても、大丈夫です。徹夜明けでも、大丈夫です。電話口の相手に心配されても、笑って「全然平気ですよ」と答える。でも本当は、全然平気じゃなかった。自分自身にまで嘘をつくようになっていた。
誰も悪くないけど孤独になる仕組み
この孤独に、誰かが悪いわけじゃない。お客さんも、事務員も、友人たちも、みんなそれぞれの人生で精一杯生きている。自分だけが取り残されたような感覚があるのは、自分自身が壁を作ってしまったからだ。地方という環境も影響しているとは思う。都会のように、ふと気軽に誰かと会える場所も少ない。仕事が終われば事務所に一人。テレビの音がやけに大きく感じる。
地方で司法書士をやるということ
東京での修行時代は忙しくても、どこかに人の気配があった。電車に乗れば誰かがいて、帰り道には立ち寄る飲み屋もあった。地方に戻った今、その「誰かの気配」が遠い。案件数はそこそこあるけれど、相談者とのやり取りが終われば、それっきり。街でばったり会うこともなく、リピートの案件が来るまで誰とも話さない日もある。そんな日々が、精神をじわじわと削っていく。
気軽に飲みに誘える友人もいない日常
学生時代の友人たちは県外に就職して、今では年賀状くらいの付き合い。地元の知人は家族を持ち、土日に誘うのも気が引ける。結局、「まあ、ひとりでいいか」とコンビニのビールで済ませる。でも、それが3日、5日と続くと、ふと「このままでいいのか」と思ってしまう夜がくる。誰にも迷惑をかけていないはずなのに、心のどこかが空虚だ。
事務所にひとりでいる時間の重たさ
事務所で一人残業していると、時計の音がやたら気になる。パソコンのファンの音、プリンタの駆動音、外の雨音。全部が「誰もいない」ことを強調してくる。事務員は定時に帰って当然だし、自分もそれを尊重しているけれど、ふと「今日一日、誰かと笑ったっけ」と思うと、胸がざわつく。仕事はちゃんとやっている。でも、生きている実感が薄れていく。
その日はいつも突然にやってくる
不安や寂しさが蓄積していく中で、「あ、無理だ」と感じる瞬間は、意外と些細な出来事だったりする。書類の山に埋もれたとき、パソコンがフリーズしたとき、電話が1本も鳴らなかったとき。そんなときに、「もう限界だな」と思ってしまう。自分で選んだ道なのに、逃げ出したくなる。でも逃げ場所はない。それが一番しんどい。
電話が鳴らないときの焦り
午前中、電話が鳴らないと「今日は静かでいいな」と思っていたはずなのに、午後になっても音沙汰がないと、急に不安が襲ってくる。「もしかして、誰からも必要とされていないのでは?」そんなネガティブな思考がぐるぐる回る。月末の帳簿を眺めても、来月の予定表を見ても、不安が消えない日がある。そんな日は、「誰かと話したい」と自然と思ってしまう。
依頼がゼロの日に押し寄せる不安
まったく依頼が入らない日。時間だけが過ぎていくと、何かをしていないと落ち着かなくなる。過去の書類を整理したり、無理にスケジュールを詰めたりする。でも本当は、ただ誰かから「お願いします」と言われたいだけだ。承認欲求なのかもしれない。けれど、この仕事を続けていくには、人から頼られることが心の支えになっている。それに気づくと、ますます孤独が際立つ。
気づけば机の上を片付けることで気を紛らせていた
電話が鳴らない日、気づけば机の整頓に熱中していた。ペンの位置を整え、封筒の在庫を数え、スケジュール帳を色分けする。そうすることで、「何かしている感」を得ようとしていた。でも、片付け終わった後に残るのは静けさだけ。達成感ではなく、虚無感がじわじわと広がる。その瞬間に、ひとりで大丈夫と思っていた自分が、嘘だったと気づく。
「誰かいてくれたら」と初めて思った日
それは特別な日ではなかった。雨がしとしと降る午後、ふと外を見たときに思った。「誰かいてくれたらいいのに」。書類を作るでもなく、業務を手伝うでもなく、ただ同じ空間に誰かがいてくれるだけで、こんなに救われるのかと。その思いに気づいてしまったとき、長年張ってきた「ひとりで大丈夫」の仮面が音を立てて崩れた。
仕事の話じゃなくてもいいから
相手が司法書士でなくてもいい。業界のことを知らなくてもいい。ただ、今日の天気の話や、最近食べたものの話をぽつぽつできるだけで、気持ちが和らぐ。自分にはそれがない。それを我慢してきた。でも、もう限界だった。孤独は強さではなかった。むしろ弱さを見せられる誰かがいることこそが、本当の意味での強さかもしれない。
結婚とか恋愛とかじゃなくても
「寂しい=結婚したい」ではない。誰かと暮らすことで得られる安心感もあるだろう。でも、自分が求めているのはそれよりももっと手前の「つながり」だった。恋愛じゃなくていい。家族じゃなくていい。ただ、日常の中で「あなた、元気にしてた?」と声をかけてくれる存在。それだけで、生きるペースが変わる。
黙ってそばにいるだけの人の存在
言葉なんていらない。黙ってコーヒーを淹れてくれる人がいて、黙ってそのコーヒーを飲む時間があるだけで、今日という一日が違って感じられる気がする。そんな関係を築くことが、どれほど難しくて、どれほど尊いことか。ひとりで大丈夫だと強がるよりも、誰かを受け入れる勇気のほうが、ずっと大きな力になる。
これからの自分に期待しすぎないために
もう、自分に過度な期待はしないようにしようと思う。完璧であろうとしない。強がらない。できない日はできないと言う。大丈夫じゃない日は、誰かに話す。そう決めたら、少しだけ生きやすくなった。「ひとりで大丈夫」と言い聞かせることをやめた日から、本当の意味での「大丈夫」が見えてきた。
完璧じゃなくていいと認める勇気
「先生なんだから」「プロなんだから」という言葉が、時に自分の首を絞める。でも、先生だって人間だし、プロだって疲れる。うまくいかない日もある。そういう日を無理やりなかったことにせず、ちゃんと感じて、ちゃんと休む。それができるようになれば、自分にも優しくなれるし、誰かにも優しくなれる気がする。
ひとりを貫くために必要なこと
皮肉なことに、「ひとりでいる力」を本当に保つには、「誰かとつながる力」が必要だった。完全な孤独は、いつか必ず壊れる。だからこそ、自分の時間を大切にしながらも、誰かと少しだけでも繋がり続ける工夫が要る。声をかける、会話をする、誘ってみる。ほんの少しの勇気が、未来の自分を救ってくれる。
頼ることと甘えることのちがい
昔は、「頼る=甘える」だと思っていた。でも違った。頼るというのは、相手を信じて一歩踏み出すこと。自分の弱さをさらけ出すことではなく、ありのままの状態を伝えること。甘えるのは相手に依存すること。でも頼るのは、自立の一部だった。ようやくその違いに気づけた今、自分の人生が少しずつ変わっていく気がしている。