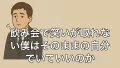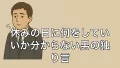なぜか調子が良かった日の不安
朝から全てが順調で、予定していた登記の申請もミスなく進み、相談の電話も少なく、事務員さんの機嫌も悪くない。こんな日は本来、ほっと胸をなで下ろすべきなのに、心のどこかで「何か忘れてないか」とソワソワする自分がいる。特に午後の静けさが怖い。急に嵐が来るんじゃないかという謎の予感。結局その日は何も起こらないんだけど、夜になると「今日の静けさは明日の地雷の予兆かもしれない」と、ひとりで勝手に疑ってしまう。うまくいった日に限って、怖くなる夜があるのだ。
終わった瞬間からよぎる「落とし穴」の予感
一日の業務が終わって、パソコンの電源を落とした途端、ふと頭をよぎるのが「本当にこれで良かったんだっけ?」という疑念。とくに登記申請を複数件一気に済ませた日なんかは、スムーズに進みすぎると逆に「間違ってるんじゃないか」と心配になる。元野球部でいうところの、無失点で9回を抑えたピッチャーが「次の登板で炎上しそう」と思ってしまうあの感覚に近い。安心するより先に身構えてしまうのは、職業病なのか性格なのか、自分でももう分からない。
電話が鳴らなかったことすら不気味に感じる
普段なら「電話が少なくて助かったな」と思うところが、妙に電話が鳴らなかった日は逆にそわそわしてしまう。「もしかして固定電話の線が抜けてる?」「スマホの着信設定間違ってた?」と確認したりする自分がいる。どこかで、「忙しい=正常、静か=異常」という思考パターンが染みついてしまっているのかもしれない。これ、決して心が休まらない思考回路だと分かっているのに、なかなか止められない。
「今日はやけにスムーズだったな」と思ったら危険信号
書類もスキャンもすんなり済んで、顧客とのやりとりも円滑だった日。帰り際に「今日は何もトラブルがなかったな」と思った瞬間、次の思考が「いや、何か見落としてるだけじゃないか?」となる。この癖、本当にやっかいだ。高校時代、ノーエラーで試合を終えたあとに「逆に明日こそエラーしそう」と不安になっていた記憶を思い出す。なんでもかんでも帳尻が合うように出来ていると思ってしまう、勝手なバランス感覚が根にあるのかもしれない。
安心感より先に疑いが来るクセ
人より少し慎重な性格だと自覚はあるが、それが行き過ぎて「うまくいったことすら信じない」というスタンスになっている気がする。楽観できる人がうらやましいが、自分はどうも「順調=危険の前触れ」というパターンを疑ってしまう。とくに大きなミスをした経験が尾を引いているのかもしれない。どんなに事務員さんに「大丈夫ですって」と言われても、どこかで「そう思ってるだけじゃないか?」とまた疑ってしまう。
成果よりも「異常値」に見えるメンタル
数字で見れば、1日に5件の登記を無事に終えたらそれは「成果」だ。でも、自分にとってはその成果より「これは普通じゃない、うまく行きすぎてる」という謎の疑心の方が強くなる。喜ぶより先に、「あとから何かしわ寄せが来る」と思ってしまう。この感覚、他の人に話してもなかなか理解してもらえない。むしろ「心配しすぎ」と笑われる。でも、自分としてはそれなりに真剣で、これまでの経験から身に染みてきたものなのだ。
過去の失敗が今も心のどこかに居座っている
10年以上前、所有権移転登記で地番を誤って申請し、依頼者に頭を下げに行ったことがあった。そのときの「油断してたんでしょう?」というひと言が今でも記憶に残っている。だからこそ、うまくいったときこそ油断してはいけないという信念ができてしまった。普通の人が安心する場面でも、自分は「これは罠かもしれない」と疑ってしまう。過去のトラウマが、今の思考をじわじわと支配しているのだ。
「うまくいくこと」が信用できなくなった経緯
昔はもう少し素直だったような気もする。でも今は、何かがうまくいくたびに「この反動がどこかでくる」という考えが自動的に湧いてくる。仕事の性質上、ミスは命取りになる。だからこそ、「うまくいった」は「何か見落としたかも」とセットになってしまった。これが自分の性格なのか、それとも司法書士という仕事柄なのか、今でもよく分からない。
新人時代の「うまくいきすぎた」地雷案件
開業して間もない頃、何もかもがスムーズに進んだ相続登記案件があった。自分でも「今日は完璧だ」と思っていた矢先、数日後に相続人の一人から「うちはそんな話聞いていませんけど?」という連絡が。完全に連絡漏れ。被相続人の長男と話し合った内容を他の相続人に共有し忘れていたのだ。「うまくいった」と思った直後に足元をすくわれた体験は、それ以来の疑い癖の始まりだったかもしれない。
順調に進んでいたはずの案件での大失敗
補正もなく、全ての書類が揃って、何も問題がないと感じていた案件で、実は住所の表記に誤りがあったことに気づいたのは提出後だった。それも、法務局から指摘されたわけではなく、依頼者の知人からの指摘。見事に自分の落とし穴だった。こうした経験が積み重なると、「順調=落とし穴を見落としている」という連想が染み付いてしまう。
褒められた翌日に届いたクレームの電話
依頼者から「さすがですね、完璧でした」と言われて気分良く帰宅した翌日、違う依頼者から「連絡が遅い」とクレームの電話が入った。こうなると、前日の褒め言葉すら疑わしくなってくる。「そのうち叩かれるんじゃないか」「好印象のあとには悪印象が来る」そんな思考回路になってしまう。これはもう、一種の防衛反応かもしれない。
性格なのか、職業病なのか
ときどき、自分のこの不安体質は性格なのか、司法書士という仕事の宿命なのかと考える。もちろん両方あるのだろうけど、他の士業の人に聞いても「似たようなこと思う」と言われることが多い。やっぱり、慎重さを求められる業務では、「うまくいった」という言葉に素直になれない人は、少なからずいるんだろう。
司法書士は「確認癖」が身に染みすぎる
登記をやっていると「再確認」「再々確認」「最終確認」というように、同じことを何度もチェックする癖が身に付く。それが私生活にも滲み出て、「鍵かけたっけ?」「ガス止めたっけ?」と何度も振り返るようになってしまった。だから仕事でも「うまくいった」で終わるのではなく、「どこか見落としてないか?」と無意識に再確認モードに入ってしまう。
何もないことが怖い、という日常
穏やかに過ぎた1日を振り返って、「何もなかったな」と言うことすら怖い。事務所にトラブルがない日ほど、逆にその静けさに居心地の悪さを感じる。おそらく、波風に慣れすぎたせいで、平穏が逆に不安になってしまうのだ。元野球部時代、ベンチで静かに試合を観ていたときより、ノーアウト満塁のピンチの方がなぜか落ち着いていた、あの感覚に似ている。