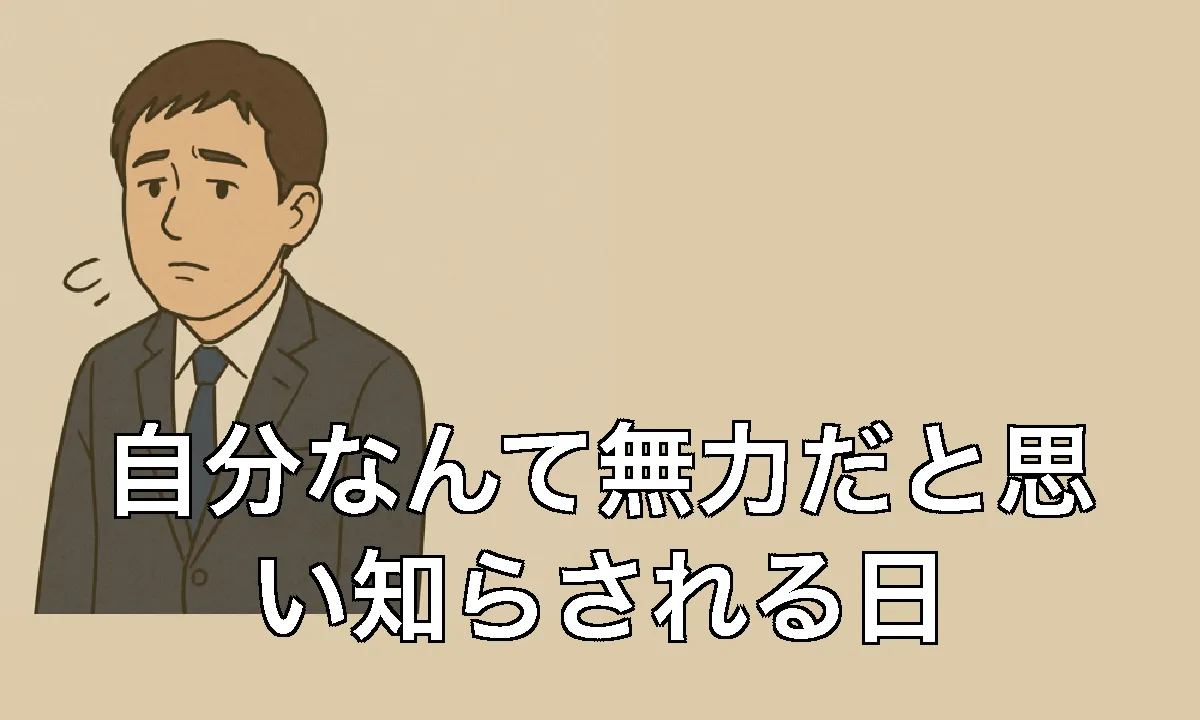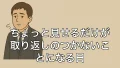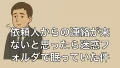無力感が押し寄せるのはいつも不意打ちだ
毎日それなりに頑張っているつもりでも、ふとした瞬間に「自分は無力だ」と思い知らされる。そんな日は、前触れもなくやってくる。たとえば朝一番の電話で心が乱されたり、急ぎの案件で手が震えたり。忙しさに流されていると、自分の心の声を無視しがちだ。でも、不意にその声が顔を出すときがある。自分を支える何かが壊れてしまったような感覚。経験も知識もそれなりに積んできたはずなのに、社会の中での自分の小ささに打ちのめされる。司法書士として人の人生の節目に関わっているのに、自分自身の人生に立ちすくむ。そんな日が、年齢を重ねるごとに増えてきた気がする。
電話一本に心が折れるとき
たった一本の電話で、一日の調子が決まってしまうことがある。朝の9時すぎ、まだ頭が働いていないときに、強い口調の問い合わせが入ると、それだけで気持ちがざわつく。用件自体はたいしたことじゃない。書類の受け取りの時間とか、説明不足への不満とか。でも、相手の不機嫌さに触れると、自分が全否定されたような気になる。特に、自分に非がないと思っている時ほど、その衝撃は大きい。「こっちは悪くないのに」と思えば思うほど、感情の持って行き場を失い、ただ静かに自己嫌悪が膨らむ。電話を切ったあと、しばらく何も手につかなくなることだってある。
内容よりも声のトーンに傷つく日
人間は内容よりも「どう言われたか」に心を動かされるのだと、司法書士をしていてよく思う。特に電話だと、表情もない分、声のトーンがすべてだ。つい先日も「そっちの説明が悪いんじゃないですか?」と強めに言われた。言葉そのものより、その言い方が胸に刺さった。たとえ内容が正論であっても、まるで自分の存在自体を否定されたように感じてしまう。冷静に対応したつもりでも、内心はぐらぐらに揺れている。相手の怒りに飲み込まれ、自分の立ち位置が分からなくなる。声一つでこんなにも傷つく自分に、また落ち込むのだ。
自分の存在意義を疑ってしまう瞬間
「俺はなんのためにこの仕事をしてるんだろうな」そんな言葉が、ふと頭をよぎる日がある。たとえば、依頼人とのやりとりがうまくいかず、トラブルが続いた時。誠意を尽くしているつもりでも、伝わらなければ意味がない。自分がやっていることが社会に役立っているのか、依頼人の力になれているのか、疑念が膨らむ。何年も続けてきた仕事なのに、自信が持てなくなる。「誰でもできる仕事なんじゃないか」「自分じゃなくてもよかったんじゃないか」そんな思考の渦に巻き込まれる。誰かに必要とされたいのに、自分自身に「必要な人間です」と言えないのが、つらい。
相談されたのに答えが出せなかった日
人から頼られることはうれしい。でも、期待に応えられなかった時の落胆は、その何倍も重い。ある日、顔なじみの取引先の社長さんから相続に関する相談を受けた。複雑な家族関係で、法的には対処できても、心情面では割り切れない問題だった。話を聞きながら、何度も言葉を選んだが、どうしても「これだ」と思える助言が出てこなかった。結局、「一度家族と話してみてください」と曖昧な返しをしてしまった。その時の社長の寂しげな顔が、今も頭から離れない。自分の無力さを痛感した日だった。
知識不足ではないのに言葉が出ない
司法書士としての知識はそれなりにある。法的な処理も手続きも、日常業務としてこなせる。けれど、時として知識ではどうにもならない壁が立ちはだかる。それが人の感情だ。理屈ではなく、相手の心にどう寄り添うかが問われる場面で、私はしばしば立ち尽くす。「どう答えるのが正解なんだろう」と考えすぎて、結局無難な言葉しか出てこない。その無難さが、時に冷たく映ることもあるのだろう。専門家としてではなく、人間として何を伝えるべきか、そんな問いに、いまだ答えは見つかっていない。
相手の沈黙が心に刺さる理由
返事が返ってこないとき、人はさまざまな不安を想像してしまう。たとえば説明を終えた後、相手が何も言わずに黙っている時間。私はその沈黙が怖い。納得していないのか、怒っているのか、それともただ考えているだけなのか。相手の沈黙に、自分の言葉の未熟さや対応の不備を勝手に重ねてしまう。そして、「また失敗したかもしれない」と心がざわつく。話すよりも、沈黙の方がずっと残酷な時がある。何も言われないまま帰られた後のあの虚しさは、慣れることがない。
解決しても残る助けられなかったという後悔
業務として手続きを終えたとしても、心の中に「本当に助けられたのだろうか」という後悔が残ることがある。形式的には完了していても、依頼人の表情に曇りがあれば、それだけで胸が痛む。相続、登記、成年後見——人生の大切な場面に関わるだけに、結果よりも「過程」が心に残る。依頼人の人生に少しでも光を届けたかったのに、ただ機械的な処理になってしまったと感じると、プロとしての誇りが揺らぐ。喜ばれたくてやっているわけじゃない。でも、無力感に襲われるのは、いつもそんなときだ。
手続きは完了しても気持ちは置き去り
とある高齢の女性から、長年住んだ家の名義変更を依頼されたことがあった。手続きは順調に進んだが、完了後に女性がぽつりと「これで終わっちゃったのね」と呟いた。その声が忘れられない。たしかに仕事としては完了。だが、その一言に、彼女の寂しさや人生の一章の終わりがにじんでいた。私は何も言えなかった。慰めの言葉すら出てこなかった。あのとき、もう少し丁寧に寄り添えていれば…と今でも思う。書類の完了だけでは、人の心は癒せないのだ。
書類の山の奥に感情が埋もれていく
日々の業務はどうしても「処理」になりがちだ。急ぎの登記、押印の確認、提出期限…気づけば机の上は書類の山。その山の下には、依頼人それぞれの事情や思いがある。でも、忙しさにかまけて、その背景をじっくり感じる余裕がなくなっている。自分が「人」と接していたはずなのに、いつの間にか「案件」としか見られなくなっていることに、時々ハッとする。大切なはずの人の気持ちが、紙の下に埋もれていくようで、自己嫌悪に陥る。
形式では癒せないものがある
法的に正しい対応をしても、それが人の心を癒すとは限らない。むしろ、形式ばかりにとらわれすぎて、本当に必要な言葉や時間を見落としてしまうこともある。とくに相続や離婚に関わる案件では、感情のケアこそが鍵だと思う。でも、自分にはそれがうまくできないことが多い。知識や資格では埋められない「人間力」のようなものが足りないのだと痛感する。だからこそ、日々自分に問う。「形式的に正しかった。でも、それでよかったのか?」と。