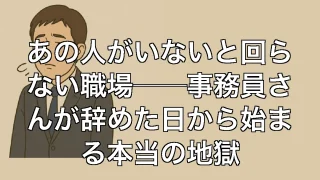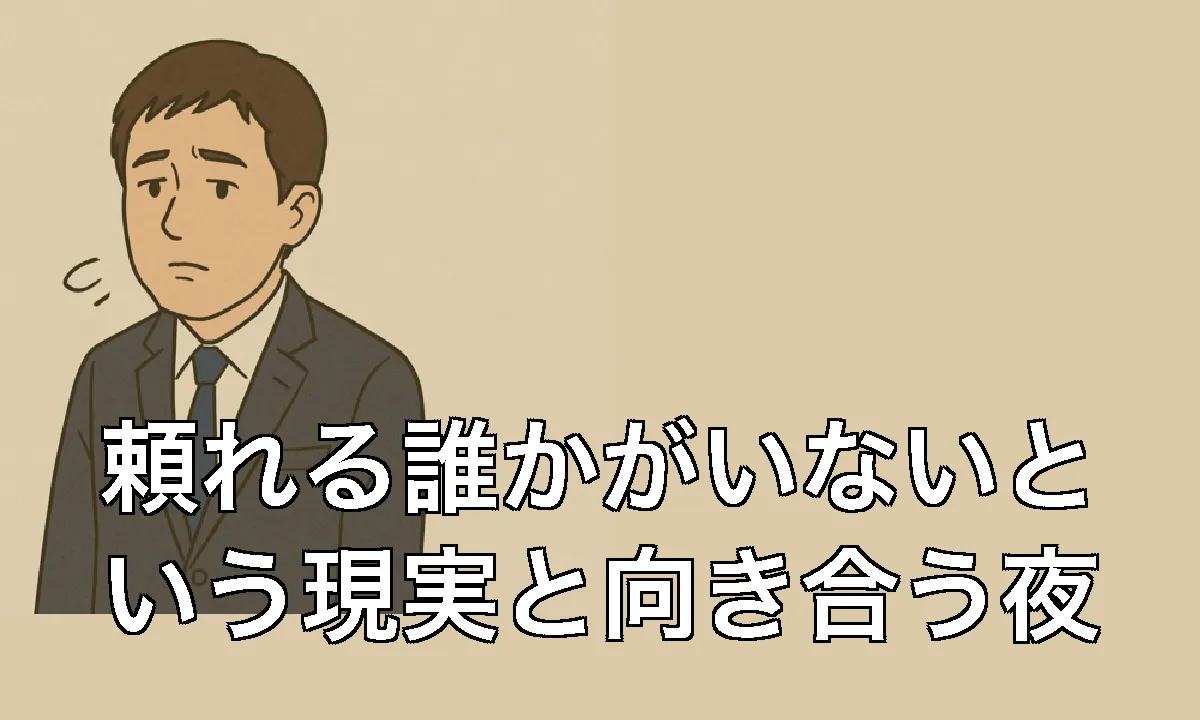夜になると強まる孤独という感情
昼間は、なんだかんだと電話も鳴るし、役所にも行かなきゃならないし、書類の山に追われているうちに1日が終わる。でも、ふと夜になって机に一人座っていると、何かがスッと抜け落ちたような気分になる。静かすぎるのだ。テレビの音がやたらと大きく感じるし、冷蔵庫のモーター音すら神経に障る。そんな時にふと思う。今、何かあったとして、俺は誰に電話をかけるんだろうかって。
日中の喧騒が終わったあとの静けさ
事務所のシャッターを閉め、事務員さんに「お疲れ様」と声をかけた後の時間が、一番しんどい。たとえば、友人と食事に行くとか、恋人と電話をするとか、そういう予定があるわけじゃない。まっすぐ家に帰って、スーパーの惣菜をつまみにビールを飲む。それだけの夜だ。20代の頃は「一人の時間って貴重だよね」なんて言ってたが、45歳にもなると、これは孤独というやつか?と胸が苦しくなる。
電話一本かける相手がいないという事実
この前、スマホを開いて、ふと連絡先を眺めた。司法書士仲間、役所関係、顧客、元同僚…。ずらっと並んでいるけれど、その中に「今すぐに電話してもいい人」は一人もいなかった。くだらない話をできる人が、いないのだ。逆に、相談の電話は夜でも容赦なくかかってくる。「今ちょっといいですか?」というやつ。でも、自分が「今、話を聞いてほしい」って言える相手は…見つからなかった。
独身という選択の代償
結婚をしなかったことに、これまで後悔はなかった。自由だし、仕事に集中できる。でも、ふとした瞬間に気づく。何かを共有できる人がいないというのは、思っていたよりも重たい。夜中に高熱を出しても、誰も気づかない。心が折れそうな夜も、自分でどうにかするしかない。これが独身という選択の代償か…そう思った夜が、ここ数年で何度かあった。
頼れないのではなく頼らないという意地
本当は、誰かに「疲れた」と言いたい。でも、それを口にすることが、なぜかできない。頼ることは悪いことじゃないとわかっていても、身体が拒否する。「甘えたら負けだ」と心のどこかで思っている。たぶん、これは若い頃の体育会系の刷り込みだろう。元野球部というだけで、弱音を吐くのが下手になった。
元野球部という肩書きの呪い
「痛くても走れ」「泣いてる暇があるなら素振りしろ」そんな言葉を耳にタコができるほど聞いた。高校時代の監督は怖かった。でも、今思えば、あれが自分のメンタルの骨格をつくったのかもしれない。弱さを見せたらダメ、助けを求めるのは恥…。それが染み付いているのだ。だからこそ、今もなお、誰かに頼ることができない。
弱音はグラウンドには置いてきたつもりだった
仕事に就いてからも、多少の無理は自分で処理してきたつもりだ。「自営業なんて、全部自己責任」それを盾にして、助けを求めることから逃げていたのかもしれない。司法書士という職業柄、弱音なんて吐けないと、勝手に思い込んでいた。でも、最近ふと思う。あの頃グラウンドに置いてきたはずの弱さが、夜になって自分の胸の中に戻ってきているような気がする。
でも本当は誰かに気づいてほしい
強がっているようで、本音は全然違う。ただの構ってちゃんだ。誰かに「疲れてるんじゃない?」と言ってほしいし、「手伝おうか」と声をかけてほしい。でも、表情には出さないし、口にもしない。だから誰も気づかないし、気づけない。そしてまた、今日も一人でなんとか乗り切ってしまう。それが繰り返される夜に、ふと涙が出そうになる。
事務員一人と回す地方の司法書士事務所
田舎の事務所で、事務員さんと二人三脚。たまに「先生は気楽でいいですよね」と言われることがあるが、気楽ならここまで胃が痛くならない。スケジュール調整も、苦情対応も、全部自分。誰もやってくれないし、任せられない。自分が倒れたら終わり。それが、地方の小さな司法書士事務所の現実。
忙しいのに誰にも愚痴れない構造
たとえば昼休みに、誰かと他愛もない会話をしたい。今日のランチがしょっぱかったとか、天気が悪くて洗濯物が乾かないとか。でも、それを話す相手がいない。事務員さんも忙しそうで、気を使って話せない。気づけば愚痴はどこにも行き場がなく、心の中でうずまくだけになる。独り言が増えたのはそのせいかもしれない。
仕事の山に押しつぶされそうになる日
依頼が重なると、頭の中が混乱してくる。どれを優先して、どこから手をつけるべきか。それがわからなくなる時がある。書類を前に呆然とする。昔なら根性で片づけた。でも今は、身体がついてこない。目がしょぼついて、肩がこりすぎて、キーボードを打つ手が止まる。そんな時に思う。「誰か、助けてくれよ」と。
相談を受ける側だからこそ、相談できない
司法書士は人の相談を受けるのが仕事。でも、その立場だからこそ、相談できないことも多い。悩みがあっても、愚痴があっても、「そんなことで?」と思われるのが怖くて、結局は黙ってしまう。話せる人がいないというより、「話してはいけない」と思い込んでいるのかもしれない。
「先生」と呼ばれるほどの苦しみ
「先生、助けてください」その言葉を何度も聞いた。でも、僕が「誰か助けて」と言うことは、ほとんどない。なぜかと言えば、司法書士という職業が、そういう空気をまとうからだ。「先生」と呼ばれることで、何かを期待されている気がして、期待を裏切るのが怖くなる。だからいつも、無理をしてしまう。
本音を出せる相手がいない専門職の現実
専門家であることの代償は、心の孤立かもしれない。司法書士同士でも、なかなか本音では話せない。競争関係でもあるし、妙なプライドもある。悩みを共有できるようで、できない。SNSでも「うまくいってます」風の投稿が多くて、ますます自分だけが取り残された気分になる。誰かに相談するって、こんなに難しいことだったか。
それでも朝は来るし、仕事も続く
どれだけ孤独な夜でも、朝は来る。新聞が届き、また電話が鳴る。やることは山ほどある。誰にも頼れないと思っていても、どこかで自分を立て直して、一日を始める。なんとかなる。そう信じるしかない。夜の闇は深いが、朝の光は、それでも眩しい。
誰にも頼れない夜を越えた先の話
一人で越えた夜は、確かにしんどい。でも、それを越えた分だけ、自分に対する信頼がほんの少しだけ育つ。「あの夜もなんとかやり過ごしたじゃないか」と思える。それがまた、次の夜を乗り越える力になる。きっと、そういう積み重ねで僕たちは生きてるんだろう。
小さな希望をどこに見出すか
希望って、特別な出来事じゃない。朝ごはんが美味しかったとか、今日の空がちょっとだけ綺麗だったとか、そういう小さなことだ。それに気づける余裕があるかどうか。誰にも頼れない夜を越えてきたからこそ、そういう小さな「良かった」に敏感になれた気がする。