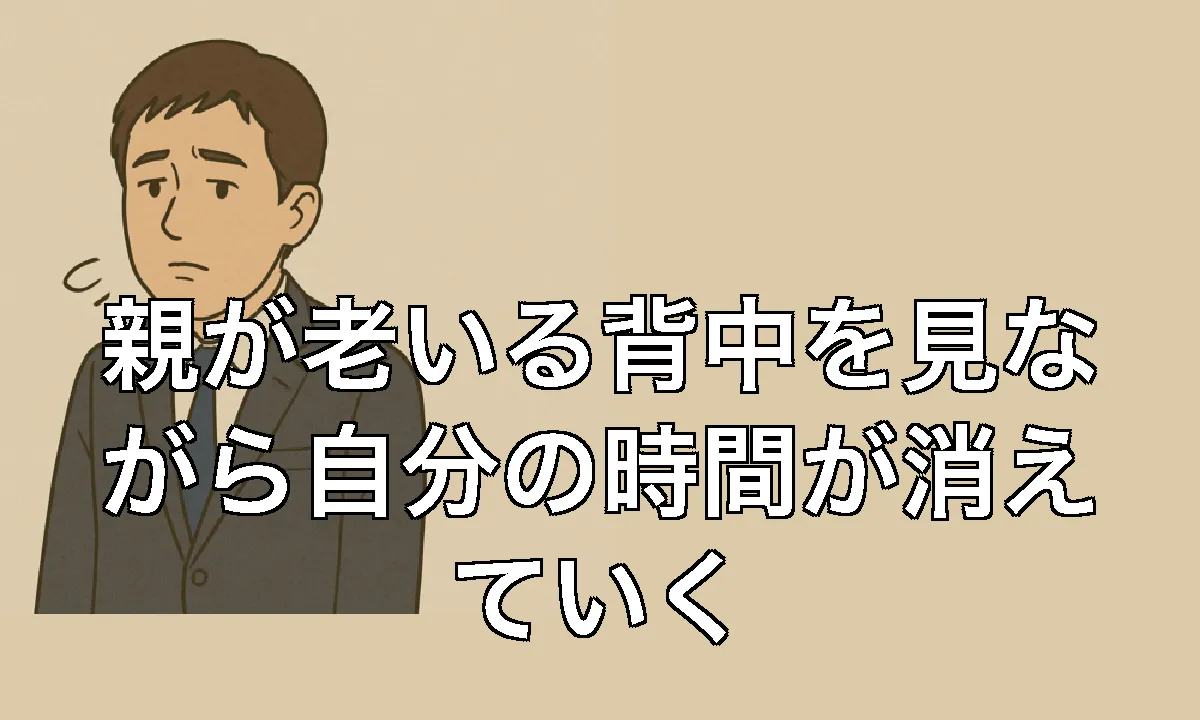親が老いる背中を見ながら自分の時間が消えていく
老いを感じたのはいつからか
司法書士として働き詰めの毎日を送っていると、親の老いに気づく瞬間というのは、ある日ふとやってくる。僕の場合、それは実家に顔を出したときだった。玄関先に出てきた母の姿が、やけに小さく見えたのだ。背中が丸まり、歩き方もどこか不安定。昔はもっとしゃんとしていたはずなのに、と思うと、胸の奥に何とも言えない違和感が残った。その違和感は、仕事中にもふと顔を出すようになり、自分の時間の中に「親の老い」が静かに入り込んでくるようになった。
声のトーンが変わった親に気づいた朝
ある朝、母から電話がかかってきた。「おはよう」の声が、以前よりもか細く聞こえた。その瞬間、無意識に受話器を持つ手が止まった。あの朗らかな声じゃない。体調でも悪いのかと尋ねると、「年のせいよ」と笑われた。でも、その笑い声にすら元気がなかった。電話を切ったあと、しばらく机に向かう気にもなれず、ぼんやりと天井を見つめてしまった。どれだけ仕事に追われていても、親の変化は突然心をかき乱してくる。
実家に帰るたびに増える「できないこと」
実家に帰省するたびに、親ができないことが増えていくのを感じる。掃除機が重い、階段の昇り降りがつらい、炊事が億劫——。それを口にするたび、親もまた「老い」と向き合っているのだと実感する。僕が子どもの頃、風邪を引けば夜通し看病してくれたのに、今は僕がその役割を担う番だ。とはいえ、忙しさを理由に頻繁に通うことはできず、電話一本で「大丈夫?」と聞くことしかできない。自己嫌悪と現実のはざまで、心がチクチクと痛む。
司法書士という仕事が親との時間を奪う
司法書士という仕事は、ある意味で「人の人生の節目に立ち会う仕事」だ。登記、相続、遺言、成年後見…。人の暮らしに寄り添う一方で、自分の暮らしは後回しになる。特に独立してからというもの、親の誕生日すらまともに祝えないことが増えた。事務所の電話は休日も鳴るし、登記の期限は待ってくれない。「ああ、親に会いたい」と思うタイミングは、いつも忙しさの山場と重なる。
気がつけば休日も仕事の延長
本来であれば休日は親とゆっくり過ごす時間にあてたい。でも現実は、電話応対や書類の整理、後見人としての連絡業務などがずるずると入り込んでくる。「ちょっとだけ」と思って開いたパソコンの前で、いつの間にか数時間が過ぎる。気がつけば日が暮れ、実家に行くはずだった予定も先延ばし。そんな日が積み重なって、気づいた頃には季節が変わっている。自分の人生は、いつから“後回しの山”に埋もれてしまったのだろうか。
事務所を休むという選択肢が見えない
独立してからは特に、事務所を「休む」ということが難しくなった。自分が動かなければ仕事が止まり、依頼者にも迷惑がかかる。そんな責任感が重くのしかかって、結局、親の通院にも付き添えず、葬儀や見舞いのスケジュール調整にも一苦労。依頼者には関係のない話だ。誰かに代わってもらえる体制があれば違うのだろうが、今の規模ではそれも叶わない。まるで、自分が自分を縛っているかのようだ。
仕事を抱えすぎると後悔に変わる
最近、ふとした瞬間に「何のために働いているんだろう」と思うことがある。依頼者の感謝はうれしい。でも、それと引き換えに親のそばにいられない今は、どこか空虚だ。仕事に埋もれている間に、親は着実に年を重ねていく。もっと声をかけておけばよかった、もっと一緒に食事をしておけばよかった——。そんな後悔が、いつか自分を責めてくる未来が見えてしまう。まだ間に合うなら、今すぐ立ち止まりたい気持ちになる。
自分も老い始めている現実
ふと鏡を見ると、目元のしわや疲れた表情に驚くことがある。親の老いに気を取られていたけれど、自分も確実に年をとっているのだ。朝の肩こり、夕方の目のかすみ、なかなか抜けない疲れ。かつては徹夜明けでも平気だった体が、もう言うことをきかない。親の老いに気づくことで、自分の老いとも向き合わざるを得ない。つまりそれは、人生の有限性を突きつけられる瞬間でもある。
野球部時代の体力はどこへやら
高校時代、僕は野球部だった。朝から晩まで走って、泥だらけになっていたあの頃の体力は、いったいどこへ消えたのか。最近では書類を持って法務局を回るだけで膝が痛むし、階段の上り下りすらため息が出る。そんな自分を見て、ふと「親も同じだったのか」と思い至る。かつての元気だった親が、今では階段をゆっくりと降りている。その姿に、自分の未来を重ねずにはいられない。
独身のまま親を看る不安と責任
僕は独身だ。結婚の予定もない。そうなると、将来親を看るのは自分一人だという現実が重くのしかかる。兄弟もいないし、事務所を回しながら介護をする未来が、すでに目前に迫っている気がする。「誰かと分担できれば…」と思うこともあるけれど、現実はそう甘くない。親の老いに向き合うということは、孤独とも向き合うということなのだ。
事務員に支えられていることを痛感する
普段は「こちらが雇っている立場」という意識が強かったけれど、最近になってようやく気づいた。事務員さんの存在は、ただのサポートではなく、僕にとっての支えそのものだ。小さな気遣いや雑談が、どれだけ僕の精神を保ってくれているか。親のこと、仕事のこと、どちらも一人で背負うのは難しい。そんなとき、静かに寄り添ってくれる人がいることのありがたさを痛感する。
一人事務所の限界とありがたみ
人を雇うのはコストもリスクもある。それでも、今の僕にとって事務員さんの存在は「業務効率」以上の意味を持つ。小さなミスを拾ってくれたり、ちょっとした雑談で気を抜かせてくれたり。もしもこの事務所が完全に一人だったら、心が潰れていたかもしれない。親のことも事務所のことも、すべて一人で抱え込むのは限界がある。支え合いという言葉の重みを、今ようやく実感している。
「無理しないでくださいね」の一言が沁みる
先日、忙しそうな僕を見て、事務員さんがぽつりと言った。「無理しないでくださいね」。その言葉に、不覚にも少し涙が出そうになった。普段は愚痴ばかりで、感謝を伝える余裕もないけれど、その一言で救われたような気がした。誰かが見ていてくれる、それだけで人は踏ん張れるものなのだと思う。たとえプライベートがうまくいかなくても、人として支えてくれる人がいれば、それは幸せの一つの形なのかもしれない。
それでも親との時間を大事にしたい
仕事に忙殺されながらも、やはり心のどこかで「親との時間は限られている」と感じている。だからこそ、できる限りのことはしたいと思う。たとえ短い時間でも、顔を見に行く。電話で近況を聞く。そんな小さな行動が、いつか自分を救ってくれる気がしている。老いる親と、自分自身の時間が、静かに交差している——そんな今を、大切に抱きしめて生きていきたい。
会話の内容が変わったことに気づく
昔は「仕事どう?」「まだ独りなの?」なんて言っていた親が、最近では「ご飯はちゃんと食べてる?」「体は大事にしてね」と言うようになった。会話の内容が、徐々に変わってきた。そこには親なりの心配と、もしかしたら別れを見据えたやさしさがあるのかもしれない。だから僕も、もう少し素直になろうと思う。「ありがとう」とか「また来るよ」とか、ちゃんと伝えていきたい。
一緒にご飯を食べるだけでも救いになる
外食でも、家の台所でもいい。親と向かい合ってご飯を食べる、それだけで心が少し軽くなる。たったそれだけのことなのに、日々の忙しさに追われていると、それがなかなか叶わない。だけど、そのひとときの温もりが、疲れた自分を少しだけ癒してくれる。時間がなくても、体力がなくても、ご飯の時間だけは一緒に過ごす。それが、僕にとってのささやかな願いだ。
親の老いと自分の生き方を重ねながら
親の背中を見ながら、僕は自分のこれからを思う。どんなふうに老いていくのか、どんなふうに人生を終えるのか。そして、その中で誰かに何を残せるのか。司法書士としての仕事も、自分の人生も、何か意味があるものにしたい。そんな気持ちが、ようやく芽生えてきた。親が老いていく姿を受け入れることは、同時に自分自身の未来を受け入れることなのかもしれない。