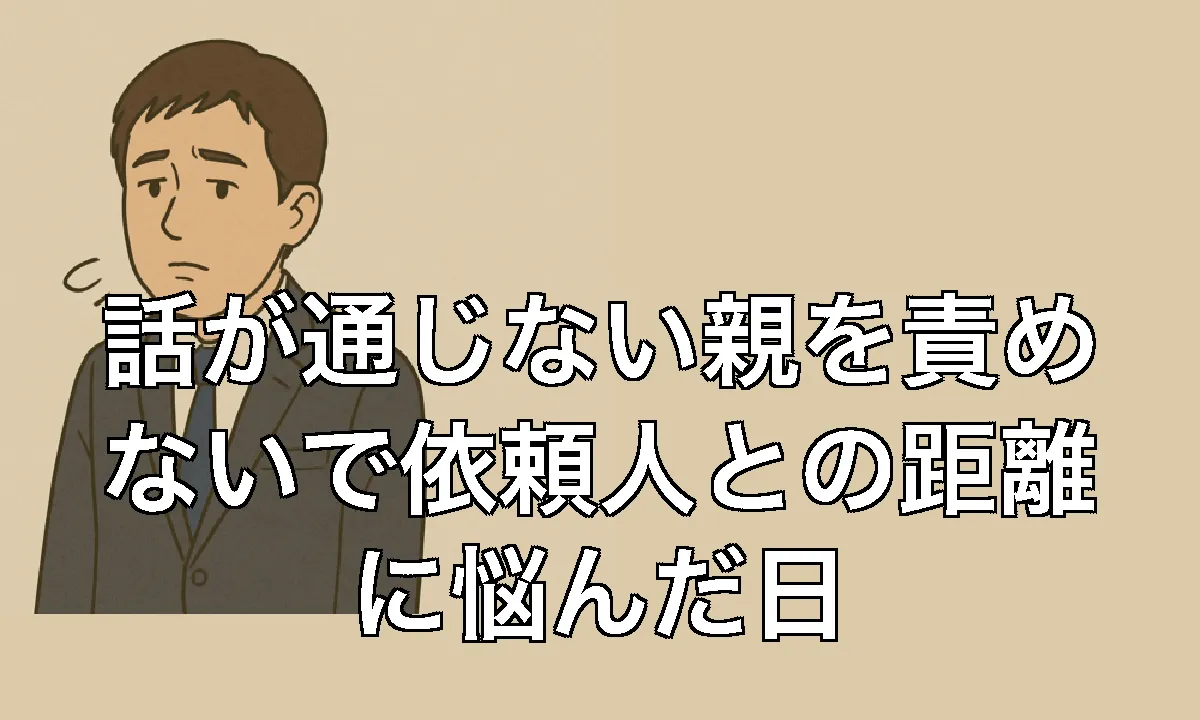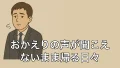依頼人の「困っている」が伝わる瞬間
事務所に飛び込みでやって来た40代の女性。母親の財産について相談したいとのことだったが、話を聞くうちに、どうも話が噛み合わない。母親はまだしっかりしていると言いながら、銀行に行っても話が通じず、手続きが進まないとこぼす。どこかで聞いたような話だな、と思いながら、私は「成年後見」の話を始める。でもその瞬間、彼女の顔が少しこわばったのを、今でもよく覚えている。
認知症の親を持つ依頼人との出会い
「まだそんな歳じゃないんです。しっかりしてるんです」。そう何度も繰り返す依頼人に、私は最初どう接すればいいのか悩んだ。こちらは法的な選択肢を提示しているだけなのに、何か否定されたような顔をされる。この違和感が拭えず、面談が終わったあともしばらくモヤモヤが続いた。認知症を「認めたくない」気持ちは、家族ならなおさら強い。自分の親の衰えを正面から見るのは、誰だって辛い。
初回面談で感じたすれ違いと戸惑い
依頼人の話を一通り聞いてから、私は「もし認知症の症状が進んでいたとしたら、成年後見制度を検討する必要があるかもしれませんね」と伝えた。すると彼女は少し間を置いて、「でも母はちゃんと喋れますし」と言った。その瞬間、私の中で一気に距離が生まれた感覚があった。私が話しているのは制度上の判断の話なのに、彼女は“母親の人格を否定された”と受け取ったのだろう。
現場で起こる小さな誤解と大きな誤解
認知症という言葉が出るだけで、感情が揺れる依頼人は少なくない。とくに、まだ症状が軽度の段階では「しっかりしているところ」ばかりを見てしまう。こちらとしては、法的な視点で必要な手続きを案内しているだけでも、それが相手にとっては「親を病人扱いされた」と感じられてしまう。このズレが、後の手続きの妨げになることもある。
「うちの母はまだ大丈夫」という言葉の裏
「まだしっかりしてるんですよ」「この前も一人で買い物に行ったばかりで」。そんな言葉を何度も聞いたことがある。でも実際に日常の手続きで問題が起きているのだから、現実には「大丈夫」じゃない場合もある。ただ、それをそのまま突きつけても、依頼人には届かない。むしろ心を閉ざされる。事実と感情の間に橋をかけるような言葉選びが求められる。
認知症の進行と法律行為のギャップ
認知症の症状が進むと、「本人の意思確認」が難しくなる。たとえ会話は成立していても、契約の意味を理解していなければ無効になる可能性がある。これは司法書士としては当然の判断だけれど、家族にとっては信じたくない現実だ。「そんなに悪くないと思ってたのに」と涙ぐむ依頼人を何度も見てきた。
成年後見制度を話しても響かないとき
成年後見制度はとても有効な制度だが、説明するタイミングが難しい。感情の整理ができていない依頼人にとっては、「親を裁判所に差し出す」ように聞こえることもある。「そんな大ごとになるなんて」と動揺されることもあるので、できるだけ段階的に説明し、まずは今の困りごとにどう対処するかから話を始めるようにしている。
書類が揃わないことを怒れない現実
「母がどこにしまったかわからなくて……」。よくある話だ。登記簿、印鑑証明、通帳――必要な書類が見つからず、何度も足を運んでもらうことになる。依頼人も苛立っているが、私も内心では「またか」と思っている。けれど、それを言ってしまったら、もう関係は終わりだ。感情を飲み込んで、「一緒に探しましょうか」と言うのが、疲れるけど必要なひとこと。
感情を受け止める仕事に正解はない
士業の仕事は、手続きだけでなく“気持ち”も引き受ける側面がある。依頼人が迷っていたり、怒っていたり、涙ぐんでいたりするのは、こちらの説明が悪いわけじゃない。でも、そこに向き合うのは、正直しんどい。どこまで寄り添って、どこから線を引くか。その判断を毎回迫られる。
「かわいそう」と「何とかしたい」の間で揺れる依頼人
「母がこんなふうになるなんて」「もっと早く気づいてあげればよかった」。責任感と罪悪感がないまぜになっている依頼人を前にすると、こちらも胸が痛む。私も40代。親の衰えを感じることも増えた今、余計に他人事に思えなくなる。プロとして冷静に対応しなければと思いつつ、「その気持ち、わかりますよ」と声をかけたくなる。
説明を尽くすことの限界と無力感
何度も同じことを説明しても、理解が追いつかない依頼人もいる。理解力の問題ではなく、感情が邪魔をしているのだと思う。「わかっているけど、踏み出せない」。そんな空気を感じながら、私は「焦らなくて大丈夫ですよ」と言う。でも内心では「早くしないとまずいのに」と思っている。この板挟みに、毎度疲れる。
自分が感情的になる瞬間が一番危ない
忙しいときに限って、手間がかかる案件が飛び込んでくる。認知症の親を持つ依頼人との対応も、時間がかかるし感情労働だ。自分の中の“イライラ”が表に出そうになるとき、「司法書士としては失格だな」と思う。でも、そういうときこそ深呼吸が必要だ。
忙しい中で押し寄せる苛立ちとの向き合い方
立て続けに登記が重なり、事務員もバタバタしている中で、3度目の電話で「通帳が見つかりません」と言われた日、私は思わず「……そうですか」と冷たく返してしまった。電話を切ってから、自己嫌悪に襲われた。相手は困って連絡してきたのに、こちらが突き放してどうする。そんな自問を繰り返す日々。
相手に優しくなれない自分が嫌になるとき
どこかで「こっちだって忙しいんだよ」と思っている自分がいる。依頼人にとっては人生の大問題でも、こちらには日常の一件。感情の温度差が、私を冷たくさせる。でも、そういうときにこそ、自分の言動を見直す必要がある。言葉一つで信頼が壊れることもあるから。
それでも冷静でいるための小さな習慣
私は最近、面談の前に一杯の白湯を飲むことにしている。深呼吸のかわりに、気持ちを落ち着かせるための儀式みたいなものだ。それから、依頼人のことを「誰かの家族」として見るようにしている。ただの手続きの相手じゃない。そう思うだけで、少し言葉が変わる気がする。
認知症の親と向き合う依頼人に寄り添うには
法律のプロである以上、正確な判断と適切な手続きは欠かせない。でも、それだけでは不十分だと感じる場面が増えてきた。特に認知症の親を持つ依頼人には、「この人なら話しても大丈夫」と思ってもらえる関係づくりが何より大事だ。冷静で、でも人間味があって、そんな司法書士でいたいと願っている。
司法書士として「手続き以外」でできること
行政の相談窓口を紹介したり、地域包括支援センターの存在を伝えたり。ときには「今日ゆっくり寝てくださいね」と言うだけでも、依頼人の表情が変わることがある。書類の準備や制度の説明だけが仕事じゃない。誰かがそばにいると思えることが、次の一歩になる場合もある。
話を聞くことの意味をもう一度考える
「先生に話を聞いてもらえて、少し楽になりました」。そう言われると、ああこの仕事やっててよかったなと思う。聞くことは簡単なようで難しい。つい口を挟みたくなるし、解決策を急ぎたくなる。でも、まずは“そのまま聞く”。それが、認知症の親と向き合う依頼人にとって、一番大きな支えになるのかもしれない。