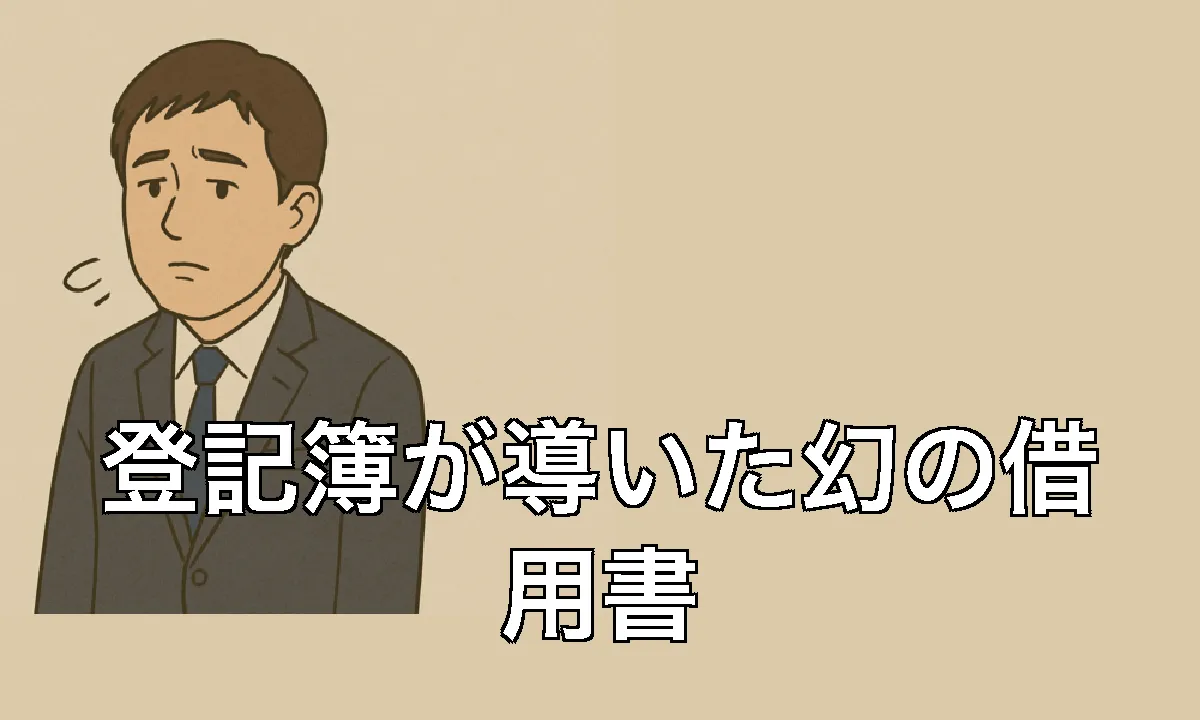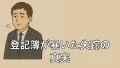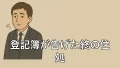登記の依頼と奇妙な一言
「昔の借用書が見つかってしまってね」——依頼人はぽつりとそう言った。 僕の机の前に座ったのは、くたびれたスーツ姿の初老の男。どこか世を拗ねたような眼差しで、封筒をそっと差し出してきた。 司法書士として数多の書類を見てきた僕でも、どこかこの封筒には違和感を覚えた。
年季の入った一通の封筒
封筒は黄ばんでおり、角はすり減り、まるで昭和の遺物のようだった。 中から出てきたのは「借用書」と記された一枚の紙。筆跡は達筆すぎて読みにくいが、確かにそこには金額と年月日、そして押印があった。 「この土地は、父が借金の担保に預けたものなんです」と男は続けた。
「昔の借用書が見つかって」
司法書士として、書面だけで判断するのは危険だ。しかし、あまりに古く、あまりに雑な保管状態の借用書は、逆に本物らしさを漂わせていた。 それが罠なのか、あるいは真実の名残か。僕はサトウさんに目で合図を送ると、彼女はすぐに調査を開始した。 この時点で、何かが引っかかっていた。登記簿にそんな担保の記録はなかったのだ。
消えた借金と現れた債権者
土地の登記簿謄本を確認しても、問題の債権者の名前はどこにも記載されていない。 それどころか、当時の所有者は一度も変更されておらず、抵当権の登記もない。 だが、借用書には確かに「担保としてこの土地を預かる」と記されていた。
三十年前の土地売買の記録
僕は旧法務局から取得できる限界まで遡って調査を依頼した。 登記簿には、その土地が三十年前から変わらず一家の名義であることが記されていた。 一見何の変哲もないこの土地に、なぜ今さら借用書が持ち出されるのか。どうにも胡散臭い。
登記簿にはない名義変更
名義変更がなかったにもかかわらず、借用書には「返済がなければ土地の所有権を移す」と明記されていた。 まるで時代劇の悪徳商人の取引のような曖昧さ。契約書として成立するには証拠が薄すぎる。 そもそもこの書面が「本物」である保証はどこにもない。
登場人物たちの奇妙な関係
サトウさんの調査により、依頼人の父親は元金融業者だったことが判明した。 かつては町のあちこちに金を貸していたが、強引な取り立てで有名だったという噂もある。 どうやら、彼の遺品の中からこの借用書が出てきたらしい。
依頼人は元金融業者の息子
「父は悪い人間でした。でも、これは本当なんです」と依頼人は語った。 彼の目には、どこか信じたいという期待と、信じられないという疑念が混じっていた。 人間関係の継承は、登記のようにスパッと記録されない。むしろややこしく絡まっていく。
近所の地主の不可解な証言
さらに話を聞いた近所の地主は、「あの家の土地が一度、売られたような話もあった」と証言した。 だが、登記簿には記載されていない。まるで口伝えの都市伝説だ。 登記簿は絶対だが、必ずしもすべての真実を記録しているわけではない。
司法書士としての疑問
「これは、、、本物じゃないかもしれませんね」 僕の言葉に、依頼人は露骨に不満げな顔を見せた。 だが、司法書士は証拠なき主張に手を貸すことはできない。
正当な債権かそれとも詐欺か
借用書が本物であれば、なぜ登記されなかったのか。 もし偽物であれば、なぜ三十年も温存されていたのか。 そのいずれにせよ、登記簿上の効力はゼロだった。
過去の登記に潜むほころび
登記簿は公の記録であり、絶対的な証明力を持つ。 しかし、記録されていない何かがあったとしたら? それを補うには、確固たる証拠が必要だ。
サトウさんの冷静な推理
その夜、サトウさんが机の上に借用書を置きながら言った。 「これ、封筒が新しすぎます。中身と不釣り合いですね」 僕は驚いて封筒をよく見た。確かに、郵便番号が7桁だった。
封筒の角度と押印の矛盾
さらに押印の部分には、妙なずれがあった。 三十年前の印鑑なら、もっとインクがかすれているはずだ。 「これはコピーじゃありませんか」——サトウさんは言い切った。
「これはコピーじゃありませんか」
たしかに押印の部分が微妙に影のようになっている。 それは、スキャナーで取り込まれた紙をコピーしたときの典型的な特徴だった。 依頼人が持ってきたのは、原本ではなく、精巧な偽物だった。
シンドウのうっかりと閃き
思わず机の上のコーヒーをひっくり返してしまい、書類の一部を濡らしてしまった。 「しまった!」と慌てて拭くと、滲んだインクの下から、薄く消された印字が浮かび上がった。 どうやら、もとの文書を上書きして作られた偽造だったようだ。
コーヒーをこぼして見えた文字
「やれやれ、、、こんなところで僕のうっかりが役立つとは」 浮かび上がった文字は、元の借用書がまったく異なる内容だったことを示していた。 依頼人は真っ青になり、ついに口を開いた。
真相への道筋
「父が遺した土地を、自分のものにしたかったんです」 依頼人は観念したように語り始めた。 「借金も嘘です。すべて、土地を奪うための工作でした」
裏書きされた日付の秘密
借用書の裏には、修正液で消された文字があった。 それをサトウさんが丁寧に透かして読み取ると、 平成ではなく、令和の日付がかすかに残っていた。
登記官の証言
法務局の登記官に問い合わせたところ、 「当時の記録にそのような担保権は一切ありません」との回答。 念のため原本照会を依頼しても、保管期限が過ぎていた。
当時の書類の取り扱いの違い
昭和の終わりから平成初期にかけて、法務局の記録は紙から電子へ移行する過渡期だった。 その過程で一部記録が失われている可能性もあるが、それでも今回の証拠にはならない。 「残念ですが、これは正式な手続きには使えません」と僕は言った。
依頼人の目的と告白
「父が遺した土地を、兄に取られるのが嫌だった」 そんな私情で偽造まで試みたことを、依頼人は静かに語った。 誰よりも信じたかった父の名誉を、自ら貶めたことにようやく気づいたのだ。
偽造の動機とその代償
司法書士として、僕は警察への報告を提案せざるを得なかった。 「あなたのためにも、嘘の登記は許されません」 依頼人はうなだれながら、静かに事務所を後にした。
結末と司法書士の務め
登記の申請は却下され、土地の名義はそのままとなった。 僕は改めて、登記とは「事実を記録する」だけであって、「真実を証明する」ものではないと痛感した。 そして今日もまた、次の依頼人が玄関のドアを開ける音がした。
「証拠がなければ、登記は変わらない」
僕はため息をひとつついて、机の上を片付けた。 傍らではサトウさんが、無言でコーヒーを入れてくれていた。 そしてまた、ありふれた一日が始まるのだった。