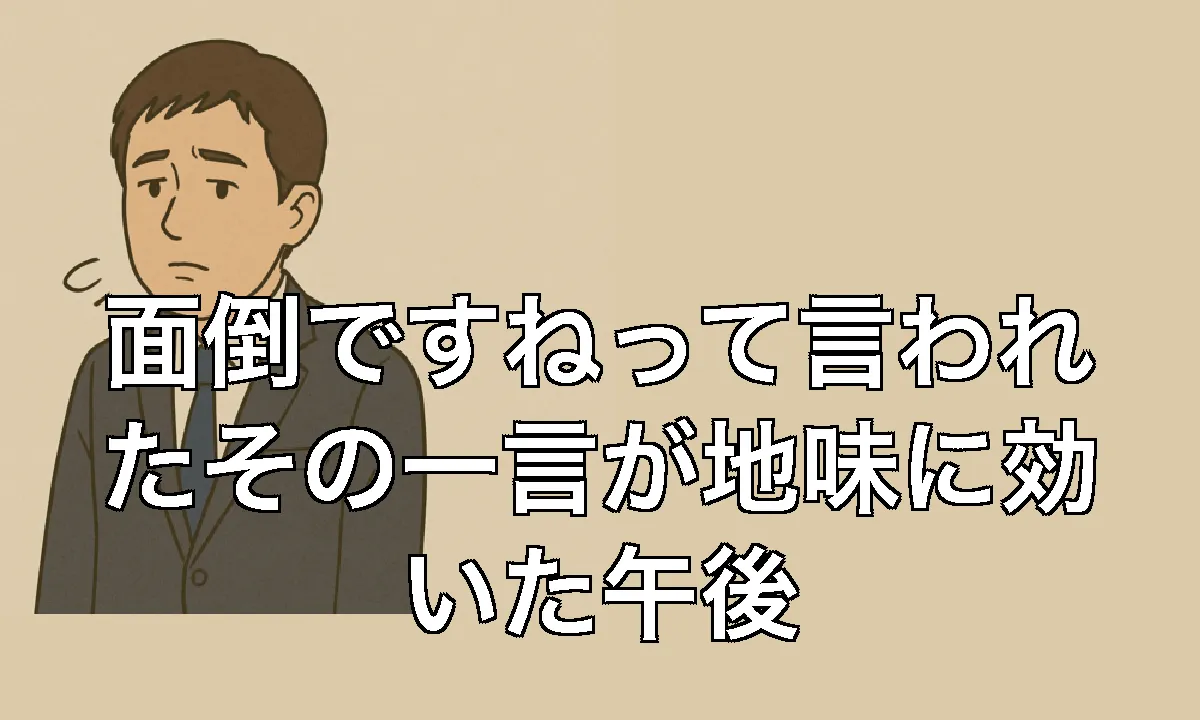あの日の午後に言われた一言がずっと残っている
「面倒ですね」——その一言を言われたのは、平日の午後三時過ぎ。銀行との書類のやりとりを終えた後、依頼者の方に説明をしていたときのことだった。決して怒鳴られたわけでも、無礼な態度を取られたわけでもない。でも、あの柔らかい語調に包まれた「面倒ですね」という一言が、なんとも言えず心に刺さった。自分のやっている仕事の意味を、ふと見失いかけた瞬間だった。
言葉は刃物より切れるときがある
仕事柄、理詰めで物事を進めるのは慣れているつもりだが、人の言葉というのは理屈では測れないものがある。たとえば「難しそうですね」と言われれば説明のしがいがあるけれど、「面倒ですね」と言われると、なんだか全てを否定されたような感覚になる。たぶん、本人は悪気なく口にしている。でもこちらとしては、時間と手間をかけて準備してきた背景があるわけで、そんな積み重ねが一瞬で軽く見られた気がしてしまう。
面倒という言葉が意味する温度差
「面倒ですね」と言う側と、「面倒を引き受けている」こちら側との間には、見えない温度差がある。私たちは依頼者のために何時間も、時には何日もかけて資料を調査し、整えている。しかしそれが伝わることは滅多にない。おそらく彼らには「自分でやるよりはマシ」といった程度の認識だろう。だが、その感覚のズレこそが、地味に効いてくるのだ。
感情を表に出せない職業ゆえの消耗
司法書士という職業は、感情を表に出さないのが暗黙のルールのようなところがある。どれだけ腹が立っても、どれだけ傷ついても、笑顔で説明しなければならない。でも、人間だから限界はある。「面倒ですね」と言われて、心の中で「ああ、またか」と呟く。何度も同じ言葉を飲み込んで、消耗していく。この静かな疲れが、あとからじわじわとくるのだ。
なぜ司法書士の仕事は「面倒」と思われやすいのか
登記や書類手続きというのは、そもそも一般の人にとっては馴染みのないものだ。さらに言えば、目に見えて「結果」がわかりにくい。契約が成立しても、家を買っても、「司法書士が何をしたか」はあまり意識されないことが多い。だからこそ、ちょっとでも手間がかかると「なんでそんなにややこしいの?」と感じられてしまうのだと思う。
説明しても伝わらない苦しさ
「それって必要なんですか?」という問いかけに、丁寧に答えるのは仕事の一部だ。でも、説明しても伝わらないときほどつらいことはない。たとえば、登記識別情報の扱いや、委任状の意味について話しても、「そんなの初めて聞いた」と言われると、ちょっと虚しくなる。制度や法律のせいではあるけれど、結果的に“面倒なことを言う人”になってしまう。
プロセスは見えないが責任は重い
私たちが担っているのは、見えない部分の整備だ。書類の整合性や法的リスクを潰しておくというのは、トラブルが起きないための「保険」のようなもの。でも、それが「やってもやらなくても結果が変わらないように見える」こともあり、そこが評価されにくい。責任だけは重くて、しかも感謝されにくいという構造には、時折、もどかしさを感じてしまう。
やること多すぎと呟かれる度に思うこと
「司法書士って思ったよりやること多いですね」と言われることがある。一見、褒め言葉のようだけど、裏返すと「思ったより面倒」という意味が込められていることもある。そう思われないように工夫はしているつもりだ。でも、それでもどこかで“めんどくさい人”に見られてしまうことがある。それが、なにより地味に堪える。
忙しさに慣れても慣れないのは人の反応
一日のスケジュールがパンパンでも、業務自体にはある程度慣れてくる。でも、何年経っても慣れないのは、人の反応だ。「ふーん」とか「そんなことでいいんですか?」という一言が、なんでこんなに刺さるのか。たぶん、自分のやっていることにもっと価値を感じていたい、そう思っているからこそなのだろう。
言葉の壁よりも心の壁がつらい
事務的な説明が通じないことには、もう慣れた。だけど、感情的に距離を置かれると、やっぱりつらい。「この人、なんか堅苦しいな」と思われていると感じた瞬間、言葉より先にこちらの気持ちが折れそうになる。専門職としての信頼と、ひとりの人間としての心の距離。このバランスが、本当に難しい。
言い返せない自分がまた嫌になる
昔なら「いや、そういうものなんです」と強めに言えたかもしれない。でも今は、相手の表情を見て「やめとこう」と自分を引っ込めることが増えた。場を荒立てたくない。でも、それが積み重なると、どこかで自己否定にもつながってくる。言い返せないことで、「自分は本当にこれでいいのか」と自問する夜もある。
元野球部だった頃の根性はどこへ
高校時代、炎天下でバットを振っていたあの頃は、根性だけで何とかなると思っていた。今はどうか。体力よりも気力が削られる毎日で、踏ん張りどころが見えにくい。気がつけば、「今日はもう帰ってもいいかな」と弱音を吐く自分がいる。あの頃の自分が見たら、がっかりするかもしれない。
それでもやっぱりこの仕事を続ける理由
じゃあ、辞めるか?と聞かれたら、それはまた違う。どんなに面倒がられても、やっぱり誰かの役に立っている瞬間がある。それは、依頼者の「助かりました」の一言だったり、事務員さんの「お疲れさまでした」の声だったり、ほんの小さなことだけれど、それが続ける理由になっている。
地味でも誰かの支えにはなっている
「先生がいてくれてよかったです」——そんな言葉をもらえることが、年に数回ある。そのたびに、報われたような気持ちになる。派手さはない。でも、地味に誰かの生活を支えている。そう信じられる限りは、もう少しだけこの仕事を続けていこうと思える。
事務員さんの一言に救われることもある
うちの事務員さんは、そんなに口数が多い方ではないけれど、たまにポツリと「大変でしたね」と言ってくれる。その一言がどれだけ救いになるか、言葉では言い表せない。誰にも見られていないところでの努力が、ちゃんと見られている気がして、涙が出そうになることもある。
一人でも味方がいればまだいける
たった一人でも、自分の味方がいてくれたら、人はなんとかやっていける。仕事の意味を問い続けながら、それでもやるしかない日々のなかで、そう思える瞬間がある限り、まだ自分はやれる。今日もまた、「面倒ですね」と言われるかもしれない。でもそのときは、心の中で静かにこう呟く。「はい、そうですね。でも、やりますよ」と。