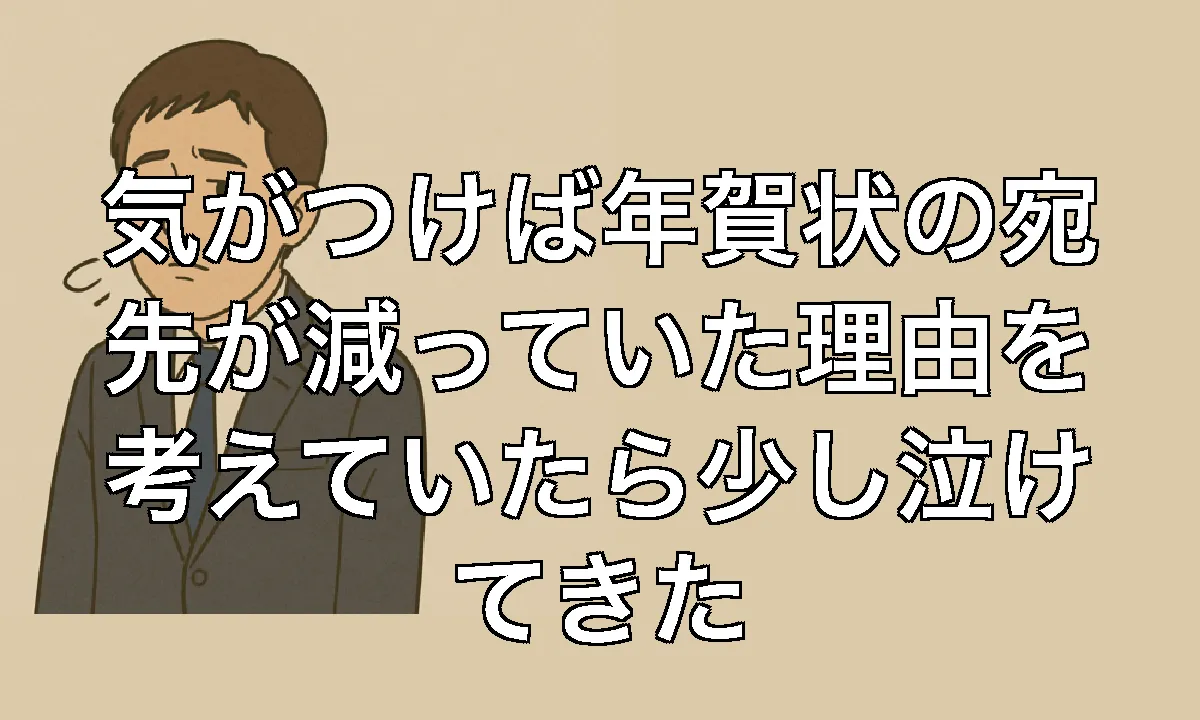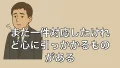気がつけば年賀状の宛先が減っていた理由を考えていたら少し泣けてきた
昔はもっと多かったはずの宛名リスト
年末になると恒例の作業がある。パソコンに保存してある年賀状ソフトを開いて、昨年のデータを読み込み、住所録を整理して、印刷の準備をする。でも今年は、なんだか様子が違った。送る相手の数が、明らかに少ない。いつの間に、こんなに減っていたんだろう。思い返せば、学生時代の友人や元同僚、取引先の担当者、そして昔お世話になった先輩。みんな、自然とやりとりがなくなっていた。年賀状って、つながりを表す小さな証だったはずなのに。
正月前の恒例作業がふと寂しくなる瞬間
年賀状の宛名面を印刷しているとき、ふと手が止まった。10年前の名簿を開いて比べてみたら、送る人が3分の2くらいに減っていることに気づく。最初は「まあ、時代の流れかな」と思ったけど、じわじわと寂しさがこみ上げてきた。付き合いがなくなったのは、向こうの事情かもしれないし、こちらの態度だったのかもしれない。どちらにせよ、「もう出さなくていいかな」と思われてしまったという事実だけが、妙に重くのしかかる。
住所録の整理で見えてくる人間関係の変化
中には、引っ越しで住所がわからなくなった人もいるし、喪中の知らせが来て、それきりになってしまった人もいる。仕事の関係だけでつながっていた人たちは、退職や転職のタイミングで自然と縁が切れていった。こちらから連絡するきっかけもなければ、向こうからも特に反応はない。そんな関係がたくさんあるのが現実だった。年賀状って、実はその人との関係を再確認するための小さな儀式だったのかもしれない。
喪中ハガキよりも無言の消滅がこたえる
喪中ハガキが来れば、「ああ、あの人のご家族に何かあったんだな」と理由がわかる。でも、一番こたえるのは、何の連絡もなく、ただ年賀状のやりとりが終わってしまうケースだ。返事が来ない年が2年続いたら、こちらも出すのをやめる。だけど、その沈黙がなんとも言えない。あの人、元気なんだろうか。今もどこかで働いているんだろうか。確認する術もなく、ただ「もう届かなくていい相手になってしまった」ことだけが残る。
年賀状文化が薄れてきたことへの複雑な気持ち
世の中の流れとして年賀状離れが進んでいるのはわかっている。若い世代はLINEやSNSで済ませるし、年賀状そのものが面倒くさいという声も多い。でも、手書きのひと言や、久しぶりの近況報告には、デジタルでは代えられない温かさがある。それを大事にしてきた自分としては、ちょっと取り残された気分になる。
効率化の中で消えていくものの重み
司法書士という仕事柄、効率を重視する場面は多い。登記業務にしても、スケジュール管理にしても、無駄を省くことが基本だ。でも、年賀状のような非効率なやりとりこそ、実は人間関係の潤滑油だったのかもしれない。効率化によって得たものと引き換えに、気づかないうちに大事な何かを失っていたのかもしれないと、最近しみじみ思う。
LINEやSNSでは埋まらない距離感
たしかに、今はスマホひとつで何でもできる。あっという間にメッセージを送れるし、既読もすぐにわかる。でも、それが便利かというと、必ずしもそうではない。既読スルーに傷ついたり、送るタイミングを気にしたり。逆に、年賀状は返事がなくても「まあ忙しいんだろう」で済んだ。そういう、ちょうどいい曖昧さが、関係をつなぎ止めていたのかもしれない。
つながりを維持することの難しさ
人との関係って、意識していないとすぐに薄れていく。司法書士という仕事は、基本的に「頼まれたら応える」スタンスなので、こちらから積極的に関係を作ることが少ない。そのせいか、プライベートでも受け身になってしまいがちだ。結果、気がつけば関係が消えていたということになる。
仕事が忙しいを言い訳にしたくないけど
実際、忙しいのは事実だ。書類も多いし、依頼者との打ち合わせもあるし、事務員さんにも気を遣う。だけど、「忙しいから仕方ない」と言ってしまったら、それで終わりな気がする。人との関係をつなぎ止める努力をしないのは、自分がその関係を手放しているということでもある。そのことに、もっと早く気づけばよかった。
こちらから切ることはほとんどない
正直、自分から関係を切ったことはほとんどない。連絡をやめた理由もなく、ただ相手から来なくなって終わる。こっちは待ってるだけ。でも、それって本当に関係を続けたいって態度なのか?と問われると、黙るしかない。受け身でいることが、関係を終わらせているんだとしたら、やっぱりどこかで動かなきゃいけない。
でも向こうからも来ない現実
とはいえ、こちらが年賀状を出しても、返事が来ない年が続くとやっぱりへこむ。「もういいか」と思って出すのをやめたら、それっきりになる。向こうもきっと、「ああ、切れたな」と思っているのかもしれない。その沈黙が寂しい。でも、それが今の自分の人間関係のリアルなのだと思う。
司法書士という職業の孤独
この仕事、感謝されることはあっても、深く関係を築くことは少ない。登記が終わったらそれで終わり、次に会うのは何年後か、あるいはもう二度と会わないかもしれない。だからこそ、自分で人とのつながりを意識して保っていく必要があるのに、それができていない。そこが悩ましい。
相談相手ではあるけど友達じゃない
依頼者はたくさんいる。でも、あくまで仕事の関係。フランクに話すことはあっても、友達にはなれない。距離感が必要な職業だというのは理解しているけれど、それが積もると、やっぱり孤独になる。「あなたに相談してよかった」と言われても、その言葉の後に続く関係はない。
感謝されても親しくなれない不思議な距離
登記が完了したとき、あるお客さんに「本当に助かりました」と頭を下げられたことがある。嬉しかった。でも、それで終わりだった。連絡は次の案件があるまで来ない。感謝と親しさは別物だというのを、この仕事をしていて何度も感じる。そのたびに、「自分が求めているのは、ありがとうの後の一言なんだ」と思う。
年賀状の宛先が減ったことで気づいたこと
年賀状の枚数が減ったことは、ただの数の問題じゃない。自分の生活の中で、どれだけ人と関われていたかを映す鏡だった気がする。無理に関係を続ける必要はないけれど、大切にしたい人との縁は、自分からも手を伸ばさなければいけない。そうしなければ、気がつけば独りになってしまう。
本当に残したい関係って何だろう
これからの年賀状は、ただの挨拶状じゃなくて、自分の気持ちを込めた一通にしていきたい。数じゃなくて質。義務じゃなくて意思。「今年もよろしく」と書きながら、「また会いたいね」と思える人に出したい。そう思える相手がどれだけいるか、それがこれからの自分にとって大事なことかもしれない。
増えることより減らさないことの大切さ
年賀状の宛先が増えることは、もしかしたらもうあまりないかもしれない。でも、今あるつながりを減らさないことはできるはずだ。そのためには、仕事ばかりしていないで、たまには自分から連絡を取ってみることだって必要だ。それが不器用でも、ぎこちなくても、つながりを大切にする一歩になる。年賀状の空白が、それを教えてくれた。