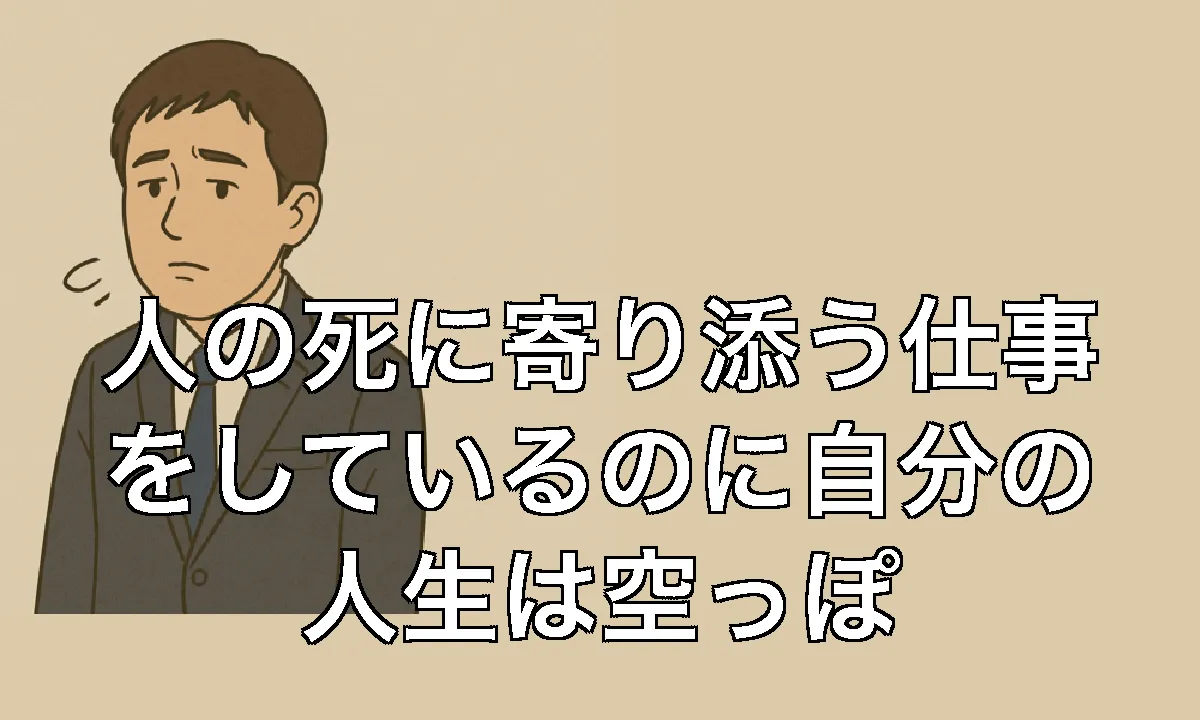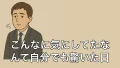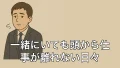死に寄り添う仕事をしているという矛盾
司法書士という職業は、時に人の死に向き合う仕事でもある。遺言、相続、死亡届、登記の抹消——誰かが亡くなった後の手続きを淡々と進めるのが役目だ。形式的な書類のやり取りの裏には、それぞれの人生の終わりがある。けれど、そんな仕事を繰り返していると、ふとした瞬間に思う。「自分の人生は一体どうなっているんだろう」と。死に関わる仕事に真面目に取り組むほど、自分自身の生活の“空っぽさ”が浮き彫りになる。
他人の人生の終わりには敏感なのに
ある日、長年連れ添った夫を亡くしたという女性の依頼で、遺産分割協議書を作成することになった。書類の説明をしていると、その女性は泣きながら「もうこの家に一人で住む意味もなくて」と言った。私はそのとき、黙ってうなずくことしかできなかった。感情を共有しようにも、どこか心が麻痺してしまっている。何件もの相続手続きをこなしてきたからか、他人の死に対して過敏に反応しすぎないよう、防御本能が働いているのかもしれない。
静かな最期に立ち会うことの意味
独身で一人暮らしだった高齢の依頼者が亡くなったと、後日親族から連絡があった。その方は「死んだときに迷惑がかからないように」と、私のところで生前に手続きを済ませていた。人知れず終わっていった人生の最後に、ほんの少しでも関われたことに意義があると思いたい。でも同時に、自分の最期はどうなるのか、誰かが気づいてくれるのか、という不安もついてくる。
感情を押し殺す日常の繰り返し
依頼者に寄り添おうとするたびに、どうしても感情が邪魔になる。だから自然と「事務的に処理する」ことに慣れていった。感情を出せば出すほど、自分が壊れてしまう気がするのだ。自分自身のことは置き去りにして、他人の“終わり”に向き合い続ける日々。そうして心が空っぽになっていく。
自分自身の人生には鈍感になっていく
日々の忙しさにかまけて、自分のことを考える余裕がなくなっている。食事はコンビニ、夜は遅く、朝も早い。休日は寝て終わる。それでも「仕事があるだけマシ」と自分に言い聞かせる。だけど、時折ふと時計を見て、人生の針が進んでいないように感じる瞬間がある。
気づけば何年も一人きりの生活
事務所にいる時間が一番長い。帰宅しても誰かが待っているわけでもなく、テレビをつけても会話はない。元野球部で、昔は仲間とわいわいやっていたのに、今ではその面影すらない。あの頃、バットを握って汗だくになっていた自分に「将来は一人で遺産分割協議書を書いてるよ」なんて言っても、信じないだろう。
誰のために生きているのかわからない
「先生がいてくれて助かりました」と感謝されることもある。それが救いになることもある。でもそれは、誰かの人生の“後始末”をしたことで得られた感謝であって、自分の人生のためではない。仕事に意味を見出す一方で、自分の生き方には意味があるのかと問い続けてしまう。
司法書士という職業の重さ
外から見れば、司法書士は安定した職業で、社会的な信用もあると言われる。けれど、その裏側には、緊張感とプレッシャー、そして孤独が隠れている。人の大切な節目に関わる仕事だからこそ、失敗は許されない。日々、誰にも見えないプレッシャーを背負いながら働いている。
社会的には立派な仕事なのに
初対面で職業を聞かれると「司法書士です」と答える。するとたいてい、「すごいですね」「頭良さそう」と返ってくる。でもその言葉に、どこか居心地の悪さを感じてしまう。実際は、地味で細かくて、クレームや突発的なトラブルにも日々対応しなければならない仕事。そんな苦労は、なかなか伝わらない。
求められるのは完璧な手続きと冷静さ
たとえば登記一つミスすれば、依頼者にとっては大問題だ。だからこそ神経をすり減らす。時に深夜まで確認作業に追われることもある。熱があっても、心が沈んでいても、手続きを誤るわけにはいかない。「感情を持つ人間でありながら、機械のようにミスなく働くこと」を求められているようで、苦しくなる。
ありがとうより先にくるクレームの恐怖
電話が鳴るたびに、クレームじゃないかと身構えるクセがついている。「登記の処理が遅い」「説明がわかりにくい」……感情をぶつけられることもある。もちろんすべてを受け止めるのが仕事だ。でも、心は少しずつ摩耗していく。ありがとうの言葉より、怒声の記憶の方が色濃く残ってしまうのが悲しい。
心の消耗に気づけないまま走る
忙しさは、時に麻酔のような役割を果たす。仕事に没頭しているときだけは、余計なことを考えずに済む。けれど、そうやって無理を重ねるうちに、心の疲れには鈍感になっていく。誰かに「大丈夫ですか?」と聞かれても、「大丈夫です」としか答えられない。自分で自分の限界に気づけなくなっている。
忙しいことは良いことなのか
「暇よりはマシだよな」「依頼があるだけありがたい」そう自分に言い聞かせている。でも、本当は「暇=自由」だったはずだ。時間があるなら、誰かと話したり、趣味に没頭したり、少し遠出したり……できたかもしれない。忙しさに埋もれることで、自分の人生を見ないようにしていただけなのかもしれない。
事務員の一言が救いになる日もある
うちの事務員さんが「先生、ちゃんとご飯食べましたか?」と聞いてくれる日がある。その一言だけで、ちょっと泣きそうになるときがある。誰かが気にかけてくれる、それだけで救われることもある。職場に一人でも、こういう存在がいてくれてよかったと心から思う。
それでも続ける理由はどこにあるのか
ここまで書いておいてなんだけど、それでも明日も事務所を開ける。辞めようと思ったことは何度もあるけど、そのたびに「今やめたら誰が困るだろうか」と考えてしまう。自己犠牲と言われればそれまでだけど、それでも今の仕事に、何かしらの価値を感じているのかもしれない。
誰かの役に立っているという感覚
相続で揉めていた兄妹が、最終的に「先生がいてくれてよかった」と笑顔で帰ったとき、胸の奥にあたたかいものが残った。「司法書士がいてよかった」と思ってもらえる瞬間が、続ける理由になることもある。日々の苦しさの中に、そうした小さな報酬があるからこそ、今も続けている。
悲しみの場で頼られるという責任
誰かが亡くなったとき、多くの人は何をどうしていいかわからない。そんな中で、私が「この順番でこう進めましょう」と言うと、安心したような表情になる。そのとき感じる「頼られている」という感覚は、重いけれど、誇らしくもある。自分の存在が、誰かの混乱を少しでも和らげるなら、それだけで意味がある。
役所の窓口よりも近くに寄り添える
私たちは、ただの事務屋ではない。役所では対応しきれない部分、人の気持ちに寄り添いながら、物事を前に進めていく存在だと思っている。無機質な手続きの中に、人間味を取り戻すことができるのが、この仕事のやりがいでもある。
司法書士という道を選んだ自分への問い直し
この道を選んでよかったのか、後悔はないのか。そう自問自答することもある。正直なところ、わからない。でも、誰かの人生の一部に関われるこの仕事を、誇りに思いたい自分もいる。
他に何ができるのかはわからない
もし今、司法書士を辞めたとして、自分には何ができるのか。それを考えても、答えは出ない。だからといって、ただ惰性で続けているわけでもない。きっと、この仕事が好きなんだと思う。苦しくても、続けたいと思う何かが、ここにはある。
それでも明日も事務所を開ける
今日もまた、電話が鳴る。新しい依頼か、クレームか。それは出てみなければわからない。でも、それでも私は電話に出る。机に向かう。書類を整える。何度目かの「もう限界かもな」と思いながらも、明日も事務所を開ける。それが今の私の、精一杯の“生きている証”だ。