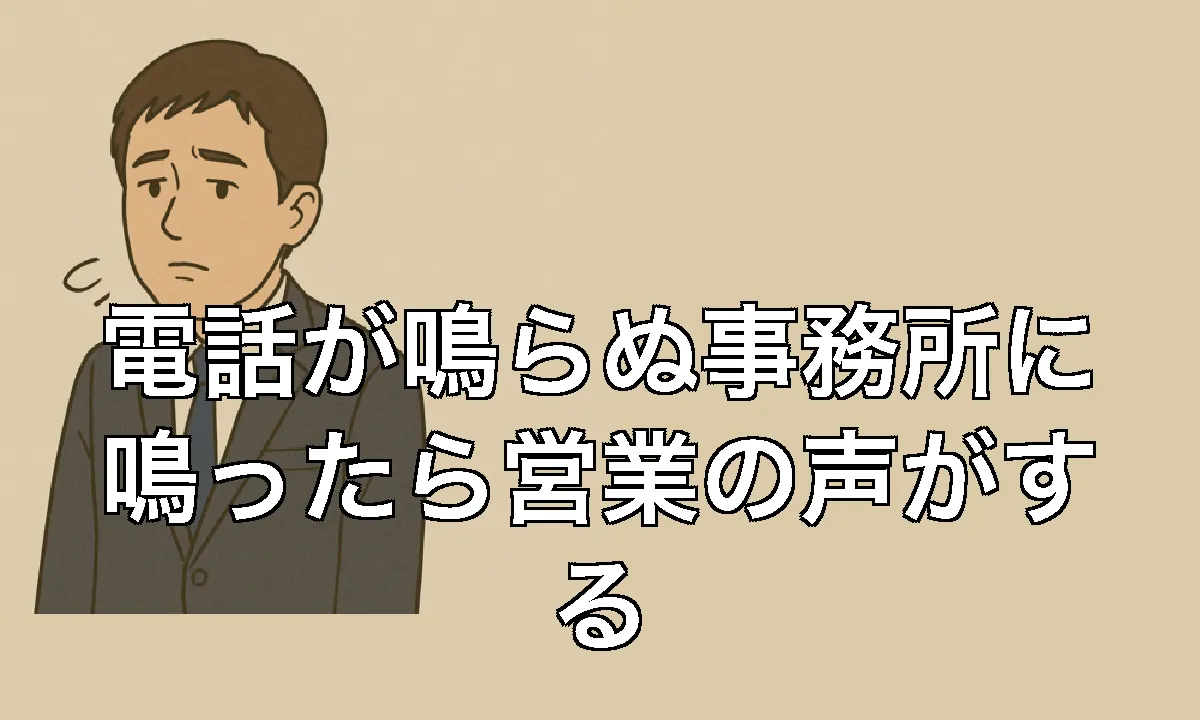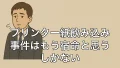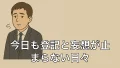静まり返る電話機に今日も耳を澄ます
朝、事務所のシャッターを開けると、静けさが肌にまとわりつくような感覚になる。パソコンの電源を入れて、コーヒーを淹れながら一日の始まりを迎えるが、電話のベルが鳴る気配はない。昔は朝から何本か問い合わせの電話があったものだが、最近は鳴らないことが多くなった。鳴らない電話機を横目に、ため息をつきながら書類に目を通す。仕事があることはありがたい。でも「外からの音」がないと、なぜか社会とのつながりが切れていくような気がして、じわじわと孤独が滲んでくる。
午前中の無音がやけに心に響く
午前中、事務員さんと交わす会話もなんだか少なくて、時折お互いのキーボードの音だけが室内に響く。静かなのは悪いことじゃないはずなのに、妙に胸がザワつく。特に午前10時から11時のあたりは「何かしら連絡が来そうな時間帯」なので、余計に音に敏感になる。だが、そんな期待をよそに、今日も沈黙が続く。受話器の横に置いたスマホの通知すら鳴らない。心のどこかで「誰かに必要とされたい」という気持ちが空回りしているのかもしれない。
昔はもっと鳴っていた気がするけれど
独立して間もない頃は、開業の挨拶回りをしたこともあってか、問い合わせもそれなりにあった。「友達の紹介で」と言ってくれる人もいた。何より、あの頃は電話が鳴ると嬉しくて、事務所に活気があった。だが、時の流れとともに、取引先も変わり、知人からの紹介も減ってきた。今思えば、あの頃の鳴り響く電話の音は、希望の音でもあったのだ。
通知音が鳴るたびに期待してしまう
スマホのLINE通知やGmailの着信音が鳴ると、つい画面を見てしまうのが習慣になってしまった。期待して開いてみると、大抵はAmazonの発送連絡だったり、ネット広告だったり。メールすら人間味がなくなってきているような気がして、余計に寂しくなる。人とのやり取りは便利になったのに、どこか「生きた交流」が減ったように思えてならない。
電話応対のドキドキがまさかの営業
たまに電話が鳴ると、「おっ、問い合わせか?」と身構える。受話器を取る手にも微かに力が入る。名前を名乗ると、相手は「すみません、営業のお電話なんですが…」と来る。正直、肩の力が抜ける瞬間だ。問い合わせじゃないのか、とがっかりする気持ちと、でも誰かが話しかけてくれたという妙な安心感が同居する。不思議な感覚だ。
「お忙しいところすみません」が心に刺さる
営業電話の定番フレーズ「お忙しいところすみません」に、つい笑ってしまう。「いや、そんなに忙しくはないですけど…」と心の中で突っ込む。最近はAI音声による営業も増えてきて、生身の人間との会話すらないこともある。そんなときは、寂しさの上にむなしさが重なる。情報社会のはずが、人との関係はますます希薄になっているのかもしれない。
営業でも誰かと話せるのが妙に嬉しい
とはいえ、たとえ営業でも「人間」が話してくれると、少しホッとする。ついでにこちらから質問したり、世間話を仕掛けたりすることもある。営業の方も意外と話し好きで、ちょっとした雑談で笑えるときもある。用件が終わったあとに「ありがとうございました」と言われると、自分も誰かに応えられた気がして、少し心が軽くなる。
なぜこんなに電話が減ったのか考えてみた
電話が鳴らないことに慣れてしまった今、ふと「なぜこうなったのか」と考える時間が増えた。自分が悪いのか、時代の流れなのか。答えは一つではないけれど、少なくとも“昔と同じやり方”ではもう通用しないのだと、ひしひしと感じている。孤立感だけが強調されるこの状況を、どう受け止めていけばいいのか悩ましい。
メール時代の落とし穴
最近の若いお客様は、ほとんどがメールやLINEで連絡を取ってくる。こちらも効率を考えて、メールでのやり取りを推奨してはいるけれど、メールでは「気配」が伝わってこない。冷たい文章だけがやり取りされて、「この人は困っているのか、急いでいるのか」といった人間味が読み取れないことが多い。そんな中、電話で直接話すことの意味を改めて考えてしまう。
メールは届いても返事は来ない
たまにあるのが、「メールしましたが返事がありません」とクレームを受けるケース。確認すると、確かにこちらから返信しているのだが、迷惑メールに入っていたり、読まれていなかったりする。電話なら一発で済むことも、メールでは宙に浮いたままになる。便利さの代わりに、確実性が薄れてきているようにも思える。
FAXすら来ないときの寂しさ
昔は午前中に1、2通はFAXが流れてきたものだった。謄本請求や簡単な依頼書など、紙でのやり取りが多かった時代の名残だろう。今ではそのFAXもほぼ来ない。受信トレイは白紙のまま。機械は元気に動いているのに、誰も呼んでくれない…そんな哀愁すら感じる日がある。
そもそも必要とされていないのではという妄想
電話もFAXも鳴らないと、「自分はもう必要とされていないのでは」と思い込んでしまうことがある。そんなときは、妙に掃除を始めたり、昔の書類を見返したりして時間を潰す。でも、心のどこかで「何かが変わってしまった」ことを実感しているのかもしれない。
同業者のSNSを見ると焦りが増す
SNSを開くと、同業者が「今日は3件の相談がありました」「新しい顧客が増えました」と報告しているのを目にする。素直にすごいなと思う反面、自分はどうしてこんなに静かなのかと焦ってしまう。自分にもかつてはそんな時期があったはずなのに、今はまるで別世界の話のように思えてしまう。
ひとり反省会が日課になる
誰とも話さず一日が終わる日、つい事務所を出る前に、今日の行動を反省してしまう。「もっと動けばよかった」「電話がないからって気を抜きすぎたか」といった自己嫌悪が頭をよぎる。そんな日が続くと、仕事の成果よりも「孤独との戦い」の方が重たくのしかかってくる。
それでも受話器を取る理由
それでも、私は毎朝、電話機の受話器のそばに座る。鳴るかどうかはわからない。でも、誰かが困っていて、私の助けを必要としてくれているかもしれないという希望だけは手放したくない。だからこそ、今日も電話が鳴るのを待ち続けている。
誰かの困りごとに応えたい気持ち
司法書士という仕事は、誰かの人生の節目や困難に関わることが多い。たとえば相続の手続きや、会社設立、離婚の登記など、それぞれに事情がある。たった一件の電話でも、その裏には大きな悩みや期待が込められている。だからこそ、どんな電話でも丁寧に応対するよう心がけている。
営業だとしても情報収集にはなる
営業電話といっても、意外と有益な情報が得られることもある。最近流行っているサービスや、他事務所の導入状況など、世の中の動きを感じ取る手がかりになることもある。断るにしても、話を一度は聞いてみることで、自分の視野が広がることがある。
事務員さんとの話題になるだけでもありがたい
事務員さんも電話の着信があると少しソワソワする。営業だったとわかると、二人でちょっとした冗談を交わすこともある。そうした小さな会話が、事務所の空気をやわらげてくれる。孤独な仕事だからこそ、そういうやり取りが意外と大事だったりする。
鳴らない電話が教えてくれること
結局、電話が鳴る鳴らないは、単なる現象にすぎないのかもしれない。だが、それに一喜一憂してしまうのが人間というものだ。私は今日もまた電話の音に耳を澄ます。鳴るその一瞬のために、誰かの人生に関われる一歩を待っている。
孤独もまた仕事の一部
孤独を感じることは悪いことではないと最近ようやく思えるようになってきた。誰とも話さない日があっても、それはそれで自分の時間を持てる貴重な時間でもある。そう自分に言い聞かせながら、また明日の準備をしていく。
次こそはと期待してしまう自分がいる
電話のベルが鳴るたびに、「今度こそ相談かも」と胸が高鳴る。その期待が裏切られることも多いが、それでもやっぱり待ってしまう。司法書士として、人として、誰かの力になりたいという気持ちが、そうさせるのだと思う。