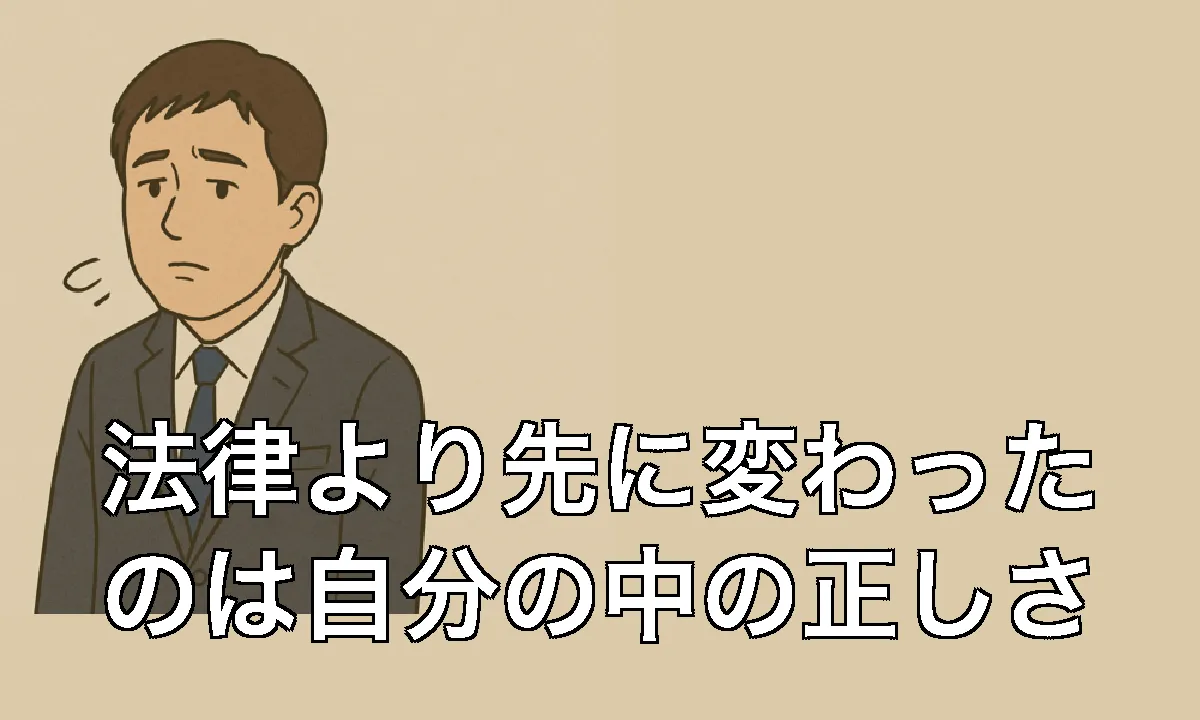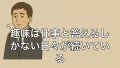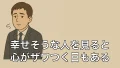価値観が先に変わってしまった瞬間
最近、仕事をしていてふと感じたことがある。「あれ、昔ならこんなことでモヤモヤしなかったのに」と。司法書士として業務に携わって20年以上。法律の条文はほとんど変わっていないのに、自分の感じ方がじわじわと変わってきた。昔は効率よく処理できればそれで満足していたのに、今は「それで本当に依頼者のためになっているのか」と自問する時間が増えた。法改正よりも、自分の内側が先に変わってしまったのだ。
昔なら違和感なくこなしていた業務
たとえば、相続登記の依頼が来たとき。昔の私は「必要な書類を集めて、手続きさえ終わればOK」という思考だった。期限内に片付けることが最優先で、細かな心情までは気に留めなかった。だが今は、相続人の表情や話し方が気になってしまう。「この人、本当に納得してるのか?」「誰かに無理させられてないか?」と、つい余計なことを考えてしまう。
登記の手続き一つ取っても気になるポイントが変わった
以前は登記簿の表記を見て「正しいかどうか」だけを気にしていた。ところが今は、「この登記がこの人にとってどういう意味を持つのか」が気になる。とくに相続の場合、単なる名義変更ではなく、故人との関係性や遺族の気持ちが絡んでくる。法律的にはスムーズでも、感情的には割り切れないことも多い。私の中で、法律の条文よりも「人の気持ち」が優先されるようになってきている。
依頼者との距離感が悩ましくなってきた
昔はビジネスライクに、淡々と話を進めていた。だが最近は、つい相手に寄り添おうとしてしまい、自分でも距離感を見失うことがある。必要以上に踏み込んでしまったり、逆に遠慮しすぎて何も言えなかったり。「司法書士」としての自分と、「ひとりの人間」としての自分。そのバランスがうまく取れなくなってきたのかもしれない。法律のプロであることと、人間としての感情。その間で揺れている。
自分の感情にブレーキが利かなくなってきた
歳を取ったせいか、感情の起伏が激しくなったように感じる。若い頃は割り切れていた場面でも、今は心がざわつく。依頼者の一言が妙に引っかかったり、自分の対応が適切だったか夜中に考え込んだりする。法改正があっても、それだけではどうにもならない部分があるのだ。自分の心の変化に、仕事のやり方も巻き込まれているような気がしてならない。
法律上正しいことがいつも気持ちいいとは限らない
例えば、相続放棄の手続き。形式的にはシンプルで、期限内に申述書を提出すればいい。でも、依頼者の「本当は兄の借金を放棄したくなかったんです」という言葉を聞いてしまうと、心がざわつく。法的には正しい判断でも、心情的には葛藤を抱えている人が多い。それを見過ごせない自分に気づくたび、私は司法書士という職業の意味を考え直している。
共感しすぎると苦しくなるというジレンマ
依頼者の気持ちに共感しすぎて、自分の中で引きずってしまうことがある。夜中にふと思い出して眠れなくなったり、夢にまで出てきたりする。昔はそんなことなかった。冷静に距離を取れていたのに、今はそれができない。優しさなのか、老化なのか、正直わからない。でも、共感が仕事の邪魔になることがあるというのは、間違いない事実だ。
法改正があっても「変われない人」は多い
法律が変わっても、人の行動がすぐ変わるわけではない。「押印不要になりました」と言っても、未だに三文判を握りしめてくるお年寄りがいる。それを見ると、「人は制度だけでは動かない」と実感する。むしろ、私のように価値観のほうが先に変わってしまった方が、やりづらさを感じることもある。
制度の変更だけでは人は動かない
登記の電子化や押印廃止、様々な法改正がなされても、現場では相変わらず紙の束が飛び交っている。手続きの説明をしても、「それって前と何が違うの?」と返されることが多い。つまり、制度が整っても、それを使いこなす側の意識が追いついていないのだ。実務は変わっていない。むしろ、混乱だけが増えている印象すらある。
結局は現場の人間の「解釈次第」
法改正があっても、それをどう現場で運用するかは、結局のところ「人」にかかっている。実際、私は新制度に対応した説明資料を作るのにかなりの時間を費やした。けれど、依頼者には響かない。形式よりも「この先生は信頼できそうか」という印象のほうが大事にされる。だからこそ、私は自分の価値観に正直でいたいと思うようになった。
実務が気持ちについてこないもどかしさ
「こうしたほうが親切だろうな」と思っても、実務上の制約でそれができない場面がある。依頼者の負担を減らしたいのに、法的には不要な書類を求めざるを得ないときもある。そういう矛盾が、今はつらい。法律が変わっても、現場の柔軟さがなければ、ただの理想論で終わってしまう。
変わったのは「世の中」より「自分の中」
法律が変わったことよりも、自分の中で何かが大きく動いたことのほうが、自分にとっては大きい出来事だった。きっかけは特にない。強いて言えば、年齢かもしれない。人の痛みに対して、以前より敏感になったのだと思う。それがいいことなのか、仕事に向いていないというサインなのか、まだわからない。
昔の自分だったら見落としていた感情
若い頃だったら「まあ、仕方ない」で済ませていた話に、今は立ち止まってしまう。たとえば、相続の場で兄弟の仲が悪いことが明らかになったとき。昔の私は「私には関係ない」と割り切っていた。でも今は、「この兄弟にとって、この登記はどんな意味を持つのだろう」と考えてしまう。気づく力が増えた一方で、割り切る力が減った。
優しさが仕事の邪魔になるときもある
依頼者に感情移入しすぎて、「それなら登記はやめておいたほうが…」と口にしそうになったことがある。でもそれは越権行為。私の役割は、法律に基づいて手続きを進めることだ。気持ちに寄り添いたい。でも、立場を守ることも大事。その狭間で揺れ動く毎日が、思った以上にしんどい。
変化は「悪いこと」なのか
価値観が変わったことは、果たしてネガティブなことなのか。自分にとっては不器用さが増したように思えるが、一方で人間味が出てきたとも言える。正解がないこの仕事において、悩むこと自体が成長なのかもしれない。最近はそう信じるようにしている。
適応力ではなく「自分軸」の話
周囲に合わせて変わるのではなく、自分の中での正しさを持ち続けることが、いまの私にとって大事なテーマだ。制度に適応するのは当然。でもそれだけでは足りない。自分の判断が「人の役に立っているか」を問い続けること。それが今の私の「自分軸」だ。
世の中に合わせることの限界
あまりにも世の中に合わせようとすると、自分の心がすり減っていく。依頼者の満足を得るために無理をしたり、見た目の丁寧さを演出することに疲れてしまう。そんなときこそ、自分の中の「正しさ」に立ち返ることが必要だ。人にどう見られるかではなく、自分が納得できるかどうか。
どこまでが自分でどこからが他人か
依頼者の感情に寄り添いつつ、線を引くのは難しい。どこまで共感して、どこからは引くのか。そのバランスは、今も迷いながら探っている。でも、それでいいのかもしれない。迷いながらでも、人に誠実に向き合うこと。それが司法書士としての誠実さだと、今は思える。
モヤモヤを抱えたままでも進むしかない
毎日が正解のない選択の連続だ。でも、モヤモヤを抱えながらも前に進むしかない。たとえ不器用でも、自分の中の変化を否定せず、受け入れながらやっていこうと思う。そうすることでしか、自分を保てないのだ。
正解を出すのではなく共に悩むことの意味
依頼者にとっての正解は何か。それを一緒に考え、悩むことが司法書士としての役割だと思うようになった。専門家だからといって、いつも明確な答えが出せるわけではない。だからこそ、「一緒に考えます」と言える関係性が大事なのだ。
疲れたときは立ち止まってもいい
無理をして走り続ける必要はない。疲れたら休めばいい。立ち止まって振り返ることで、また一歩進めることもある。変わってしまった自分を否定せず、受け入れる。そんな司法書士でいたいと思っている。