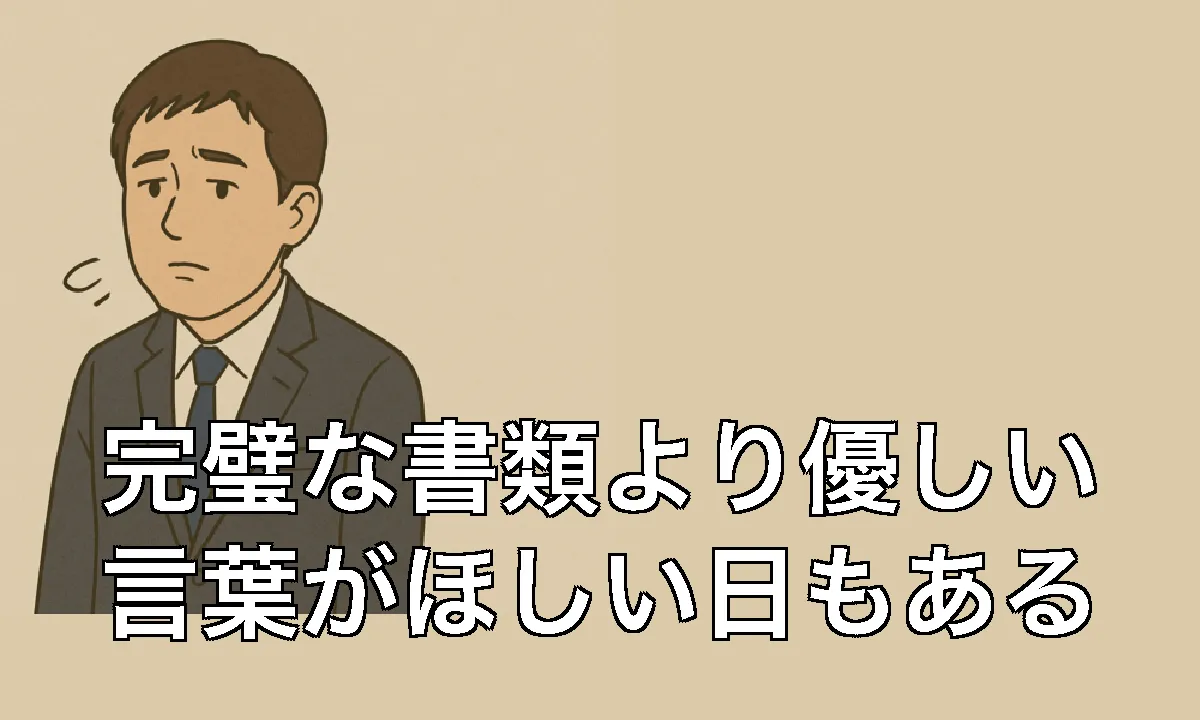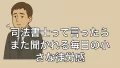完璧なはずの書類が心に引っかかった理由
完璧な書類を出したのに、なぜか相手の顔が曇る。それは、司法書士として十数年やってきた中でも何度か経験したことだ。内容に不備はなく、形式も整っている。それでも、無言の反応に「何か違う」と感じてしまう。おそらく書類の中に、人としての温度が欠けていたのだろう。書類だけでは伝わらない「配慮」や「共感」、そういうものを置き去りにしていた気がする。
形式上の正しさと人としてのやりとり
役所でのやりとりでは、正確さとスピードが求められる。それはわかっている。けれど、たとえば目の前にいる依頼人が、何かを言いたそうにしているとき、「ではこれで」とだけ言って済ませるのは、たぶん少し寂しいことなんだと思う。以前、ある依頼人に「この書類、すごくきれいですね」と言われたとき、心のどこかで嬉しい気持ちがあった。でもそのあと、「でも…やっぱり、相談したかったことがあったんです」とつぶやかれたとき、自分の態度に少し後悔した。
「これで大丈夫ですか?」と聞けなかったあの日
昔、とある登記案件で、書類だけ先に完成させて郵送したことがある。時間に追われていたし、手間も省けると思ったからだ。でも、あとから電話がきて、「これで本当に大丈夫なのか不安で…」と依頼人の声が震えていた。そのとき初めて、「完璧に整った書類」だけでは、人の不安は拭えないと気づいた。ほんの一言、「不明な点があればいつでもどうぞ」と添えていれば、違ったかもしれない。
訂正印が押されるたびに心が削れる
法務局に提出した書類に、訂正印がいくつも並ぶことがある。もちろん自分のミスではない。依頼人が出した戸籍や証明書類に不備がある場合だ。でも、訂正印を押すたび、どこか虚しい気持ちになる。「これが仕事」と割り切っているつもりでも、そこに「お手数をおかけして」と一言あれば、気持ちのやりとりは少し和らぐのに。逆に、ただ無言で返されると、訂正印の数だけこちらの心が傷んでいく。
言葉ひとつが救いになることもある
司法書士の仕事は書類を通じて人と関わる。だけど、書類は「伝える」ものであって、「伝わる」とは限らない。むしろ、書類の横にあるちょっとした言葉のほうが、心に残ることがある。言葉には温度がある。温度が伝われば、不安や緊張がほどける。そんなことを、開業から数年たった今になってようやく実感している。
たったひとことの「おつかれさま」に泣きそうになった
ある日、年配の依頼人が帰り際に「大変なお仕事ですね。おつかれさまです」と言ってくれた。たった一言なのに、その日はなぜか涙が出そうになった。書類の準備で徹夜明けだったのもあるけれど、その一言が、誰かにちゃんと見てもらえてる感じがして、救われた。完璧な成果物より、あたたかい一言のほうが人を元気にさせることがあるのだと、身にしみてわかった。
正論よりも共感が欲しかった午後三時
午後三時、クタクタの状態で電話対応をしていたとき、「それは法律上できませんね」といつものように返した。相手は納得していたけれど、しばらく無言だった。「…そうですよね、でも、ちょっと不安で」と漏れたその言葉にハッとした。正しい答えを返したつもりでも、相手は「大丈夫ですよ」と言ってほしかったのかもしれない。その日から、説明のあとに「心配な点があればいつでもご連絡ください」と必ず付け加えるようにしている。
書類の山の中に埋もれた思いやり
書類が山のように積まれていると、どうしても作業的になってしまう。「これをさばかないと」と思えば思うほど、人との関わりが雑になる。事務員さんにもつい「これ急ぎで」とだけ言ってしまう日がある。でもあるとき、「ちょっと息抜きしませんか?」とコーヒーを差し出された。その気遣いに、目が覚めるような気持ちになった。人に対してあたたかくいられる余裕を、自分が持てていなかったことを反省した。
自分自身が冷たくなっていないかの反省
気づけば自分が「正しさ」ばかりを重視するようになっていた。誤りのない書類、効率のいい業務、それ自体は大事なことだ。でも、その過程で誰かの気持ちに蓋をしていたかもしれない。依頼人だけでなく、事務員さんにも、郵便局の窓口の人にも、もっと言葉をかけられたんじゃないかと、ふとした瞬間に思う。
ミスを責めるのは簡単だけど
事務員さんがミスをしたとき、つい「なんでここ間違えたの?」と強めの口調で聞いてしまったことがある。でもそのときの表情が、今も頭に残っている。「すみません…」と申し訳なさそうにうつむく姿に、自分の言葉の冷たさを思い知らされた。それからは、まず「ありがとう。あとはここだけ確認しようか」と言うように心がけている。正しさより先に、人を大事にしたいと思うようになった。
昔の上司の言葉が今になって刺さる
若い頃、厳しい上司がいた。「書類は間違えるな。でも、人には優しくしろ」と言われたことがある。当時は「それ無理だろ」と思っていた。でも今、自分がその立場になってみて、その言葉の意味がわかる。完璧を追うのは疲れるけど、優しさを忘れたら、ただの作業員になってしまう。司法書士は、人の人生に触れる仕事だからこそ、言葉の重さも背負っていかなきゃいけないのだと思う。
完璧を押しつける怖さに気づけた日
「これくらいできて当然だろう」と思った瞬間、自分がどれだけ傲慢だったかを振り返る必要がある。事務員さんのちょっとした入力ミスにイラっとしたとき、その人がどれだけ気を使って仕事しているか、どれだけ緊張しながら間違えないよう努力しているかを想像できなかった自分が恥ずかしい。完璧であることを求めすぎると、人との関係が壊れてしまう。そう思えた日が、少しだけ自分を変えてくれた。
心をほどく言葉は難しくても必要だ
「ありがとう」「助かりました」「お疲れさま」——たったそれだけの言葉なのに、どうしてこんなに難しいのだろう。男同士でも、上司部下でも、たとえ一言でいいのに、つい飲み込んでしまう。でも、その言葉があるかないかで、相手の心の動きはまったく違ってくる。自分にとっても、相手にとっても。だから今日も、意識して言葉を届けようと思う。
事務員さんとのやりとりで気づいたこと
ある日、「今日お客さん多かったですね」と事務員さんがポツリと声をかけてくれた。そのとき「うん、でも君が受付まわしてくれてたから助かったよ」と返したら、ちょっと照れたように笑っていた。その笑顔を見て、「ああ、自分にもこういう言葉をかけられる余裕が残ってたんだな」と思った。人は言葉でつながっている。無言の効率より、言葉のぬくもりを大事にしたい。
感謝は声に出さないと伝わらない
心の中で「ありがとう」と思っていても、声に出さなければ伝わらない。相手にしてみれば、何も言われなければ「感謝されてない」と思うのが普通だ。だからこそ、たとえ照れくさくても、口に出すことが大事だとわかってきた。完璧な業務報告よりも、「本当に助かったよ」という一言が、人との距離をぐっと縮める。そんな実感を、最近ようやく持てるようになってきた。
「ありがとう」が苦手な自分との戦い
それでも、まだうまく「ありがとう」が言えないときがある。なんだか負けた気がするというか、情けないというか、素直になれない。でも、そんな自分に気づいているだけでも、少しは成長したと思いたい。元野球部のクセか、つい強がってしまうけど、少しずつでも変わっていきたい。「完璧な書類より、あたたかい言葉がほしい」と思う自分がいるのなら、まずは自分から言葉をかけていこう。