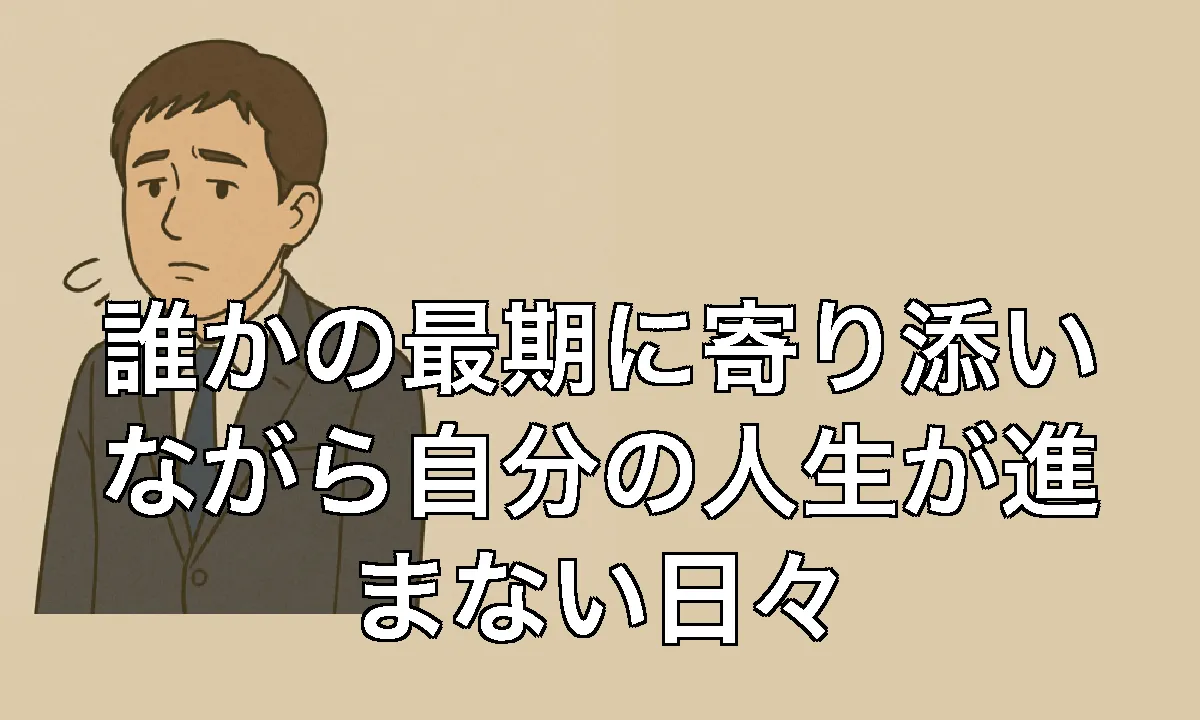最期を見送る仕事の重さと静けさ
司法書士という仕事には、想像以上に「人の死」がつきまとう。相続、遺言、成年後見……いずれも人生の終末に関わる業務が多く、依頼者の死を知らせる連絡が来るたび、何とも言えない静けさが胸を覆う。最初の頃は身が引き締まる思いだったが、数が重なるにつれ、慣れではなく鈍さのようなものが心に芽生えてくる。その静けさは、決して穏やかなものではない。
淡々とした日常に潜む感情の波
日々の業務は淡々としている。朝は事務所に行き、書類を確認し、午後は登記申請。依頼人との面談では、必要な説明を冷静に進めていく。でも、たまにふとした瞬間に感情が揺れる。たとえば、高齢の依頼者が笑顔で「先生、頼んでよかった」と言ってくれた帰り道。コンビニの駐車場でひとり、車の中で涙が出そうになったことがある。理由は自分でもよく分からなかった。
死と向き合うたびに抱える疲労感
「人の死に慣れないでくださいね」と言われたことがある。だが正直、慣れざるを得ない。毎回感情を引きずっていたら、仕事が続かない。だけど、それでも少しずつ心が削れていくのは感じる。葬儀の手続き、遺言執行、相続争い。命が終わった後に残されたものたちと向き合うたびに、「またか」と思う一方で、「自分は何をしているんだろう」と空を見上げる。
誰にも話せない心のざらつき
愚痴を言う相手がいないわけではない。でも、こうした感情はうまく言葉にできないし、言ったところで伝わらない気もする。事務員さんには負担をかけたくないし、同業の友人には「おまえ、優しいな」と笑われそうで話せない。夜、風呂で湯船に浸かりながら、ふいに襲ってくるざらついた気持ち。それをただ、黙って受け止めている自分がいる。
寄り添うだけで自分の足元は見えなくなる
「人の人生に寄り添う」ことを美徳として、この仕事を選んだわけではない。でも、気づけば最期の時間に立ち会うような場面が増え、誰かの人生の終着点に関わることが日常になっていた。人の足跡を丁寧に辿るばかりで、自分の道のりがぼやけてくる。そんな違和感を抱えて、また一日が終わる。
誰かの人生の終点に立ち会いながら
最近もひとつ、印象に残る案件があった。90代の女性が亡くなり、その息子さんが相続の相談に来た。話を聞くうちに、親子の間に積み重ねた時間や後悔がにじみ出てきて、胸が締めつけられた。最期を見送る側の苦しさも知っているからこそ、こちらも真剣になる。でも、その帰り道、自分には見送ってくれる人はいるのかと、急に不安になるのだ。
「お疲れさまでした」と言うことの意味
亡くなった方の戸籍をたどり、必要な手続きを整え、提出し、すべてが終わったときに心の中で「お疲れさまでした」とつぶやく。これは形式ではなく、自分なりの儀式だ。でも、そう言うたびに、どこか自分の命の時間も少しずつ削られている気がする。見送る言葉は美しいが、残された側は、その言葉を重く引き受けている。
事務所に戻ればまた無言の書類作業
手続きが終わって事務所に戻ると、目の前には山積みの書類が待っている。会話はなく、ただひたすらに書類と向き合うだけ。人の死に触れた後でも、現実は無情に続く。仕事とはそういうものだと割り切っていても、机に向かう背中が重たい。誰かの人生を締めくくったその手で、また新しい案件の表紙をめくる。その繰り返しに、自分がどこに向かっているのか、分からなくなる。
自分の人生が空白に感じる瞬間
ふと時計を見ると、もう夜。1日があっという間に終わっている。でも何をしたのか、どんな感情を抱いたのか、記憶が曖昧だ。誰かの人生の断片ばかりを見つめ、自分の生き方は空白のまま。その事実に気づくたび、心がすうっと冷える。
ふとした時に押し寄せる喪失感
仕事帰りにスーパーへ寄ったとき、家族連れの楽しそうな笑い声が耳に入ってきた。それだけで胸がズシンと重くなる。自分にはない風景。自分には訪れなかった未来。そんなものを突きつけられるたび、「こんなに人の人生を見てきたのに、自分の人生は何だったんだろう」と、足が止まる。
結婚しなかった理由をまた一人で考える
若い頃は「いつかできるだろう」と思っていた。忙しさを言い訳にして、恋愛を後回しにしてきた。気がつけば45歳、そして独身。事務所にこもって書類を眺めている時間の中で、誰かと過ごしたいと思う気持ちはある。でも、その扉を開ける勇気ももう残っていない気がしている。
やりがいと空虚感は同居できるのか
この仕事に誇りはある。誰かの人生を支え、最期を見届ける役割を担っていることに意義も感じている。でも、その裏にある「自分のことは何もできていない」という空虚さもまた、消えない。やりがいと孤独。その二つが同居しているのが、司法書士としての今の自分だ。
それでもこの仕事を続ける理由
心が疲れていても、やめたいとは思わない。それは、この仕事が自分にとって「人とつながる唯一の場所」だからだ。書類の先にいる誰かの人生に触れられること。それが、ささやかながら生きている実感を与えてくれるからかもしれない。
誰かの最後を丁寧に扱うということ
誰かが亡くなった後に残るもの、それは記録であり、手続きであり、想いだ。そのどれもが丁寧に扱われるべきものであり、それを支えるのが自分の役目だと思っている。華やかさはない。感謝の言葉すらないこともある。それでも、「この人が生きた証を形に残せた」と思える瞬間だけは、誇れる。
野球部時代のチームプレーと重なる思い
昔、野球部で補欠だった。スタメンにはなれなかったけれど、仲間のためにベンチで声を出し、道具を整えていた。今の仕事も少し似ている。主役は依頼人であり、その家族。自分は裏方だ。それでも、誰かの人生を支える存在であることに、変わりはないのだと思う。
「ありがとう」が支えになる日もある
滅多に言われることではないけれど、たまに心からの「ありがとう」をもらえる日がある。手続きを終えた帰り際に深々と頭を下げられたとき、言葉にならない何かがこみ上げた。そんな日があるからこそ、また明日も誰かの人生に静かに寄り添っていこうと思える。