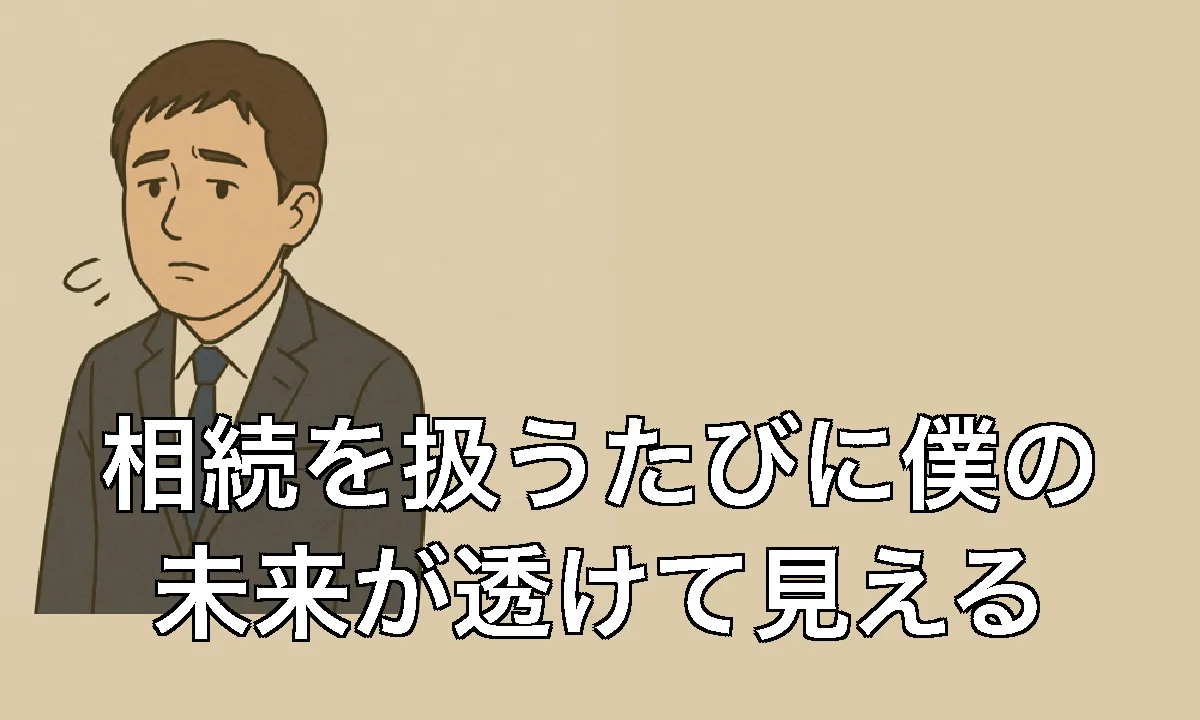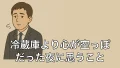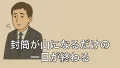相続の書類を前にしてふと手が止まる瞬間
日常的に相続登記の案件を扱っていると、ふとした瞬間に手が止まることがある。依頼者の名前や被相続人の生年月日を見て、どこか他人事ではなくなる感覚。年齢も近く、自分と重ねてしまうのだ。「この人の人生は、どんなふうに終わったのだろう」と考えると同時に、「自分が死んだら、誰がこの書類を作るんだろう」という疑問がよぎる。法的な作業のはずが、いつのまにか感情の整理を迫られてしまう瞬間だ。
誰かの人生の終わりを処理する仕事
司法書士の仕事の一つに、亡くなった方の名義を現世の誰かへと移す「相続登記」がある。つまり、誰かの人生の終焉を法的に整理する仕事でもある。そこには悲しみもあれば争いもあるが、いずれにせよ「残された人」がいて初めて成立する業務だ。僕はそれを、書類として淡々と処理していく。でも、ふと手が止まる。これが自分だったら、どうなるのかと。
残された人がいるということの重み
相続とは、故人の痕跡を誰かが受け継ぐことであり、残された人がいる証だ。兄弟や子ども、配偶者。依頼者の多くが「面倒だけどやらなきゃ」と言うが、僕からすれば羨ましい。だって、その「面倒」を引き受けてくれる人がいるってことでしょう?それって、すごいことだよ。僕なんか、何を残したって誰にも文句を言われずに放っておかれる気がする。
自分には誰が残るのだろうと考える
兄は遠方で家庭を持ってるし、親も高齢だ。僕が倒れたら、事務員さんが気づいてくれるかもしれない。でも、その後のことは?自分のパソコンの中のデータも、机の引き出しにある書類も、誰が触るんだろう。ひとり身の司法書士って、まさに“孤立したサーバー”みたいなもので、誰にもアクセスされないまま電源が落ちる日を待っているようなものだ。
依頼者の家族がねと言う言葉に心が揺れる
「家族がね、こう言っていて」そんな一言が、打ち合わせ中によく出てくる。依頼者にとっては何気ない言葉かもしれないけれど、僕にはその言葉がずっしりと胸に響く。相続の手続きを通して、人と人との関係が見えてくる。故人と生きてきた日々、残された人たちのつながり。僕にはその「家族がね」と言える相手がいないのだ。
家族とのつながりが生む葛藤と温度差
家族がいれば幸せというわけではない。揉める相続も山ほど見てきたし、絶縁していた親子が手続き上だけ再会することもある。それでも、そこには「関係性」がある。対立でも憎しみでも、それは一つの存在証明だ。僕には、誰と対立することすらできない空白がある。ただ無風のまま終わっていく未来が、どこかで待っている。
相続争いを見ながらも羨ましさを感じる
以前、相続財産を巡って姉妹が激しく争った案件があった。書類は進まないし、感情的になって何度もやり直し。でも、心のどこかで「こんなにも強く言い合える相手がいるっていいな」と思ってしまった。愛憎の裏には、それまで一緒に過ごしてきた時間がある。僕にはそんな時間があるだろうか、誰かと「遺す」「遺される」関係を築けるのだろうか。
争う相手がいるという豊かさ
皮肉な話だけど、相続争いは「絆の証明書」みたいな側面もある。財産があるから争うのではなく、その人の存在が大きかったからこそ、奪い合いになるんだ。僕が死んでも、誰も奪い合わない。残された事務所、古いパソコン、無記名の書類。誰かが惜しんでくれるのだろうか。いや、きっと静かに片付けられて、静かに消えるんだろうな。
相続登記を終えて戻る夕暮れの事務所
外は茜色に染まり、商店街のシャッターが閉まり始める時間。僕は事務所に戻ってきて、郵便物の整理をする。依頼者の手続きが無事終わった達成感とともに、どこか虚無感が押し寄せる。「今日も他人の人生を整理したな」と感じながら、自分の人生の“未整理”具合に気づく瞬間だ。
ひとり事務所で流れる無音の時間
事務員さんは定時で帰っていく。僕はしばらく、誰もいない事務所でキーボードを叩いたり、ポストの整理をしたりして過ごす。音はない。BGMもつけていない。だけど、その無音が今日はやけに響く。疲れた心に、静寂が染み込むような感覚。こういう時、誰かがいればなと思うが、それは贅沢なのか。
机の上に残るのは申請書とコンビニのコーヒー
机にはまだ提出していない申請書と、飲みかけのコンビニコーヒーが置かれている。ペンのキャップを閉めながら、今日はこれで終わりだと小さくため息をつく。仕事は確かに進んでいる。でも、自分の人生は、進んでいるのか?どこに向かっているのか?誰と歩いているのか?答えがないまま時間だけが過ぎていく。
明日もまた同じような日が来る予感
夜の事務所に鍵をかけ、振り返ると暗がりの中に僕の影が一つだけ映っている。誰にも気づかれずに、今日も終わった。帰ってもテレビの明かりが待っているだけ。冷蔵庫の中は昨日と同じ。明日も、また似たような日が来るんだろう。でも、その日々の繰り返しが、今の僕を支えていることも確かだ。