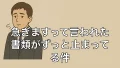静かすぎる夜が問いかけてくるもの
夜になると事務所の喧騒が消えて、やっと一息つけるはずなのに、妙に落ち着かない。テレビもつけず、スマホも触らず、ただ布団に横たわると、不意に心のどこかがざわつく。昼間は「忙しい」でごまかせる感情が、夜になると一気に押し寄せてくる。誰かと話したかったな、そんな些細な感情が胸の中でじんわりと広がる。そしてふと思う。「このままでいいのか」と。
日中の喧騒が消えた後に残るもの
業務の合間に飛び交う電話、書類の確認、登記の段取り。忙しい時間帯には、余計なことを考える暇なんてない。でも一日の仕事を終えて、机を片付けて帰る道すがら、ふと足が止まるときがある。コンビニの灯りがやけにまぶしく感じる日、そこに立ち寄る誰かが誰かを待っているように見えて羨ましくなる。自分には今、誰がいるだろうか。そんな問いかけを、誰にするでもなく繰り返してしまう。
仕事の疲れより心の重たさが勝つ瞬間
今日も朝から晩まで駆けずり回って、足もパンパンにむくんでいるのに、心がなぜか重い。達成感ではなく、ぽっかり空いたような感覚。誰の役に立てたかもしれないのに、自分自身が報われていないような気がしてならない。きちんと報酬もいただいている、書類も完璧に仕上げた、それでも夜の静けさのなかでは「虚しさ」の方が勝ってしまうのはなぜだろう。心の体力が足りていないのかもしれない。
ひとり暮らしの布団の中でよぎる思い
実家を出て何年経つだろう。今や自分の居場所は仕事場とこの部屋だけ。帰宅後は簡単に晩飯を済ませ、湯船につかるでもなくシャワーで済ませてしまう。風呂上がりに冷えた缶ビールを開けて、適当にネットニュースを眺めると、あっという間に夜は更けていく。でも布団に入ったとたん、今日話した会話の数を数えてしまう。「お疲れさまでした」と「お願いします」の繰り返しばかりで、誰とも心を交わしていないことに気づく。
結婚していれば違ったのかという妄想
もし誰かが隣にいたら、この孤独感は少しは和らぐのだろうか。たとえば「今日もお疲れさま」と声をかけてくれる人がいれば、夜がこんなにも長く感じることはないのかもしれない。かといって、誰かと暮らすことの現実も分かっているつもりだ。自由は減るし、気を遣うことも増える。それでも、自分のことを少しでも心配してくれる存在がいることは、心の支えになるのではないかという妄想が頭を離れない。
元野球部のくせに心は弱いままだ
中学高校と野球に打ち込んでいた頃は、「気合い」と「根性」が全てだと思っていた。真夏のグラウンドで、泥だらけになっても文句ひとつ言わずに走り続けた日々。あの頃の自分は、まさか将来、寝る前に孤独に押しつぶされそうになるとは思ってもいなかった。人は鍛えれば強くなる、そう信じていたけれど、心だけはどうやって鍛えればいいのか、今も答えが見つからないままだ。
司法書士という職業の孤独さ
司法書士は、一見すると「先生」と呼ばれて信頼される仕事に見えるかもしれない。たしかに、人から感謝されることもあるし、責任ある役割も果たしている。でも、そのぶん悩みや葛藤を誰かに話せる場が少ない。失敗できないというプレッシャー、些細なミスが大きな問題につながる怖さ。それを誰かと共有することも難しい。孤独は、仕事のなかにも息をひそめている。
信頼されても相談されないこの立場
依頼者は、こちらを「プロ」として頼ってくる。でも、それは一方通行の信頼であって、こちらが弱みを見せたり相談したりすることはない。たとえば、「今日は本当にしんどいんですよ」なんて話したら、仕事に不安を感じさせてしまうだけだ。だから黙って聞く側に徹する。それが当然の振る舞いだとわかってはいるけど、心の中では誰かに「今日も疲れた」と言ってしまいたい夜もある。
依頼者の人生を背負ってしまう感覚
とくに相続や家族に関する案件を扱うとき、書類の裏側にある人間関係や人生の機微を見せつけられる。そこに自分の感情を乗せてはいけないと分かっていても、気づけば感情移入してしまうこともある。それだけ依頼者に真摯に向き合っている証拠かもしれないけど、誰かの問題を抱えたまま自分の夜を迎えるのは、思っている以上に重たい。眠れない原因のひとつかもしれない。
感謝されてもどこか埋まらないもの
「助かりました」「本当にありがとうございます」と言われると、その瞬間は報われた気になる。でも、その温もりは長続きしない。感謝の言葉を受け取った数時間後、ひとりの部屋で夕飯を食べていると、再びぽっかりと心に穴が空いたような気分になる。たぶん、誰かと感情を共有する時間や関係性が、自分には圧倒的に不足しているのだろう。心の空白は、仕事の成功だけでは埋まらない。
日報では埋められない隙間
毎日、今日の業務を頭の中で整理しながら寝るのが習慣になっている。「あの書類はOK」「次はあの申請だな」と頭の中は仕事の段取りで埋め尽くされているけれど、それで気が紛れるわけでもない。むしろ、その合間にふと入り込んでくる「自分の人生って何だったんだろう」という問いが厄介だ。事務所の数字では測れない何かが、心の隙間にこぼれ落ちている気がする。
事務員との会話が一日の全て
唯一、事務所で人と接するのが事務員の彼女。でも、業務的なやりとりが大半で、たわいない雑談をする余裕もない日が多い。「お先に失礼します」と彼女が帰ったあとの静まり返った事務所に残るのは、パソコンのファンの音だけ。その音が逆に寂しさを引き立てる。人と話す時間の少なさが、こんなにも精神に影響を与えるものかと痛感する。
帰り道に誰とも話さない日々
帰宅途中に立ち寄るのは、せいぜいコンビニかスーパー。そこで「袋いりますか?」と聞かれるくらいで、誰かと目を合わせて会話をする機会なんてほとんどない。家に着いて、テレビをつけて、スマホを見て、何も起こらずそのまま寝る。こんな毎日が何年も続くと、自分がだんだん無機質な存在になっていくような錯覚に陥る。誰かに話しかけてほしい、そんな願いが心の奥に居座っている。
それでも朝は来るし仕事は待っている
そんな夜を何度繰り返しても、朝は容赦なくやってくる。布団の中で「今日は休みたいな」と思っても、誰も代わりはいない。司法書士という立場は、孤独だけど逃げられない。だからこそ、自分自身との付き合い方を少しずつ学ぶしかない。寂しさをごまかすのではなく、ちゃんと受け止めながら、それでも前に進む力を持てたら、きっと今より少しだけ夜が静かに感じられる気がする。
布団の中で見つけた小さな解像度
ある夜、眠れずに天井を見つめながら思った。「ああ、今日も誰とも笑っていないな」と。でもその後すぐ、「じゃあ明日、自分から笑いかけてみようか」と思えた。その瞬間、心の中に小さな火が灯った気がした。孤独を完全に消すことはできないかもしれない。でも、少しずつ角度を変えて捉えてみることはできる。それが眠る前の静かな時間にできる、自分なりの癒しなのかもしれない。
ひとりでも続ける理由は何か
「誰のために働いているのか?」そう自問する夜もある。答えはいつも曖昧だけれど、時折見える依頼者の安心した顔や、「助かったよ」の一言に、何か救われる気がする。たとえ誰かと一緒にいなくても、自分が果たせる役割があるなら、もう少しだけ頑張ってみよう。そんな気持ちで、また布団をかぶって目を閉じる。きっと明日も、朝は変わらずやってくるから。