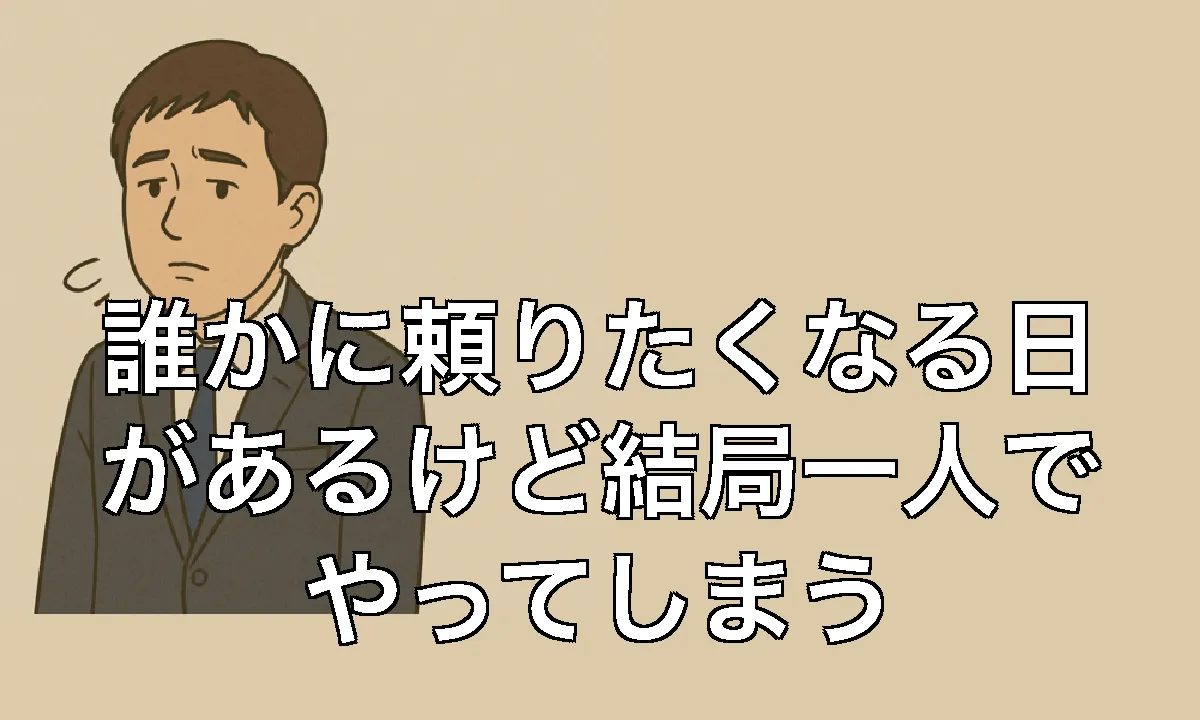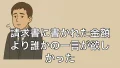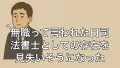頼ることに抵抗を感じてしまうのはなぜか
司法書士という仕事は、見た目以上に「個人商店」的な性格が強い。日々の登記や相談、時にはお客様の人生に踏み込むような事案もあり、常に慎重さと責任感を求められる。そんな中で、「人に頼る」という選択肢が、どうしても自分の中で薄れてしまう。やればできる、というより「自分でやらなければならない」と思い込んでいるのだ。気づけば、自分の背中にどんどん荷物を積んでしまっている。誰かに少し預けるだけでも楽になるのに、なぜかできない。そんな日々を、静かな疲労感とともに過ごしている。
迷惑をかけたくないという思いが先に立つ
実は頼りたいのに頼れない。そんな自分に気づいてはいる。でも、頭にまず浮かぶのは「この忙しいときに頼むなんて、相手の負担になってしまうのではないか」という遠慮だ。事務員さんにちょっとしたことを頼もうとしても、つい「いや、これは自分でやった方が早いな」と思い直す。結果として、どんどん自分の仕事が溜まっていく。ある日、「先生、それ今日までですよね」と事務員さんに言われて青ざめたことがあった。あの時、素直に聞いておけば…と思っても、もう遅いのだ。
相手の忙しさを勝手に想像して遠慮してしまう
事務員さんが書類を整理している姿を見ると、「今声をかけるのは悪いかな」と勝手に判断してしまう。実際には、それほど手間のかからない作業だったかもしれないのに、「自分のことは自分でやる主義」が発動してしまうのだ。昔からこの癖はある。高校の野球部でも、誰かがノックを受けている間に自分でグラウンド整備をしていた。たまに先輩に「それ、みんなでやるんだから残しておけよ」と怒られたが、自分の中では“迷惑をかけない努力”だったのだ。
昔の男は黙って耐える精神がまだ染みついている
「人に弱みを見せるな」「泣くな、我慢しろ」。そんな言葉を耳にして育った世代だ。気づかないうちに、それが心の奥に根を張っている。自分が大変なときでも「大丈夫です」と言ってしまう。人前では崩れられない、そんな思いがどうしても拭えないのだ。結果、誰にも頼れず、自分の中に抱え込んでしまう。夜、帰宅して誰もいない部屋でようやく「もう無理かも」と小さくつぶやく。そういう瞬間が、最近増えてきたように思う。
そもそも人に頼るという経験が少ない
振り返ってみれば、子どものころから「頼る」より「任される」経験のほうが多かった。親からも「しっかり者だ」と言われ、先生からも「君に任せて安心だ」と言われ続けてきた。気がつけば、それが自分のアイデンティティになっていたのかもしれない。人に頼ることは、自分の役割を手放すような気がして、どうしても苦手意識が抜けない。
学生時代から頼るよりも任せられる側だった
中学・高校と野球部でキャプテンをやった。練習メニューの管理、後輩指導、遠征の準備など、自然と自分が段取りを取る側になっていた。「困ったら稲垣に聞け」なんて言われて、ちょっと誇らしかった。でもその裏で、「本当は俺も誰かに聞きたいよ」と思う瞬間もあった。だけど、そこで甘えるという選択肢はなかった。ただひたすら、できるフリをし続けていた。
仕事でも家族でも気づけば自分がまとめ役だった
兄弟の中でも長男で、親戚が集まれば率先して動く。「お前はしっかりしてるな」と褒められるたびに、「期待には応えなければ」と思ってしまう。そして今、司法書士として小さな事務所を一人で切り盛りしている。結局、自分の人生は「任される人生」だった。だからこそ、ふと立ち止まったときに「誰かに寄りかかってみたい」と思ってしまうのだ。
事務所という名の小さな世界で感じる孤独
毎日顔を合わせるのは事務員さん一人。もちろん信頼しているし、頼りにもしている。でもやはり「雇う側」と「雇われる側」という微妙な距離感は存在していて、ふとしたときに寂しさを感じる。仕事の愚痴を気軽にこぼせる相手がいないというのは、思った以上に精神的にこたえる。孤独というより、無音の中にぽつんといるような感覚だ。
事務員さんとの距離感の難しさ
ときどき冗談を交えながら話すこともあるが、やはり線は引いている。相手もそれを感じているだろう。変に甘えすぎても気を遣わせてしまうし、かといって堅苦しすぎても働きにくい。たとえば、自分の体調が悪い日。「今日はちょっとしんどい」と言いたくても、それが負担になりそうで飲み込んでしまう。結局、何もなかったようにデスクに向かう日々だ。
優しさと仕事の線引きに悩むこともある
たとえば、彼女が昼休憩を削って書類整理をしているとき。「ちょっと休んで」と言いたいけど、それが“上司としての指示”になると考えてしまう。プライベートな気遣いと職場の上下関係、その間の微妙なバランスにいつも戸惑う。本当は「ありがとう」「無理しないでね」と気軽に言える関係でいたい。でも、それができない自分もいる。
誰にも言えない決断と責任
登記の内容一つ、書類の提出タイミング一つが大きなトラブルを招く可能性がある。だからこそ、最終判断は自分で下すしかない。その責任感の重さを、誰かと分け合うことができればどれだけ楽かと思うことがある。でも、それはできない。ミスしたらすべて自分の責任。そういう世界で仕事をしていると、どこか自分の感情にも蓋をしてしまうのだ。
判断を誤ればすべて自分に返ってくる重圧
何度も見直した書類でも、「間違っていたらどうしよう」という不安は消えない。実際に、書類の一部で提出先に確認が必要になり、先方から厳しい言葉をもらったことがある。あの時、「俺一人のせいじゃないのに」と思いつつも、言い訳はできなかった。そんな経験が積み重なり、「だったら最初から自分一人で全部やる方がいい」と思ってしまうのだ。
それでも誰かに頼るという選択肢
頼れない性分。それでも、最近になって少しずつ「それではもたない」と感じ始めている。完璧じゃなくてもいい。弱さを見せても、きっと世界は壊れない。そう思えるようになったのは、何もかも抱えきれず、事務員さんに「ちょっとだけ助けてほしい」と言ってみた日からだ。驚くほどすんなり助けてくれて、そのあと「先生、そういう時は遠慮せず言ってください」と笑われた。
ちょっと聞いてくれるから始めてみる
誰かに頼るのは、大きなお願いをすることじゃない。まずは「今日こんなことがあってさ」とつぶやくことから始めてみる。それだけで心が少し軽くなることもある。完璧じゃない自分を少しずつ認めていくこと。それが、司法書士という堅い肩書きの奥にいる“ただの自分”にとっての救いになるのかもしれない。
野球部時代のように背中を預けてみたい
あの頃は、ピッチャーが苦しければキャッチャーが声をかけてくれた。守備が乱れたら、ベンチから仲間の声が飛んできた。一人で抱える必要はなかった。司法書士という仕事は孤独だ。でも、誰かの声を受け止めたり、声をかけたりすることはできる。自分もまた、誰かの支えになれるように、まずは頼る練習から始めようと思う。
ピッチャー一人では試合に勝てなかった
自分がどれだけ投げ込んでも、エラーが出れば点が入る。逆に、守備が固ければミスもリカバリーできた。そんな連携があってこそ勝てた試合がいくつもある。仕事も同じだ。自分だけで完璧にやるのは無理がある。だからこそ、チームで支え合うことの意味を思い出していきたい。頼ってもいい、自分を甘やかしてもいい。そう自分に言い聞かせながら、今日も書類に向かう。