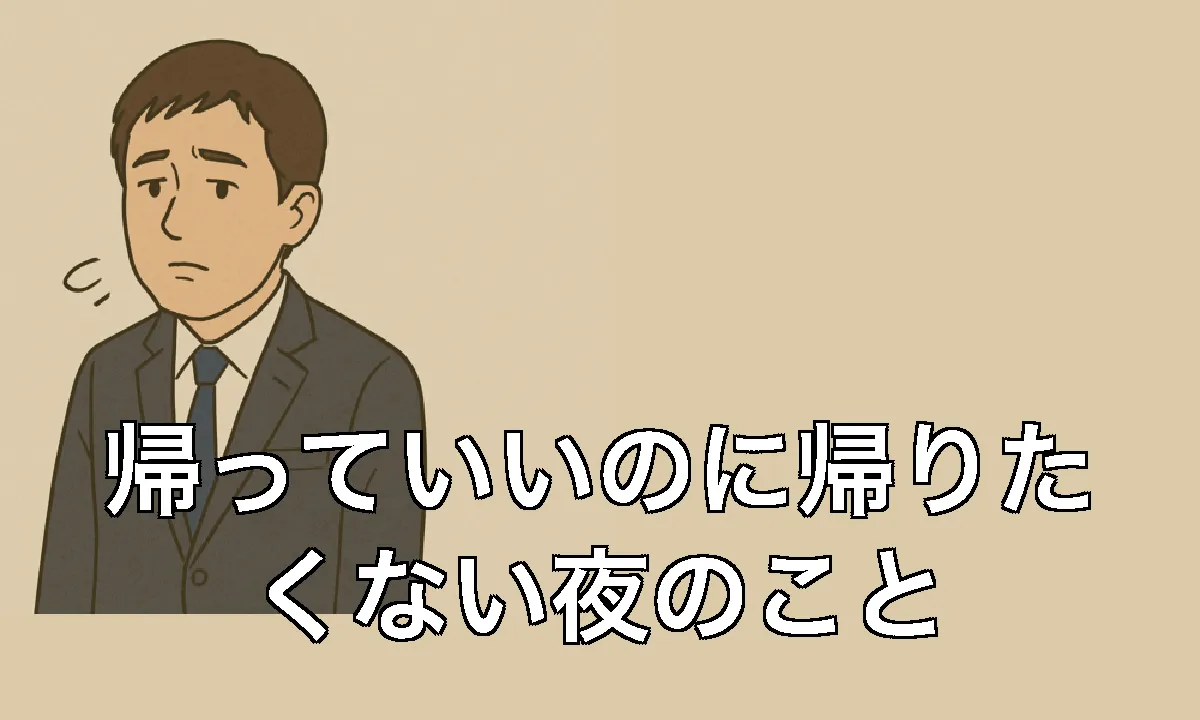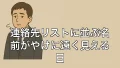帰れるはずの喜びが重くのしかかる夜
定時で終わった仕事、今日は珍しく残業もなし。事務員さんが気を利かせて「もう帰っていいですよ」と声をかけてくれた。でもその瞬間、心の奥にモヤっとしたものが沈んだ。帰っていいはずなのに、どこかに居場所がなくなったような気がして、急に事務所の机が恋しくなる。家に帰っても、待っているのは誰もいない静かな部屋。だったらもう少しここにいて、何か片付けるふりでもしていた方が気が楽じゃないか、そんなことを考えてしまう自分がいる。
定時退社のはずなのに心が軽くならない
本来なら「やった、今日は早く帰れる!」と小躍りしていいはずだ。けれど司法書士として独立して十数年、そんな日は年に数えるほどしかない。そしてその希少な「自由時間」に、逆に苦しさを感じるとは思ってもみなかった。結局、心が軽くならないのは、自由になった時間をどう使っていいか分からないからかもしれない。やりたいことも、会いたい人も、思い浮かばない。まるで時間だけが与えられて、中身が空っぽのプレゼントみたいだ。
誰にも引き止められない寂しさ
「もうお帰りください」と言われるのが業務上当然なのは分かっている。でもそれを言われたとき、「もう帰っても誰も困らない存在」と認定された気がして、少しだけ心がざらつく。昔、野球部の頃は誰かが「先に帰るなよ」と言ってくれた。あの無意味な引き止めが、実はどれほどありがたいものだったか。今はそんな言葉をかけられることもなく、去るときは静かに去る。それが大人というものかもしれないが、胸の奥にぽっかりとした空洞が残る。
事務員に「先に帰っていいですよ」と言われた日の気まずさ
ある日、事務員さんが気を遣ってくれた。「もう帰っていただいて大丈夫ですよ」と言われた瞬間、なんとも言えない気まずさが走った。ありがたい言葉なのに、まるで「あなたがいなくても大丈夫です」と宣告されたように聞こえた。彼女に悪気はない。むしろ優しさなのだ。それでも、自分の存在が事務所にとって「いてもいなくても変わらない」存在だと感じてしまい、なぜか気分が沈む。家に帰る足取りも、いつもより重かった。
仕事が終わったのに終わらない気持ち
日報をまとめて、机を拭いて、戸締まりを確認。全て終えたのに、心が終わらない。むしろそこからが本番のような気がする。何をするでもないのに、ひとりになってからの時間が一番しんどい。やるべき仕事があった方が、ずっと楽だったと思える夜もある。気を抜いた瞬間に押し寄せる孤独。司法書士という仕事は、成果を出すたびに一人でそれを消化しなければならない。終わった瞬間の静寂に、救いがないのだ。
忙しさのあとにやってくる空白の時間
昼間はひっきりなしに人が来る。登記の相談、相続の説明、電話応対…。その瞬間は目まぐるしくて、自分の時間なんてなかったはずだ。でも、その反動が夜にやってくる。特に何も予定がない日は、時計の針が妙にゆっくり進む。あの空白の時間が怖い。趣味があればいいのかもしれない。でも今さら新しい趣味を始める気力も湧かない。気づけばスマホを眺めて数時間。そんな時間が何より自分を削っていく。
テレビも音楽も響かない夜の部屋
家に帰ってテレビをつけても、ただの騒音にしか感じない。BGM代わりに音楽を流しても、逆に心がざわついてしまう。そんなとき、「自分は今日、生きたと言えるだろうか?」とふと問いが浮かぶ。誰かに会ったわけでもなく、笑い合ったわけでもなく、ただ業務をこなしただけ。それで良かったのだろうか。司法書士という仕事は、日々淡々と進む。それが尊いことだと頭では分かっていても、心が追いつかない夜もある。
元野球部のくせに自宅では無口になる理由
学生時代、野球部ではとにかく声を出せと言われていた。元気だけが取り柄だった。あの頃の自分を知っている人が今の自分を見たら驚くだろう。今では、自宅ではひとことも発さずに夜が終わる日もある。声を出す相手もいなければ、話すこともない。誰とも会話しない日常に慣れてしまった。司法書士の仕事では言葉を使うが、それはあくまで「業務上の言葉」だ。本音を話す場面など、どこにもない。
事務員が気を遣ってくれるのがつらいとき
本当にありがたいことに、事務員さんはよく気を遣ってくれる。「先生、お昼まだですよね」「お茶入れましょうか」——そのひと言ひと言が心に染みる。でも、その優しさがつらいときもある。なぜなら、それが自分の孤独や弱さを映し出してしまうからだ。何気ない一言で「一人でいること」に気づかされ、余計に胸が締めつけられる。優しさは、ときに鏡になる。
「気を遣わせてるな」と思った瞬間の自己嫌悪
彼女が気を遣ってくれるたびに、「ああ、また気を遣わせてしまった」と思ってしまう。たぶん、そんなつもりはないはずなのに、こちらの空気を読んで先回りしてくれる姿に申し訳なさを感じる。まるで、自分が“空気の重さ”になってしまったような感覚。頼られる存在でいたかったはずなのに、いつの間にか“気を遣わせる存在”になっていることが、情けなくもある。だからこそ、自分の中でバランスを取りたくて、逆に無理をしてしまう。
「もう帰ってください」の裏にある優しさが刺さる
「今日はもう大丈夫ですので、お先にどうぞ」——そんな言葉は、一見すごく自然だ。でも、こちらとしては「帰っていいですよ=もうあなたに頼ることはありません」と解釈してしまうこともある。本当は感謝すべき場面なのに、勝手に寂しさを感じてしまう。これは完全に自分の問題だと分かっているが、だからこそやっかいだ。相手の優しさを素直に受け取れない自分が情けなくて、また落ち込む。
ひとりの職場で気まずさが倍増する日常
そもそも少人数の職場だと、空気の変化にとても敏感になる。こちらが少しでも落ち込んでいると、事務員さんも気を遣って無言になってしまう。そしてその無言が、さらにこちらを追い詰める。「気まずい空気」が場に充満すると、お互いに息苦しくなる。こんなとき、人数の多い職場なら誰かが笑ってくれて空気が変わるのだろうか。けれどこの静かな職場では、それができない。孤独というのは人数の問題ではなく、気持ちの行き場のなさだと思う。
司法書士という仕事の孤独な側面
この仕事には誇りもあるし、感謝される場面も多い。けれど、どうしても一人で抱える場面が多くなるのが実情だ。誰かとチームで進めることも少ないし、成功してもそれを誰かと分かち合う機会は少ない。だからこそ「もう帰っていいですよ」の一言が、思いのほか重く感じるのだ。誰にも必要とされていないような錯覚に陥る夜、それでも翌朝にはまた普通の顔で事務所に向かう。この繰り返しの中で、なんとか日常を保っている。