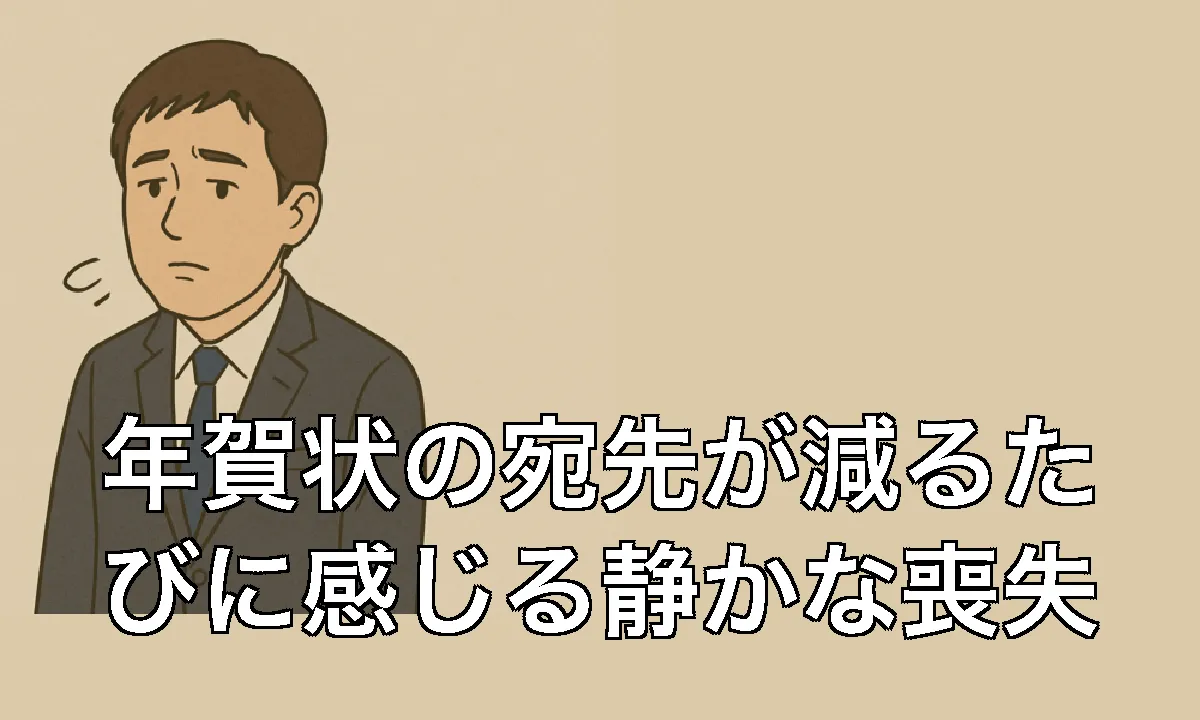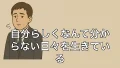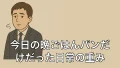年賀状の宛先が減るたびに感じる静かな喪失
年賀状の束が薄くなるたびに心がざわつく
年が明けるたびに、昔はもっと分厚かった年賀状の束が、今では郵便受けの底に寂しく貼り付いているような薄さになっている。正月早々に感じるのは、年の始まりの希望ではなく、「あれ、また少ないな」という物足りなさだ。以前は20枚以上あったのに、今では10枚あるかどうか。仕事上の挨拶も含めればもっとあってもおかしくないが、気がつけばその役目もメールやLINEに取って代わられている。そんな些細な変化に、なぜか胸がざわついてしまう。
数年前はもっと多かったはずの名前たち
10年前の年賀状ファイルを開いてみたことがある。そこには、今よりもずっと多くの名前が並んでいた。中学の同級生、元彼女の親、かつての顧客、亡くなった親戚…どれも一度はちゃんと年賀状を送り合っていた人たちだ。それが徐々に、更新が止まり、返事が来なくなり、こちらも送らなくなっていた。まるで「関係が終わった」ことを認めるような行為だった。思い出の中で生きている名前ばかりが残る。
親戚から届く年賀状が減った理由
親戚からの年賀状が減ったのは、明確な理由がある。まず高齢化だ。伯父や伯母が亡くなったり、施設に入って年賀状どころではなくなったり。あとは「もう年賀状は卒業します」と宣言されたりする。そのたびに「そんなもんか」と思いつつ、実際に届かなくなると、意外と胸にポカンと穴が開く。出す方は楽になったのかもしれないが、受け取る側としては「今年も生きてるな」と確認する最後の通信手段だったのに。
仕事関係の人との年賀状もフェードアウト
士業という立場上、昔は顧問先や同業者と律儀に年賀状をやりとりしていた。ところが近年、形式的なものとして省略されるケースが増えた。私自身も忙しさを理由に「メールで失礼します」としてしまった年がある。そこから関係が少しずつ薄れていった気もする。一枚の葉書に名前と一言を添える、その小さな行為が、実は案外大きな意味を持っていたのかもしれない。
LINEやメールで済まされる時代の流れ
今は何でもスマホで済んでしまう。年賀状アプリや自動作成サービスもあるが、結局「送った感」だけが残って、相手との実際の距離は近づかない。LINEで「あけおめ」と送れば、それで関係が保てていると思い込んでしまう。でもその「関係」は、紙の年賀状で結ばれていた頃のような温度がない。印刷のズレや、手書きの字の震えにすら、相手の存在を感じていたのに。
年賀状の減少は人間関係の減少か
年賀状の減り方を眺めていると、自分の人付き合いの狭さや、日々の暮らしの中で誰かとの接点がどんどん少なくなっていることに気づく。自分から切ったわけではないが、気づいたら誰もいなくなっていた、そんな感覚。これは単なる葉書の問題ではなく、人間関係がフェードアウトしていく過程の象徴かもしれない。
疎遠と自然消滅は紙一重
「最近どうしてるんだろう」と思っても、電話をかける勇気もなければ、突然のLINEも気が引ける。そんなときに年賀状という年一回の口実はありがたかった。でも、それをやめてしまえば、もう再接点の糸が切れてしまう。疎遠という言葉はまだ関係が続いている前提があるが、自然消滅はもう関係がなくなったということだ。紙一重のようでいて、その差は深い。
こちらから出すのをやめたら終わった関係
年賀状を毎年こちらから出していた相手がいた。返事は来ないけど、なんとなく続けていた。でもある年、こっちから送るのをやめたら、そのまま何も起こらなかった。そのとき、「あ、もう終わってたんだ」と気づく。自分だけが関係をつなごうとしていたのかもしれないと虚しさが襲ってくる。
もういいかと思う気持ちの裏にある寂しさ
「もういいか」と思ってやめた年賀状のやりとり。でも年明けにポストが空っぽだと、なぜか胸にチクリとくる。自分がそれを望んだはずなのに、いざ孤独が現実になると、思った以上にこたえる。年賀状って、そんなに重要だったんだなと気づいたのは、失ってからだった。
亡くなった人の名前に赤線を引くという行為
年賀状リストには、住所や名前がずらっと並んでいる。そこに赤ペンで引く線が増えていくたびに、時の流れと命の重さを実感する。仕事柄、死というものには慣れているつもりだったが、いざ自分の知っている人が「もういない」となると、その現実は冷たく突き刺さる。
喪中はがきで知る悲しい現実
年末になると届く喪中はがき。見慣れた名前の右に添えられた「父○○が永眠いたしました」の文字。声を出して「うそ…」とつぶやいてしまう。年賀状を書こうとしていた矢先に、その人がもうこの世にいないことを知る。そんな経験が増えてきた。
年賀状リストが訃報リストに変わる感覚
昔は年賀状リストといえば「誰に出すか」を確認するための明るい存在だった。それが今では「誰がまだいるか」を確かめる作業になってきた。生存確認のためのリスト。自分の生きている世界が、静かに縮んでいることを年賀状が教えてくれる。
赤線を引くたびに自分の年齢を意識する
赤ペンで名前を消すたびに、「自分もいずれ誰かの赤線になるんだろうな」と思う。40代になってようやく実感した、死の現実。自分はまだまだ若いつもりでも、年賀状リストの“減り”は、確実に時間が進んでいることを突きつけてくる。
それでも年賀状を出す理由
そんな思いをしながらも、私は毎年年賀状を出している。宛先は減っても、ゼロにはしたくない。もしかするとそれは、相手のためというより、自分自身の「まだ誰かとつながっている」という証明をしたいのかもしれない。
形式ではなく自分の存在確認かもしれない
形式的な挨拶かもしれない。でも、筆を取って住所を書き、一言添えるその過程で、「ああ、自分はまだこの人のことを覚えている」と実感できる。返事が来なくても、出すことで自分の心の整理ができるのだ。
返信があるとそれだけで救われる
たまに予想外の人から返事が来る。「久しぶりに会いたいね」と書かれていたりすると、それだけで正月の寂しさが和らぐ。紙の向こうに、まだ自分を覚えてくれている人がいると感じられる。それがあるから、やっぱり出す意味はある。
ポストに投函する最後のアナログなやりとり
デジタルでなんでも完結する時代に、あえてポストに投函するという行為は、もはや儀式に近い。年に一度の手間暇を惜しまず行うことで、自分がまだ誰かと繋がっているという感覚を持てる。それだけで、この仕事にも、この日常にも、ほんの少しの温かさが戻ってくる。