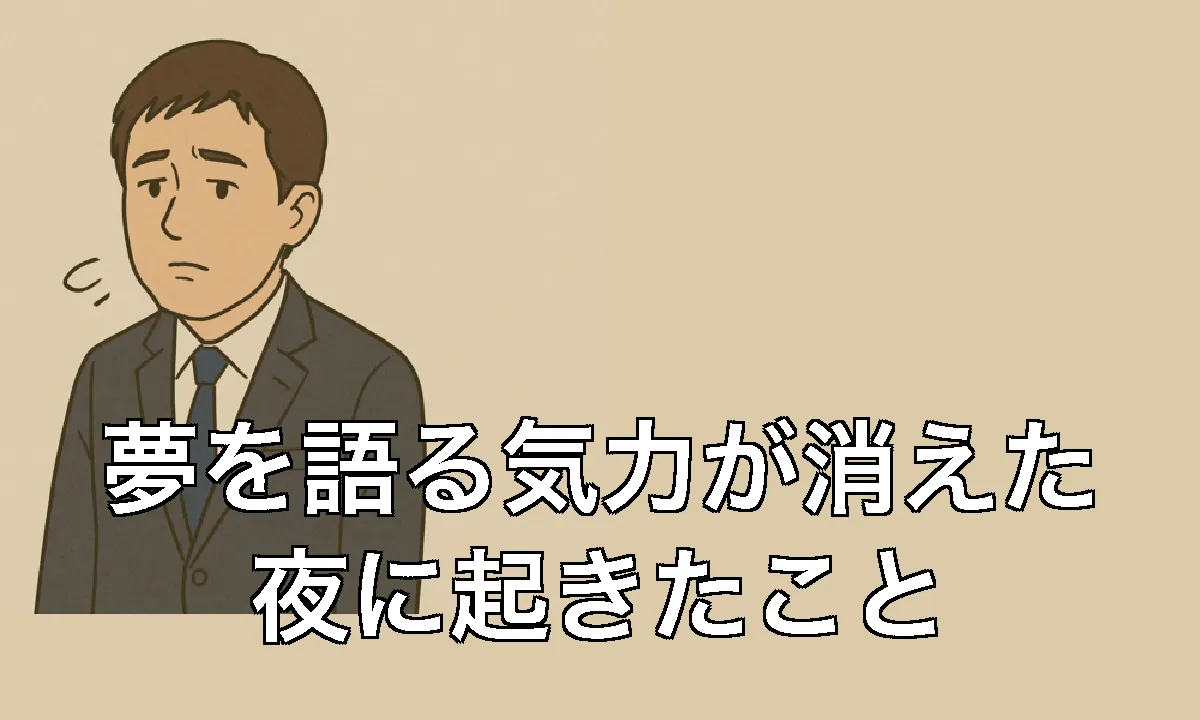夢を語る気力が消えた夜に起きたこと
誰にも言えなくなった夢の話
かつて「プロ野球選手になりたい」なんて、風呂上がりに牛乳片手に叫んでいた少年も、今では役所と依頼人の板挟みに疲れた司法書士になってしまった。夢を語る気力なんて、もうずっと前にどこかに置いてきた。机に積もるファイルの山を見ていると、あの頃の熱は、まるでドラえもんのポケットに吸い込まれた秘密道具みたいに思える。
書類に埋もれた日々と心の空白
午前中から登記の件で電話応対に追われ、昼もろくに食べられず、ようやく落ち着いたのは午後3時。サトウさんが淹れてくれたぬるくなったコーヒーを啜りながら、ふと天井を見上げた。「俺、何がしたかったんだっけな」——問いかけは風のように虚しく消えた。
昼休みにふと気づいた「昔の自分」
手帳の片隅に書かれたメモ。昔、法学部の学生だった頃、「困ってる人の役に立ちたい」と書いていた。今はどうだ?期限に追われ、印紙に追われ、目を合わせずに去っていく依頼人を見送る日々。
「そういえば、夢って何だったっけ」
まるでサザエさんの波平が日曜夕方のテーマを聞いた瞬間のような、あの寂寥感が押し寄せる。月曜日はやってくる。夢は語るもんじゃなく、処理するファイルの隙間に落ちていくものだったのか。
サトウさんの何気ない一言が刺さった日
「先生って、昔何になりたかったんですか?」書類の束を仕分けながら、サトウさんが何気なく口にした一言。思わず手が止まった。
「先生って、昔何になりたかったんですか?」
「さあね、忘れちまったよ」そう笑ってごまかすのが精一杯だった。でも、サトウさんは黙って見ていた。見透かされるあの沈黙。まるで名探偵が核心を突く前の“間”だ。
ごまかす自分と見抜かれる沈黙
「やれやれ、、、そんな顔しないでくれよ」俺はそう言って背を向けたが、どこかでズキンと胸が鳴った。
依頼人の遺言書が呼び起こした記憶
その日届いたのは、ある老婦人の遺言書作成依頼。書き出しに「私の夢は、家族に感謝を伝えることでした」とあった。まるで探偵漫画のトリックが解ける瞬間のように、心の中に何かが閃いた。
忘れていた父の言葉
父は口下手な人だったが、「誰かの役に立つ仕事をしろ」とだけは何度も言っていた。司法書士の道を選んだのは、たしかにその言葉がきっかけだった。
「誰かの役に立つ仕事をしろ」
でもそれは「夢」ではなかったのかもしれない。「夢」はもっと熱くて、ちょっと恥ずかしくて、語ると笑われるようなものだった気がする。
夢と現実の折り合いをつけた瞬間
「夢を持つこと」と「現実に立つこと」は、まるで怪盗と警部のように対立する。どちらも正義で、どちらも嘘じゃない。
法務局で見た“若い自分”の幻影
翌日、書類提出のために法務局へ行くと、新人らしき司法書士がキビキビと動いていた。あの姿はまるで、かつての自分の残像だった。
新人司法書士の目の輝きがまぶしかった
「この書類、念のため控えとっておいた方がいいですよ!」と声をかけられたとき、驚いた。まるで自分に言われたようだったから。
「あんな頃もあったな」とつぶやく癖
つい癖で「やれやれ、、、」と漏らした。これから彼は夢を語り、現実にぶつかり、そして何かを選ぶんだろう。俺はその後ろ姿をしばらく見送った。
やれやれ、、、まだ終わっちゃいないらしい
心のどこかで、そう聞こえた気がした。夢は捨てたんじゃなくて、棚の上に一時的に置いてただけかもしれない。
夢を語る気力が消えた夜に起きた小さな事件
その夜、事務所に届いた一通の封書。差出人不明、内容は「司法書士シンドウへ お前の夢はどこへ行った?」という一文だけ。ぞっとした。サトウさんと目を合わせた。
怪文書の差出人は依頼人ではなかった
封筒のノリの貼り方、印字のフォント、妙に見覚えがある。まさかとは思ったが、机のプリンターを見る。サトウさんが静かに言った。
字の癖と封筒の貼り方に気づいたサトウさん
「先生、これ、ウチのプリンターの印字ですよね」
「これ、ウチのプリンターの印字ですよ」
「……バレたか」いたずらだった。いや、自分で自分に出したメッセージだったのかもしれない。
真相と再燃する想い
「これ、先生が自分に出した“登記”じゃないですか?」サトウさんの冗談に、思わず笑ってしまった。確かにそうだ、心に押印するような一言だった。
くだらない事件ほど心が動く不思議
探偵でもなく、怪盗でもなく、ただの司法書士が挑んだ“自分の夢の謎解き”。こんな事件なら、たまに起きてもいいかもしれない。
また語ってみたくなった夢のかけら
その夜は、サトウさんとコーヒーを飲みながら、昔話を少しだけした。夢を語るには気力がいる。でも、ほんの少しの笑いと誰かの気遣いがあれば——語る勇気は、また戻ってくるのかもしれない。