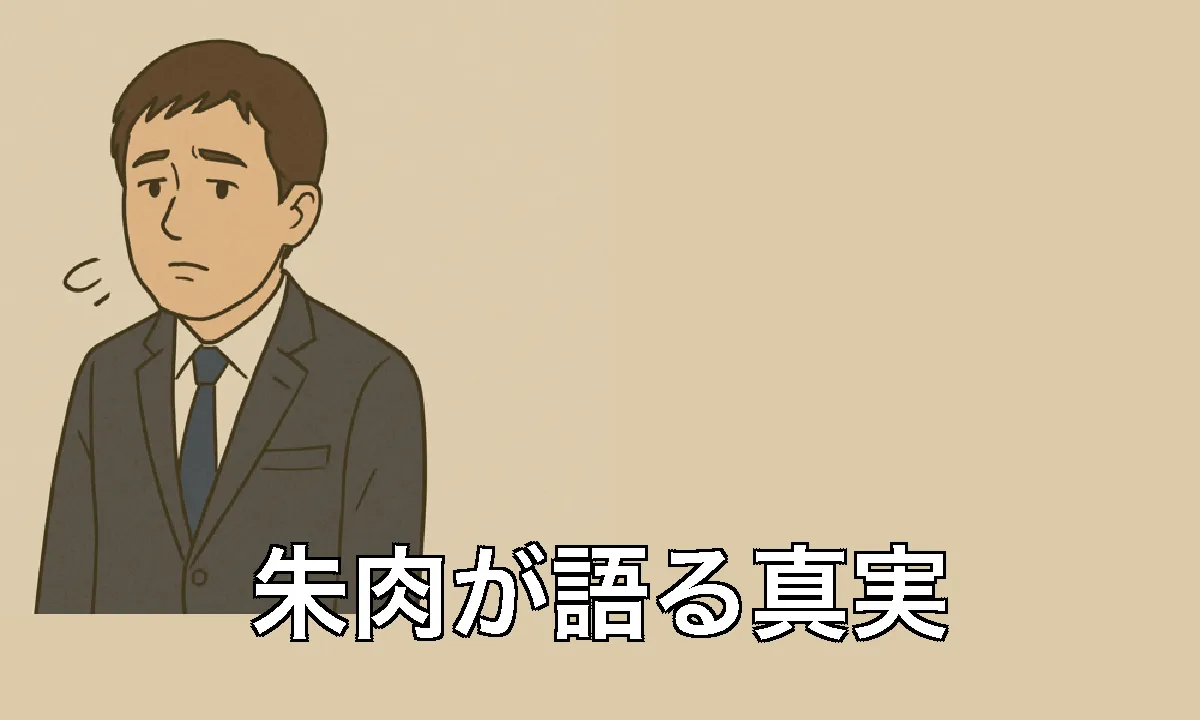依頼者は午前九時にやってきた
認印が押された委任状
私が事務所の鍵を開けると同時に、ひとりの男が玄関の前に立っていた。 紺のジャケットにやや大きめのカバン。どこにでもいる中年男性に見えたが、その手には丁寧にホチキス留めされた登記関係の書類があった。 「この物件、兄の名義なんですが、相続で手続きしたいんです」と彼は言った。
曖昧な依頼と不自然な表情
その話は一見、ごく普通の相続登記の相談だった。 だが、委任状に押された認印を見た瞬間、私は軽い違和感を覚えた。印影が少し斜めになっていたからだ。 もちろんそれだけで疑うには早い。ただ、それがこの後の展開に妙な伏線を張ることになるとは、この時の私は知る由もなかった。
物件調査のはずが相続調査に
亡くなった兄と生きている妹
提出された戸籍を追っていくと、亡くなったという兄には唯一の相続人である妹がいるはずだった。 しかし相談者は「兄には自分しかいない」と言い切っていた。戸籍に記載された妹の存在について聞くと、彼は一瞬言葉に詰まった。 「死んでます」とぽつりと答えたが、その目は明らかに泳いでいた。
登記簿から消された記録
登記簿を確認すると、平成初期に所有権移転が一度行われていた形跡があった。 しかし謄本の写しには、その前後の書類がまるごと欠けている。 これは、保存期間が過ぎたことで破棄された可能性があるが、それでも気になる。
サトウさんの冷たい視線
朱肉の色が違っていた
書類のコピーを机に広げていた私の背後から、サトウさんの鋭い視線が突き刺さる。 「この印鑑、色がちょっと赤すぎません?」と彼女が言った。 確かに、他の印影よりも明らかに鮮やかな朱色をしていた。
筆跡ではなく押印の角度
司法書士の端くれとして、私は筆跡よりもむしろ印影に注目する癖がある。 押印の角度、圧力、にじみ方。それらは人間の無意識のクセを映し出す。 今回の委任状に押された印は、明らかに他の過去の書類と違っていた。
昔の謄本に潜む違和感
平成三年の委任状を見返す
昔の謄本とともに残されていたコピーの中に、同じ認印が押された委任状があった。 それは兄が生前に作成したものらしく、印影はややかすれていて、斜めではなく真っ直ぐだった。 この違いは小さいようでいて、致命的な意味を持っていた。
押印の濃さは何を語るか
朱肉が新しければ印影は濃くなる。古いものはかすれる。 今回の書類は新しい朱肉を使って押されたことがわかる。 つまり、兄が亡くなってから用意された「新しい書類」に、彼の認印が「誰かによって」押された可能性が高い。
犯人は書類の中にいた
二重申請のトリック
男は以前にもこの物件の登記を試みていた痕跡があった。 法務局の記録に残っていた一次申請は、不備で却下されていたが、その時も認印が問題となっていた。 それに気づいた私は確信した。彼は二度目の申請で印影のズレを修正したのだ。
相続放棄に仕組まれた嘘
戸籍上の妹は、実はまだ生きていた。 そして過去に相続放棄した記録はなかった。 つまり、兄が亡くなった今、正当な相続人は彼女であり、目の前の男にその権利はない。
やれやれ俺の出番か
印影照合と司法書士の眼
私は印鑑登録証明を市役所に照会し、さらに登記官に相談して書類を一時保留にしてもらった。 「これは刑事案件に該当するかもしれませんね」と登記官。 やれやれ、、、また面倒なことになってしまった。
たった一つの違和感から
最初の違和感——斜めに押された印影。 それを見逃していたら、この詐欺も成立していただろう。 小さな違和感を拾い上げるのが、司法書士という仕事の醍醐味なのかもしれない。
犯人の動機は過去にあった
消された兄の借金
調べてみると、兄には消費者金融の借金が残っていた。 妹にその支払いが回ることを恐れた男は、自分で登記を済ませようとしたのだ。 つまり、動機は「優しさ」だったのかもしれない——歪んだ形ではあったが。
妹の静かな復讐劇
事実を知らされた妹は、一度だけ男に会い、こう言ったという。 「あなたのしてきたこと、全部わかっています。許すつもりはありません」 その目には涙も怒りもなく、ただ静かな拒絶があった。
最後に残った一枚の紙
本物の印鑑はどれだったのか
事件後、私の元に妹から簡易書留が届いた。 中には兄の本物の認印と、彼女からの丁寧なお礼状が入っていた。 本物の重みが手の中にずしりと残った。
印鑑証明の嘘と本当
制度の網をすり抜けようとする者は、必ずどこかで「誤差」を残す。 そのズレを拾うことが、我々の役目だ。 認印ひとつが、人の嘘を暴くこともあるのだ。
サトウさんの無言のツッコミ
「初めから気づいてましたよ」
報告を終えると、サトウさんはいつもの無表情で私を見た。 「先生、印影の傾きくらい、最初に確認しておかないと」 まるでカツオの言い訳を一蹴するサザエさんのようだった。
コーヒー一杯分の事件
その日も彼女はコーヒーを淹れてくれた。無言のまま。 苦い味が舌に残る。だが、その後味が悪くないのが不思議だった。 事件は終わったのだ。
事務所に戻った静かな午後
印鑑と人間の関係を考える
印鑑はただの道具だ。けれど、その使い方で人の心が透けて見えることがある。 そう思いながら、今日も私は書類に目を通す。 ペンを持つ手に、少しだけ力がこもった。
やれやれ今日も疲れた
時計は午後五時を指していた。 外は蝉の声が響き、夏の終わりを告げていた。 やれやれ、、、明日もまた、地味な事件が待っているのだろう。