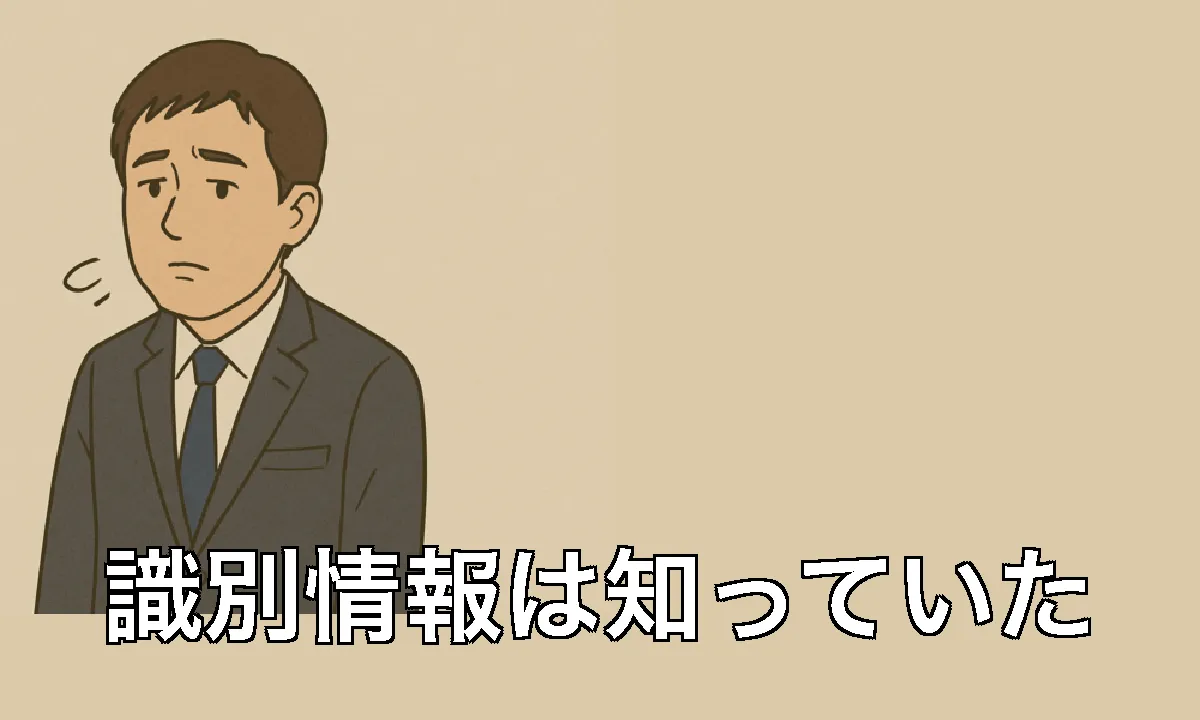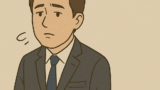朝の一通の電話
盆明けの月曜、鳴り響いた一本の電話が一日を狂わせた。
「登記識別情報が消えたんです」
落ち着いた声だったが、妙な湿り気があった。まるで隠し事をしている人間の声だ。
依頼人は妙に落ち着いた声だった
名前はササキと名乗った。亡くなった父の名義を相続したが、登記手続きの途中で識別情報が紛失しているという。
「登記済証ではなく、識別情報の通知書をお持ちなんですね?」と尋ねると、曖昧な返事が返ってきた。
これは、普通の相続案件じゃなさそうだ。
識別情報が消えた
封筒ごと無くなったらしいが、そもそもなぜ識別情報があるのかが気になる。
というのも、父親名義の不動産が10年以上も前の登記で、原則識別情報は交付されていないはずなのだ。
この矛盾が、朝から頭に引っかかっていた。
なぜか登記済証ではなく識別情報通知を所持していた
依頼人が持ち込んだ封筒のコピーには、確かに識別情報の印字がある。
だが、それは明らかに後から誰かが加工したように見えた。
「サトウさん、このフォント……なんか変じゃないか?」
「平成初期のインクリボンプリンタの書体ですね。こんなフォント、法務局は使ってません」
現場は封筒一枚の中に
本物の識別情報通知であれば、目隠しシールの貼付位置、台紙のマーク、発行庁名の配置などが微妙に異なる。
だが依頼人の持参したものは、どれも“惜しい”出来だった。
ニセモノには、職業柄すぐ気づく。問題は、誰が何の目的で偽造したかだ。
シワだらけの封筒が語る違和感
封筒の中からは、委任状のコピーも出てきた。だが、そこには印鑑も署名もない。
「これ、使えないですね」
サトウさんの声には、すでに見切りをつけた冷たさがあった。
事務所に持ち込まれた混乱
午後には、別の相続人を名乗る人物からも電話が入った。曰く「兄が勝手に登記を進めようとしている」と。
話が一気にドロドロしてきた。どうやらこの登記、兄弟間で争いがあるらしい。
やれやれ、、、また骨のある依頼だ。
サトウさんの目が鋭く光る
「シンドウ先生、このケース、もしかして共有状態のまま放置されてませんか?」
言われて古い謄本を確認すると、確かに亡父名義の他に、弟名義の持分も存在していた。
そしてその弟は、数年前にすでに亡くなっていた……。
登記識別情報のルール
そもそも登記識別情報は、登記名義人が申請人であることを証明するものだ。
だが名義が亡父のまま、しかも共有だったとなれば、識別情報は出るはずがない。
つまり、依頼人が持ち込んだそれは完全にニセモノ。問題は、誰がそれを作ったか。
登記識別情報は誰のためにあるのか
形式的には、本人確認の手段だ。
だが、逆に言えば“それっぽく”作れば、素人には区別がつかない。
そう思うと、急に背筋が冷えた。依頼人の「落ち着き」は、それを知っていたからなのかもしれない。
封筒の真贋
サトウさんがスキャナで封筒を拡大していた。
「この角の折り目、インクが剥がれてます。明らかにプリンタの後で折られてますね」
「つまり、あの識別情報は、後から貼ったってことか」
「ええ。しかもこれ、別件で偽造されたものと酷似してます。去年、福島で」
あえて古いプリンタで印字された文字
フォント、インクの濃さ、台紙の質感——すべてが“わざと”に見えた。
まるで推理ドラマで登場する、雑な偽造パスポートのような演出だ。
こちらを試しているのか? 誰が? なぜ?
「共有者」という落とし穴
登記簿をよく見ると、死亡した弟の持分は未登記のまま相続されていなかった。
つまり、現在の名義人は存在せず、登記は一時的に“浮いた”状態だった。
この隙をついて偽造し、すべてを自分の名義に移そうとしたのだろう。
権利証の存在しないもう一人の影
依頼人は、「自分がすべて相続するはずだった」と語った。
だが、弟の子どもが複数存在しており、当然共有相続となる案件だった。
法定相続すら理解していないのに、なぜ登記識別情報を偽造する必要があったのか。
最後の証明書
法務局に照会をかけた結果、識別情報は発行されていなかったことが確認された。
サトウさんの指摘が的中した形だ。
「先生、例の通帳の写し、銀行印が一致してません。やっぱり偽造ですね」
空欄の委任状が導いた裏の顔
依頼人に問い詰めると、急に態度が豹変した。
「お前ら、グルになって俺から権利を奪おうってのか!」
すっかり逆ギレモードだったが、ここまで証拠を揃えた以上、観念してもらうしかない。
サトウさんの推理
事後処理を終えて一息ついたサトウさんが、ぽつりと呟いた。
「最初から偽物に頼る人って、たいてい真実に触れたくない人ですよね」
その通りだ。真実は、いつも地味で手間がかかる。
すべては識別情報をすり替えるためだった
法務局、司法書士、そして書類。
どこかに“本物”を装えるスキがあれば、悪意は必ずそこを突く。
だがその隙を見抜けなければ、こちらの資格も疑われるのだ。
法務局での真実
後日、本人確認の際に提出された通帳の印影が決定打となった。
「依頼人」は実の兄ではなく、甥だった。しかも筆跡も別人。
成りすましによる詐取目的。まさにキャッツアイのような大胆不敵さだった。
通帳の印影が告げた結末
警察への通報は当然だが、通報までのあいだ、甥はずっと他人のフリをしていた。
「俺はあの家の長男だ」と言い切った姿は、ある意味で見事だった。
演技力だけは、舞台俳優レベルだったかもしれない。
封筒に刻まれた裏切り
古い封筒には、かつて父親が送った手紙の跡があった。
たった一枚の紙が、家族の信頼と法の隙を突くために使われたのだ。
やるせなさが残る事件だった。
見落とされたナンバリング
偽造された識別情報の隅に、存在しない番号が印字されていた。
「最後の数字、ゼロが三つっておかしいですよね」
サトウさんが指摘しなければ、私も見逃していたかもしれない。
告発と静かな引導
依頼人……いや、元依頼人は、連行されるときも笑っていた。
「登記って、便利だな」
そう言い残したその姿に、皮肉の効いた推理マンガのラストを感じた。
依頼人の背中はやけに小さかった
法を使って人を欺く者ほど、最後には小さく見える。
書類一枚に人生を乗せてくる人間を、今日も私は見届けていた。
そう、登記識別情報は、すべてを知っていたのだ。
事務所に戻って
夕方、冷めたコーヒーを飲みながらサトウさんが言った。
「先生、たまには平和な相続だけの仕事がしたいですね」
「俺もだよ……もう少し歳をとっても、事件は寄ってくるんだろうな」
冷めたコーヒーとサトウさんのため息
「せめて今度は登記識別情報じゃなくて、はんこの話にしてくれ」
「それはそれでトラブルになりますよ」
やれやれ、、、司法書士ってのは、楽な仕事じゃない。
識別情報は知っていた
事件の始まりも終わりも、すべてはあの一枚からだった。
紙は黙っているが、真実だけはそこに刻まれている。
司法書士の仕事とは、そういうものだ。