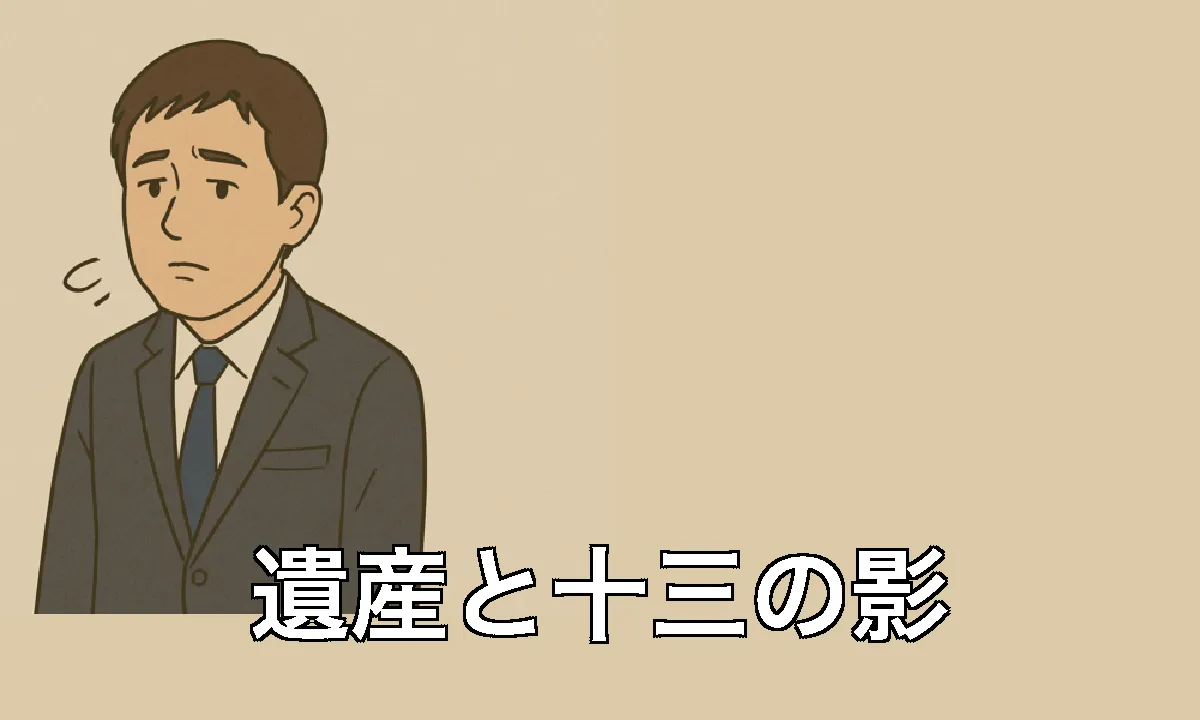遺産と十三の影
謎の電話と旧家の依頼
電話が鳴ったのは、昼食後の微妙な時間だった。眠気と書類に挟まれながら受話器を取ると、声の主は地方の旧家の長女を名乗った。「父が亡くなりました。遺産の件で相談したいことがあるのですが……」 依頼自体は珍しくもないが、次の言葉で背筋が伸びた。「相続人が、十三人います」
戸籍謄本に現れた名前たち
事務所に届いた戸籍の束は、まるで地層のようだった。明治から続く家系の中に、見知らぬ名がいくつも散りばめられている。 「これは……まさか全部相続人?」とつぶやくと、サトウさんが無表情に「ええ、推定相続人の数と一致しています」と返す。 私は慌ててコーヒーを飲み干した。やれやれ、、、これは骨が折れそうだ。
忘れられた養子縁組
戸籍を遡る中で、昭和52年のある届出が目に留まった。「養子縁組届 義男(旧姓〇〇)を養子とする」 しかし、その義男の名前は他の資料に一切現れていない。 「これ、養子にしてすぐに疎遠になったんでしょうかね」と言うと、サトウさんが「それが誰かの利益になるなら、逆に怪しいです」と切り捨てた。
遺言書の筆跡は誰のものか
遺言書が見つかったのは、仏間の床下だった。ボロボロの封筒に入った手書きの一枚。そこにはこう書かれていた。「すべての財産を長男・信介に譲る」 だが、筆跡は明らかに年寄りのものではなかった。 「これは…誰かが書いた可能性があるな」と呟くと、サトウさんがスマホを見ながら「鑑定依頼、しておきます」と一言。
サトウさんの冷静な推理
「遺言書は偽物。しかも、相続人の一人が作ったものでしょう」サトウさんは無表情で言い切った。 「そこまでわかるのか?」と驚く私に、「封筒の消印、平成27年。被相続人が入院していた時期です。しかも筆跡がその本人とは明らかに違う」 彼女の指摘は、まるでコナン君か金田一少年。私はというと、ただ頷くことしかできなかった。
遺産を巡る相続人の本音
全員を集めた話し合いの場では、空気が重苦しかった。誰もが他人の一言を待っている。 やがて一人の男性が言った。「正直、金さえもらえればどうでもいい」 その瞬間、他の相続人たちがざわめき、遺産という言葉が一気に生臭く感じられた。
一通の転送郵便が暴いた事実
郵便局から転送された封書の中に、一通の通知書が紛れていた。それは数年前、義男宛に届いていた相続通知だった。 「ということは、彼は他の家の相続もしていた…?」 私はその偶然に震えた。義男の存在が、二重生活の鍵を握っていたのだ。
長男の名は本物か
本籍地の調査で出てきたのは、もう一人の信介という名の男性だった。 「これは同姓同名じゃなくて、なりすましの可能性があります」サトウさんが書類を差し出す。 遺言の受取人が、本当の長男ではなかった。そう気づいたとき、事件は静かに動いた。
消えた被相続人の戸籍
さらに調査を進めると、あるはずの戸籍が抹消されていた。 「本人が亡くなる前に、自ら抹消を依頼した記録がある」 私は思わず「それって、誰にも財産を渡さないようにするってことか?」と聞くと、サトウさんは「ええ、そしてあの偽の遺言書は、それに対抗する偽造だった」と断言した。
古い書庫に残された公正証書
屋敷の蔵から出てきた古いファイル。中には公正証書遺言の控えがあった。 それは、すべての財産を市の児童福祉施設に寄付するという内容だった。 「誰にも知られないように隠していたんですね」とサトウさんがつぶやいた。
やれやれ、、、また厄介な家だ
事件が終わった後の静かな事務所で、私は湯呑みを手にしていた。 「結局、相続人十三人のうち、本当に権利があったのは三人だけか」 サトウさんは「あとは他人の空似か、なりすましか、ただの勘違いです」と冷たく言い放った。
サザエさん一家と違いすぎる現実
私はふと、テレビで見たサザエさん一家を思い出した。あれだけ多くても、ちゃんとまとまってる。 こちらはといえば、血縁も信頼も崩壊した相続劇。 「現実って、笑えないな……」私は苦笑しながら言った。
戸籍上の真実と血の繋がり
最終的に残った戸籍は、被相続人の孤独を物語っていた。 血が繋がっていても、心が繋がっていない家族の形。 「戸籍って、結局は紙の記録にすぎないんだな」と呟いた。
全員が相続人ではなかった理由
法律上、相続人は限られている。にもかかわらず、多くの者が名乗り出るのはなぜか。 答えはひとつ、「お金」である。誰もが名義に目を光らせていた。 だが、その目は真実から遠ざかっていた。
最後に明かされる名義の真相
すべての謎が解けたとき、相続登記はすでに整っていた。 「サトウさん、あとは登記申請だ」 「ええ、申請書も出来てますよ。いつもより丁寧に作っておきました」 少し微笑んだように見えたが、きっと気のせいだ。
シンドウの独り言と冷めたお茶
私は一息ついて、冷めたお茶をすすった。「やれやれ、、、相続ってのは人間模様の縮図だな」 それにしても、サトウさんは本当に頼りになる。いや、怖いくらいだ。 私は机に突っ伏して小さくつぶやいた。「次の事件は、できればサザエさんレベルでお願いしたい…」