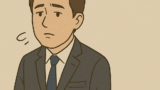朝の静寂に響く電話
夏の朝は、事務所の冷房が効き始めるまでが地獄だ。ようやく椅子に座ったその時、黒電話のような音が鳴った。受話器を取ると、妙に落ち着いた中年女性の声がした。
「お宅で登記簿を見てほしい記録があります。昔のものですが……間違いなく存在したはずなんです」
奇妙な依頼だった。存在した“はず”の登記簿? 幻でも見ているつもりか、と口に出しそうになって、それを飲み込んだ。
サトウさんの冷たい一言
「お化けでも探すんですか」そう言ってサトウさんは書類を放り投げた。ひやりと冷たいその視線は、目覚めのコーヒーより効いた。
「念のため、法務局に行って調べてくるよ」と言った僕に、彼女は「うっかりミスしないでくださいね」と皮肉を忘れなかった。
彼女の塩対応も、もう慣れたつもりだったけれど、朝から精神力が削られる。
登記簿の違和感に気づく
法務局で古い不動産の登記簿謄本を取り寄せた。昭和の終わり頃の記録だ。
そこには、土地を共有で持つ「高木タカシ」「村上ノゾミ」の名があったが、委任状の記録が抜けていた。記録が途中で「空白」になっている。
まるで誰かが「書かない」ように意図的に空白を残したかのような記載だった。
依頼人の素性と曖昧な記憶
再び事務所に戻ると、依頼人の女性が待っていた。白髪まじりだが、背筋の通ったその姿は、不思議な重みを放っていた。
「高木と村上は、私の父と叔母なんです。ふたりは若い頃、駆け落ち同然で家を出たと聞きました」
登記簿には彼らが共有名義人として登録されていたが、どちらも数年後に所在不明扱いで消えていたという。
登場した「二人」の名前
登記名義はそのままだ。しかも、住所欄には同一の番地が記されていた。
「同じ家に住んでいたという記録が、登記には残っている。でも、それ以降は何もない。消えたままです」
依頼人は涙を浮かべながら語った。記録にはないが、確かに生きた人間の時間が、そこに刻まれていたのだ。
登記原因に潜む矛盾
どうにも腑に落ちない。登記原因の欄には「売買」とあるのに、対価の記録もないし、委任状の提出日も不明瞭だった。
まるで書類が「抜かれた」ような不自然な空白。昭和の時代には、こうした抜け道が見逃されていたこともある。
だが、これは単なるミスではない。意図的な「空白」だった。
調査開始そして旧友との再会
登記簿に記された住所の近くに住んでいた人物を探し、地元の名簿を調べていく中で、思いがけない名を見つけた。
それは高校野球時代のキャッチャー、安井の名前だった。
「お前が司法書士なんてなぁ」と笑う安井に、僕は登記簿を見せた。彼は目を細め、しばらく沈黙した後、ぽつりと語り始めた。
高校野球仲間が語った事実
「ああ、村上ノゾミさんって、当時噂になったよ。戦後すぐの駆け落ち事件ってやつ」
地元じゃ“恋愛逃避行”と揶揄されていたらしい。ふたりは人目を避けて山間の廃屋に住み着いていたとか。
やれやれ、、、まるで昭和版のルパン三世と峰不二子だ。逃げて、隠れて、それでも一緒にいたかったのだろう。
サザエさん家のようなズレた日常
その家の近くには、小さな八百屋があった。近所の婆さんが言うには、「昔よく、男が無言で野菜を買いに来た」らしい。
まるでサザエさんのマスオさんのように、どこか頼りなくて、でも優しさのにじみ出る男だったという。
その「無言の男」が、高木タカシだったのかもしれない。
所有権移転の謎と消えた委任状
結局、土地は誰のものにもなっていない。売買も名義変更も未了のまま、数十年が経過していた。
委任状がないのは、もともと「他人に渡すつもりがなかった」からではないか。
ふたりはきっと、他人に渡すくらいなら、名前のまま一緒にいようと誓ったのだ。
法務局の端末が示したもの
最新の情報を確認しようと、法務局の端末を検索すると、「死亡により権利関係未処理」とだけ表示された。
二人は記録上はまだ所有者のまま。しかし、実体はとうの昔に失われていた。
法という記録は、時に優しく、時に冷酷だ。
印鑑証明の発行履歴の闇
市役所で確認したところ、どちらの印鑑証明も一度も発行された記録がなかった。
つまり、ふたりは一度も「誰かに譲るため」の手続きを考えていなかったのだ。
この登記簿は、ふたりの「誓いの証」だったのかもしれない。
やれやれ、、、本音を引き出す時
サトウさんは依頼人を前に、ゆっくりと口を開いた。「あなた、本当はお父様がどこで亡くなったか、知ってますよね?」
依頼人は目を見開いた。しばらく沈黙の後、こくんと頷いた。「この土地で、静かに暮らしていました」
「でも、私はあの記録を、残しておきたかったんです。父と叔母の人生を、消したくなかった」
サトウさんの心理戦が炸裂
「だったら、今あなたがするべきことは、土地の名義変更じゃありません。物語を語ることです」
冷たいようで優しいサトウさんの声に、依頼人は泣きながら頷いた。
やれやれ、、、ほんと、うちの事務員は手厳しい。
証拠の写真と一枚の古いはがき
帰り際、依頼人は一枚の古びたはがきを置いていった。そこには若い男女が肩を並べて写っていた。
裏にはただ、「いつかこの家を登記して、あんたの名前と並べよう」と、男の文字で書かれていた。
記録にはないが、確かにそこには、二人の物語があった。
終章二人が記録に刻んだもの
その後、僕はふたりの名義をそのまま残すようにアドバイスした。時効取得の申請も、相続放棄の登記も、今回は不要だ。
登記簿は、彼らが生きた証だ。そして、依頼人にとっても、それが一番の形見になるだろう。
システムは更新され、法は進化しても、人の想いは消えずにそこに残る。
悲しい約束と法の救済
今回の依頼に、明確な報酬はなかった。でも、不思議と心は軽かった。
法という無機質な世界の中で、僕ら司法書士ができるのは、ほんの小さな救いかもしれない。
それでも、誰かの記録を守れるなら、この仕事も悪くない。
それでも僕らは記録を残す
「今日もやるか」と呟いて、机に向かう。すると背後からサトウさんの冷たい声が飛んできた。
「その前に、昨日の未完了処理を終わらせてください」
やれやれ、、、今日も記録と戦う一日が始まる。