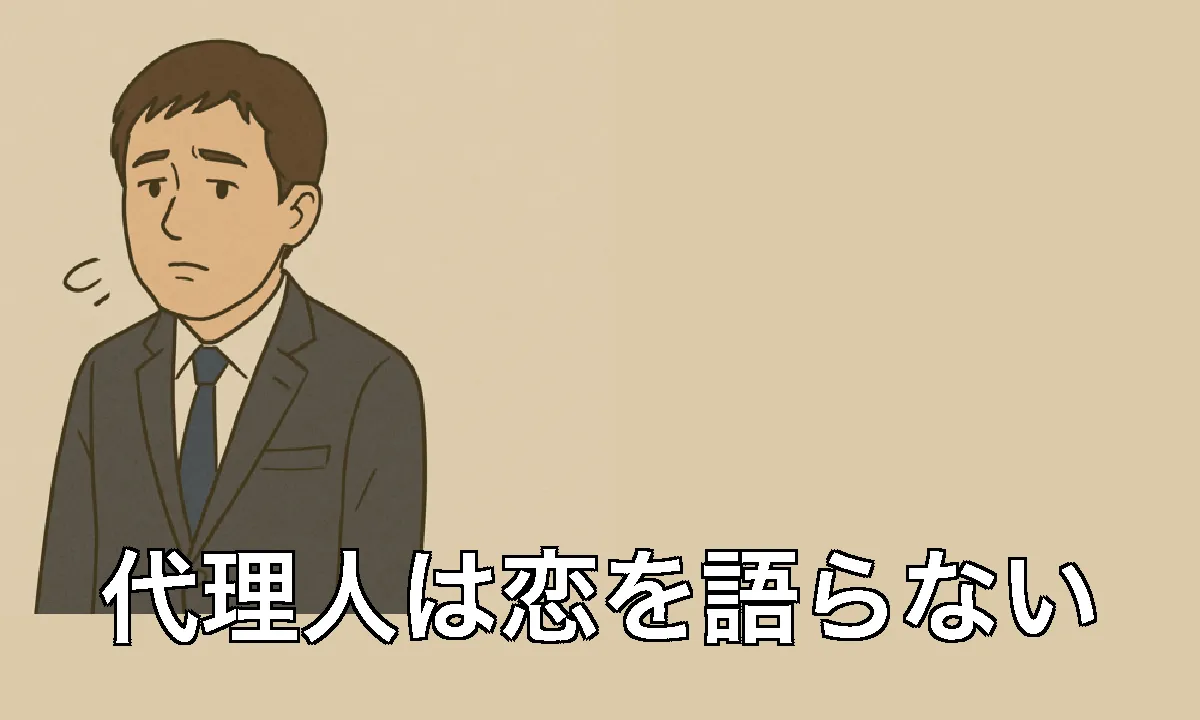朝の来客と曖昧な委任
その日、朝の9時を少し回った頃だった。事務所のドアが控えめに開き、黒いレースのマスクをつけた女性が入ってきた。薄く微笑むその姿に、俺は一瞬だけ「何かのドラマか?」と首を傾げた。
依頼内容は登記の名義変更だった。だが、渡された委任状には受任者の名前が書かれていない。恋人との共同名義のマンションだというが、相手の姿はどこにもない。「代わりに全部手続きしてください」とだけ言われた。
後ろで無言でお茶を置いたサトウさんの動きが、やけに機械的だったのが気になった。
コーヒーとともに現れた依頼人
「コーヒー、お飲みになりますか」と俺が訊ねると、依頼人は軽く首を振った。代わりにサトウさんが小声で「冷たい水でよければ」と言った。俺の扱いと違って、やけに丁寧だ。
女性は「彼はもう戻ってきません」と小さく呟いた。その口ぶりが、遺産の話なのか、破局の話なのか、すぐには判断できなかった。
それでも委任状の署名はしっかりしていた。形式上、受け入れられる書類だ。だが、何か引っかかる。
恋人かどうかを問われて
「恋人……なんですよね?」と俺が訊ねると、女性は初めて笑った。「そう思ってたのは、私だけかもしれません」
その言葉は何かを封印するかのように重かった。サトウさんが目を細める。「あの委任状、まだ見てませんよね」
机の上で、俺の手が一瞬止まった。委任状の書き方、住所の書き方、それらすべてが妙に「仮」のように思えてきた。
委任状に書かれた違和感
住所が微妙に違う。住民票と照らし合わせると、番地が一つズレていた。だが字体は同じ、押印も問題ない。
だが、俺の中にある違和感が膨らんでいく。この感覚は、かつて市役所から持ち込まれた偽造登記の相談を思い出させた。
「書いたのは本人じゃない」とサトウさんが即断した。根拠を訊ねると、「こういう字を書く人は“恋人”とは言わないものです」ときた。やれやれ、、、理屈が通らないようで、妙に納得できた。
日付のずれと不可解な記載
委任状の日付は昨日になっていた。しかし、登記原因証明情報には一週間前の日付がある。登記手続きにおいては重要な食い違いだ。
しかも、登記識別情報通知書が別名義で届いていた。これはつまり、名義を分けたまま登記を済ませる気がなかった、ということになる。
つまりは、共同名義というより、相手の名義だけを残して自分を消す計画。それを「委任」として処理させようとしていたのだ。
サトウさんの冷静な指摘
「このまま受けるとトラブルになりますよ」サトウさんがため息交じりに言った。「どちらか一方が自分の感情だけで手続きを動かすと、あとで訴訟になります」
「恋愛も登記も、バランスが大事です」と真顔で言いながら、ペンを持ち替えるその姿は、まるでベテラン刑事のようだ。
俺は思わず「サザエさんで言うなら波平だな…」と呟いたが、「それ、褒めてます?」と冷たく返された。
調査開始と古い契約書
俺は依頼人に事情を説明し、一時的に手続きを保留することを伝えた。彼女はそれを聞くと、小さく「そうですか」とだけ言った。
その後、彼女が置いていった分厚い書類ファイルを調べてみた。すると、三年前の賃貸借契約書が出てきた。そこに記載されていた住所と、委任状の住所が一致していなかった。
さらに驚いたことに、委任状の「相手方」には、過去に不動産取引のトラブルで名の上がった人物の名前があった。
不動産登記の裏側に潜む嘘
そこから先は芋づるだった。過去の登記簿、法務局への問い合わせ、オンラインで閲覧可能な登記履歴。
すべてを合わせると、依頼人の名義は一度もマンションに載ったことがなかった。つまり、彼女は恋人でも何でもなかったのだ。
ただ、何かしらの感情、あるいは執着からその物件に関わっていただけ。そしてその証拠を「委任」のかたちで残そうとした。
元恋人の影を追う
男の行方はつかめなかった。連絡先も電話もすでに止まっていた。結局、彼女の想いは書類という形でしか残らなかった。
俺は法的に手続きできないことを伝えた。すると、彼女は何かに納得したように席を立った。「やっぱり、そうですよね」と。
背中に哀しさを滲ませながら、彼女は事務所を去っていった。俺はその後ろ姿を見送りながら、どうにも言いようのない気持ちになった。
真相と隠された動機
後日、俺は調査結果をまとめた書面を作成し、サトウさんに提出した。彼女は書類に目を通すと、無言でうなずいた。
「人間って、証明したくなるんですよね。存在とか、関係とか。登記でさえそれに使われる」
その言葉に、俺は何も返せなかった。どれだけ制度が整っていても、人の気持ちは書類一枚では収まらない。
委任者の本当の目的
彼女の狙いは登記ではなかった。あのマンションに「関わっていた」という証跡を、残したかっただけなのかもしれない。
委任状はただの方便。恋が終わった証明を、法的に処理したかったのだろう。
それが意味をなさないことをわかっていても、人は記録を欲する。まるで、推理漫画で犯人が動機を語りたがるように。
あのとき交わされた約束
もしかしたら、彼と彼女の間に「いつか一緒に住もう」という曖昧な約束があったのかもしれない。だが、それは実現しなかった。
未練だけが残った。その未練を、「委任」という形で俺たちに委ねてきたのだ。
俺はふと、サトウさんが置いたコーヒーが冷めているのに気づいた。まったく、恋も登記も簡単にはいかない。
終幕とそれぞれの距離
その日の夕方、俺は事務所の片づけをしながらふと呟いた。「やれやれ、、、今日もまたドラマか」
サトウさんはすかさず「司法書士ドラマですけどね」と返してきた。塩対応にも、少しだけ温度がある気がした。
委任状も恋も、どちらも「任せる」ことで成り立つ。だが、任せた側が語らない限り、真実にはたどりつけないのかもしれない。
委任状の処理と恋の終わり
俺は書類棚の一番奥に、処理できなかった委任状をそっとしまった。廃棄するには惜しい、そんな気がしたからだ。
法的には無意味な紙切れ。でも、誰かにとっては、過去と向き合う大事なピース。
次に同じような依頼が来たとき、俺は今回よりも上手く対応できるだろうか。それは、自分が「恋」を経験してからだろうなと思った。
やれやれというには切なすぎる
帰り道、夕焼けに照らされる事務所の看板が、少し歪んで見えた。誰もいない歩道で、俺は小さくため息をついた。
「やれやれ、、、」声に出して言ってみたが、今日は少し、しんみりしてしまう。
俺にはまだ、「恋を語れる代理人」にはなれそうもなかった。